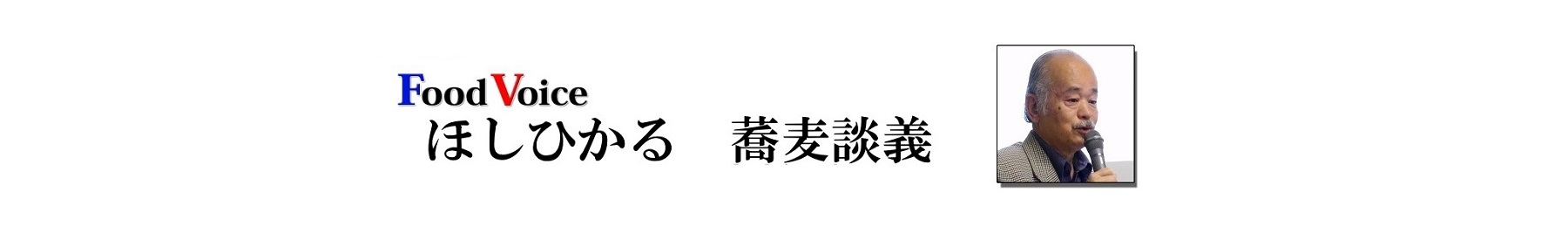第287話 お寺のごはん-Ⅱ
この欄に「お寺のごはん」を掲載したところ、江戸ソバリエ・ルシック「寺方蕎麦研究会」の世話人代表・小林尚人さんから、そのことについて話してくれと依頼された。
お引き受けしたものの、これは大変だと思ったが、とにかく「日本文化を理解するためには日本仏教史を知らなければはじまらない」ということだけは真面目に思っている。
逆のことをいえば、欧米旅行をしたときとか、欧米の著書を読んだときに、キリスト教を知らないとその本質が理解できないと感じることがある。
たとえば、題名からして、てっきり碾臼に関連する小説だと思って『碾臼』という本を読んだら、まったく違っていた。
それもそのはず、欧米人の認識では「碾臼=罰」という関係があるらしく、そこから小説は「碾臼=人生の重荷」としてストーリーを展開しているのであった。
なぜ「碾臼=罰」かというと、「マタイ伝」には「私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな碾臼を首に懸けられて、深い海に沈められる方がましである」とか何とか、異教徒にとってはチンプンカンプンのことが述べてあるが、そこら辺から「碾臼=罰」ということになったらしい。
とにもかくにも欧米の文明・文化を理解するためにはキリスト教を理解していなければ前には進めないということが、これでよく分かる。
マそんなこともあって、小林さんの指示も、せっかくの機会だと思うことにして、少ないながらも頭の中のものを出してみた。
☆日本仏教史
昔は「政治」と書いて「まつりごと」と読んでいたように、「歴史」というのは「祭政一致」から始まって、「祭政分離」への道だと理解すればわかりやすいと思う。
たとえば日本の曙が弥生時代だとすれば、そのころ北九州にあった邪馬台国では女王卑弥呼が銅鏡を用いて「鬼道」なる原始宗教を操り、国を治めていたという。
丁度そのころ中国大陸では、後漢が仏教を採用した。そのことが東南アジアへ及ぼした影響はまことに大きく、4~6世紀には朝鮮半島の国々が仏教を採用し、6世紀に日本列島へも伝わってきた。
それまでのいわゆる「古墳時代」の大王たちは卑弥呼女王と似たような原始宗教で国を治めていた。その宗教の表現形式が前方後円墳という墓である。
仏教が日本に伝来してから、飛鳥仏教、そして天平文化の花が開くが、仏像を見るとまだ大陸っぽい。しかし、仏教という新しい波は強烈だったようで、このころ日本列島は大和国としてほぼ統一された。教科書には、聖徳太子、天智天皇、天武天皇などが活躍したと紹介してある。
その天武天皇が仏教の教えにしたがって放生会を始め、殺生を禁じた。そして米を主食とすることも決めた。このときからわれわれ日本人の食生活の基本が決まったわけである。
それから都は奈良に遷り、全国に国分寺・国分尼寺が配置され、さらには大仏、東大寺、唐招提寺が建立され、奈良仏教として祭政一致のピークを迎えた。
しかし、それも平安時代になると少しちがってくる。最澄、空海の天台・真言の二大山によって、宗教らしくなるのである。これを京の平安仏教という。
この最澄、空海にしてもそうであるが、これまで日本は行き詰っては中国大陸へ渡って何か学んできてそれをわが国にもたらすことによって解決する方法をとってきた。
だから、国内の貴族(政治家)も、外国(中国)信奉派が多かった。ところが、ここにきて「う~ん、それでいいのか?」「日本は唐の属国ではない!」などという気持を持つ者が現れた。やがてこの中国を信奉する保守派と国内・改革派は激しく対立するようになった。そして突然のクーデターが起きた。改革派の藤原時平が「そんなに唐が好きなら、もっとも近い九州の太宰府に行け」とばかりにガチガチの中国信奉者・菅原道真を追放したのである。
その後から、わが国には国風文化が芽生えてくる。つまり、初のひらがな和歌集『古今和歌集』、初のひらがな日記『土左日記』などがそうである。それが10世紀のころであった。
もはや大陸に頼ることなく、日本独自の道を歩もうとする下地ができた。その上で、政権は貴族から武家の手に渡っていった。
とはいっても、仏教界・知識界の一部はまだ外国を頼みとした。
鎌倉時代の栄西、道元が入宋し、南宋から蘭渓道隆が渡来して鎌倉五山、京都五山体制が整い、北条政権、足利政権の支柱となった。
その一方で、中国留学とは無関係の宗教家が現れた。親鸞、日蓮、一遍らがそうであるが、彼らは庶民の仏教を目指した。これらを鎌倉仏教という。
台頭してきた武士の本質は軍人である。当然、武力オンリーの戦国時代がやってくる。やがて武力の前には宗教の力も地に墜ちた。
そして終戦となって江戸時代を迎えると、天海が東叡山寛永寺を建立、つまり比叡山に類似するモノが時の政権によって作られたのである。
宗教はかつての政治権力を失い、檀家制度という戸籍係を任せられ、庶民仏教への道を歩み始めていった。
と、仏教史を駆足で述べればこういうことであろうか。
☆日本料理史
中国大陸、朝鮮半島の国、あるいは琉球王国にも宮廷料理があったが、日本では宮廷料理は生まれなかった。
それは天皇制度に因るところが大きい。天皇には収穫した穀物を天神地祇に奉納し、また神と共食するという大きな役目がある。その表れが大嘗・新嘗祭であるが、これがわが国の最高権威の形である。
だから、日本料理の初めは神祇に供える「神饌料理」であるといえる。
それでも宮中では皇族や大臣クラスが正月に宴をもつこともあった。その料理を「大饗料理」という。
料理は天武以来主食としたご飯や、他にも色々仰々しく並べてあるが、よく見ると、だいたい生の物か、干した物を切っただけである。現代人の眼から見れば料理とはほど遠い。
そこへ宋で禅宗を学んできた栄西や道元らが帰国した。栄西は茶を、道元は精進料理をわが国にもたらした禅師としてだれでも知っている。だが、彼らはなぜそれらを持ち込んだのか? それを知るには、禅宗を把握しておかなければならない。
達磨が中国にもたらした禅宗は特に南宋へ広まって、臨済宗、潙仰宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗と、臨済宗の分派である楊岐派と黄竜派の五家七宗が派生した。うち、日本には栄西(帰国1191年)が臨済宗黄竜派を伝え、道元(帰国1228年)は曹洞宗、円爾弁円(帰国1241年)・蘭渓道隆(来日1246年)・無学祖元(来日1279年)が臨済宗楊岐派を伝えた。
これら禅宗系の特色には「生活=修行」であるという教えがある。したがって彼らは大陸での修行生活をそっくりそのまま日本にもちこんだ。それが栄西のお茶、道元の精進料理、そして円爾弁円が石臼である。
彼らの文化輸入は日本人の食生活を根底から覆した。
先述したように平安時代の「大饗料理」は、生物か、干物を切って並べ、脇に塩などの調味料を添えてあるだけであったが、栄西は食べ物には「甘・鹹・酢・苦・辛」の五味があるという分類認識を持ち込んだ。したがって、栄西は「食の思想家」と呼ぶにふさわしい。
続く道元は、禅宗の清規『禅苑清規』を引用して「甘・鹹・酢・苦・辛・淡」の六味を主張した。
その六番目の「淡」とは何だろうか? それを問うとき、老子の言葉が参考になる。
「五色令人目盲 五音令人耳聾 五味令人口爽 (五色は人の目をして盲ならしめ、五音は人の耳をして聾ならしめ、五味は人の口をして爽わしめ)」。
つまり、五味を抑えるものが「淡」だという。私流に図を描けば、淡を中心にして、甘・鹹・酢・苦・辛の五味が周囲に配されている図だろうか。
ここで話が少し変わるが、「日本人は仏教の影響で一般人も肉食をしなくなった」と枕詞のようにしてよく言うが、これは真実であろうか? 仏教にそれほどの強制力があるとしたら、仏教国の中国大陸や朝鮮半島の一般人はなぜ肉を食べたのか?
私の回答は別にある。それはわが国の水質である。軟水は肉料理に合わなかったからではないだろうか!この現実が先にあって、「仏教の影響で」というのは後で貼った膏薬のようなものだろう。
話を戻して、留学によって日・中を知った道元も、そのことに気づいた。それゆえに「淡」を持ち出した。
道元の頭の中には【油脂⇔軟水=「淡」⇒素材を活かす⇒旨味】というイメージがあった。
ここから1)「日本の料理は素材を活かす」ということや、2)他の国のように油を使わないで、「旨味」を出そうという、新しい道でありながら、日本に合った道を歩むようになった。
さらには、円爾弁円が石臼を導入したことによって日本は粉文化(麺文化)の時代へと入っていったことは麺の世界では広く知られている。
繰返すが、鎌倉時代の道元が始めた料理は平安時代の切って並べただけとは異なった、本格的に煮る、蒸す、炊く、茹でるなどの調理だった。それゆえに道元は日本における「食の革命家」とよんでもいいだろう。
そして道元が始めた精進料理は、首都京都へ広まって、さらに洗練されることになる。というのは、この京都という環境が、さらに和食を特色づけた。つまり海から離れていた地域であったために、魚介類からタンパク質を摂る機会に恵まれなかったから、植物性の大豆や小麦を主材とするようになった。その結果、豆腐、納豆、湯葉、麩の料理が発展した。
続く室町時代になると、料理は武家の本膳料理として、麺は素麺・饂飩・蕎麦としてあるていど実を結んだ。現在でいうところの「和食」の誕生である。
余談だが、私はこの鎌倉時代から江戸時代までの日本の料理を「和食」とし、古代の縄文土器を使っての原始的料理から、明治以降のカツ、カレーライス、ラーメンにいたるまでの総称を「日本料理」と表現することにしている。
とにかく本膳料理は、精進料理の料理法を採り入れ、貴族社会の大饗料理に代わって、武家社会における正式の日本の料理の膳立となったが、やはり基本は「御成」といって部下が上司を自邸に招いての宴であった。そのために料理道が大躍進し、四條流、大草流、生間流、進士流などが腕を振るった。
料理は海の物、山の物、野の物、里の物の順序に並べるとか、献立は一汁三菜・一汁五菜・二汁五菜・二汁七菜・三汁五菜・二汁七菜・三汁十一菜まで多彩になった。
また本膳には真名箸と菜箸を併置され、右前に味噌汁、左前に飯、左向こうに鱠、左向こうに野菜の煮物、中央に香の物。二の膳は右側、三の膳は左側、本膳の右向こうが与の膳、その左が五の膳、与と五の間が向詰で魚の姿焼を置くようになった。
膳のあとに能狂言の演技も行われ、「後段」に麺類やさらに酒肴が続くこともあった。
映画『武士の献立』を観ると、この本膳料理の様相がだいたいつかめる。それにしても、ここでもやはり加賀前田家は将軍家代理の使者に気を遣っている。なにしろ、使者のご機嫌を損えば、お家のとり潰しになる時代である。つまりは日本には殿さまが部下を宴に招く伝統はない。あくまで招かれる方である。ここに日本では食事のマナーが発展しなかった原因がある。
安土・桃山時代に簡単な馳走「懐石料理」が生まれた。これは脚のない平膳「折敷」と利休箸を用いる。食材は旬・新鮮・良質の物を選ぶ。料理は、左に飯を少し盛り、右は汁椀、向こうには陶磁器に生魚を盛る。酒器は最初は漆器。汁のお代わりは好み次第。次に漆器の煮物椀。陶磁器の酒器では好みで飲む。途中、飯を食べてもよい。この後、盛合せ、和え物か酢の物の「強肴」。薄味仕立の小吸物「箸洗」。八寸。最後に漬物と湯桶という具合である。
時間は、寒い冬の早朝に催す暁の茶事。夏の朝五~六時の朝茶事。わりあい多い正午の茶事。冬の薄暮から夜にかけての夜噺。こうした季節と時間に適する料理を作ることになっている。
江戸時代に入ると、酒宴の席の料理「会席料理」が誕生した。最初は「茶会」に倣った「俳諧の席の料理」として始まった。中身は簡素で、礼儀正しく、酒は少量であったが、だんだんと宴会本位に変わっていって、本膳料理を簡単にした高級料理屋となっていった。
最後に、料理の色彩について一言。単純、かつ個人的な思いかもしれないが、和食は白、洋食は赤、中国料理には黄色のイメージがある。
洋食、中国料理のことはさておいて、和食の白は、天武天皇が主食を白いご飯と決めたためだろう。奇しくも、白は無垢で穢れのない色とされ、またニュートラルである。だから何色にでも変化する、あるいは取り入れる可能性をもっている。それがため日本の料理は色彩が豊かであるし、食器にも自由性がある。つまり、陶磁器、漆器、ガラス器、金属器、竹や笊、はては石や木の葉ですら、食器として利用する。これもご飯の力である。
よって、色彩の面からいっても、日本の料理、特に和食を決定させたのは、仏教を深く信奉した天武天皇ということになるだろう。
以上、この項も走馬灯を観るように眺めてみたが、とにかく禅宗系僧侶の帰国、ないし帰化が日本の食生活を変えたターニングポイントであったことだけは、ご理解いただけると思う。
さて、これからの課題である。
繰返すが、鎌倉時代の道元は、料理人の心得『典座教訓』と、食べる側の心得『赴粥飯法』の両者を述べた。それは、料理は作る人と食べる人が共同で作り上げるものだという思想だ。しかし、日本では御成のための宴であったため、食べる側の心得は育たなかった。
明治になって、岡倉天心も『茶の本』で茶の世界は点てる者と頂く者との共同によって生まれると解説したが、それでも茶の世界だけに留まり、一般の世界までは届かなかった。
とくに高度成長時代はひどかった。酒飲みは酒だけを飲み続け、料理には箸も付けない人がいた。なにしろ「肴は焙った烏賊でいい」という庶民美学がまかり通っていたぐらいだ。その隣にはタバコの吸殻を刺身用の醤油皿に山と積む人もいた。いま反省を込めて、それを言うと、たいていの人が「そんなのはごく少数派だろう」とおっしゃるが、そんなことはない。逆に多数派だった。
ところが、ここ五、六年の食ブームによって、やっと日本人も食べ方が上手になってきたとつくづく思う。それはたぶん、食について何かしら勉強し始めたからだろう。
料理人と食べる側が共同して、新しい食文化を創ってゆくのはこれからだ。
参考:第284話 お寺のごはん、マーガレット・トラブル著『碾臼』(河出文庫)、朝原雄三監督『武士の献立』、『老子』第12、35、63章、岡倉覚三『茶の本』(岩波文庫)、
〔深大寺そば学院 講師 ☆ ほしひかる〕