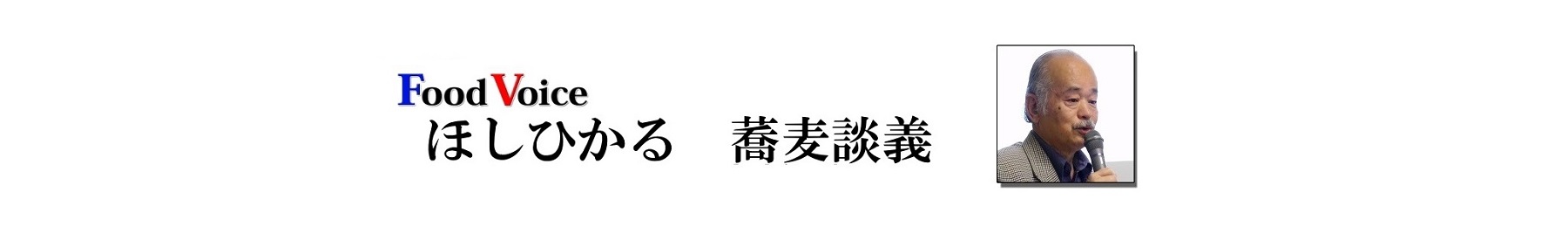第313話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅸ」
2021/11/11
~ A Lover’s Concerto ♪ ~
健と恵子はニューヨークのマンハッタン・ホテルで待ち合わせていた。
一足先にホテルに入った健は、テレビを見たり、ホテルの近辺を散歩したりしながら、恵子を待っていた。
テレビでは『Charlie's Angels』をやっていた。アメリカの人気番組で、女性たちのファッションやヘアスタイルの流行が、この番組から生まれているみたいな記事を日本の雑誌で見た覚えがあった。
また街を歩いていると、アメリカ、とくにニューヨークという所は世界中の人種が集まっているという思いを強くする。彼らは元は何処の国の人間か分からないが、みな母国語を使わないで英語で会話する。アジア人らしき人間でもそうである。
野中は、故郷を出て、東京にやって来た学生のころ、方言ではなく必死になって東京弁を話す努力をしていたことを思い出した。 (東京弁を話すことによって東京人になろうとしているのと同じ心理なんだろう) と何となく思った。
街ではファスト・フード店が目立った。山本先生は「〔マクガバン・レポート〕が発表されてから、日本の今の時代の食べ物が注目されている」と言っていた。また野中の友人で舞台の音響を仕事にしている男によれば、「日本のガール・ポップは将来軽音楽として人気が出るといわれている」と言っていた。
しかし、こうやってマンハッタンを歩いているかぎり、そんな感じは微塵も受けない。むしろニューヨークという大都会の活気からはアメリカ文化の勢いすら感じた。
部屋に戻った健は、大きな椅子に深々と座って、恵子が来るまで、ニューヨークの地図を広げて眺めていた。野中は地図を眺めるのが嫌いではなかった。というよりか、全体の位置や方向を確認しないと何となく落着かないところがあった。だから旅行するときはいつも地図を見る癖があった。
見てみると、ニューヨーク市も、東京の都内と都下のように、中心部と外辺部に分けられた。
中心部が西に流れるイースト・リバーと東のハドソン河にはさまれたマンハッタン島だ。その中の南がロウワー・マンハッタン、真ん中はミッド・タウン、北はアッパー・サイド地区。各々の都市景観はまったく違っていると聞いている。さらに眺めていると、ロウワー界隈にはチャイナ・タウン、リトル・イタリー、ソーホーなど、ロウワーとミッドタウンの間には、グリニッジ・ビレッジ、グラマシー、チェルシーなど聞き覚えのある地名があった。そしてアッパーはセントラル・パークを挟んで、イースト・サイドとウェスト・サイドに分かれていた。
それを南北にアベニュー、東西にストリート、斜めにブロードウェイが貫いている。
さらにアザー・ニューヨークとして、マンハッタン島北のハーレムと、島外にあるブルックリン、クイーンズ、ブロンクス地区がある。
島と陸をつなぐのはイースト・リバーに架かるブルックリン橋、マンハッタン橋、ウィリアムズ・バーグ橋、クイーンズ・ミッドタウン・トンネル、クイーンズ・ボロ橋、ということになる。何かにつけてよく聞く橋の名前だ。もちろんハドソン河にも橋は架かっているが、向こうはニュージャージ州になる。
(ふ~ん。) と思いながら見ていたが、ノックの音がした。
健は飛んで行ってドアを開けた。廊下に恵子がニッコリ笑って立っていた。南米人らしきボーイが荷物を部屋に入れてから、ドアを閉めるや健と恵子はしっかり抱き合った。
「やっと会えたっていう気がする。」二人は同じことを言った。
「お店の人は、日本へ向かった?」
「うん。」恵子は自分の額を健の額にくっつけたまま肯いた。
健は、会社の病院部の仲間とワシントンで開催された国際医学大会に来ていたが、他の連中は「日本はコールデンウィーク真っ只中だ。せっかくだから、」と言って、アメリカ各地へと散って行った。
恵子は、店の女の子たちとの年一回の海外旅行にカナダへ行っていた。
健は会社の連中と別れ、恵子は店の女の子たちと別れ、ニューヨークで落ち合う約束をしていた。
そしてニューヨークに行ったなら、ジャズクラブに行こうと話していた。
「疲れた?」
「大丈夫よ。」
「大丈夫じゃなさそうだよ。」
「いやだわ、分かる? ごめんね。あの子たち最後の夜はハメを外したように飲んじゃって、私を眠らせてくれないの。徳ちゃんなんか強くてね、あの子は底なしなの、もう大変。その上『NYには誰と行くのか?』って、しつこく訊くのよ。」
「フフフ。そりゃ大変だったね。少し眠ったら、」
「大丈夫よ。だからね、『一番大切な方と会うの』って言ってやったの・・・、」恵子はベッドの上にバタンとうつ伏せになって、「ふー、あなたと会ったら安心しちゃった。やっぱりちょっと眠ろうかしら・・・、一番大切な方! こっちに来て一緒に寝てちょうダ・・・、」言いかけたところで恵子は、睡魔に捕まってしまった。
恵子が目覚めたのはほぼ30分後だった。恵子はシャワーを浴びた。
「夕食に行こうか?」
「うん。」恵子はニューヨークでの予定は全て、健に任せていた。
その日のディナーは、ステーキハウス〔keens〕という店を予定していた。
タクシーに乗ったとき、健が思い出し笑いをした。
「どうしたの?」
「恵子の細くて長い首は日本にいるときだって冴えているけど、先ほどエレベーターに乗っていた女の人はきみの4.、5倍ぐらい太い首だったね。お尻なんか10倍ぐらいでかかったよ。」
「ま、どこを見てらっしゃるの。」
タクシーは店の前に停まった。健は料金とチップを渡した。
「アメリカはチップが面倒だね。店はここだ。」
店に入ると、天井にパイプがぎっしりと並んでいる。圧巻である。とても数えられないが、おそらく1万個ちかくはあるだろう。全体の雰囲気にも格調がある。店は会社の先輩に教えてもらった。1885年から続く老舗であるらしい。それにしても部屋が暗い。蝋燭だけの灯である。
恵子は健の腕に摑まって、椅子に座った。
ステーキを頼もうとして、お隣をチラリと見ると、白い皿に巨大なステーキが鎮座ましましている。
「われわれは、2人で1人前ぐらいでよさそうだね」と健が言って、ウェイターにそれを伝えようとするが、なかなか分かってもらえない。
英語を話せる恵子がそれを手助けしてくれたから、うまく伝わった。
すぐに、ワインとサラダ、そしてステーキがきた。さっそく塩・胡椒を振って、肉を口にする。
「こっちではよくサラダが出るわね。」
「うん。日本ではまだ少ないね。酢の物が日本のサラダっていうところかな。」
「ね。この前、洋子さんが作ってくれた酢の物は美味しかったでしょう。」
二人は、ナイフで肉を切って口に入れる。「美味しい!」(さすがに老舗だ) と恵子も健も思った。
ただ、たしかに肉は美味しかったが、塩・胡椒ぐらいの原始的な味付けでは飽きてきて、そんなに多くは食べられない。
日本のステーキハウスでは、適量のニンニクと一緒に焼いて、目の前の鉄板の上で食べやすい賽の目くらいにカットしてくれ、さらにはソースが美味しい。
あれは日本のステーキ、これがアメリカのステーキだな。
そんな健の話を恵子は微笑みながら聞いている。
「ごめん。オレはすぐこんな風に整理整頓しないと気が済まない性質で。」
「いいわよ。私にはない、あなたのそういうところが好きなんだから。もっと話して、」
「優しいな。」
「そうよ。私はあなたのことをもっと知りたいの。そのための旅行よ。あなたと二人っ切りで4泊5日も過せるのよ、嬉しいわ。」
恵子は、初めのころは「野中さん」、それから「健さん」と呼ぶようになっていたが、近ごろは「あなた」と言うようになっていた。最初は恥ずかしかったけれど、「特別の人」という感じがして、心地よかった。
店の隣の席では数名の若いレディーたちが談笑しながら大きな皿にのった巨大なレア肉を食べ尽くしている。そのずっと奥の若い恋人どうしも、その先のご夫婦も・・・。
「みんなすごいね。軽く平らげているよ。」健が声を落として感心したように言う。
恵子も釣られて視線を向け、肯いた。
「暗い所でさ、あんなに大きい肉をペロリと食べてる姿は、やっぱり彼らは狩猟民族、あるいは肉食動物そのものだね、われわれ農耕民族とは違うんだよ。」
「ほんとによくそういう風にまとめちゃうわね。感心します。」
「もしかしたら、バカにしてない?」
「ちがいます。恵子はあなたのことを尊敬してます。」
「男と女はソンケイするのではなく、カンケイするものだって、誰かが言ってたな。マキアヴェリかな。」
「え! マキアヴェリがそんなこと言ってるの?」
「ウソッ。」
「ンもう。」
「中学生のころに先生がさ、『桐一葉落ちて天下の秋を知る』って言ったんだよ。」
「何それ?」そう言うと、恵子は赤ワインのお代わりをした。
「天下の変化には必ず小さな徴候があるから、それを見逃すな、という意味だよ。これが頭の中に残っててね、ずっとモノの見方の一つになってるんだ。」
「へえ~、中学生で? オマセさんだったのね。」恵子はワザと両肩を窄めて笑った。「そのころのあなたに会いたかったわ。」
「ただの夢見るガキだよ。」
「その夢が私にはないのよね。」恵子はワインのお代わりをかなり重ねている。
「ところがね、うちのオーナー社長だけどさ、凄いんだ。」健は点けた煙草の煙を吹かしながら続ける。「これまで40年にわたる事業経営で得たエキスを大学ノート10冊くらいに、ビッシリ書き残してるんだよ。」
「へえ!」恵子の眼が光った。
健はそれに気付いて、(やはり恵子は経営者だナ) と思った。「さっき言った『桐一葉落ちて天下の秋を知る』みたいな名言がずらりと並んでるんだ。他に『便利、簡便、横着』とか、もういっぱいに・・・。出版すれば、『カーネギー名言集』より立派な書物になるくらいの。」
「横着には、どういう意味があるの?」
「人間の歴史は便利、簡便を求めて動いてきた。それは人間が横着だからってさ。分かりやすいだろう。」
恵子は真剣な目をして頷きながら、聞いている。
「それで、社長なりに難問にぶつかったとき、自分の大学ノートを捲り、問題解決のヒントを探すんだよ。」
「・・・・・・。」
「そんな姿を見て、オレも少しぐらい真似てみたいと思って、いろいろと整理したり、まとめたりするようになったというわけ。」
恵子は微笑みながら小さく拍手をする。「ね。恵子って、お付合してて、て、面白くないでしょ。」恵子の舌が少しもつれ始めたようである。
健はそんな恵子を見ながら笑って言う。「そんなことないよ、楽しくて仕方がないよ。」
「恵子にもね、いろいろ教えたくれた明子ママっていう人がいたの。その人がね、あなたの会社の社長さんみたいなことを言ってくれたの。」
「へえ、どんな?」
「商売は四つのン、ソロバン、ロマン、ガマン、ジョウダンが必要だって。そしてね、恵子にはソロバンとガマンはあるけど、ロマンとジョウダンが足りないと言われたの。言っときますけど、恵子のソロバンはケチっていう意味じゃないのよ、金銭感覚があるっていう意味なの。でも、夢やジョークがないって言われたのよ。」
「へえ。」
「いやだ、感心しないでちょうだい。」
「そうじゃないよ。ぼくにとっては、キミそのものが夢だよ、ロマンだよ。」
「どうもありがとう。あなたからの電波は恵子もちゃんと感じてます。」
「分かってるの?」
「分かってますよ。だから、恵子は嬉しいの、幸せなの。」恵子は上機嫌だった。健とここまで話ができたことが。「ネ、あなた。もうホテルに帰りましょ。」
「へい、へい。」
二人は椅子から立った。恵子の足元が少し危ない。健は恵子の身体を支えた。恵子が健の耳元に熱い吐息で囁いた。「恵子はあなたをソンケイしています。だから、あなたは恵子とカンケイしてちょうだい。」
「すごい。ジョウダンを言うタイミング抜群!」
「ふふふふ、あなたのせいよ。」
翌朝はホテルでモーニングを食べた後、イースト・リバーを観光する船に乗った。船はブルックリン橋の下を通る。その先にはマンハッタン橋が見えるが、その前で旋回して、河口のニューヨーク湾に向かった。
そこはマンハッタン島の入口になる。映画『ゴッドファーザーⅡ』では、1901年にシチリアのコルリオーネ村から逃げて来た少年ヴィトーが、ニューヨーク行きの船に乗り込み、エリス島にあった入国管理所を通ってマンハッタンへ上陸する。長じて、その少年がゴッドファーザーへとなっていく・・・。
船からでも古風なヨーロッパ調の屋敷というか、古城のような赤っぽい建物が見える。それが入国管理所である。
そのエリス島と並んでいるのが、「自由の女神」像が立っているリバティ島だ。
女神像が見え始めると、観光客は一斉にカメラを向けた。
「自由の女神」はアメリカの精神の表現であるといわれる。日本人の富士山のようなものだ。
健は、恵子に「〔自由の女神〕のようにトーチを持ったつもりで右手を上げて、気高く堂々と立ってみて」と頼んだ。恵子はその通りやった。
健は〔ニコン〕のシャッターを切った。
すると他の観光客も寄ってきて、バシバシとシャッターを押し始めた。
恵子が驚いて手を下ろすと、「No.No、まだポーズを続けろ」と注文したり、なかにはもっと違うホーズを求めたりする。
年齢のいった白人女性が恵子を手で指しながら、健に「Pretty Girl」と言ったので、健は「サンキュー」とお礼を言った。
頃合をみて、恵子は健の所に走って戻って、健にしがみ付いた。「ね、あの女の人、何か言ってたの?」
「君のこと、Pretty Girlだって。よかったね。おれだけの〔愛の女神〕が皆さんの〔自由の女神〕になっちゃったから、どうなることかと思ったよ。」
「まあ、憎いこと言うわね。」
船から下りた健は、「さっきウィリアム・バーグ橋が見えなかったから、行ってみたいけど、いい?」と言った。
「ソニー・ロリンズの橋ね。何処でもお付合しますよ。」
20年前ごろ公演活動を停止していたロリンズが、スランプを克服するためにウィリアム・バーグ橋の袂で、人知れずサックスの練習を重ねていたという話はもうジャズファンにとっては伝説となっている。
健と恵子は地下鉄の「Z」という線に乗ったが、驚いた。若者がギターを弾きながら、車両を歩いて来て、一曲終わると帽子を差し出すのである。お金を入れてくれというのだろうが、二人はアメリカという国は何でもありだと呆れてしまった。
「そういえば、この地下鉄の「A」が、デューク・エリントンの名曲【Take The A Train】のことだよ。」
「エッ! そうなの、びっくりだわ。」
「だろう。おれもさ、【銀河鉄道の夜】みたいな憧れをもってたけど、これがA Trainだったのかと、夢から覚めた思いだよ。ハハハ。」
そんな話をしながら、二人はとにかく橋までやって来た。
「ここでロリンズは吹いていたんだ」と健は、煙草とライターを取り出した。
恵子は、健からライターを取って煙草に火を点けてやりながら、「今度はどう? 憧れの聖地だった?」
「うん、ロリンズのサックスが聞こえるようだよ。分かってくれる?」
「分かるわ。あなたの顔にそう書いてある。」恵子は優しい眼差しで健を見ながら、ライターを返した。恵子の煙草は営業用だから、健の前ではほとんど吸わない。
健はライターをポケットに入れながら、「おれはジャズメンでも何でもないから、ここに来たかった理由はちょっと変わってるからね。」
「そうなの? 聞かせて。」
「小諸の〔懐古園〕って知ってる?」
「行ったことはないけど、名前は知ってるわよ。」
「そこに行ったときね、60歳ぐらいの乞食坊主みたいなが人が草笛を吹いていたんだ。藤村の〔千曲川旅情〕をね。
小諸なる 古城のほとり 雲白く 遊子悲しむ・・・・・・♪
それはね、もの哀しくて、胸に迫ってくるんだよ。まるで草笛のために作った曲のようだったよ。おれは、その人に話しかけたんだ。
そしたらね、昭和33年から今日まで、一日も欠かさずここに来て、草笛で〔千曲川旅情〕を吹き続けているって言うんだよ。その訳がね、島崎藤村を理解するためにって言うんだよ。おれはそのとき20歳、その半分ちかい7年間吹き続けているって言われて、その乞食坊主が何か大きなことをやろうとしている巨人のように見えてきてさ、震えたよ。」
恵子が健を抱きしめて頬摺をし始めた。「ああ、そのとき恵子も一緒に小諸に行きたかったな~。そしたら、震えるあなたを抱きしめて上げられたのにね」と言って笑い転げた。
「それはそれはどうもありがとうございます。でもさあ、明子さんという人が、きみにジョウダンの心が足りないって言ったというけど、そんなことないよな。キミはユーモアのセンスがたっぷりだよ。」
「ふふ、それはね、あなたといるときだけなの。ううん、あなたと愛し合うようになったからなのよ。」
「それはどうもありがとう。」
「それより、この橋下に来てみて何か神の啓示を感じた?」
「ナイ。まったくない。」
「ふふふふ。」
「ははは。」
「ほんとに、キミは楽しい人だよ。」
「それはそれはどうもありがとうございます。」恵子はペコンと頭を下げて、
「だからね、それはあなたのお蔭なの。」
「そんなことはないよ。」
「そんなことあるの。恵子はね、大学生のころから〝大人の女〟になるのを目標にして、すぐにママという仕事に一直線。いま思えば、恵子には〝青春時代〟がなかったの。それが、あなたを愛するようになってから、私は〝自由〟になったような気がしているの。それまでの私は堅苦しいだけの女だったのに、それさえも気付かなかったのね。お店の女の子たちが、あなたと一緒にいるときの恵子の顔を見たら、きっと驚くわよ。」
亡き父が恵子に言っていた〝幅〟とはアーティストとしてのそれだった。しかし健を愛するようになってから、幅にも〝人間としての幅〟というのかあることを恵子は知った。明子ママが「人間を成長させてくれるような恋をしなさい」と言ってくれたことがあった。恵子は今の自分がそうだろうと思った。それを恵子に贈ってくれたのが健なのだ、と思っていた。
「ごめんなさい。私、あなたの話の腰を折ったのかしら?」
「いいんだよ。ソニー・ロリンズより恵子の方が大切だからね。」
「ンもう、憎いこと言うわね。」
「さっき思ったけどね、あの乞食坊主はいまも草笛を吹いているだろうかってね。方や世界のソニー・ロリンズ、方や草笛を吹く無名の乞食坊主、二人とも自分の中から何かを見つけようとしていたんじゃないだろうか。」
恵子は両腕を組んで、眉を寄せて言う。「エヘン! 野中健君よ、小諸城址で草笛を吹いていたお坊さん、それから橋下でサックスを吹いていたソニー・ロリンズ、二人とも偉いがの、それよりきみの方がズンと凄いぞ。」
野中は呆れたような顔をして笑った。
「20歳のときの感動を10年間抱き続けて、そしてここにやって来たんだからの。しかも可愛い可愛い恋人と一緒にの、エライぞ。」
「だけど、おれのはただの遊び心だよ。そんなに偉いとか言われると、身体がムズムズしてくる。」
「それはイカン。どこがムスムズするか言いなさい。愛する恵子ちゃんが何とかしてくれるじゃろう。エヘン。」恵子は、少女のようにこんなにおどけたことのできる自分に驚き、恥ずかしくなって健に抱きついた。
夜は、グリニッジ・ブリッジにあるジャズクラブ〔Blue Note〕に行った。
「いよいよか」と健が期待を膨らませる。
今宵の出演者は第一級のミュージシャン、ハービー・ハンコックである。
その前の食事のとき、恵子は健に訊いた。「いつごろからジャズを聞いてたの?」
「高校のころからかな。小さなラジオでね。ラジオは曲を選択できないから、一方的に流れてくるものを聴くだけだよ。田舎の10代の少年に何枚もレコードを買うお金なんかないからね、ただただラジオから流れるジャズに、一人でしびれていたよ。
そのうちに、戦前のスイング系ジャズと、戦後のモダン・ジャズの判別がつくようになった。そのなかのモダン・ジャズ系にも、クール・ジャズ、ウェスト・コースト・ジャズ、イースト・コースト・ジャズ、フリー・ジャズなどの変遷があることもチョッピリ分ってきた。
で、おれが好んだのは、後から見れば、イースト・コースト・ジャズ=ニューヨーク黒人ジャズだった。」
健は続ける。「何しろ当時はニキビの高校生、何かを探そうとしている青春時代だからね。たぶん、古いジャズより、戦後生まれのモダン・ジャズの方に何かを期待していたのかもしれないね。大学を出たころかな、ジャズが好きな小父さんと知り合ったらさ、いろいろ教えてくれてね。その中で『1950年代、60年代のジャズは人類の遺産だ』っていう台詞を吐いたんだよ。それが妙に耳に残っていてね。」
「あなたは受信機がいいのよ。」
「そうかね?」
「そう思うわ。」恵子はほんとうにそう思っていた。ただ(それを活かしなさい)といったようなことは、何か姉さん女房のようで嫌だったから、それ以上は言わなかった。代わりに「高校生のとき、ニキビ出てたの?」とだけ言った。
「少しだけね、」
「ふふ、」
「何?」
「何でもない。ちょっと想像してみただけ。今度、あなたの子どものころのアルバムを見せて。ゼッタイよ。」恵子は甘えるようにしてねだった。
恵子は食事が終わると、正面の席から健の隣に移って座り、頭を健の肩に預けた。「高校生のとき会ってたら、こうやって二人並んで座って、ラジオから流れてくるジャズを聞いてたかもしれないね。」恵子は健の顔を見た。
健は憧れの所に来た喜びで、夢でも見ているような目をしている。
演奏が始まった。ハービー・ハンコックのピアノは切れがよくて、上品である。クインテットは「The Sorcerer」「One Finger Snap」「Jack Rabbit」「Watermelon Man」などお馴染みの曲を楽しみながら軽やかに次々とプレイする。
「いいね、いいね。ハービー・ハンコックの生だよ、しかもN.Y.の〔Blue Note〕でだよ。」健は上機嫌である。
恵子はワイングラスを傾けながら、思い出した。何かのレコード・シャケットに〔ブルーノート・レーベル〕を創立したアルフレッド・ライオンと二度目の妻のエピソードが書いてあった。妻の名前は覚えていないが、その女性はアルフレッドにベタ惚れだったのに、音楽が恋人のアルフレッドは全く気付いてくれなかった。しかたがないから音楽に夢中になっているアルフレッドを眺めることを楽しんだという。(その人の気持がよく分かるわ。) 恵子は一人で笑みを浮かべながら、悪戯っぽい目で健の顔をちらりと見た。恵子は健が可愛いらしく感じた。だから姉のような優しい気持になるのだが、それにハッと気付くと、自分が健より年上であることを誤魔化すかのように健に甘えるように強く縋りついた。
ハービーはエンディングに名曲「処女航海」の演奏を始めた。
「そのころから、きみは優しい美少女だった?」
恵子は酔っていた。「えっ?」(あ、そうか。さっきの高校時代の話か)と思って、「さあ、あまり優しい女の子ではなかったわね。」
「今は優しい女だよ。」
「だから、それはあなたにだけ、あなたにだけ・・・、」
「それはありがと。」
「どういたしまして。これからも、もっと、もっと優しくしてさし上げますわ。でもね恵子ちゃんは今、少し酔ってますの、だから今夜は甘えさせて~、」
翌日はブロードウェイでミュージカル『アマデウス』を鑑賞し、夜はウェスト・ビレッジのジャズクラブ〔Village Vanguard〕に行った。
そして、その翌日はとうとうN.Y.最後の日である。
二人は、五番街、マディソン街、ミートパッキング・ディストリクト辺りを歩いた。〔Tiffany〕〔Ralph Lauren〕 〔Calvan Klein〕〔Brooks Brothers〕〔Diane von Furstenberg〕など有名ブランドの店がたくさん並んでいる。
健は、こうしたブランド品にあまり関心はなく、ブランド名も映画でお馴染みの〔Tiffany〕以外はほとんど知らなかった。
「〔Tiffany〕か。」そう言って、映画音楽【Moon River】を口笛で吹いた。
しかし恵子の態度は違っていた。店内にいる恵子の姿は観光客のそれではなかった。まるで店のオーナーのように見える。しかもどの店に行ってもそうだった。似合っているのである。その上に身体から何かが発散しているのを健は感じた。それは、(恵子が時々見せる経営者の姿だ) と健は思った。
恵子は〔Brooks Brothers〕に立ち寄ったとき、健にジャケットか何かを買って上げようと思った。
今回のニューヨーク滞在費用について、恵子は自分が用意するつもりであったが、健は「費用は全部出す」と言ってきかなかった。恵子は、30歳のサラリーマンの給料がどのていどかは知っていた。しかし、健のプライドを傷つけてはいけないと思って、今回は甘えることにしたが、心苦しさが残っていた。だからといって、ここで 「買って上げる」 なんて言ったら、健はいい顔はしないだろう。
「ね、あなたに似合いそうなジャケットがあるわよ。」タイミングよく、恵子は健に似合うジャケットを見つけた。
「そうお?」
「これ買いましょうよ。」
「え?」
「恵子に任せて、お礼よ。」
「お礼?」
「うん。あなたの中学、高校、大学時代へ、恵子を連れて行ってくれたお礼よ。」
「子供のころのことを話しただけだよ。」
「それが嬉しかったの、恵子には。納得してくれる?」
「ま、何か言いくるめられた感じはするけど、ありがとう。」
健は健で、さきほどの恵子の雰囲気が気になっていた。自分の好きなことだけに恵子を振り回して、このファッション街で何かを得ようとしている恵子のことも考えて上げねばならないと思った。
夕方になって、二人は予定していたジャズクラブ〔Birdland〕に出かけた。
夜空には銀色の大きな月がイースト・リバーの上に浮かんでいた。
恵子は (あっ、満月だ。健と初めて結ばれたあの夜も隅田川の夜空に満月が浮かんでいた。) そう思いながらうっとりして暫く見上げていた。
野中もつられて見上げた。「イースト・リバーの満月か、いいね。【Moon Rever】って実際にあるんだね。」
「ほんとね。恵子、満月好きよ。」
「いいね、かぐや姫みたいで。でも『私、月へ帰ります』なんで言わないでくれよ。」
「あ、それっていいわ。そのときはあなたも一緒よ。」
「そうか、安心しましたよ。ハハハ」
「ふふ。」
二人は、〔Birdland〕に入った。
野中は(できれば今夜は早めにホテルに帰って、恵子の話を聞いてやってやろうか) とも思っていた。
しかし、イザ店内に入ると、すっかり興奮につつまれてしまった。黒人の女性ボーカリスト・カサンドラ・ジョーンズの力強い歌、トランペッターの誇りに満ちた顔、「ジャズはオレたちのミュージックだ」と言わんばかりの板に付いた演奏振り、そして客の歓声を聞いていると、やはり最後まで堪能したくなる。
恵子も雰囲気にのまれて興奮し、カクテルを何杯もお代わりしていた。
野中は10代のころからジャズを聞き始めた自分がタイム・スリップして今、ニューヨークでジャズに生で接してにいるという不思議さに感動していた。
時折、トランペットが悲痛に叫ぶ。これを聞く度に健は感傷で涙が出そうになる。
曲が変わった。ラテン系の〔Fenzy=恋の狂乱〕だった。テンポのいい曲だった。恵子は健を舞台の袖まで引っ張って行って、一緒に踊った。恵子は上手だった。しかも女性客の中では目立つぐらいきれいだった。
一曲歌い終わったとき、カサンドラが恵子を舞台に引き上げて、次の歌を一緒に歌った。曲は、驚いたことに恵子が好きな〔Lovin’you〕だった。
先ずはカサンドラが歌う。
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in the springtime
Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you
Lovin' you I see your soul come shinin' through
And every time that we oooooh
I'm more in love with you
La la la la la...
Doot-n-doot-n do doo
Ah...
恵子の番だと言われたとき、最初は英語で歌っていたが、途中から恵子は日本
語にした。
なぜってあなたを愛することそれは私の人生
そして私の一日一日は あなたへの愛で満たされてゆく
愛すれば あなたの心がはっきり見える
そして あの後はいつもあなたのことがもっと好きになる
La la la la la...
Doot-n-doot-n do doo
Ah...
歌う恵子の眼は涙に濡れていた。涙ぐんでいた。そんな恵子をカサンドラが背
後から抱きしめながら最後を歌った。そして歌い終わると、カサンドラは恵子の涙を吹いてやって恵子の唇にキスをした。
曲はガラリと変わってラテン・ロックになった。カサンドラは、美人でスリムな歌手だった。それが一旦歌い出すとエネルギッシュで、その女彪のようにしなやかな身体はセクシーであった。女性の恵子でも見惚れてしまう。舞台の上で、恵子は歌うカサンドラと並んで踊った。カサンドラは大歓迎、客も歓声を上げる。その熱気に応えてカサンドラはラテン・ロックを繰返して歌った。
観客は手拍子を叩き、踊り続ける。
恵子は (まだ帰りたくない、いつまでも二人でいたい。) そう呟きながら、髪を振乱し踊り続けた。
曲が終わった。
健は舞台の下まで恵子を迎えに行った。
恵子は子どものころ、盆踊りの日に舞台に立って踊ったことを思い出していた。踊り終わったとき、ニコニコしている父親に向かって飛びかかったことがあった。
歓声の嵐の中で恵子は舞台から健に飛び付いた。
健は恵子の身体を受け止めて抱き締めた。「大丈夫か?」
「うん。恵子、とうとう狂ったみたいよ。ふふふ。」
健は、そんな恵子を可愛い女だと思った。「みんな乗っていたよ。」
「そうお?」
二人は抱き合ったままであった。
そして、とうとう今宵のエンディング、恵子と健にとって、ニューヨーク最後の夜は「ラバーズ・コンチェルト」の曲で締められることになった。
力強い愛の歌である。カサンドラは高らかに歌う。観客も全員立ち上がって一緒に歌った。熱気の渦である。暗い中で、何組もの恋人たちが抱擁して離れようとはしなかった。恵子と健も抱き合って踊っていた。
「ねえ、あのコ、恵子のことが好きみたいよ。さっき本気でキッスされたわ。」
「ナニッ、あのコって、歌手の? それは困るな、あのコはオレのライバルだな。」
「ふふふ、妬いてる?」
「少しね。」
「嬉しいわ。」
「恵子、おれは間違っていたよ。」
「なんで?」
「おれは小諸の草笛やニューヨークのジャズが一番だと思っていたけど、違うな。おれの最高の音楽は、恵子の〔Lovin’you〕だよ。」
「ア・・・」ありがとう、と言いかけたとき、恵子の唇は健によって突然塞がれた。
健は恵子の舌が痺れるまで放してくれなかった。
カサンドラが舞台を下りる前に手を上げて叫んだ。「Hey Boy! Take good care of a lover!」
「ふふ、あなたによ。『恋人を大切にしなさい』だって♪」恵子は健の手を掴んで高く上げた。
カサンドラは恵子と健に向かって投げキッスをして舞台から去った。
その夜、恵子と健は一晩中、抱き合ったまま離れなかった。
(Ⅹ.〔去りし君へのバラード〕へ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕