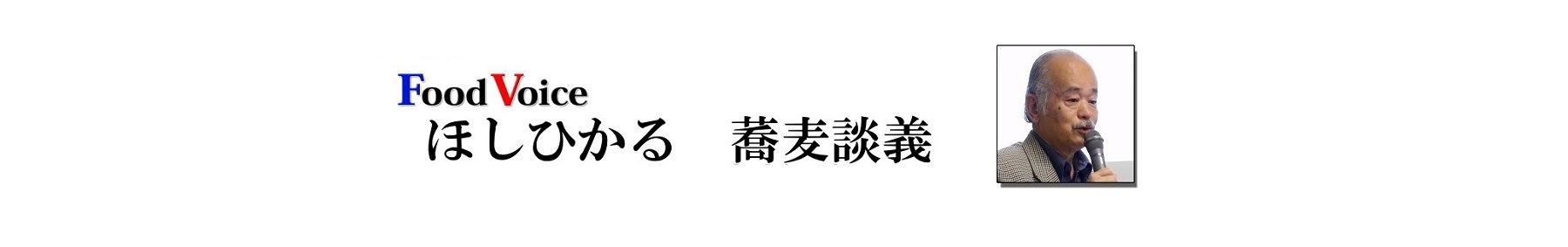第345話 小説「コーヒー・ブルース- XVII」
2021/11/12
~ My One and Only Love ♪ ~
野中がシステムのテストを依頼したのは、近所のかかりつけ医の小川クリニックだった。といっても〆鯖を食べて中ったときに飛び込んだていどであったが、以来親しくしていたので野中が頼むと、「面白そうだな。テストならいいよ」と二つ返事で了解してもらった。
野中は古賀と共に、東長崎の小川クリニックへパーソナル・コンピューターを運んだ。
野中が「小川クリニックを」と思ったのは、二つの理由があった。一つは小川院長の手堅い経営法だった。院長は、どんなものでも新規導入については、半年に1件しか採用しない方針をとっていた。それは院内のスタッフが新しい物事を十分理解し、十分使いこなすためには、そのくらいのペースが最適だという考えからだあった。そういう院長だから、野中たちのシステムについても何かいい考えを供してもらえるのではないかという期待があった。
もう一つの理由は、小田社長の言葉だった。「今までのような製薬会社と医者の関係ではない、新しい関係を見つけろ!」これは魅力的な考え方であった。そういう関係を見出すためには、野中のかつてのお得意先ではない方がいいと思ったからであった。
クリニックの診療が終えたころ、野中と古賀はシステムを診察室にセットした。
古賀たちが開発しているシステムは、①臓器のイラストが瞬時に表示されるシステムと、②検査データがグラフによって表示できるシステムと、③レセプトがコンピューターによって計算できるシステムであった。
③は事務機能であるが、①と②は患者さんに見せるためである。だから、コンピューターは診療室に置く必要があった。
院長も、看護婦たちも野中たちが持ち込んで来たパーソナル・コンピューターを興味深い目で注視していた。
コンピューターのメーカーは〔ハート〕といった。ハードウェアの「ハー」とソフトウェアの「ト」を取って付けられた社名だというが、日本で最初にパーソナル・コンピューターを発売したベンチャー企業として新聞、雑誌を賑わしていた。
その〔ハート〕のパーソナル・コンピューターを選んだのは古賀だった。古賀は〔ハート〕の篠塚社長に憧れていた。
古賀は大事そうにパーソナル・コンピューターをセットし、その後に小川クリニックのレセプト一カ月分の入力を始めた。
業界関係とは面白いもので、医師と製薬会社の者の間には、暗黙の信頼関係がある。医療機関は製薬会社の人間になら、大事なレセプトを無条件で預ける。
ではあるが、そのデーター入力は大変だ。「コンピューターはデーターがなければただの箱」とよくいわれる所以だ。
院長は「今日は往診が多いんだよ」と言って、自転車で出かけた。
古賀は入力作業を続けた。横顔を見ると、頰が紅潮している。張り切っているようだ。
野中は古賀一人を残して、クリニックを辞することにした。
野中は会社に戻る前に、池袋のデパートに立ち寄った。
「人が集まる所を見てこい。デパート、スーパー、劇場・・・。そこに人はなぜ集まるのか?」小田社長の口癖である。おかげで新規事業部の者は何もすることがないときや迷ったときにはデパートへ行く癖がついていた。野中もそうだった。
野中は店内を見て回っていいるうちに、万年筆のインクが切れていることを思い出した。文房具売場は7階であることを知っていたから、エレベーター乗場へ行った。壁にも7階が文房具売場であることを表示してあった。野中は何となく後を振り向いた。すると、そこにはファミリー・コンピューターに似た器械の売場案内器が設置してあった。遊び心が生まれた野中は、乗場から離れて器械を操作してみた。
「開始しますか?」→「はい・いいえ」→「ご用件を選択してください」→「1・2・3・4・5・・・」→ 「はい・いいえ」→「はい・いいえ」→ → ・・・ 。少しもどかしく感じながらも操作を続け、万年筆売場の表示に辿り着くまで10分以上かかった。
それから野中は、受付嬢が立っているカウンターの所に行って、「万年筆のインク売場は何処ですか?」と訊いてみた。
即座に、笑顔の受付嬢が「ありがとうございます。万年筆用のインクでございますね。売場は7階でございます。あちらのエレベーターに乗って頂きますと、下りた所が売場でございます。」と丁寧な手振で案内してくれた。
全館の売り場表示の掲示板、質問に即答する受付嬢、それに引きかえ器械による案内のもどかしさとバカバカしさ。普通なら笑ってしまうところであるが、野中はそれどころではなかった。いま進めている事業のことを考えると、ショックだった。野中は、インク売場に行くことすら躊躇し、脚が止まってしまった。
野中は心配になって考え込んだ末、近くにある電化製品の大型量販店に足を向けた。店内に入ると冷蔵庫が並んでいる。札に赤い字で10万円と書き殴ってあった。アパートの冷蔵庫も買い替えなければなと思いながら、電化製品を手当たり次第に触って歩いた。電気釜、洗濯機、掃除機、テレビ・・・、全てスイッチ一つでオン ・オフ。簡単である。
次に、コンピューターのフロアーに行った。だいたいハードウェア100万円、プリンター100万円の値札が付いている。さらにソフトウェアは100万円が相場であろう。
このとき野中は考えた。 (そうか。パーソナル・コンピューターは情報機器なんだ。ただの便利・簡便・横着を求める電化製品とは訳が違う。さっきのデパートのファミリー・コンピューター型の案内システムは使い方が間違っているんだ。) そう思うと、やっと胸の痞えが消えるような感じだった。
(今の今まで、コンピューターの基本中の基本に気付いていなかったナ。) そう思いながら、野中は店を出て、電車に乗った。そして呟いた。「ユースウェアか。」前に、古賀が言ったことがある。「ユースウェアという考え方があるそうですね。」その物を使用するには、考え方や使用体制を確立する。そんな考え方である。小川院長の考え方もそうであるのかもしれなかった。
「ハードウェアはよし、ソフトウェアは今テスト中、ユースウェアか。」野中は電車に乗るといろいろと考えを巡らせるタイプだった。「パーソナル・コンピューターを使った新しい診療スタイルを編み出さなければ・・・、」吊革にぶら下がりながら、野中は一人言を口にした。
すると、前の座席に座ってスポーツ紙を読んでいた男性が「何だ」というような目付でジッと観た。
そんなことにも気付かない野中は、吊革をしっかり握りながら、以前に岩崎が言った話を思い起こした。
「そのころになると、ドクターのデスクの上にパーソナル・コンピューターが置いてあって、ドクターは診療開始前にスイッチを入れる。そうすると患者さんから電子メイルがきている。コンピューターには患者さんのこれまでの病状や検査データが蓄積されている。ドクターはそのデータを見ながら、患者さんの質問に回答して上げる。」
(やっぱり、これだな。パーソナル・コンピューターは、ドクターの秘書だ。それが「情報化医療」だ。)
岩崎はこうも言った。「21世紀は情報社会というけれど、情報とはinformation itelligenceのことばかりではない。コンピューター化、IT化ということにも目を向けなければならない。もっとはっきりいえば、僕たちの周りはコンピューターだらけになる。そうなると、将棋や囲碁の名人とコンピューターと勝負すれば、どちらが勝つか? なんていうバカなことを言い出す者も出てくるけれど、それは車と人間で100mの競争をするようにバカバカしいことだ。人間が車を乗りこなしたように、人間はコンピューターを使いこなさなければならない。」そのときの岩崎の表情には強い志が溢れていた。
(そうなんだ。だからパーソナル・コンピューターはこれからのドクターの秘書だ。入力作業が一段落したら、パーソナル・コンピューターをドクターの秘書とする診療スタイルについて、古賀と一緒に考えなければなるまい。)
翌日。野中は、小田社長に呼ばれた。
用件は「情報医療プロジェクトを子会社にしろ」ということだった。
野中は狼狽した。実際には「検討しろ」という言葉だったが、野中には社長の意図がよく分かった。「製薬会社と医療機関という関係とはちがうビジネス関係を創れ、そのためには子会社にしろ」ということなのであろう。社長の思うところはよく分かる。だが、会社経営なんて経験がない。
しかし、それを言っても、「僕も経験はなかった。でもできた。僕にできて、野中にやれないことはない。野中ができないと思っているだけだ。目的に目を向けろ。過去の経験ではない。意識を変えろ。自分を変えろ。」と、相変わらずの檄である。野中は「分かりました」としか返事せざるを得ない。
すると社長は「約束したらなら、死んでも約束を破るな。」
「はい。」
「返事はいい。やるのだ。」
「・・・・・・。」
「いいか。経営者は絶対社員に給料を出さなければならない。その社員には家族がいる。だから絶対給料は欠かせない。それが雇った者の責任だ。それから、会社経営は給料だけではない。その3倍の経費が要る。10人の社員がいる会社は、30人分稼がなければならない。だから売らなければならない。売れるものを開発しなければならない。そして決め手はナ、」
「は?」
「ボクシングや相撲を観たことがあるか?」
「はい。ボクシングなら、後楽園で、」
「そうか。何よりも、相手を叩きのめす気持が必要だ。野中は優しすぎる。」
「・・・・・・。」
「まあ、それも長所だろうが、それは格好付けているからだ。野中の後に付いている者のことを思え。それが経営責任だ。」
野中はグーの音も出ない。社長室から出た野中の眉間は皺が立っていた。しかし野中の胸の内は、社長に煽られたせいか、逆に燃えていた。(コノヤロウだな。やるしかないじゃないか・・・。)
これまでもエリザベスは、恵子にファッション誌『NY』の編集長ダイアナ、ジャーナリストのウィルソン、カメラマンのトミーを紹介してくれたり、大小のファッションショウやアンダーウェアのショウに一緒に行ってくれた。
しかし、それより何よりたくさんのデザイナーたちに会わせてくれた。そして今日は、NYにあるデザイン・スクールに連れて行ってくれた。
校内を行き交うデザイナーの卵たちは、歩きながら熱っぽく、明日のデザインを捲し立てている。
恵子は、そうした若い生徒たちを見て楽しくなった。
エリザベスは、院内にあるティルームで講師にも会わせてくれた。
中年の女性講師は「つまるところデザインは、時代によって足したり、引いたり、あるいは丸っぽくしたり、四角っぽくしたりの繰り返しだけど、その中から新しさ、ユニークさをどう生み出すかなのよ、」とそのポイントを語ってくれた。
恵子は「確かにそうだわ」と頷いた。そして学院を出て、道すがらエリザベスが口にした台詞も恵子にとっては、ファッションの目的を明示しているようすかのように心に残った。
「オシャレは女の嗜みよ。」「ファッションは私たちを別人にしてくれるのよ。だからある意味、元気の素なのね。」
エリザベスは、異国からやって来た恵子にわが娘を見るような慈しみのある目を向けながら、ファッションにおいては業界全体の構造を見せようとしていた。それは明子ママのやり方とはまったく違う方法であった。
(大学を出たころの私には明子ママのやり方がよかったけれど、三十半ばの今の私にはエリザベスのやり方がふさわしい。) そう思うと、振り返って自分は徳子に何にもして上げなかったことを悔んだ。
恵子がアパートメントに戻ったとき、桃子から電話があった。「今、アメリカの西海岸にいるの。」ご主人の忠夫さんと一緒に、アメリカ大陸横断鉄道に乗って、ニューヨークへ向かっているという。
「えー、ほんと。嬉しいわ」恵子は上ずった声をあげた。
3日後、夫婦は恵子の所にやって来た。途中シカゴに寄って来たらしいが、ご主人の忠夫さんは鉄道ファンらしく、アメリカ大陸横断鉄道に乗りたくて、桃子姐さんが「恵子さんの所へ行く」と言ったら、「オレも行く」と言い出したという。
「おかげでお店は全休よ。」と文句を言いながらも、久し振りの夫婦旅行に二人とも満更でもなさそうな顔をしていた。
そんな二人はダウンタウンにホテルを予約していたが、結局桃子姐さんは、3日間も恵子のアパートメントに泊まることになった。
二人は抱き合って再会を喜んだ。
「さすがの銀座でナンバー1の恵子ママも、赤ん坊には勝てないわね。だいぶ横綱級になってきたわよ。徳ちゃんたちが見たら、目を丸くするわね。」
「私自身が信じられないくらいよ。」
「恵子さん、見ると優しい顔付だから、赤ちゃんは女の子ね。」
「そうなの?」
「たぶんそうよ。でも思ったより元気そうで、安心したわ。」
「おかげさまで。恵子ってほんとうに人様に恵まれていると思うの。こうやって桃子姐さんに来て頂けれるし、」
「だから、恵子って言うんじゃないの。」
「まあ、ふふふ。」
「でも、ご主人が鉄道ファンでよかったわね。」
「まるで子供よ。サンフランシスコのケーブルカーに乗ったときは、小学生みたいにはしゃいでいたわ、恥ずかしいくらい。」
「ふふ。それも夫婦善哉?」
「まあね。それにしても、ほんとうに驚いたわ。日本を離れるとき、恵子さんは悲壮な覚悟が漂っていたわよ。」
「それは確かよ。この児をアメリカで一人で産もうと覚悟はしたものの、無事に産めるかしらって本当に不安でしたもの。そしてその先には、一人で育てていかなければという心配がいっぱいで押し潰されそうでしたわ。だから、最初のころは、夜になるとあの人のことを思い出し、狂おしいほど寂しくなることが多かったわ。」
「かわいそうに、」
「でもお蔭さまで、いい病院と、エリザベスといういい人と巡り会えて、だんだん心が落着いてきたの。今では自信がもてるようになって、面白いくらいよ。外国に来て世界観も広がったみたいだし、」
「NYっていう所がよかったのよ、きっと。たった数日だけど旅をして、アメリカっていう国が何となく分かるわ。自由というか、女でも一人で生きていける国っていうか。とにかく日本と違うわね。」
「それもそうね。でも恵子が思ったのは、反対のことなのよ。」
「えっ、」
「この子を産んだら、あの人にプロポーズしたいの。」
「ンマア! そこまで自信がついたの、驚いたわ。」
「あの人と離れたものの、というよりも離れたこそ、やっぱり離れられないと思ったの。My One and Only Love よ。」
「ヒエー、ごちそうさまだわ。」
「ふふふ。」
「でも、そこが〔美薗恵子〕かもね。」
「桃子姐さんは、それをよく言うけれど、どういうこと? 分からないわ。」
「そうね。貴女は、人を信頼するところがあるのよ。だからいい人と出会うのよ。だからまた人を信頼できるの。普通は、それを善良な人と言うけれど、貴女は善良というよりもうちょっと上の品格みたいなところが備わっているのよ。だから、銀座でよかったのよ。新宿だったら、うまくいったか、どうか分からないわ。」
「・・・・・・、」
「これからやろうというファションも、いいわね。貴女にお似合いだと思うわ。ただし、高級な世界がいいわよ。」
「心がけます。」
その日、桃子姐さんはマンハッタン観光のために、忠夫が待つホテルに戻った。
そして、恵子が結婚を決意したことを何より喜んでいるため、それを旦那に報告した。
すると、忠夫は腕を組んで、珍しく一言加えた。「う~ん。産んでからより、その前にプロポーズする方がいいじゃないのか。男はナ、女と違って、生まれてくる子に自信がもてない。だから言うなら、早目に言った方がいい。」
「あんたもそうだったの。」
「バカ、結婚していない場合だよ。『突然、貴方の子です』と言われても、戸惑うだけだ。しかも半年も経ってるんだろ? 下手すれば、こじれる。」
「そうかあ。」
「それからな、恵子さんより、野中さんからプロポーズするようにした方が長続きするよ。子を宿したことで女の覚悟は並大抵のことでないことは分かる。しかし、男はそうはいかない。だからそれに代わる覚悟の場があった方がいい。」
「あんた、凄いよ。あんたが亭主でよかったわ。」
「何だいそりゃ。褒めているんだろナ。」
「もちろんよ、チュウして上げるわ。」
「よせよ、照れるじゃないか。」
「ここはアメリカよ、みんなやってるから平気よ。それより、これからどうすればいいの。」
「お前がお節介役になるんだな。」
「野中さんにプロポーズさせるわけね。」
「そうさ。」
その夜、桃子はこの話を恵子にもって行った。
「そ、そうなの。恵子もおばかさんね。」恵子は俯いた。「あの人の立場をちっとも考えていなかったのね。」
「そんなことないわよ、恵子さんの覚悟が分かったからこそなのよ。」
「でも・・・、」
「で、ちょいと聞くけどさ、どうしてNYで出産しようと思ったの。」
「それはここが、あの人と恵子とこの児にとって運命の地だからなの。」
「ははあ、なるほどね。」
「そういうことなの。」
「分かったわ。ここはあたしに任せて。何しろ恵子さんの妊娠に気が付いたのは、この桃子姐さんだからね。」
野中は小川クリニックの他に、もう一軒テスト機関を探していた。(木村病院を) とも思ったが、(本格的なことを依頼するときのために、とっておこう) と考え直して少し待つことにした。そんなとき、遠藤医師から連絡があった。「西銀座クリニックの院長の了解をとったから、パーソナル・コンピューター・システムを設置していい」という。ただし遠藤医師の患者さんだけということだったが、古賀は「それで十分です」と喜んだ。
たぶん山本部長がそれとなく遠藤医師をプッシュしてくれたのだろう。
古賀は、2軒のテストに追われた。その作業の中で、古賀は仮称としてシステムのことを〔ケア・システム〕と呼んでいた。
しかし小川院長にも、遠藤医師にも、その意思は伝わらず、二人とも「パーソナル・コンピューター」としか言ってくれなかった。
それを見て、野中はシステムにきちん名前を付けた方がいいと思った。(何か、いい商品名はないか? 部内では〔情報医療システム〕という言葉を使っていたが、それは事業目的名である。) 野中はまた電化製品の量販店やデパート、本屋などを巡った。その末に手塚治虫の『ジャングル大帝』の白いライオンが目に入った。子供の名前は〔レオ〕。可愛いかった。父親ライオンは品格があって強そうだった。野中の頭に〔レオネス・ケア・システム〕というネームが閃いた。野中は公衆電話を見つけて、会社にいた古賀を外に呼び出した。
「どうだ。〔レオネス・ケア・システム〕というのは?」
古賀は、野中が「ケア・システム」という言葉を使ってくれたことで、嬉しそうな顔をした。「カッコいいですね。」
「それから、社長は小会社にしろとおっしゃっている。もし、そうなったときの社名は〔ケアネット〕でどうだい。」
「いいですね。われわれがやろうとかるのは医療じゃないですからね。」
「たろう。じゃ、これで決まりだな。」
野中と古賀は、水割で乾杯をした。
その夜、気分がよくなった健は恵子のマンションで、お手伝いの洋子さんがいつも淹れてくれている珈琲を温めながら、エラ・フィツジェラルドの「My One and Only Love ♪」を聴いていた。
このとき、電話のベルが鳴った。電話は神楽坂の桃子姐さんであった。「野中さん、お久しぶり。お電話したのはね、先週までアメリカに行ったのよ。それでね、NYで恵子さんに会ったの。」
「え!」
「恵子さんのことで話があるから、お会いしましょうよ」と言う。
「何事だろう?」(桃子さんは知らない仲ではない。でも、電話してくるなんて珍しい。NYにいる恵子に何かあったのだろうか? いい話か? 悪い話か?) 健の胸の鼓動は激しくなった。
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕