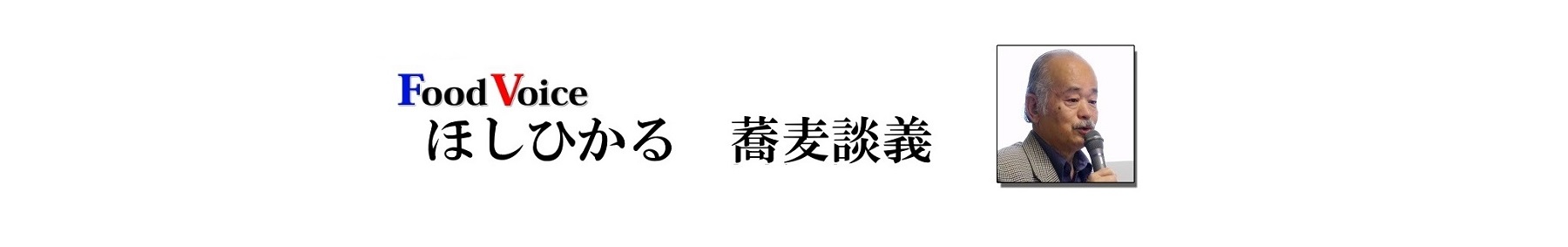第111話 石臼があった!
~ 中国麺紀行③ ~
☆萬里の長城
北京から北東へ230km、車で約3時間、世界遺産で知られる避暑山荘のある承徳市へ向かう。
途中、私たちは萬里の長城の金山嶺に登った。登山口からゴンドラで15分、標高1,000mの嶺に着くと、あとは徒歩。
すぐに煉瓦造りの長城が険しい嶺に衝立を立てたように遙か彼方まで続いているのが見えた。よく長城は「龍が昇るよう」と例えられるが、その通り。凄い! 普通は1物1枚ぐらいしか撮らない私だが、ついつい興奮してカメラのシャッターを押し続けた。これまで幾つもの世界遺産や、名所・旧跡を見てきたが、この萬里の長城ほどの感動はなかった。なぜだろうか。彼方まで連なる山波のせい? そんなはずはない。たかだか標高1,000mでないか。長城のせい? そんなはずはない。これまで姫路城、大阪城など立派な建造物をたくさん見てきたではないか。
萬里の長城は、東端の遼寧省虎山から西端の甘粛省嘉峪関までの総延長8,900kmもあるという。日本列島を何往復もするほどの、とてつもない距離のせい? そうかもしれない。長城は、最初は紀元前の秦の始皇帝が造り始めてから、明時代までの約2000年にわたって造られてきたという。そのとてつもない年数のせい? そうかもしれない。


 【萬里の長城 ☆ ほしひかる 絵】
【萬里の長城 ☆ ほしひかる 絵】
紀元前221年の秦王が史上初めて中原を統一し、初めて「皇帝」と称した。だから、彼は「始皇帝」と呼ばれる。始皇帝は国土の縄張りのため、また異民族の攻撃から護るため、防壁として長城を造り始めた。それは有効な策であった。が、皮肉なことに、北方民族にとってもそれは越えるべき目標となった。王の中の王になるためには、①長城を越えること、②皇帝を名乗ること、というヤル気をもたせることにもなった。ある意味では〝矛盾〟の誕生であった。以来、長城をめぐって漢民族と北方民族 ― 匈奴、契丹(遼)、女真(金)、モンゴル(元)、満州(清) ― との攻防は続いた。「歴史ロマン」と言ってしまえば美しすぎるが、2000年間に流れた汗血は大河の量を越えるだろう。その矛盾する攻防遺産はまさに中国そのものである。イヤ、この矛盾は決して中国のものばかりではないだろう。人間がもつ矛盾である。だからこそ、宇宙からでもその姿がキャッチできるのである。もしかしたら、毛沢東はそのことを看破して、あの「矛盾論」を書いたのではないだろうか、と思ったりした。
☆承徳市 避暑山荘
清国も、定石通りに①長城を越えること、②皇帝を名乗ること、を目標として動いた。初代ヌルハチ汗は「後金」を建国した。2代ホンダイジは国名を「清」と改め、「皇帝」を名乗った。そして3代目の順治帝のとき、清は萬里の長城を越えて明国を滅ぼし、北京入りを果した。ただし、順治帝はこのときわずか10歳、実際の偉業を成就したのは叔父のドルゴン王であったことは別稿「紫禁城の夜明け」に書いた通りである。ドルゴン王のすべての政策は、成人した順治帝に、ただ1点だけを除いては全て受け継がれた。継がれなかった1点とは・・・・・・、亡きホンダイジの弟はドルゴン王、息子が順治帝であったが、ドルゴン王は兄が亡くなったあと、兄の妻を娶った。それは狩猟民族である満州人には普通の慣習であった。つまり遺族を引き受けたのである。しかし、北京入りして儒教にどっぷり浸かった順治帝にとっては、母を〝盗られた〟ことが許せなかった。だから、順治帝はドルゴン王の死後、王の実績を抹殺し、関係者を追放しようとした。これに反抗したのが、ドルゴン王に協力して明国を攻め、その後に半独立国家として認められていた呉三桂 (拙著「紫禁城の夜明け」に登場) をはじめとする3人であった。彼らの統治するクニは雲南、広東、福建であったが、これを「三藩の乱」という。この抵抗には順治帝は手を焼いたが、跡を継いだ若き皇帝4代康煕帝はそうではなかった。若いにもかかわらず康煕帝は喧嘩のやり方を知っていた。皇帝は『三国志』を暗記するほど読みこなし、そこから政治的駆け引きを学んでいたのである。そんな眼で見れば、父順治帝から仕掛けられてからはじめて抵抗するような呉はたいした男ではなく、それに70歳に手が届くほどの高齢である。放っておいても3~5年で崩れるにちがいない、とゆとりをもって見ていた。この悠々たる態度が就いたばかりの皇帝をジッと観察していた、部下や敵を威圧していった。彼は戦わないうちから勝っていたのである。果せるかな、康煕帝は三藩を滅ぼし、初の皇帝試験にパスした。・・・・・・かどうかわからない。 しかし結果的には、最強の中央集権国家を創り上げたのだから、もし康煕帝を材に小説を書くとすれば、こういう人物だったろうと私が勝手に想像しただけである。
私たちが訪ねた承徳市の避暑山荘というのは、その康煕帝が建てた離宮である。三藩の乱の最中の1677年、康煕帝は内モンゴルの木蘭(mulan)を訪れた。そこは柳や白樺の大樹や草がうっそうと茂り、猪、虎、狼、豹、熊、鹿、狐、大山猫、山荒などの野生の獣が闊歩していた。昔は鹿の肉を喰い、鹿の血をすすったという満州族の血が騒いだのか康煕帝は、ここに皇室専用の狩猟場を作ることを計画した。そして、その途中の「熱河」あるいは「承徳」とも呼ばれる地に別荘を作った。それが避暑山荘である。
工事は康煕帝の1703年に始められ、6代乾隆帝の1790年に完成した。
私は、山荘内の湖を見て、園内を歩いた。そのときに、ピョンピョンと地面跳ねている数羽の鵲と出会った。懐かしかった。鵲は清の皇室・愛新覚羅家の祖であるという (参考「紫禁城の夜明け」) 。中国北部や朝鮮半島にしか生息しない留鳥であるが、ただ特別に私の故郷佐賀にはいる。それは秀吉が朝鮮を攻めたとき、兵の誰かが鵲を掴まえて連れてきたからだという。カチカチと鳴くので、子供のころは「カチガラス」とか、「カラス」とか言っていた。というよりか、てっきりカラスはこれだと思っていた。それが小学校の遠足で佐賀市から外に出たとき、初めて黒いカラスを見て、びっくりしたものだった。その佐賀の鵲も、今では黒いカラスに追われて少なくなってしまった。だから、つい「お前、ここにいたのか」と避暑山荘の鵲に声をかけたほどであった。
この山荘に康煕帝と乾隆帝は、毎年旧5月から9月は避暑し、政治を行い、大典を挙行、そしてモンゴルやチベットの王候貴族に謁見して、さらには狩をした。
その間、溥仁寺、溥善寺、普寧寺、安遠廟、普楽寺、普陀宗乗之廟、殊像寺、須弥福寿之廟の外八廟の寺は様々な事件の記念として建立された。
ご覧の通り、われわれ日本人には馴染みのない異様な建物群である。それもそのはずモンゴルやチベットの征服記念、あるいはその王候貴族に謁見するために建てられたチベット様式の寺や廟だからである。
それにしても、見よ! この獅子の爪の鋭さ、それに比べれば日本の狛犬クンなんて可愛いものだ。仏様も獅子も、日本に渡来すればみんな温和に優しくなる。
 【飛び入り参加 ― 浦賀・叶神社の、恥ずかしそうに隠れている狛犬クン】
【飛び入り参加 ― 浦賀・叶神社の、恥ずかしそうに隠れている狛犬クン】
さてさて、今日のランチは避暑山荘に隣接する大酒店であった。最後に押し出し麺も出たが、それよりもわれわれの目をひいたのは店の入口にデーンと置いてあった大きな石臼であった。それを見て、さすがは「そばの会」の皆さんである。飛び付くように石臼の写真を撮った。
世界三大穀物の米、小麦、トウモロコシは、だいたい世界の1/3ずつの人々がそれを主食的に食べている。うち、米は粒にしても、粉にしても旨いから、普通はわざわざ粉にしないで粒のまま食べる。ところが、小麦は粒のままだとあまり旨くないのに、粉にするととたんに美味しくなる。誰が粉にする石臼を作ったかはわからないが、とにかく中国には漢代に、小麦と共に「石製手回し磨り臼」が西域からが伝わった。その後、三国時代に「役畜石臼」が見られ、晋代に「水力石臼」現われた。そして唐代には、「碾磑」が作られ、粉食が盛んになった。特に華北では小麦の栽培が適していたため日常的に食べるようになったが、中国の偉いところは西アジアやヨーロッパのようなに焼かないで、蒸したり、茹でたりして、饅頭や麺を発展させたことである。
そんな石臼は、日本にはやっと鎌倉時代に入ってきた。そして麺が定着し、日本も≪麺文化 同盟国≫入りをしたのである。
ともあれ、目の前に堂々として坐す石臼が、なぜ、どのような理由からここに飾ってあるのかは知る由もないが、印象としては粗っぽい石臼のような気がした。
そして、これから向かう蕎麦処を予感させる石臼だった。
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕