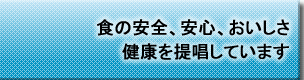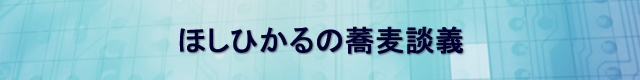|
☆ ほし ひかる ☆ 佐賀県出身、中央大学卒、製薬会社に入社、営業、営業企画、広報業務、
ならびに関連会社の代表取締役などを務める。「荒神谷遺跡の謎を解く」「朔太郎と私」
などのエッセイ・コンクールに数多く入賞する。
|
|
ほしひかる氏 | ||
【4月号】第34話 香りの研究
|
|
誘惑する香り 「今川小路(神保町3丁目)を九段の方へ歩いていると、楊枝を咬えた中国人とすれ違った。その刹那に、紹興酒の匂いが伯爵の鼻をおそった・・・・・・。」 谷崎潤一郎著の『美食倶楽部』の主人公は、この〝匂い〟がきっかけで魔界のような中国料理店「浙江会館」へと迷い込んでいく。 この小説が頭にあったため、江戸ソバリエの会ができるとき、その名前を「江戸ソバリエ倶楽部」としたのであったが、それはともかく、この神保町の場面は、〝匂い〟が美味の世界への誘い役であることを谷崎は言っているのだと思う。 しかし、こうした怪しくも妖しい小説を引き合いに出さずとも、焼き肉、焼き鳥、鰻の蒲焼き、焼きソバ、お好み焼き、カレーなど、食欲を刺激されるような強烈な匂いに誘われた経験は誰にでもあることだろう。 モノの本によれば、匂いも味と同様に物質によって生じるものらしい。味というものは、水に溶けている物質が舌の味蕾に直接くっつくことによって感じるのであるが、匂いの方は、空気中に漂っている気体状の物質が鼻の粘膜にくっつくことによって感じるのである。このように匂いというのは空気中に漂っているだけにとらえ難い点もあるが、だからこそ誘導役が担えるのである。これが匂いのひとつの特質であろう。 日常の香り 現代の日本では、8割の家庭が朝食はパンだという。ご多分に漏れず、わが家も40年ちかく、淹れ立ての珈琲とトーストを頂いている。珈琲はこだわって入谷の「キャラバン」という店の豆だけを愛飲し続けている。パンの方は特定はしていないが、あるていどの期間は同じものを買っている。いえば、40年ちかく決まった珈琲とトーストの匂いのなかで生活をおくってきたのである。 そんなとき、偶々出張で泊まったホテルの朝食で、いつもと少し違うなという思いをしたことがある。というのは、そのホテルのパンは美味しかったのであるが、珈琲が不味かった。とくに珈琲の香りに違和感をもったのである。でも、そのときは深く考えずに、そのパンと珈琲を頂いたのであったが、何かしら満足できずに、まるで仮の食事でもしたような気持に陥ったものであった。 翌日は、自宅の、いつもの珈琲とトーストを口にした。そのとき、この香りこそはわが家のわが朝食の香りだとつくづく痛感したものだった。 その家の香りというのはどこの家庭にでもあるものだが、そのなかに居ることが日常ということではないかと思った。香りというのはそういう役割もあるのではないだろうか。 美味しさの香り よく、美味しさを決める要因は、7つの味(甘味、酸味、塩味、苦み、旨味、辛味、渋味) + 香り + テクスチャー(硬さ、粘度) + 温度 + 色、形、だといわれている。では・・・・・・、 [問]風邪をひいたらどうなるか? [答]食事が不味くなる。 [理由]鼻が効かなくなって香りが感じられず、味がしなくなるからである。 これはたいていの人が経験していることだろう。ということは、美味しさを決めるのは、味ではなくむしろ香りだったということになりはしないか。 それなら、基本味覚があるように、基本臭覚というものがあるのだろうか。 欧米では、「7つの原香」として分類されているが、しかしその中には「高貴な匂い」というような抽象的表現もあれば、「ニンニクのような匂い」というような具体的表現が混じっていて、分類基準がよく理解できない。 それよりか、われわれ日本人は、爽やかな良い「香り」、強烈な厭な「臭い」という漢字によって使い分けているが、それを分類する感覚的基準に納得がいける。 また良い香りも、さらにはもやもやとした「薫」、澄んだ「馨」、植物の「芳」、ふくよかな「馥」、草の芽や花の「芬」、と繊細な分類をして字を当てはめている。それでいて、一方では香りの濫費を日本人は好まない。 われわれ日本人には、こうした細やかで単純な香りが美味しさ感覚に寄与しているのだろう。 可能性の香り 江戸蕎麦について語るとき、〝いき〟ということを抜きにしては語れない。その〝いき〟について考察したのが九鬼周造の『「いき」の構造』であるこ とは広く知られているが、その準備原稿である『「いき」の本質』は1926年(大正15年)にパリで書かれている。 そこが注目すべき点であると思う。なぜなら、日本の〝いき〟がパリで書かれているのである。そのきっかけが〝香り〟であったというから、面白い。 大正14年、九鬼は短歌『巴里小曲』を発表した。その中の「Nocturne」にこんな短歌を載せている。 ふるさとの 「粋」に似る香を 春の夜の ルネが姿に 嗅ぐ心かな すなわち、春の夜に出会ったルネという女性の匂に、37歳の九鬼は日本の「粋」を感じたというのである。そして、その翌年に彼は『「いき」の本質』を書き上げたのである。 九鬼はまた、随筆「音と匂 ― 偶然性の音と可能性の匂」の中で、匂には創造性があるかのようなことを書いている。それはルネの香から『「いき」の構造』が生まれたことを述懐しているのではないだろうか。 参考:谷崎潤一郎著『美食倶楽部』(ちくま文庫)、谷崎潤一郎著「支那の料理」(みすず書房)、篠田一士著『世界文学「食」紀行』(講談社文芸文庫)、開高健著『最後の晩餐』(光文社文庫)、栗原堅三編著『香のふしぎ百科』(樹立社)、ほしひかる筆「蕎麦談義 ― 第5話』(フードボイス)、九鬼周造著『九鬼周造全集』第一巻(岩波書店)、菅野昭正編『九鬼周造随筆集』(岩波文庫)、 〔江戸ソバリエ認定委員・(社)日本蕎麦協会理事 ほしひかる〕
次回第35話は「フレスコ画『天・地・人』」を予定しています。
|
| ▲このページのTOPへ |