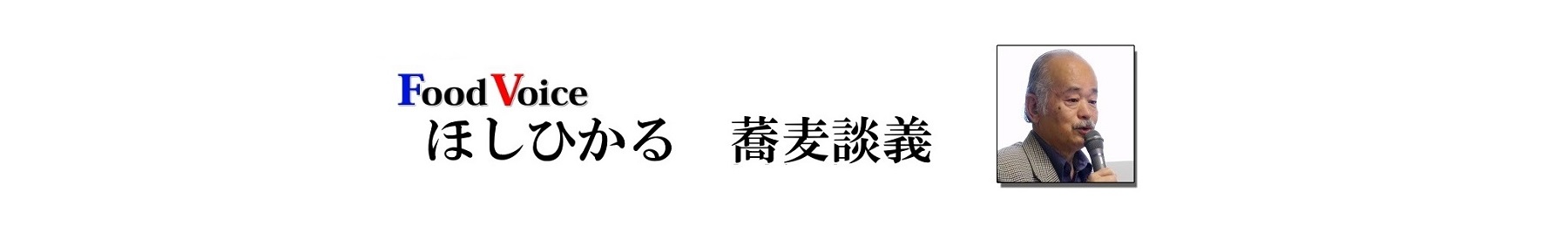第105話 典座の教訓
蕎人伝12 栄西、道元、円爾
「日常茶飯事」という言葉がある。「普通のこと」という意味である。
この普通の「飯(米)」と「茶」とそれを入れる「食器(磁器)」は大陸から渡来したものであるが、そのうちの「米」は縄文晩期、「茶」は鎌倉時代、「磁器」は秀吉の時代に入ってきた。いずれもその上陸第一歩の地は九州の佐賀である。
という文章を見たとき、この執筆者は私以上に愛郷心のある人だなと一人で苦笑いしたものである。
今回の話は、「日常茶飯事」の「茶」、つまり宋文化の輸入が日本の麺文化を育成したという話である。
Ⅰ.栄西の五味論
ご承知のように栄西は2回の入宋経験(1168年と1187年)を通じて茶の効能を知り、2度目の帰国の際、茶の苗木と種、それに茶器を携えてきた。そして母国の第一歩の地である肥前の背振山(佐賀県神崎郡)にその種を植えた。そして栂尾高山寺の明恵上人に種を贈ってその効能を伝えたため、それが契機となって栂尾を中心に植茶が広まり、やがては宇治、伊勢、駿河、川越へと拡大していった。
このことは日本に本格的に茶が入ってきたこととして有名な話である。もちろんそれ以前にも茶はあったらしい。それは中国が唐の時代にわが国に入ってきたため、「唐茶」ともいわれるが、実態はよくわかっていない。栄西がもってきた茶は「宋の抹茶」であるが、後に明代に入ってきたものが「煎茶」である。要は、中国は時代によって異なる茶の文化を有していたのである。
話は戻るが、栄西の茶の導入は、モノだけにとどまらなかった。つまり、彼が著した『喫茶養生記』(1211年版、1241年版)では、「甘、鹹、酸、辛、苦」の〝五味〟が陰陽五行説に則って論じられている。これは宋の食味学の輸入であり、わが国で初めての食味論の登場となるのである。
Ⅱ.道元の六味三徳論
ところがである。同じく宋から帰国した道元は、『典座教訓』(1237年)の中で、「甘、鹹、酸、辛、苦、淡」の〝六味〟や、軽軟・浄潔・如法の〝三徳〟について述べている。
つまり、道元は五味に「淡」を加えて〝六味〟へと進化させているが、しかもこの考え方は、宋の『禅苑清規』の引用によるものだとも述べている。
では、その『禅苑清規』とは何なのか?
元々、禅宗の清規は、唐の百丈懐海が初めて制定したとされているが、その『百丈清規』が散逸していたため、それを遺憾とした長蘆宗賾という人が、広く当時の叢林古刹などに行われていた行法を調べ、依準すべき禅門の規矩を定めて、1103年(宋の崇寧年間)に刊行したものだという。そこに「六味三徳」が述べられているというのである。
では、その六番目の「淡」とは何か?
そういえば、この言葉は「無為の哲人」といわれる老子の思想に見出すことができる。老子は、第35章と第63章でこう説明している。「道之出口 淡乎其無味 (道の口より出るは淡乎として其れ味、無し)」。「為無為 事無事 味無味 (無為を為し、無事を事として、無味を味わう → 余計な事はするな、味のないものを味わえ)」。そして、第12章では「五色令人目盲 五音令人耳聾 五味令人口爽 (五色は人の目をして盲ならしめ、五音は人の耳をして聾ならしめ、五味は人の口をして爽わしめ)」と快楽主義を非難している。つまり、五味を抑えるものが「淡」だという考え方であると私は理解したい。
では、なぜ禅(仏教)の清規に、道教の思想が入っているのかといえば、それが宋の時代らしさであった。つまり、この時代に仏教、道教、儒教の理論上での融合がはかられたのである。
Ⅲ.円爾の挽臼
栄西、道元は中国へ渡って、道教の考え方をわが国にもたらしたが、わが国の宋国詣はまだ続いた。なかでも重要なのは1241年に帰国した円爾である。この人は茶や穀物を粉にすることのできる挽臼をわが国にもたらしたとして多くの伝説をもつ人である。つまり、円爾がわが国に麺食を導入したともいえるのである。現に、麺類の初出を見てみると、次のような具合である。
1340年(足利尊氏の時代)、ソーメン
1347年(足利尊氏の時代)、うどん
1405年(足利義持の時代)、冷麦
1438年(足利義教の時代)、蕎麦
1574年(織田信長の時代)、蕎麦切
ご欄のように、円爾の帰国後の、足利時代に麺類が勢揃いしている。
Ⅳ .ポスト道元
その普及ぶりを確認できるのは、本願寺の慈俊(覚如の子)が企画し、沙弥如心という絵師が描いた(1351年) 本願寺三世覚如の伝記絵巻『慕帰絵詞』のうちの巻五である。
~ 覚如の屋敷内の厨の間は、多くの使用人や弟子たちが饗応の準備に大忙し。一人は正方形の俎板の上で真名箸と庖丁を使って鯉をさばいている。その様は「庖丁儀式」でよく見る姿と同じである。その横では麺を器に盛っており、その手前で一人の僧が旨そうに麺汁の味見をしているところである ~。
14世紀半ばというと、足利尊氏と直義の兄弟が争っているころであるが、寺社ではこのように麺と麺汁が食されていたのである。
この『慕帰絵詞』の坊主の何ともいえない表情を見ていると、彼が味わっている麺汁こそ、道元の言う「甘、鹹、酸、辛、苦、淡」の〝六味〟や、軽軟(=アッサリとして軟らかいこと)、浄潔(=清潔でサッパリしていること)、如法(=理にかなった適切な料理法のこと)の〝三徳〟に基づいて調理された麺汁であることがうかがわせる。道元の「淡」が調味の慣習を、道元の「如法」が料理の概念を、日本人のなかに植え付けたことの証ではないだろうか。
なにしろ、道元は料理も修行のうちとして、永平寺の典座たちに「六味三徳」を教訓し、実践させているのである。
こうした僧たちの修行、すなわち「六味、三徳」の教訓を念頭においた調理が、中国やヨーロッパのスープとは異なった味付けとなり、それが精進料理、懐石料理、そして和食の基礎となっていったのであるから、道元の役割は大であったといわざるをえない。
参考:ほしひかる「蕎人伝」第104、102、99、91、88、87、82、70、65、64、62話、ほしひかる『小説「典座教訓」』(日本そば新聞)、ほしひかる「栄西『喫茶養生記』」(日本そば新聞)道元『典座教訓・赴粥飯法』(講談社学術文庫)、頼住光子『道元』(NHK出版)、中尾良信『道元』(吉川弘文舘)、監督・脚本:高橋伴明『禅zen』、栄西『喫茶養生記』(講談社学術文庫)、小川環樹『老子』(中公文庫)、
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕