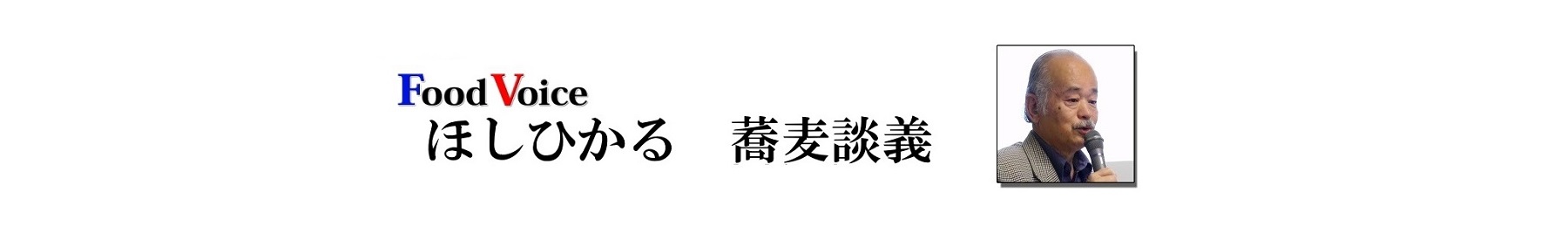第695話 目撃者、みみずく土偶
『世界蕎麦文学全集』物語37
「なぜ年越に蕎麦を食べるのか?」という問いに対し、こんな考え方がある。
年を越し、新年を迎えるにあたって、古代の日常食を食べたり供えるようになった。「古代の」というのは「縄文時代の」ということであって、蕎麦、里芋、栗、柿、橙、昆布、そして食器代わりの裏白、譲葉などだというのである。
たしかに、それらのほとんどは縄文遺跡から出土している。そして縄文人が食べていた里芋を供えるときは搗いて練って、円形か楕円形にしていたというのである。やがて米の時代になると、米になった。これがいわゆる「鏡餅」であり、併せて搗栗、干柿、橙、昆布、裏白、譲葉なども供えられた。そして大晦日に蕎麦を食べ、新年には飾ってある鏡餅を「代々、譲る、喜んぶ、勝ち栗」などとおもしろおかしく言葉遊びを交えて(ダジャレ)語り合い喜び合ったという。
さて、ここで問題にしたいのは年越しではなく、日本における蕎麦の栽培はいつごろかといううことであるが、それは縄文後期(~3000)~晩期(3000~2300)のさいたま市岩槻の真福寺貝塚遺跡から小豆・胡麻・瓜・茶ノ木などの栽培植物と一緒に栽培蕎麦が出土した例をとり上げたいと思う。
このころは、岩槻あたりまで東京湾が入っていたらしく、現在では奥東京湾とよんでいる。奥東京湾の集落一帯は、葭などが生える湿沢地が拡がり、それに接して、小楢・水楢・栃の木・銀杏・栗の木・鬼胡桃・榎・臭木などの落葉樹や、榧・犬榧・椿などの常緑樹の原始林が茂っていたようである。そして森に鹿・猪・狸などの獣類が棲息し、実る果実を求めて雁・鴨・雉などの鳥類が飛来していた。
部落の人たちは、裏山で食用果実や山菜や山牛蒡などを採集し、森林に分け入っては丸木弓・石鏃・石器を使っての狩猟、あるいは川や海に下りて行って大和蜆・蛤・牡蠣・灰貝などの貝類や、鯉・鮒・鰡・鱸・鯛といった魚類や鯨などの漁撈生活をおくっていた。その魚介類を煮炊きすることから土器が考案された。今でいう〝煮る〟料理である。また煮炊きすることから栃の実などの灰汁をとる工夫も生まれた。さらに真福寺部落では製塩土器も出土し、さらには貯蔵用の土坑も見つかっている。蓄えておいた栃の実を土器で灰汁抜きして、石皿磨石で粉にし、それを団子にして、土器で山菜や魚貝と一緒に煮て、味が足りない場合は塩を加え、木の枝の箸を使って食事をとっていた。
このようにかれらは生産的な農業を手掛け始めていたと考えられている。
そのことを考古学という理論からではなく、感性から解決しようと試みた人がいる。考古学者の大島直行である。彼の著書『月と蛇と縄文人』の表紙を見ていただきたい。画家廣戸絵美(1981~)の写実的な油絵「妊婦」と、国宝「縄文のヴィーナス」が並べてある。廣戸がこれを描いた意図は知らないが、大島はこの絵画に「縄文のヴィーナス」と共通する〝生〟を感じたという。
こうした土偶は土器とともに縄文時代の特色である。しかも土偶のほとんとが女性。考古学者の井口直司は縄文土偶の特徴として、女性性器、乳房、臍、妊娠線があると述べ、それは産む(女性性器)、育てる(乳房)、絆(臍)を印象づけると述べている。
すなわち、ここに見られる〝生〟とは産、育、絆である。だから大島は廣戸の「妊婦」と「縄文のヴィーナス」を並べたのだろう。
そして、真福寺貝塚遺跡からは有名に土偶が出土している。それが【みみずく土偶】である。頭髪は天然パーマのようにクルクル巻いていて、目が大きいためこの名が付けられたが、やはり妊婦像である。これもすなわち産、育、絆=生の象徴であり、縄文晩期人の蕎麦栽培の、目撃者であることに他ならない。
『世界蕎麦文学全集』
63.真福寺貝塚「木菟土偶」
64.廣戸絵美「妊婦」(大島直行『月と蛇と縄文人』)
*井口直司『縄文土器・土偶』
文:江戸ソバリエ認定委員長 ほし☆ひかる
写真:大島直行『月と蛇と縄文人』
「みみずく土偶」(ほし所蔵)