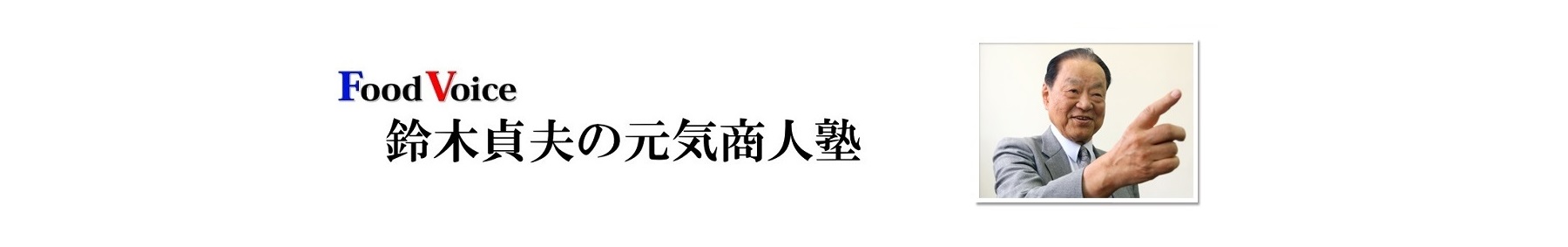<コンビニ創業戦記『鈴木貞夫言行録』>(第71回)
2023/11/07
第6章・(株)ミトリズ時代
『最近の読書シリーズ』(其の10)
<マーカス・K・ブルネルマイヤー著『レジリエントな社会』を読んで>(その1)
(--日本経済新聞社刊・2750円)

予測困難で危機に満ちた危機の時代に不可欠な「レジリエンス」は、
「負のショックから立ち直る力・柔軟性」を意味している。
この数年来のコロナ禍で、人類はあらゆる面でレジリエンスを試された。
本書はレジリエンスの基本概念と原理を、体系的に提示した概説書である。
扱うのは個人や一組織のレジリエンスにとどまらない。
人類的危機にも対応できる『レジリエントな社会』を築く道を探っている。
リスク管理を重視するが故に挑戦の断念につながりやすい「リスク管理」の考え方から、
試行錯誤や再挑戦を促す「レジリエント管理」への転換を説いている。
本書はレジリエンスを考えるための貴重な基本文献となるだろう。
著者・マーカス・k・ブルネルマイヤーは、米プリンストン大学教授で、
国際研究機関やIMFなどの国際金融機関などのアドバイザリーボードメンバー等を歴任し、
ノーベル経済学賞を受賞も絶賛する世界的に著名な経済学者である。
本書『レジリエントな社会」(危機から立ち直る力)は、次の全4部から構成されている。
序章・『始めに』
パートⅠ・『レジリエンスと社会』
ーーリスク管理からレジリエンス管理へ――
パートⅡ・『ショックの封じ込め』
――新型コロナウイルスの事例に学ぶ――
パートⅢ・『マクロ経済のレジリエンス』
――イノベーションが長期的な成長を促進する――
パートⅣ・『グローバル・レジリエンス』
――新たなグローバル世界秩序――
今号では、『序章』と『パートⅠ』について概説したい。
先ず『序章』から。
リスクは世界のいたるところにある。
新型コロナパンデミックや、ロシアによるウクライナ侵攻、気候変動や技術変化など、
近年の出来事は、世界中の社会を混乱と危機に直面させ、脆弱感を痛感させた。
リスクへの対処は永久に必要であるが、今、本書が主張するのは、
伝統的な「リスク・マネジメント」ではなく、『レジリエンス・マネジメント』への転換である。
鍵となる概念『レジリエンス』とは、「負のショックから立ち直る力、復元力」を意味する。
「リスク・マネジメント」が、「行動を起こすときに、リスクの規模を計算し、
どれだけのリスクを許容できるかを評価すること」であるのに対し、
『レジリエント・マネジメント』は、「レジリエンスを高める要素を育成して、
レジリエンスを壊す要素を回避すること」である。
人は夢を描き、実験し,戦略を練り、計画を立て、失敗もするだろう。
それには個人の自由が不可欠である。
その自由を認めなければ社会進歩はない。
失敗から学び、立ち上がり、再び挑戦する能力を高めるべきだ。
社会は失敗しないように囲い込むのではなく、むしろ実験と好奇心を奨励し、
個人のレジリエンスを高めていくべきである。
パート1・レジリエンスと社会
第1章・『リスク管理からレジリエンス管理へ』
――レジリエンスの定義--
レジリエンスは財務管理やリスク管理とは異なり、リスクの回避を意味するものではない。
いくつかのリスクを負う方がレジリエントであることもあるからだ。
リスク管理のやり方は、一つはリスク回避であるが、これには常に失敗の可能性がはらむ。
レジリエンスはリスクを回避するのではなくレジリエンスのあるリスクと無いリスクを区別することである。
前者は引き受ける価値のあるリスクであり、後者こそ避けるべきリスクである。
レジリエンスは、ショックが起きた時に対策を講じ、弾力的に回復する能力を意味する。
レジリエンス戦略は二本の柱からなる。
第1の柱は、最初のショックを封じ込める事だ。
第2の柱は、復元の条件を作り出すことである。
この二本に柱を並行して追求することが大切である。
レジリエンスを目指すことは、あらゆるリスクを回避することではなく、
レジリエンスを発揮できるリスクを選択し、レジリエンスを発揮できないリオクを
回避することである。
ーーレジリエンスを高めるにはーー
第1には、「順応性」「柔軟性」「変化能力」を高めることである。
必要なのは、新しい環境に順応し、俊敏に、臨機応変であることだ。
予測不能な出来事への反応を可能にする制度的枠組みを埋め込んで置くことだ。
第2に、代替可能性」を高めておくことが、ショックへの切り抜けるレジリエンスを高める。
第3に、「多様性」と「開かれた心」を高めることである。
これが低い組織はショックに弱く、脆弱なことが多い。
多様性のある文化は、創造性や独創的な発想を生みやすく、ショックをうまく切り抜けるからだ。
第4に、時に、小さなショックを経験することで、それへの対応方法を学ぶことができる。
ときおり起こる小さな危機は、レジリエンスを高める手段となり、その経験を通じて、
その後のショックにうまく対処できるようになる。
成功著しいユニコン企業も、倒産の危機を経験することで、洞察と実践の質を向上させたのだ。
――レジリエンスを壊す「罠」に注意ーー
誰かが負のショックにさらされた時に取る対応が不安定化のループを呼び、
それが全体のレジリエンスを弱める恐れがある。
特定の状況においては、人びとの対応がレジリエンスを破壊する要素になる場合に、臨界点が表れ、
深刻な「レジリエンスに対する脅威の罠」となる。
社会は臨界点を特定し、これを回避しなければならない。
( 以下次号に続く)
『鈴木貞夫年譜・2023年度第三4半期②』
8月度 1日・朝礼
・部門長MT
2日・経営会議
4日・新人事制度説明会
8日・朝礼
・部門長MT
14日・ 新宿海上診
15日・朝礼
22日・朝礼
・PJMT
・部門長MT
・部門報告会
23日・経営方針会
29日・朝礼
部門長MT
30日・月例取締役会
9月 5日・朝礼
・部門長MT
12日・朝礼
・PJTMT
・部門長MT
・経営会議
・月例フードボイス会(於学士会館)
14日・SC会(於・千葉CC川間c)
20日・朝礼
・部門長MT
26日・朝礼
・部門長MT
・リスクコンプライアンス委員会
28日・月例取締役会
・部門報告会
以上
(次号は『鈴木貞夫言行録』(第72回)を掲載します)
――バツクナンバーは<鈴木貞夫プロフィールと『目次と索引』を検索してください>――