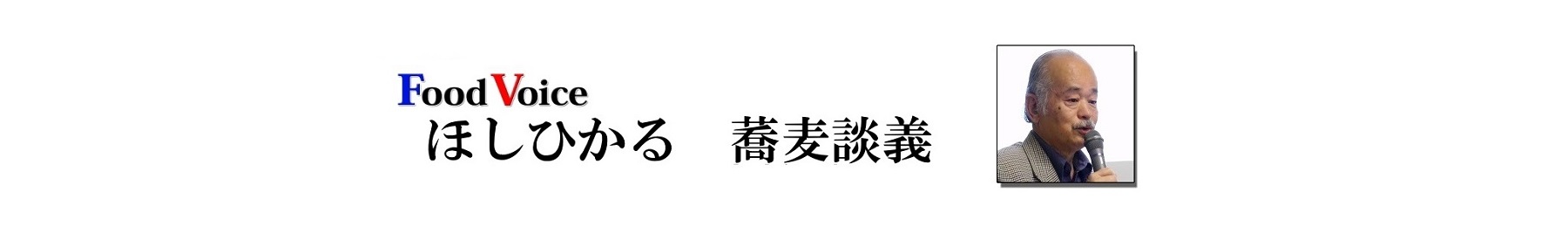第295話 たたかう小説「陶然亭」
夏も終わりのころです。用があって京都に行ったとき、割烹【陶然亭】に寄りました。
☆紫陽花の
「陶然亭」― その名を初めて聞いたのは、私の竹馬の友である次郎の親父さんからでした。次郎とは小学校から大学まで同じ学校でしたから、その親父さんも文字通り「親父」みたいなものでした。出張で東京に見えたときは、「下宿生活のお前たちは、ろくな物を喰ってないだろうから、食って行け。この旅館の飯は、下手なレストランで食べるよりよっぽど旨い」と二人を定宿の水道橋駅前旅館に招いてくれるのでした。それは私たちが十九、二十歳のころでした。
ある日の食事は新米のご飯に赤だしとトンカツでした。赤だしの滲みるような味、新米の爽やかな弾力性、トンカツを噛んだときのサクッという音はたまりませんでした。日ごろ下宿先の近所で食べる中華食堂の「野菜炒めライス=100円」の古米のような飯とはえらい違いです。とはいっても、私はそこの食堂が嫌いではありませんでした。たとえば、それまで「野菜炒めライス=90円」だったのを10円だけ値上げするのに「兄さん、すまないね。今月から10円上げさせもらっている」と、19歳の私を拝むように誠意をもって言うのです。後年になって、それを思い出す度に、これが本物の「顧客主義」というものだろうと思ったものでした。今の口だけの顧客主義、実は会社中心主義とは全く違うと皮肉を言いたくなります。
それはともかく、親父さんは子犬のようにがっつく息子たちを眺めながら、いつも満足そうに盃を運んでいました。「飯は新米の炊き立てに限る」とか、「飯の後の煙草は旨い」などと、何でも断定的に言う親父さんでした。そういう強い口調だからか、私には金言のように心に残りましたが、実の息子である次郎といえば、いつも鼻で笑っていました。でも今思うと、それは次郎のてれかくしだったにちがいありません。それから親父さんは chain smoker に、chain reader、つまり煙草と本を手離したことがない人でした。旅行するときの本はたいてい推理小説だと言っていましたが、なかでもF・W・クロフツが大好きだったようです。だから今でも本屋の棚にクロフツが並んでいるのを見かけたりすると、二階建駅前旅館で食べたトンカツの歯触りを思い出します。
そんな付合の中で、親父さんに「青木正児に教えてもらった」と言って【陶然亭】のことを聞いたのでした。青木という人は中国文学者で、麺好きにとっての必読書の一つだといえる『華国風味』を著した人物です。当然食通でもあったはずです。次郎の親父さんもまた旨い物好きでしたが、昔は中国にあった南満州鉄道㈱に勤務していた人でしたから、その辺りで中国文学者の青木と何か縁があったのかもしれません。ただ、そのころの人たちはあまり昔のことを話したがりませんから、これは私の想像です。
旧満鉄といえば、私の義父もそこに勤務していました。義父は小柄でしたが、男らしい貫禄が漂っている人でした。日本の敗戦が濃厚になったころのことです。満州では明日にでもソ連軍が攻めて来るとの噂が飛び交っていたそうで、早く日本へ引き上げようと騒いでいるとき、現地の日本の銀行にある貯金を「あれは俺たちのものだ。あれも持って行こう」ということになりましたが、担当者は逃げ出してもういません。そこで仲間のみなが義父に「あんたが頭になってくれ」と頼まれ、何人かの仲間を結成し、金庫から金を奪い返したのでした。しかし、一転して敗者になった日本人を現地の中国軍は許しません。「あの銀行の金は中国のものだ」と主張して金は没収され、頭である義父も捕まって市中を引き回されたのでした。
しかし、義侠心に富んでいた義父は日頃から中国人と平等に接していたため、恩義を感じていた中国人たちもたくさんいました。そういう中国人に義父は助けられ、何とか日本に引き返してきたそうです。
そんな話などを大阪にいる義叔父にしたら、「兄貴ほど兄貴らしい男はいない」と言ってから、「そういえば、船場に【田舎亭】といって【陶然亭】の舎弟の店があると、大久保恒次という食のジャーナリストが何かに書いていたな」と教えてくれました。その義叔父もやはりジャーナリストでしたから、大久保という人と仕事の関わりがあったのかもしれません
ただ、これらの話はみんな学生時代の話です。
とにかく、それから次郎は札幌に住むようになり、私は東京の会社に就職して、とうとう四十数年も東京という大都会の片隅で暮らすようになってしまったのです。
その後、義父も、次郎の親父さんも、義叔父も亡くなり、以来二つの隠れ家的名店については名前さえ忘れてしまっていました。
そんな私は九州の田舎者です。だからでしょうか、いつも「田舎:都市」ということとか、「西日本:東日本」ということが、無意識の中に横たわっているのです。
食文化においても、そんな相違がベースとなって、「比較食文化研究会」なるものを仲間と一緒にやるようになりました。当然、食に関するいろんな書物に目を通すようになったのですが、ある日、神吉拓郎さんの『ニノ橋 柳亭』という小説に廻り合い、その中で懐かしき【陶然亭】と【田舎亭】の名前と再会したのでした。
そうしてまたタイミングというものはあるものです。今は京都に住む学生時代の友人が「五条辺りに【陶然亭】という料理屋があるから、来なさいよ」と勧めるのです。
もちろん大いに興味をそそられました。でも、その一方では「何だい、それは! 次郎の親父さんから聞いたのはもう遠い昔のこと、青木の隠れ家とは似ても似つかぬ店だろう」ということで、結局は生返事をしておいたのです。
ところがです。一昨年、北京に行ったときの最後の夜、ホテルのベッドで北京市内の地図を眺めていたら、「陶然亭公園」という文字が目に飛び込んできたのです。思わず私は上半身を起こし、ホテルの机の上にあった地下鉄路線図を手に取りました。すると、あったのです。「陶然亭」という駅が。「へえ!」と呻きながら、室内のインターネットで検索してみると、中国語だからよくは分かりませんが、白居易の詩「共君一醉一陶然」から採った公園というような説明がしてありました。
《與夢得沽酒閒飲且約後期》白居易
少時犹猶不憂生計, 老後誰能惜酒銭。
共把十千沽一斗, 相看七十欠三年。
閑徴稚子窮経史, 醉聴清吟勝管絃。
更待菊黄家醞熟, 共君一醉一陶然。
私は頭の中に稲妻のようなものが走りました。当然、「陶然亭公園」とやらへ行ってみたい気持もわいてきました。しかし、翌朝はそんな時間がありません。すぐに飛行場へ行かなければならないのです。残念ですが、幸いなことに今日まで北京の多くの公園を訪ねていますから、中国の公園のだいたいの雰囲気はつかめました。だからというわけではありませんが、北京で「陶然亭」という名に遭遇したことと、それが白居易の詩に由来するということを知ったことの方が重要なことではないかと私は思い直すことにしました。
成田へ帰る機中、私は次郎の親父さんや義叔父が言った、京都の【陶然亭】や大阪の【田舎亭】、そして小説で描かれていた東京の【柳亭】のことを「どんな店だろうか」と想い描いていました。
そして、北京から成田に戻ってから数か月後、件の【陶然亭】を初めて訪ねたのです。私にとっては行きつくまで半世紀ちかくもかかった店です。季節は梅雨の晴れ間のことでした。案内してくれたのはかつて誘ってくれた学生時代の友人恵子さんでした。
そこは白い大きな暖簾のかかった小さな店でした。亭主と女将と弟子の板前さんの三人でやっている、カウンター十席ぐらいの店でした。席の奥は、小さな庭になっていました。
私と恵子さんは、その庭に近い奥の席に座りました。
酒は伏見の銘酒。杯の底を見ますと、白磁に一枚の紫陽花の花弁が入っています。そこに酒を注ぐと花弁が浮かぶのです。連れの友人は女性ですから、何ともまあ雰囲気のある演出です。といっても、彼女は昔の恋人というわけではありません。はっきりというと友人の恋人だった女性なのですが、なぜか五、六年に一度ぐらい会う機会が巡ってくるのです。
酒に浮かぶ紫陽花の花弁を見ながら、私は江戸時代の林信篤の『本朝食鑑』の中の言葉を思い出しました。「およそ食に形あり、色あり、気あり、味わいあり」と述べていることと通じるナと恵子さんに言いましたら、彼女は頷きながらも「相変わらずね」と笑いました。彼女は私より一回りも若いのに、口の利き方は生意気というか、同年齢みたいなんです。またそれだけに知的な魅力をもった人なのです。
☆蓮の葉の
さて、再びの【陶然亭】です。訪れたのは今日で二回目になります。
京都で用事ができたためその気になって、行く前に東京から友人の恵子さんに電話をしたのですが、「残念だけど、そのころはフィレンツェよ」と言うのです。
「フィレンツェか。何しに行くんだい?」
「京都とフィレンツェが姉妹都市なの、その交流で、お蕎麦とピッツオケリの、共宴よ。」
エッ!と驚きました。「君は蕎麦を打つのかい?」
「やらないわよ。通訳がわりよ。」
「そうか。恵子さんはイタリア文学専攻だったね。」
「ついでにヴェネツィアにも足を伸ばして、橋を見てくるわ。」
「何処の橋?」
「全部よ。須田敦子の『橋』ってエッセイ、知ってる?」
「須田敦子は聞いたことがあるけど、読んだことない。」
「それ、読んでからね、見てみたいナと思っていたの。ちょうどいい機会だわ、」
「ついで」とか「ちょうどいい機会」とか言うわりには、恵子さんの強い意思が電話を通して伝わってきました。
「そう、分かった。行ってらっしゃい、気を付けて。土産話はいらないから、お土産だけほしい」と笑って、携帯電話を切ったのでした。
それから、彼女が言った『橋』を読んでみて、「なるほど」と思いました。それにはヴェネツィアの大運河に架る橋と大阪の橋のことが書かれていたのです。今は京都に住んでいるけど、大阪で育ったという彼女にとっては、やはり関西出身のイタリア文学者須田と重なるところがあったのだろうと納得しました。
それから、私も須田敦子の著書に関心をもち、『オリエント・エクスプレス』なんかを読んで、娘を思う父の気持に娘が気付いた場面にジーンときたりして、ヨーロッパに行ったら、ぜひオリエント急行に乗ってみたいものだと思ったものでした。
そんな私は、いま京都行の新幹線〔のぞみ〕の中で半分うとうとしています。夢と現の間で、恵子さんのことが頭にあったためでしょうか、フィレンツェを舞台とした小説『冷静と情熱のあいだ』があったことを思い出していました。その小説は一つの恋の物語を、男性側から辻仁成さんが、女性のサイドからは江國香織さんが書くというシャレた企画でした。「ああ、あんな風なシャレた企画を立ててみたいな」と溜息を吐いたときです。
〔のぞみ〕が、駅でもないのに突然、急停車。そして車内放送が流れてきました。「伊豆地方でM8クラスの地震が起きたので、暫く停止します!」
それだけが何ども繰り返されますが、その声は落ち着いているようでいて、緊張もしているようなトーンでした。
「ここは、どの辺りだろうか?」
うとうとしていたので場所が分かりません。隣の席の人に「ここは何処ですか?」と訊こうとした、そのときです。
新幹線の車体が大きく何度も横揺れしたのです。
「キャー!」前方の席の子供たちが大きな悲鳴をあげます。
私も思わず肘掛をしっかり握りました。
多くの人は、立ち上がって逃げようとします。
そこへ「落ち着いてください」のアナウンス。
人々は座席に座り直しましたが、不安はおさまりません。
窓の外を見ますと、小さな沼の水面がまるで洗面器の中の水のようにポチャ・ポチャと揺れています。左前の席に座っていた女の人が船に酔ったように青い顔をして口を押さえ、人にぶつかりながら後の車両にあるトイレに駆け込みました。
暫く・・・というか、だいぶ長く感じましたが・・・、横揺れが続き、そしてやっと静かになりました。
私は東京の自宅も揺れただろうなと思いましたので、携帯でメールを打ちました。すぐに「家族は何ともない」との返信がきました。とりあえず安心しましたが、古い家ですから箪笥の上に載っていた小荷物や食器棚などは無事ではなかったでしょう。それに私の部屋の本棚からも、たくさんの本が落ちたことでしょう。
このとき私は、なぜか、森鴎外の『小倉日記』や松本清張の『或る「小倉日記」伝』、さらにはピエール・ロチの『江戸の舞踏会』、芥川龍之介の『舞踏会』、三島由紀夫の『鹿鳴館』などがゾロゾロと崩れ落ちるのを想像してしまいました。
新幹線は2時間ぐらいストップしていたでしょうか。やがて私たちの乗った〔のぞみ〕は、抜足差足でゆっくりと用心しながら動き始めましたので、まずはホッとしました。
やっと〔のぞみ〕は京都駅に到着しました。駅はダイヤの乱れの影響で大混雑していましたが、街中に出ますと日常の京都でした。
私は、本日アポをとっている人に電話をしました。「やっと着きましたが、今から伺ってよろしいでしょうか?」
新幹線の中から、緊急メールを入れていましたので、相手は待っててくれました。
用件を済ましてから私は、夕方に【陶然亭】に行くつもりでした。ですが、時計を見ると、まだ少し時間があります。私は四条辺りをぶらぶらと歩きました。「先刻の地震騒ぎが嘘のようだな」と思いながら、本屋さんの前に来ますと、店のガラス窓にポスターが貼ってあります。
「松本清張 朗読劇『或る「小倉日記」伝』○月○日 △△小ホールにて」
清張の写真もありました。煙草を銜えて考えているポーズです。眼鏡の奥の眼差に強い意志が感じられます。
このとき私は「そうか」と思いつくことがありましたので、店内に入って三島由紀夫の顔写真が載っている本を探しました。ありました。三島の挑むような視線が私を睨みつけています。
「そうか、そうか。」
私は店を出て、五条へ向かって歩き始めました。
森鴎外の『小倉日記』と松本清張の『或る「小倉日記」伝』、
芥川龍之介の『舞踏会』と三島由紀夫の『鹿鳴館』。
先刻の大揺れが惰眠していた脳を揺り動かしてくれたのでしょうか。落下した本の著者たちの思いが、私に届いたような気がしたのです。
松本清張は森鴎外を尊敬していたからこそ、『小倉日記』に挑んだのだ。
三島由紀夫は芥川龍之介を尊敬していたからこそ、同じ題材の「鹿鳴館」を書いたのだ、ということに気付いたのでした。
だとしたら、神吉拓郎さんも【陶然亭】と【田舎亭】に惚れ込んだからこそ、たたかうようにして【柳亭】を書いたんだろう。
そうすると、江國香織さんと辻仁成さんの企画もシャレてたなんていうものではなく、二人のたたかいだったんだと思い直しました。
私は【陶然亭】の暖簾を手で分けて店内に入りました。入ってすぐの右手に置いてある手水鉢の中に蓮の葉が浮かせてありました。その葉に溜まった水が銀色の玉になっています。
私は子供のころを思い出し、蓮の葉を指でちょんと軽く動かしました。すると、銀色の玉がコロコロと滑りました。たったこれだけのことで心が和みます。
私は奥のカウター席に一人で座って、箸を取りました。隣に誰もいない食事とは寂しいものです。しかし代わって、料理というものに真正面から対峙するにはいい機会でした。
先ずは、浅草海苔を炙って揉んで小皿に入れ、花鰹を一撮みつまみ込んで醤油をかけ、擦山葵を多量に副えた御撮肴が出てきました。
私は驚きました。これは青木流の撮肴です。陶然亭さんは、名前は拝借しても青木流の撮肴を出さないはずです。なのに、今日はどうしたことでしょうか。
今評判の『天皇の料理番』秋山徳蔵は言ってます。「最初に出す料理が、勝負だ。」
そういうことなんでしょうか。それにしても、この一品に味と香りと新鮮な気があることをあらためて感じます。
「今日はお一人ですか?」女将が徳利を手に取り、注いでくれました。
私は、軽く頭を下げながら言いました。「一回しか来てないのに、覚えておいてくれたんですね。」
「実は、貴方様のお話は時々恵子さんから伺っておりましたから、」
「あ~、そうだったの。変なこと、言ってませんでしたか。」
「そんなことはございませんよ。」
このとき私は得心しました。きっと恵子さんは、私が青木の著書に導かれて、【陶然亭】を訪れたことを。「
だったら一度くらい、青木流の撮肴を味わってもらおうか」ということになったのではないでしょうか。
目前に立つご主人の庖丁を引いている真剣な姿を見ながら、私はその心遣いに震え、そして思いました。
きっと、この方も青木の『陶然亭』を尊敬しつつも、青木とたたかい続けているのかもしれない、と。
そういう真剣にたたかう姿勢からはいい作品が生まれものです。
亭主は、その作品を私の前に丁寧に置いてくれました。《鯛のそぎ造り》です。
その所作を見て思い出しました。「京料理は〝儚い〟と思うわ。口にしただけでホロリと崩れる少片の鱧、極細の切身、だからこそ真剣に、丁寧に・・・・・・」と、恵子さんが前回来たときに言ってたことを。
醤油は京都産でしょうか。色も香りも酷度も関東のものとは違います。《鮪の平造り》などは関東の醤油が合いますが、白身の魚は関西の醤油が合うなと私は思います。
女将がまた言いました。「恵子さんは今ごろイタリアですね。」
「そう。須田敦子を追いかけて行っちゃったんですよ、」
女将は返事のかわりに微笑んでましたが、亭主がこう言いました。
「皆さん、一所懸命ですね、」
「・・・・・・!」
参考:
青木正児『陶然亭』、大久保恒次『田舎亭』、神吉拓郎『ニノ橋 柳亭』、
須賀敦子『橋』、須賀敦子『オリエント・エクスプレス』、
江國香織『冷静と情熱のあいだ Rosso』、辻仁成『冷静と情熱のあいだ Blu』
森鴎外『小倉日記』、松本清張『或る「小倉日記」伝』、
ピエールロチ『江戸の舞踏会』、芥川龍之介『舞踏会』、三島由紀夫『鹿鳴館』、
〔エッセイスト ☆ ほしひかる〕