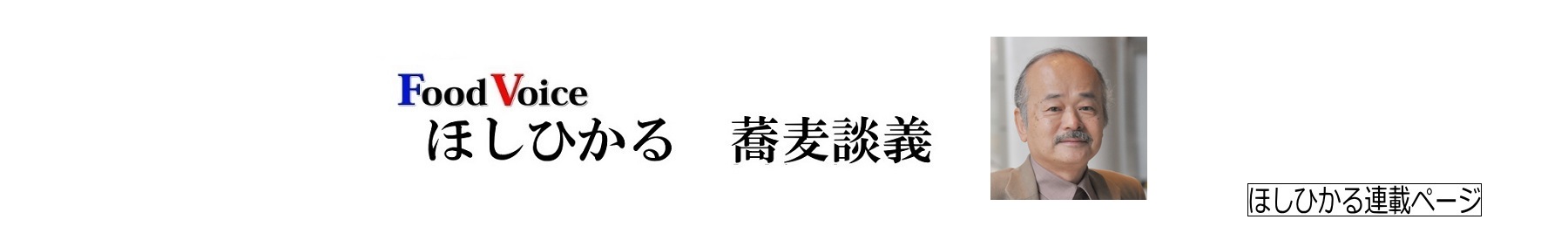第311話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅷ」
2025/12/06
~ 愛してる ~
野中は山本部長からまた課題をもらった。
ソウルの漢江循環器中央病院で講演を頼まれたから、一緒に行こうというのである。アメリカで開催された学会で、Dr.Kimと知り合って話が合い、「来韓しないか」と誘われたらしい。部長は、漢江循環器中央病院の病院長から東京消防病院長宛ての講演依頼書を送付してもらうよう、秘書の上村さんに指示していた。
個人的な頼まれごとでも、公的な仕事にしてしまう、山本医師らしい考え方だと思った。
野中は、(そのくらいの経費捻出は、何とかなるだろう)と踏ふみながら、山本部長に倣って、(公的な仕事にするにはどうなんだろう)と頭の体操風に考えながら、山本部長の話を聞いていた。
すると、最後に部長は付け加えた。「君の会社は、韓国輸出はどうなんだ?」
「輸入物は販売していますが、海外輸出はありませんね。」
「だったら、これを機会にマーケットリサーチしたらどうかね。」
これは営業マンの域を越えた仕事である。ではあるが、そういうことを考えてみるのも面白い。そう思った。
野中は山本部長室を出たが、廊下を歩いているときだった。
後で思うと、映画だったらベートーベンの『運命』でも聞こえるかのような場面に遭遇した。
昔から、野中は人と偶然に再会することが、おかしいくらいによくあった。
たとえば、ある人物と路上で4. 5年ぶりに会ったので、暫く立ち話をした後に、別れのお辞儀をし、その頭を上げると、さらに向こうからまた別の知人が近づいてくる姿を確認したことがある。その知人ともまた10年ぶりの再会だった。
またあるときは、会社のAと歩いているとき、遠くから知り合いの者が手を挙げてやって来る。野中も手を挙げると、一緒にいたAも手を挙げている。「何だ?」と思ったら、その知人はAの従兄だということを知った。どうりで野中もAも手を挙げるはずである。Aと知人と野中は大笑いをしたこともある。
こんな偶然の遭遇をまとめれば「ショート・ショート・ストーリー」ぐらいにはなるだろうが、しかし、これらは聞いて面白いけれど、あまり深い意味はない。
ところが、〔らんぶる〕での恵子との出会いは、形としてはよくあるケースだったかもしれないが、いま思えば運命的な奇跡の出会いだったと野中はつくづく思う。
そして今日もまた野中は奇跡の出会いに遭遇した。
消防病院の待合室を通ったとき、その先に野中の方をじっと見ている女性がいることに気が付いた。野中は何気なくその方を見た。
ト、そこに真知子が立っていた。野中は心臓が停まるかと思った。真知子は10年前と同じく和服姿であったが、真知子は黙って頭を下げて、優しい笑みを浮かべた。
19歳の野中は、この笑みに強く魅かれたのだった。
ずいぶん女らしくなったと思いながら野中は声をかけた。「お久しぶりです。」
「お元気そうですね。」
それは何でもない普通の挨拶だったが、九死に一生の苦い体験をしたばかりの時だったら、野中には辛い言葉だったろう。しかし真知子はそのことを知らない。野中は気を取りなおして訊いた。「どうしたんですか?」
「美知子のお義父さまが、入院なさっているので、お見舞いに参りました。」
「美知子さん? ああ、たしか妹さんでしたね。」
二人の会話は、どことなくよそよそしかった。
「ええ・・・・・・、」
「・・・・・・、」野中は何をどう話したらいいのかと、次の言葉を探した。しかしせいぜい「そこに座りませんか」と言うぐらいだった。
「は、はい。」真知子の声も小さく、迷いがみられた。
「じゃ、美知子さんも見えてるの、」
「いえ、美知子はお仕事中ですから、」
「健ちゃん、イエ野中さんは、お仕事? ですか。」
二人の間にはまだ見えない壁があった。
野中と真知子は高校の同級生だった。卒業後、野中は東京の大学へ、真知子は福岡の短大へと進んだ。高校のころは普通の友だちだったが、段々きれいになっていく真知子に魅かれて、恋焦がれるようになり、とうとう東京からその気持を綿々と綴ったラブレターを送った。
そして夏休みの帰郷のとき、喫茶店で待っている旨の手紙を投函して、柳川に戻った。野中は待った。
しかし、現れたのは真知子の母だった。
「健ちゃん、ごめんなさいね。あんたがそういう気持だったなんてちっとも知らなかったよ。もっと早く言ってくれればよかったのに、」
母親のそんな言葉を聞いて、野中は失神しそうになった。真知子はどちらかといえば真面目な父に似ていたが、この母親は美人の方だったが、開っ広げなところがあった。
その母親の「もっと早く言ってくれればよかったのに」という言葉が今の野中には返って悔しさを意識させた。「ううう、」とついつい感情を抑えきれずに嗚咽してしまった。
母親はびっくりして、ハンカチを差し出した。そして煙草を取り出し、火を点けた。「真知子から健ちゃんのことを聞いてね、お父さんとも相談したんですよ。」
野中はじっと俯いたまま聞いていた。
「知っての通り、うちの〔黒木茶舗〕は昔からのお茶屋でしょ。絶やすわけにはいかないのよ。私も姉妹の長女だったの、それでお父さんを養子として迎えたの。それで今は真知子と美知子の娘二人でしょ。真知子はね、店をやってもいいと言ってくれたから、養子さんになる人を探していたの。そしたらやっと見つかったね、先月結納を交わしたばかりなの。まだ真知子は学生だけどね。そこに健ちゃんの話を真知子から聞いたのよ。」
野中は黙って聞いていたが、「結納」という刺激的な言葉を聞かされ、絶望感をもった。
「真知子も、迷ったようだよ。」母は語気が少し強くなった。
野中は、母親が「余計なことをしてくれたね」とでも言ってるように聞こえた。
母親は続けた。「私もね、健ちゃんと真知子ならいいなと思ったわ。でもね、お父さんは世話になった人たちに申訳ないから、今の話を進めなさいと言ったの。真知子は親孝行だから、お父さんに言う通りにしますと言ってくれたの。」
母親はまた煙草を取り出した。
「健ちゃん。」
「はい。」野中の声は小さかった。
「うちのお父さんはね、心の中じゃ私と同じだったかもしれない。でもね、ああ言わざるをえないの。養子のお父さんは、家を守らなければと思っているの。分かる? うちのお父さんはあれでも男らしいのよ。」
「家」のことを言われ、野中は自分は何て子どもなんだと、打ちひしがれてしまった。
「だからっていうわけじゃないけど、貴方も男なら、いさぎよくなりなさい。真知子ぐらいの女なら、これから健ちゃん、いっぱい見つかるよ。」
最後の励ましや慰めなんかは、もう野中の耳には入ってなかった。
店を出た野中は乗ってきた車を運転して帰るつもりであったが、何処をどう走ったか、まったく覚えていなかった。
気が付いたときは、山のS字道をスピートを出して走っていた。道はジャリだった。野中はハンドルを切り損ねた。慌ててブレーキを踏んだが、車はジャリで滑った。アッ!と思ったが、遅かった。車は崖下に飛び込もうとする。野中は目を瞑った。ドン!! と車はL字型に曲がって聳えていた大きな松の樹にぶつかって停まった。前輪は宙に浮いたままだった。野中は (真知子に振られた今、どうにでもなれ) と思って目を閉じた。
2時間か、3時間ぐらい経っただろうか。通りかかったダンプカーが野中の車を見つけて、綱で引張って引上げてくれた。車の前は凹んでいたが、何とか動いた。まさに九死に一生だった。
「健ちゃん。」真知子は若いころ呼んでいた名前を言った。「お嫁さんは?」
野中は困ったような顔をして首を横に振った。
真知子は眉を曇らせて、下を向いた。
野中は慌てた。「いや、彼女みたいな人はいるんだけど、まだ・・・、」
真知子の目が少し明るくなった。「健ちゃんなら、その方を大事にするでしょうから、きっと・・・、」
「・・・・・・、」野中は何と返事していいのか、分からなかった。ただ、真知子との厚い壁が少しだけ崩れかけたような気がした。だからといって、野中は真知子に近づくようなことはしなかった。過去に戻ることは、いま一番大切な恵子を裏切ることになると思った。ただ10年を経て、真知子との壁が少しなくなったような感じになったのは野中にとって救いだと思った。
真知子は立ち上がった。「お会いできてよかったわ。」
「僕もだよ。」
「健ちゃん。幸せになってね。」
「真知子ちゃんも、」
「ありがとう。」
野中は真知子を玄関まで送って行った。いま思い出せば、真知子のお父さんとお母さんは偉かったナと思った。しかし野中はそのことを真知子に言わなかった。入院しているという、妹のお義父さんの名前も、担当医も訊かなかった。そのようなことをして、再び昔の世界に戻るようなことは、恵子のためにしてはいけないことだと思った。
真知子は振向いて会釈をし、去って行った。
病院の玄関のドアが閉った。
野中は (サヨナラ) と呟いて、地下の駐車場へ下りて行った。
野中は会社に戻って、山本部長のことを病院部長に話して、出張の許可をもらった。
話を聞いた佐藤たちは「先輩、大丈夫ですか?」と半分笑いながら、心配してくれた。
昨年、韓国へ行っていた会社の者が、朴大統領暗殺事件に遭遇し、数日足留を喰ったことがあるからだ。
野中は「ン~、だから面白いじゃないか」と笑った。
実際、野中は子供のころから、未開拓分野に行くとか、他人が行かない時に行きたがるような臍曲がりのところがなくもなかった。
佐藤は「ノナさんらしでいね」と言って笑った。
翌月、山本部長と野中は成田空港から飛び立った。金浦空港までは約2時間。二人とも韓国は初めてだった。
機内で読んでいた週刊誌はゲートを出るときに没収された。情報統制が厳しいようである。
空港には旅行社の人が迎えに来てくれた。
先ずは、タクシーに乗って、ホテルへ向かった。車は現代自動車、タクシーは車線規制やスピード規制がないかのよう突っ走った。煙草を吸おうとして灰皿を探すと、ガイドは空き缶を指してそれが灰皿だと言う。
ソウルの空はグレーだった。
街行く人たちの服装はかなり地味である。チマチョゴリを着た人もいる。
〔ホテル シーラ〕へ付いてから、夕食のためにソウル市内の店に案内された。その店で、山本部長はビールだけ飲んで「悪いけど食欲がない。ホテル戻ろう」と言った。
旅行社の人には帰ってもらったところで、山本部長が不愉快そうな顔をして言った。「あの店の大蒜や唐辛子の匂いには参ったよ。もっと他の店はなかったの。」
「申訳ございません。」
「ここのホテルで食事をしょう。」
ホテルの雰囲気は清潔そうである。ここならよさそうだと思ったが、実際、食事もコーヒーも普通だった。それに比べると、あのレストランの鼻につく匂い、大盛の皿、鮮度のなさそうな生の物・・・。日本の食事とはまったく異質のものだった。山本先生がクレームを突き付けた気持も野中には理解できた。
翌朝は病院から迎えが来た。
病院に到着すると、お土産のネクタイとウィスキーを金ドクターに渡した。
さっそく、院長他医師たちの紹介を受けたが、会う人会う人が金さんや李さんという姓ばかりで訳が分からない。それから院内の外来・薬局・手術の状況、カンファランスの様子などを見学。韓国の保険制度は日本と同じようだったが、その他はとくに目新しい発見はなかった。山本部長が言っていた、マーケットは小さいだろうと思った。午後から山本部長の講演となった。
夜になると、病院が二人を接待してくれた。店は〔韓国レストラン 燕〕といって、なかなか立派なレストランであった。
最初はビールで乾杯、ラベルを見ると〔OBビール〕とか〔クラウンビール〕とか書いてあった。すぐにお粥が出た。金先生が言う。「韓国人はお粥が大好きなんです。」
続いて、栗・人参・芋などが大盛で出てきた。これは生のままで食べるという。こんな食べ方は初めてである。
「山本先生、野中さん。韓国の料理は歴史があります。今度見えたら〔宮廷料理〕をご馳走します。ぜひまた来て下さい。」
と言ったかと思うと、金先生たちは「米:イの対立をどう思うか?」とか言ったりして、政治に関心が高い。日本人だったら接待のとき、こんな政治情勢の話は持ち出さないだろう。とくに「北は怖い」という言葉を何回聞いたことか。現在の韓国は崔圭夏大統領体制であるが、朴大統領暗殺後は、解放感もあるが、緊迫感も漂っている。
「朝鮮半島の対立は資本主義対共産主義の問題ではない。建国当時からの、騎馬民族対農耕民族の宿命的な闘争だ。その国民感情の複雑さは日本人の想像以上だ」とは、野中の会社の小田社長の歴史観だが、金先生らと話していると、たしかにそんな感じがする。
それはそれとして、金先生は自ら酒を注いだり、踊ったりと大サービスもする。
「『サランヘ』というのは日本語で『愛してる』という意味です」と言うや、歌い始めた。
サランヘ タンシヌル チョンマルロ サランヘ
タンシニ ネギョトゥル ットナガン ディエ
オルマナ ヌンムルル フルリョンヌンジ モルンダオ
イェイ イェイ イェイ ・・・♪
食事の最後は麺である。
金先生が説明してくれた。「韓国人は麺も大好き。日本人と同じですね。」
二人が肯くと、金先生は続けた。「昔、中国から麺が来たので『麺(ミョン)』という言葉も使いますが、韓国語では『クッス』という言葉を使います。『クッス』という言葉は、18C後半~19Cごろから使い始めたようです。私は知りませんでしたが、韓国の食に詳しい友人が教えてくれました。中国から入ってきた麺を韓国人は大好きになり、蕎麦・緑豆・大豆・葛・黍・山芋・天花(タカヨモギ)・栗・百合と、何でも麺にしたようです。それが18C後半~19Cだというのです。こうしたことを経て、韓国人は麺が好きになったのです。どうですか、面白いですか?」
「なるほどね。」山本部長も野中も感心した。そこには日本人とちがって、韓国人の〝愛国心〟のようなものが感じられた。
二人はホテルに戻ってから、ホテル内にあるナイトクラブで一休みした。
明日は、金先生らとゴルフ、さらに明後日は陶磁器に関心をもっている山本先生の希望で、国立中央博物館と窯元を見学し、その後に金浦空港から帰国の予定である。2日とも時間に余裕がある。
野中は提案した。「先生。韓国は射撃をやらしてくれるみたいですよ。」
「ああ、そうか。何か懐かしいな。」
「え?」
「子供のころ、チャンバラとか、玩具のピストルで戦ゴッコみたいなことをやったね。」
「そうですね。私のころは『笛吹童子』とか『紅孔雀』なんで流行って、二組に分かれて、戦ゴッコをやってましたよ。」
「行ってみませんか。」
「そうだな。」
「それにしても、金先生たちはサービス精神旺盛ですね。私なんか足元にも及びませんよ。」
「最初の日は悪かったね。」
「えっ?」
「食事する所が、ひどいのは君の責任みたいなことを言ってさ、」
「いいえ。」
「あれが、この国の食事なんだね。今日の〔燕〕も高級レストランだったと思うよ。だけど、やはり僕の口には合わなかった。金先生たちには悪いから美味しかったと言ったけどね。」
「いいえ。先生の問題じゃないと思いますよ。日本料理と韓国料理はまったく違うようですね。われわれは匂いのキツイものはダメですよね。」
「日本の料理は清々しいからな。」
「新鮮な刺身、盛付もきれいに・・・と。」
「そういえば、昭和の今の日本の食事が世界で一番健康的にバランスがいいといって、アメリカでは注目されつつあるんだよ。」
「へえ、そうなんですか。」
「それはそれとして、金先生が麺の歴史を述べたように、僕は鮨や蕎麦や天麩羅の歴史を外国から来たお客さんに語ることができるだろうか、と反省もしたよ。それから、さっき君が誘ってくれた射撃は、やっぱり止めておこう。」
「分かりました。」
「子どものころは子どものころ。今の僕は人の命を救う医者だ。その僕が殺人の道具で遊ぶわけにはいかないよ。」
「・・・・・・。」野中の胸の中ではギャフンと言っていた。
二人はそれぞれの部屋に戻った。
時計を見ると11時少し過ぎ。野中はテレビをつけた。白黒だった。チャンネルを回すと3局あるようだが、どこもニュースのようなことをやっていた。それも11時半になると、放映が終わった。(そうだった。韓国のテレビ放映時間は、平日は夕方6時から夜の11時半まで、土日は午後1時半から夜11時半までと聞いていた。) 野中はテレビを消した。
それから、バスルームに入って湯に浸かったが、野中は山本医師が言った言葉にまだショックを受けていた。
「人の命を救う医者が殺人の道具で遊ぶわけにはいかない。」
(オレは何という情けないことを言ったのだ) と後悔した。製薬業界で働く者として、倫理感のなさを恥ずかしく思った。
山本先生という人は、東大医学部 ⇒ 東大医局という東大の譜代大名とは異なって、他の大学を卒業した後に医局だけ東大を出た、いわば外様大名である。だからこそ、がんばって今の〔山本学校〕と呼ばれるシステムを作られた。それにはああいうしっかりした倫理・理念があるからだろうと野中は思った。
野中は、先ほど金先生が歌った〔サランヘ〕が、思わず口からこぼれた。
(「サランヘ」は「愛している」という意味です。)
野中は、バスで【Lovin’you】を歌っていた恵子のことを連想した。(恵子と海外旅行でもしてみたいな。) そんなことを考えていたら、ベッドに入っても眠れなかった。
野中は起き上がって、ソファに座って煙草に火を点けて、ボーっとしていた。
やっと夜中の1時になった。野中は恵子の電話番号を交換に言った。
ベルはすぐ鳴った。
「もしもし、健さん!」恵子の声がする。
「うん。」
「電話くれでありがとう。どうしてるかなって思ってたところよ、」
「今すぐ会いたい気持、」
「嬉しいわ。」
「サランヘ」
「エッ?」
「いや、好きだよって言いたかったの。」
「ま~!どうしちゃったの? 立て続けにそんな優しいことを言ってくれて♪」
「いま、そういう気分になってんの、」
「ふふふ、ホームシックになったんでしょ。日本に帰ってきたら、オレそんなこと言ったっけ、なんて言わないでね。」
「言わないよ。ン~、もしかしたら言うかな、」
「いやん。」
恵子の声を聞いた健は、やっと落ち着いて眠ることができた。
健から国際電話をもらった恵子は、成田に迎えに行きたいと思った。
便名と到着時間は聞いていた。丁度、その日は日曜日。
恵子はお手伝いの洋子に頼んで、一緒になって食事の支度をしてもらった。前に店の女の子たちと一緒にハワイやパリに行って、日本に帰ったとき、みんなが「ああ、日本の料理が美味しい」と言ってたことを思い出し、洋子に和食にしてほしいと頼んだ。
洋子は洋子で、浮き浮きしながら働く恵子を見て、自分のことのように嬉しく思っていた。
お手伝いの洋子は若いころ、一人娘を亡くしていた。それが原因で夫とも別れた。亡き娘は恵子と生年月日が同じだった。そのことを恵子には言ってなかったが、洋子は給料をもらわなくてもいいから、恵子の面倒だけは自分の身体が動くかぎりやっていきたいと密かに思っていた。
洋子は、恵子から野中さんという恋人がいるということは少し聞いていた。洋子が知るかぎり、恵子の彼を思う気持は本物だと感じていた。
洋子は、恵子が幸せになってほしいと亡き娘の位牌に祈ってあげることもあった。
【ご飯、お味噌汁、秋刀魚の煮付、鶏肉・じゃが芋・蒟蒻の煮物、金平牛蒡、和布の酢物】
「こんなものでよろしいのでしょうか?」洋子が申訳なさそうに言う。
「そう、これがいいのよ。外国から戻って来た人はね、皆さんご飯とお味噌汁が美味しいって言うのよ。」
「そんなものでしょうか。」
支度が終わってから、恵子は成田へと出かけて行った。
洋子は、恵子を見送ってから、帰って行った。
恵子はゲートで待っていた。胸が少し高鳴ったが、こうした時間にも幸せを感じていた。
しばらくして健の顔が見えた。健は気づかないようだった。
山本先生らしき人は野中とちょっと話してからその場を離れた。その人は電話ボックスまで行って電話をかけて、終わると野中に手を振って、タクシー乗場の方へ去って行った。
野中は先生の後姿に一礼すると、恵子の方へ真っ直ぐ歩いて来た。
恵子は驚いた。(何だ、気づいていたのか)と嬉しくも思った。
「お帰りなさい。」
「ただいま。」
「気づいていた?」
「そりゃ分るさ、きれいな人がいるから、すぐに分かるさ。」
「え~! びっくり、」
「どうして、」
「ううん。ふふふ。」
恵子がタクシーを拾った。運転手が荷持をトランクに入れている隙を狙って、恵子は健の頬にキッスをした。「さっき『きれいだ』って言ってくれたご褒美よ」と言って、ハンカチを取り出し、頬に付いた口紅を拭いてやった。が、わざと少しだけ残して、悪戯っぽく笑った。
気が付かない健は恵子の手を握って、指と指を絡ませた。
恵子のマンションに着いてから、健は鞄から二つの花瓶を取り出した。池順鐸作の青磁と、安東五作の白磁だった。
「まあ、きれい。」
「だろう。国立中央博物館に行って、高麗青磁と李朝白磁を見たときはうっとりしてしまった。だから窯元へ行ったとき買ったんだ。」
「健さんは焼物が好きだったの。」
「そうでもないけど、この風格に魅かれたのさ。日本には日本刀という凄いものがあるけど、陶磁器はやはり中国か、朝鮮の物が本物だとつくづく思ったよ。」
「あなたは美術が好きなの? 知らなかったわ。」恵子はちらりと父のことを想った。
「そういうわけではないけど、いい物はいいと思うよ。そういう感性を持っていたいというだけのこと。女性の中ではキミに一番魅かれたように、」
「エー! どうしちゃったの?」
「何が?」
「だって、ソウルからの電話では『会いたい』とか、『好きだ』とか、空港では『きれいだ』とか・・・。そんなにホントのことばかり、フフ♪ 言ってくれるなら時々外国へ行ってちょうだい、っていう感じよ。」
「ははは。一つはキミへ、一つは僕自身へのお土産、どちらか選んで。」
「え~、ほんとうに頂いちゃって、いいの?」
「もちろん、キミに買ってきたんだから。」
「嬉しい。どちらが窯元で?」
「白い方。」
「じゃ、白磁の方を頂戴。」
「よかった。青磁のこのラインはキミの身体のラインみたいだから、手元に置いておきたかった。」
「ンもう。」
「でも、どうして白磁を選んだの?」
「形もいいけど、それよりもわざわざ窯元まで行ってくれたあなたの匂いが残っているような気がするから、」
「んもう。」
「いやん、真似しないでっ、ンもう。」
翌朝、健は会社に出かけた。
恵子は一人ベッドに取り残されていた。健が出かけた後、まだ温もりが残っているベッドに潜りこんでいたが、まさに「取り残された」感じだった。
昨日一日は幸せだった。新婚夫婦のように浮き浮きしていた。子供のママ事のように楽しかった。成田に迎えにも行った。昨夕はこの部屋で食事を一緒に食べた。今朝は健が出かけるときに恵子も起きて、トーストを焼いて上げた。
恵子は健のお世話をすることがこんなに幸せなことかと思った。
それに何よりも嬉しかったのは、健が初めて「きれいだ」と言ってくれたこと
だった。恵子は、健がこれまでそれを言ってくれない理由を何となく察知していた。その原因は自分の水商売にあると分かっていた。「きれいだ。きれいだ」と軽々しく言う客を営業のあの人は知っている。だから、それとは一線を画したいという気持があるのだろうと思っていた。それに応えて恵子も仕事のことは口にしないようにしていた。健も、自分も、愛し合っているからこそ、互の気持を尊重しているのだと思っていた。しかし、気遣いはハードルがあるから気遣いである。恵子にはそのハードルが歯痒かった。 (素直に話ができない関係、このままでいいのだろうか?) そう思うと急に不安に襲われくる。恵子は枕に顔を埋め、何かを堪えていた。今の恵子は、人も羨む銀座の高級クラブのママではなかった。一人のただの少女だった。
(Ⅸ.A Lover’s Concertへ 続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕