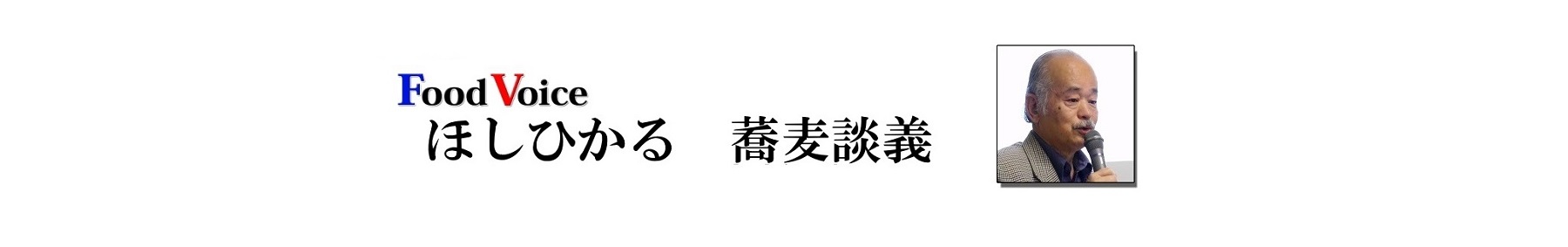第412話 万葉の珍味《がんつけ》
佐賀の実家にはもう誰も住んでいないから、帰郷したときは「画家の青木繁ゆかりの宿」といわれる和風旅館「あけぼの」か、あるいはお濠端に建つ「ホテルニューオータニ」に泊まることにしている。
和風旅館の方は食事が美味しいけど、ちょうど今、お濠端の桜が満開だから、今回はニューオータニにした。それに「たまには《ホテルのモーニングセット》もいいかナ」と思ったわけだ。かといって、パン、コーヒー、各種ジュースはじめ、テーブルに並んでいる玉子、野菜サラダ、ベーコン、ウィンナー、コーンフレッグや、たくさんのフルーツとトロトロのヨーグルトなどが珍しいわけではない。またどのホテルでも似たようなセットであろうが、これだけ揃う《ホテルのモーニングセット》というのはもはや【ホテル文化】みたいなところがあって、それを頂くことも【旅の証】のような気がするのである。
さて、故郷での用件を済まし、「九州佐賀国際空港」から羽田へ向かうことにする。
その前に時間があったので、土産品売場を覗くと珍しい《がんつけ》が目に留まった。
たまたま、別のところで『出汁・醤油・つゆ』についてのエッセイを書いていたところだったから、さっそく一壜購入した。
この《がんつけ》は「塩辛」の一種で、商品名は《まがに漬》となっている。でも佐賀では《蟹漬 ⇒ がにつけ》が訛って《がんつけ》と呼んでいる。
その《がんつけ》と『出汁・醤油・つゆ』のエッセイがどう関係するのかというと、《がんつけ》は「魚醤」の一種、あるいはルーツとみられているのである。
たとえば、『万葉集』に蟹と塩を搗き混ぜる歌が載っている。歌の舞台は難波であるが、現物は佐賀の珍味として確認できるというわけだ。たぶん古に中国大陸、朝鮮半島を経由して、北九州に上陸したのであろう。
アジア食文化的視点に立てば、魚醤も塩辛も同類である。だから《がんつけ》はもともとは塩漬けであったのだろうが、今の物には唐辛子も入っている。
だから「辛い、鹹いぐらいか」と思って、この万葉の珍味を口にした県外の人や現代の佐賀人はたいてい口をへの字に曲げながら「ウワッ、これ何ですか!!」と衝撃を露にする。
この《がんつけ》というのは、「真蟹=まがね」を殻ごと粗く潰し、塩と唐辛子で漬けたものである。「まがね」は3cmぐらいの小さな蟹だけど、片方の鋏だけが身体より大きく、その大きな鋏をオッ立てた様は異様だが、別の目で見ると、小さな体で有明海の潮を招いているかのようだということから「シオマネキ」という学術名が付けられた。
《がんつけ》は、そんな「まがね」の殻をそのままジャリジャリと噛んで食べる。スルト、辛い! 鹹い! を通り越し、その殺伐した野蛮性に、たいていの人は「ウワッ!」という言葉を発してしまうのである。
よく、古の食べ物が復刻再現されると、「古代人はグルメだった」などとマスコミは常套文句で報道するが、この《がんつけ》もそうだし、時々再現料理を体験している私は、「決まり文句ほど当てにならないものはない」と思っている。他にも、邪馬台国論などは、決まって九州説:近畿説を対抗軸として並べた書き方をするが、過去の歴史における文明・文化の東漸は、列島の気流が西から東へ流れるがごとくに自然のことであるのに、これも興味を誘導する記事の手段であろう。
とにかく、日本の魚醤は江戸時代からの「いかなご醤油」「いしる」「しょっつる」などがわずかに生き残っているが、日本は仏教の影響で、穀醤の味噌・醤油が大いに発展することになる。それゆえに、「魚醤」は珍味の類であるといえる。
そうした歴史の忘れ物 ― 、それが郷土食である。
そのひとつである《がんつけ》を熱いご飯にのせて口にすると、たとえ他国者が「ウワッ!」と悲鳴を上げようと、その風土に育った者は、この原始クササ、泥クササが一入だと思うのである。
〔文・絵・写真☆エッセイスト ほしひかる〕
《参考写真》
・佐賀の珍味「まがに漬」(平成29年4月12日撮影)
・韓国の塩辛「アミ塩」、韓国の魚醤「イワシエキス」はJKフーズの商品(平成29年4月14日ウンナンの会にて撮影)

アミ塩

イワシエキス