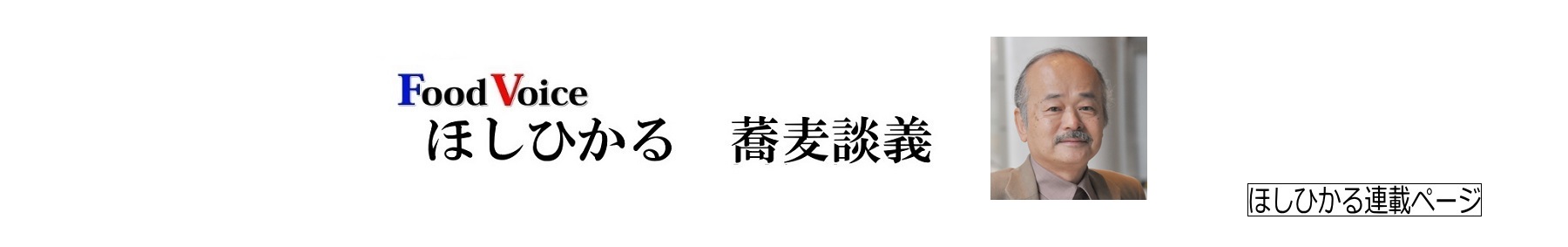第282話 ほの甘い小説 「いきの構造」
2025/12/06
~ 青い時間 ~
桜吹雪の季が終わろうとするころだった。
友だちの遥さんから「隠れ家のような蕎麦屋があるから行きましょう」と誘われた。彼女の仕事はテレビのディレクター。何でも興味を示す人で、仲間と女性だけの食の集まり「小粋の会」なんかをつくったくらいの人だから、「どんな店?」なんて、野暮な確認はしない。行く先は女舟頭さんにお任せの舟に乗った。
約束の日、明け方に降っていた小雨も止んで、空は瑠璃色に晴れわたっていた。
僕は「未知駅」という小さな駅で降りて、駅前を流れている川に架る石橋を渡った所で待人を待った。駅前は、この橋のためにタクシーが入って来ないから、橋を渡った大きな桜樹の辺りで待っててほしいと言われていたからだ。
その橋は、よく長崎の街で見かける眼鏡の形をした橋だった。古くからあるのか、石の色はなかなか重厚で、所々に苔や草が生えていた。
樹木には若々しい葉が顔を出し初めていた。流れる川面を見るともなく見ていると、上流から花筏が幾つも幾つも流れてきていた。
「お待たせ、」背後から声をかけながら遥さんが現れた。
振り向いた私も右手を上げて挨拶をした。
遥さんは着物姿である。深緑色のスキッとした生地に菜の花色の粋な経縞が三筋立に走っている。よく似合っていた。そのためか僕は胸がときめいた。
目指す店は、駅から少しあると聞いていたから、僕はタクシーを捕まえた。
車の中で彼女は言った。
「そのお店、“コウシャクテイ”って言うの」と僕に言ってから、彼女は運転手さんに「分かりますか? 築地塀のある所ですけど」と声をかけた。
「はい。お蕎麦屋さんですね。」運転手さんが答えたので、「お願いします」と遥さんが言う。
ここでちょっと云っておきたいが、遥さんの声はハスキーの上にややねっとりしている。ジャズシンガーのカサンドラ・ウィルソンのCDを聴いたとき「あ、遥さんの声に似ている」と思ったことがあった。たまたまニューヨークのWest 3rd Streetにある「ブルーノート」で彼女が歌っている日と遭遇し、聴いてから、ますます好きになった歌手だ。そんな遥さんの声を耳元で聴かされるとゾクっとする。その震えを隠すようにして、僕は訊き返した。「コウシャクテイ?」
彼女は僕の方に向き直って言った。「お店は、看板を出してないの、」
そのとき、揺れた彼女の髪からほんの微かにスイートフローラルな香りがしたような気がした。
「・・・・・・」
「店主の姿を見た人があまりいないの。だから、滅多に顔を出さない、元侯爵様かしらって、おっしゃる方もいらっしゃる一方では、たまにお顔を出したら講釈が始まって止まらないとおっしゃる方も、」
「フッ。成るほどね。要するに謎の人物というわけだ。」僕はまだ見ぬ店主のイメージを無理に決め付け、自分を納得させながら、遥さんの、誘惑するような甘い花様の香気が一瞬で消えたにも関わらず、なおもそれを堪能していた。
そういう束の間の僕の幸福感も知らず、遥さんは続ける。「それなのに、店主は“柳亭”の最後のお弟子さんっていう噂もあるのよ。」
「“柳亭”の! それは凄いな。」僕はにわかに興味をもった。
京都高台寺近くの“陶然亭”という食通御用達の隠れ家があるという。その弟子の大阪船場の“田舎亭”、そのまた弟子の東京麻布二ノ橋の“柳亭”の三軒は、食通の間では伝説となっている。僕はそうした世界とは縁がなかったから、それらの店を訪ねたことはなかったが、名前ぐらいは耳にしていた。
「共君一醉一陶然」
「エッ?」
「白居易の詩だって。北京の、陶然公園に立ち寄ってとき、この詩を知ったんだけど、“陶然亭”の名は、それに由来するらしいよ。」
「えっ、そんな公園があったの。」
「君は、北京へ行ったときは、よく胡同へ行くよね。好きなんだ。」
「そう、」と言い終わらないうちに彼女は運転手さんに言った。「そこで止めてください。」
どうやら着いたようだ。築地塀の前で車のドアが開いた。
不覚にも、僕は遥さんに気持を奪われていたため、何処をどう走ったか道順を覚えていなかった。
玄関の脇の、魚尾形の細長い小旗のようなものが微かな風で揺れていた。横目で見ると「手打蕎麦」と書いてあった。他にはたしかに看板らしきものはなかった。
二歩先を歩く彼女の後姿は相変わらず凛としていた。このとき僕は、ある女優さんが「女は背中で歩くのよ」と言っていた言葉を思い出し、成程と思った。
遥さんは砥草色の大きな暖簾を分けて敷居を跨いだ。その瞬間、着物の裾から遥さんの白い足がちらりと覗き、また隠れた。
僕も遥さんの後について暖簾をくぐった。その暖簾の左下の方には先ほど渡った眼鏡橋が染めてあった。「あ、あの橋だ」と僕は思いながら入ると、すぐにショパンのピアノ「ノクターン第2番」が転がるように流れてきた。部屋の隅に設置してあるスピーカーは、あのデザインからするとフランコ・セルブリンである。音質がいいはずだ。ただ、ピアノの旋律は基本的には蕎麦と合わないかもしれない。だが、その繊細さは、江戸蕎麦の細さと合わないでもないと感じることもある。
足元は敲土であった。丼鼠色のしっとりとした土が控えめな光沢を放っていた。彼女の白い足袋が際立って見える。
店内は電灯だった。それに思ったほど広くない。四人掛の卓が五つ。先客が一組入っていた。
「いらっしゃいませ」。黒いシャツに黒のピッタリしたパンツ姿の若い女性が先客とは離れた卓に案内してくれた。
卓の板は相当に厚い、それに自然のままの形をしていた。隣の卓を見比べると、各々形が違っている。椅子は欧州の宮殿あたりに合いそうなバロック調だった。僕は先に彼女に座ってもらってから、ゆっくり腰を下ろした。座り心地のいい椅子だった。そしてあらためて遥さんの姿を見てみると、彼女の背後にある大きな美濃焼の花瓶に生けてある白いカサブランカたちをまるで従えているかのように絵になっていた。
見とれていると、先刻の黒シャツの女性が蕎麦茶とお品書を持ってきた。蕎麦茶の焼いたような香ばしさが辺りの空気を変えた。
彼女もまた素敵なプロポーションの持主だ。しかしその店員さんはすぐに引下がった。
「今日は、目の保養デイかな」と思いながら、卓の上を見ると、桜の花弁の形をした小さめの箸置の上に先の細い竹の箸が用意してあった。
「このお店はね、毎月箸置が違うの。桜、紫陽花、菖蒲、水仙、椛、桔梗、柿、椿・・・・・・、あとは何だったかしら、」
「なるほどね。」
「ちょっとお花のデザインがユニークでしょ。でも、すこし小さいわね。」
「箸置だから、それでいいじゃないの。」
「そうか。箸置君、君は脇役ですよ、っていうわけね。ふふ、」
胸の内の幸福感とは別にそっけない返事をしている自分にやや呆れていたが、彼女の「ふふ、」に救われ、僕はお品書を取って隅まで眺めた。
メニューの中に「常陸秋そば」の名前が記してあったが、それとは別に「今月の蕎麦は対馬在来です」と筆で書いた栞も挟んであった。それを見て、やっぱりいつものように《笊蕎麦》にしようと思った。
そのとき、先ほどの黒シャツの店員さんが近づいてきた。「何にいたしましょうか」。
タイミングがいい。一旦離れて、頃合を見計らって現れる。教育がゆき届いていると思った。注文を受けるまで横に立っておられては鬱とうしいものだ。
しかし今日は案内人にお任せである。黙っていると、彼女が注文してくれた。「“直侍”を冷やで、それに万願寺甘唐、マシュマロと人参の天ぷら。」やはり彼女はいい声をしている。でもカサンドラ様の声もお酒によって七色に変化するようだ。時にはハスキーのダイアナ・クラールにもなるし、時には粘りのあるサリナ・ジョーンズの声にもなる。サリナの生の歌は聞いたことはないが、CDではよく聞く。なかでも魂の籠った「I Love You」はほんとうに癒される。
そんな遥さんの声に反応してか、先客の男性が何気なく、こちらを見た。
今度は彼女、可愛らしく言う。「ちゃんと憶えてるでしょっ。」
僕は笑った。ずっと前に、身体にいい食べ方は、空中に生っている物、土に生えている葉物、土中の根物の順で食べるといい。なんてことを僕が言ったのを憶えているというわけだ。
「論理的とは思えないけど、何か理屈が通っているのよね」
「そう?」
「私、油断すると太るタイプだから、守っているの。母や姉と温泉に入ったとき、そう思ったの、」
美人から裸を想像させるような話を聞くのは刺激的だ。気のせいか湯の香が鼻先を横切った。
遥さんはといえば、そんなことにはお構いなく、注文に精を出す。
「鴨はどこの?」
彼女は、私が好きなものを知っていた。
「シャロンです。」
「すてきだわ。じゃ鴨も、」
「かしこまりました」と答えると黒シャツの彼女は奥へ引っ込み、すぐにお通しを持ってきた。
揉んだ浅草海苔に花鰹を一撮み込んだものに醤油をかけ、擦山葵を添えてある。
「これが噂の陶然亭流のお通しか」。
海苔の香りと鰹の味と山葵の気が鼻先で踊っている。
これが江戸の香りだ。通の間では芸術品ともよばれている。
続いて店員は、ウルトラマリーン色をしたガラスの徳利と猪口を運んできた
“直侍”というのは紀州の酒らしい、最近彼女はその酒蔵を訪ねたとか言っていた。元々は浅草の隅田川酒造が明治時代に売り出した銘酒だが、東京大空襲で焼失したのを復元したものらしい。その酒蔵の杜氏は女性のためか、お酒も女性に人気だという。
僕はガラスの徳利を手にして、彼女の猪口にお酒を注いだ。
徳利と猪口はヴネツィアのアイス・グラスのような骨董品だった。もちろん元々は徳利でも猪口でもなかったのだろう。
「ありがとう」と言って、彼女も僕に注いでくれた。軽く乾杯の仕草をしてから、舌を濡らした。
「旨い」。酒に強くない僕だけど、酒の味は分かる。ほんの少しだけ酸味、あるいはデリシャス林檎のような漢方のような味がしないでもなかったが、「日本酒の中の日本酒」というたしかな深い風味がした。
「君は、着物がよく似合うね。」
「ありがとう。そう言ってくれれば朝から格闘した甲斐があったわ。」
「こうして座っているときも、歩いているときも、」
「ああ、美味しいお酒だわ。私、褒められるの大好き、ふふふ。」
「君と仕事をしたら、どちらが女優さんか、わからないだろう。」
「そんなことはありません。それに、私は演技には興味ないの、」
「そうかね。」
「ね、前にね、ひろすえ涼子と篠原涼の歩く姿を前から見ると、色っぽいと言ったでしょ。」
「そんなこと言ったけ、」
「言いました。たまたま二本の映画を見るときがあって、見ていたの。そうしたら確かにそうだったわ。もう若いとはいえなくなったけど、もちろん熟女というほどではない年ごろの女性の色香が太股あたりに走っているのを、女の私でも感じたの。だから確かに『前から見ると』よね。同時に、『アイツはいつも何処を見てんダ』って思わず叫びそうになったわ。アイツって貴方のことよ。ふふ、」
「僕はどこも見てないよ。」
「うそっ。」
「ほんとだよ。感じるだけだよ。」
「よけい、変だわ。」
「ほんとだって。絵画展なんかに行ったときもサ、会場で一番惹かれる絵っていうか、僕に呼びかけてくれる絵はどれかって探すんだ。絵の一番から五十番までを一つひとつ丁寧に観て回るなんていうことは絶対しない。だから展覧会を観に行っても10分もあれば十分。」
「ふ~ん。全体像をつかむとか、何が一番大切かを見るというわけ? 貴方はライターっていうより、画家か、プロデューサーね。」
「中学校のときの絵の先生がさ、『キミは着眼点がいい』って褒めてくれたから、その気になっていたら、高校時代の絵の先生には『お前は下手だ』って言われてしまってさ、もうがっくり。ははは。」
「中学の先生がおっしゃったように、やはり何かをつかむのはお得意だったのね。この前は『速水優子に赤いワイングラスを持たせるとよく似合うだろう』って言うしさ、ほんとに。事務所の人を知っているから、言っておきましたよ。速水優子には赤いワイングラスがよく似合うって、」
「何か変な雰囲気になったようだから、マ、一杯どうぞ、」
「ありがと。あ~、美味しいわ。」
頷きながら僕は“直侍”の説明書を見てみた。【アルコール分】15.3、【日本酒度】-1、【酸度】1.5 、【使用米】酒こまち58%、とあった。
唐辛子の天ぷらがきた。大きくて緑色が鮮やかだ。おもったほど辛くはない。続いてマシュルーム。これも大きい。小ぶりの餡パンのようだ。だからナイフを添えてある。だけどナイフは一本。彼女がそれをとって十文字にナイフを入れてくれた。そうか、ナイフ一本は、お店のニクイ演出だったのか。
「ありがとう」と言って、かじるとジュースで口の中がいっぱいになった。
彼女も口にしてから、「静岡産なの。ここの農家さんはまだ若いのよ」と言った。彼女の形のいい唇が濡れていた。私はマシュマロにジェラシーを感じた。
ピアノは「幻想即興曲」から「ノクターン第20番」になっていた。この曲は男女で聞くにはいいかもしれないが、旋律はあまりにも甘く哀しすぎる。
遥さんは、年上の恋人ジョルジュ・サンドが毎日のようにショパンのために作ってくれたショコラのせいでショパンの旋律は甘くなっているのだと言っていたが、そんな見方をする遥さんにも恋人にトコトン尽くすようなところがあるのではないかと思ったりした。
ショパンはピアノ演奏に革命を起こした人でもある。彼の手は小さかったらしい。友人のリストと比べても彼の指は短かった。そのためピアノの演奏者としては失格ともいわれた。しかしショパンは手首をしなやかに動かす演奏法を編み出していった。その結果、打楽器的なピアノから脱却して、優しく哀しい旋律が彼の手首から生まれ、人の心を魅了したのである。
そんな話を高校時代の友人である山岡という男にしてやったことがあった。彼は指が短かく、蕎麦打ちのとき困るとぼやいていたからだ。
話したとき、「持つべきものは、やっぱり友だな」と言って、山岡は喜んでいた。彼は山登りもやっていた。百名山のうちやっと五十幾つ登ったとか言っていた。しかし四年前の冬の日にトムラウシの山奥へ行ったきり、二度と戻って来なかった。あいつは言っていた。「危ないと思ったとき、引き返せば助かるのに、あっちへ行けば何とかなると思ってしまう。それが命とりだと皆言うけど、あっちの魔力ってあるんだよ」と。
夏になって、僕は彼の弟と一緒に山岡を探しに行ったが、見つからなかった。弟は「遺体が見つからなければ、納得できない」と辺りに悲しみをぶっつけていた。捜索隊員が申訳なさそうな顔をしていたが、もちろん弟はその人に憤慨しているわけではなかった。すると捜索隊員の中で一番ベテランらしき人が「お兄さんは山の神になったんですよ」とポツリと言った。その言葉に山岡の弟は肯きながら、いつまでも泣きじゃくっていた。そのとき僕は山岡を「バカな奴だ」とは思わなかった。むしろ「お前は、幸せな生き方をしたんだ」と言ってやった。
今でも僕は、北海道に行ったとき、いつも大雪山の方に向かって同じことを言っている。
木枯らしのような「ノクターン第20番」の一節のせいか、急にそんなことを思い出していると、笊に盛られた《対馬在来》が運ばれてきた。私は我にかえって蕎麦切を見た。竹笊は伽羅色と白橡色の竹が織り合った網代編、それに縁はよく締まった成形縁だった。品のいい笊だ。
二人は、箸を取って「頂きます」と会釈をし、何も付けないで一啜りした。
すると、「対馬」という辺境のイメージにしてはおとなしい味わいである。
「どう?」遥さんが目を大きく開けて訊いてきた。
「うん、美味しい。ただ想像したものよりマイルドだね。」と言ったとき、仄かな甘さが口内に広がってきた。
私と遥さんは、つゆを付け、一啜り、二啜りした。麺は硬くも、柔らかくもない。絶妙な腰が蕎麦切の醍醐味だ。
頂きながら僕は、この蕎麦の、世紀の旅路を想った。起源地といわれる四川・雲南を旅立って、満州から朝鮮半島を経由し、わが国の対馬へ辿り着いた無限の歳月。陽を浴び、霧につつまれ、星月に見守られながら、蜂の営みとともに繰り返してきた生成。その数千年を想像するだけで身体が震えてくる。
渡来してから江戸に伝わった蕎麦切は、インドカレーと日本のカレーの違いのようにまったく異なった麺に生まれ変わった。去年、北京北方にある張三営という村で古くから食されているという中国の蕎麦を食べたときそう思ったものだった。
続いて、《常陸秋そば》がやってきた。これは抜実の緑ッポイ実だけを選りすぐって、挽いたもの。僕の好きな蕎麦だ。とたんに蕎麦独特のグリーンノーツの香りが漂うが、自然の匂いというものはなかなか言葉で表現するのは難しい。若葉のような茸のような野性の匂い、バラのようなバニラのような華の香り。
言い表すには「ような」としか、いいようがないが、蕎麦好きにとって至幸の風味だ。僕は、これは日本蕎麦の銘品だと思っている。その銘品を堪能しながらまた啜る。野性味がありながら、繊細さもある。この微妙さが他の麺類には見られないお蕎麦の魅力だ。それを一言で〝粋〟だと言い切った江戸人の意気も鮮やかだ。
お蕎麦が終わってから僕は、在来種、銘品種、そのどちらも堪能できた幸せを最後の蕎麦湯と一緒に飲み込んだ。
そのとき、遥さんが訊いてきた。
「貴方、ミラノへ行くんですって、」
僕は、蕎麦湯を飲んで、ほっと一息吐いてから言った。「取材でね、」
「ふ~ん、」
「ついでにフィレンツェなんかも行ってみたいな。」
ミラノは万博の取材だった。しがないライターの僕は頼まれれば、何でも引き受け、海でも山でも、何処へでも行く。「ミラノへ行ってこい」と言った雑誌の編集長は日頃から「今のうちは何でも書いといた方がいい。一所懸命にやれ」と言ってくれているが、それを信じて今は書いている・・・・・・。
「何かあるの?」
「いや、特にないけど・・・、」
「けど、って何?」
「井上靖の詩に『エトルスカの石棺』ってあるのを知っている?」
「詩は知らない。エトルスカがイタリアの先住民エトルリア人のクニだってゆうことは何かで聞いたことがあるわ、」
「高校生のころ読んでから、憧れていたんだ。」
「その石棺の前に佇んでみたいの? ふふ、」
「なんだい?」
「フィレンツェに恋人でもいらっしゃるのかしら、と思ったの。男の人ってロマンチックよね。恋人なんて現実的なことより、高校生のころのときめきを今も抱き続けている・・・・・・、」
このときからピアノは激しい風雨のような「革命」に変わっていた。
「中学校の同窓会のときにね、母に『お会いしたかった』といって涙ぐんだ男の人がいらっしゃったんですって、その方は母が初恋の人だったのね。おかしいわ、」
ふっと見ると、彼女の白い指が曲に合わせてピアノの鍵盤を叩くようにトントントンと動いている。遥さんは、ピアノは弾かないはずだけど、と思って顔を見ると、珍しく固い表情になっている。
「どうしたのだろう」
僕は、遥さんがドラクロアの「自由の女神」のように立ち上がって、後の花瓶でも割ってしまうのではないかという妄想までしてしまった。
彼女は何事かに怒っているようだ。
いったいどうして?
そうか。僕が、子供のような話をしたから、呆れて怒っているのか。
「でも、そんなことをとがめられても困るけどな」と思ったとき、遥さんは指を止めて、はっきり言った。
「私も、行ってみたい。」
いい声だった。そうか、遥さんは何か考えていたのか。彼女の本気も伝わってきた。だから即座に返答ができないでいた。
「・・・・・・、」
「ご迷惑でしたら、諦めるわ。」遥さんの視線が流れた。
「迷惑だなんて、そんなことはないよ。」
「そ。ね、フィレンツェっていえば、前に、『冷静と情熱のあいだ』っていう小説があったでしょ。」
「Rosso』と『Blu』だったけ。」
「そう。同じ恋の物語を、男性の視点から辻仁成さんが、女性の視点から江國香織さんが書いたの。おシャレな企画よね。ああいう、気のきいた仕事をしたいわ。ね、何か考えてくれる。」
「いいね。面白いね」と僕は返事をしてしまった。
それにしても、遥さんはやっぱり素敵な女性だ。感情を出しながらも、その感情を越えて、手を差し伸べくれる。
僕は、そんな彼女が好きだということをはっきりと知った。僕はいたたまれなくなって、遥さんに声をかけた。「行こうか。」
「え~」と彼女は頭をちょっと横に傾け、そして微笑みながらバッグを取って囁くように言った。「ごめんなさい。その前にちょっとお化粧室へ、」
美女から、「お化粧室」とか、「おトイレ」などと囁かれると、何か秘密を打ち明けられたときのようにドギマギしてしまう。なのに、分かっているような顔をしてウンウンと僕は頷く。
そのとき黒シャツの女の子が出てきたので、僕はお勘定を済ませた。
暫くして遥さんも戻ってきた。
「ありがとうございます。」黒シャツの女の子が暖簾を上げてくれた。
僕たちは外に出た。
女の子も先に出て、見送ってくれる。
空が焼けていた。瑠璃色の空に柿色と鬱金色が交り合って、妖しい空に変わっていた。昼でもなく、夜でもない、静かな時間だと思った。
僕は調香師ジャック・ゲランの伝説を想い描いた。
あるとき、彼はパリのセーヌ河に架かる橋の上に佇み、太陽が沈みかけるのを眺めていたらしい。静かな時間であった。陽が沈んでいるから昼ではない。でも星が煌めいていないから夜はまだ。この止まったような時間の感覚を香水で表現できないかと思って作ったのがL’heurs bleuk(青い時間)だといわれている。
このとき僕は、タクシーの中で遥さんから漂ってきたスイートフローラルな香りはL’heurs bleukだったのだと確信した。
頭のいい彼女のことだ、お蕎麦の香りをじゃましないように、車中でだけ漂うていどのL’heurs bleukをほんの少しだけ髪に吹きかけていたのだろう。さらに彼女は、もしかしたらもしかしたら蕎麦切が食べ終わる時刻が夕方になるのはお見通しだったのかもしれない。そしてこんな夕焼空を想定していたのかもしれない。
謎でも解いたような目で僕は、暫し彼女を見つめた。そして「そんな粋な心遣いは、何処から生まれるの?」と目で訊いていた。
彼女の眉が少しだけアーチ型になり、眼が微笑んだ。
その笑みを見て、僕はどうしようも堪らなくなって、その場で遥さんを抱きしめた。遥さんの身体は華奢で、柔らかかった。このとき花のような香りが心にまで沁みてきた。僕はいっそう強く遥さんを抱きしめた。
それから僕たちは歩き出した。彼女は黙っていた。
その沈黙は「今度は貴方が舟頭さんよっ」て言っているみたいだった。
暗くなった夜道の先にブルーの明りが見えていた。
山岡の声も聞こえてきた。「あっちへ行けば別の世界があるような気がする。」
彼女と僕はしぜんに手と手を結び合っていた。
僕たちはそのブルーの明かりの方へ行かなければならないかのように歩いて行った。
僕は、パリで詠ったという九鬼周造の歌を想い浮かべていた。
ふるさとの 「粋」に似る香を 春の夜の ルネが姿に 嗅ぐ心かな
参考:九鬼周造『「いき」の構造』(岩波文庫)、『九鬼周造随筆集』(岩波文庫)、山田詠美『ラバーズ・オンリー』(角川文庫)、ゲツァ・フォン・ボルヴァーリー監督『別れの曲』、イェジ・アントチャク監督『ショパン 愛と哀しみの旋律』、高樹のぶ子『ショパン 奇跡の一瞬 ~ 聴きながら読む ジョルジュ・サンドとの愛』(PHP)、ドラクロア画「民衆を導く自由の女神」、江國香織『冷静と情熱の間 Rosso』(角川文庫)、辻仁成『冷静と情熱の間 Blu』(角川文庫)、SALENA JONES「I LOVE YOU」(『SALENA sings-BALLAD』)、DIANA KRALL「WHEN THE CURTAIN COMES DOWN」(『GLAD RAG DOLL』)、
〔☆ほしひかる〕