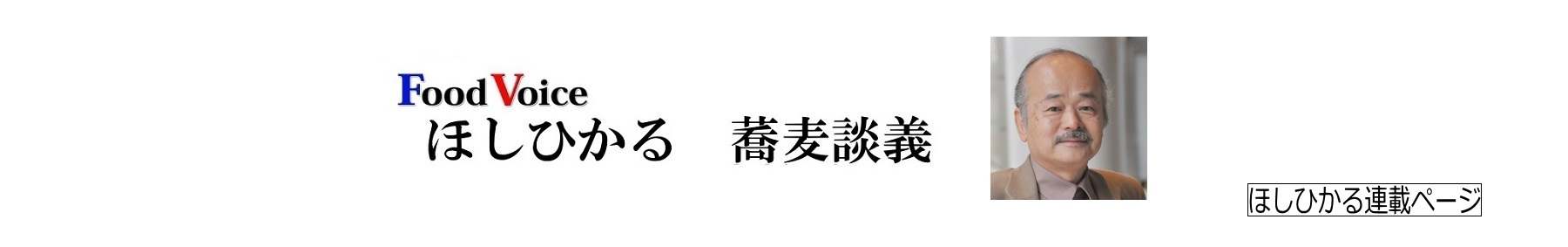第67話「体育、徳育より食育が大切だ」
2025/12/06
食の思想家たち一、村井弦斎
近ごろ「食育」ということがよく言われるようになった。この言葉を創って、唱えたのは明治の作家・村井弦齋(文久3年~昭和元年)である。彼は、小説『食道楽』の中で「食育論」を述べているが、その発想をどこから得たのだろうか?
☆村井弦齋の『食道楽』
その前に彼の人生をざっと辿ってみよう。
村井家は三河国吉田藩に儒家として仕えていた。とうぜん弦齋は幼いころから祖父と父に漢語を習い、長じてニコライ堂や東京外語学校でロシア語を学び始めた。ロシア語は父のすすめもあったが、もともと語学好きだったのだろう。そして学問がかなり好きだったようで、勉学に励みすぎて身体を壊したぐらいだった。それでも独学で経済、政治、商法、文学と幅広い勉強を続けた。
そして21歳のころ幾つかの論文募集に応募し、入賞した。その一つに横浜の英字新聞に投稿した論文があった。懸賞はアメリカ留学であった。
弦齋はサンフランシスコへ渡った。サンフランでは、ロシア人の家庭に住み込み、皿洗いなどをしながら、英語を習得し、一年間滞在したという。帰国後、「加利保留尼亜」を書いている。
弦齋は、実業家になりたかったが思うようにいかなかった。そこでシスコで知り合った報知新聞の創業者・矢野龍渓に誘われ新聞社に入り、編集長兼物書きとなった。
37歳のとき、弦齋は尾崎多嘉と結婚した。これが彼に大きな影響を与えた。多嘉の父は大隈重信の従兄弟、母の妹は後藤象二郎の後妻だった。
弦齋は、40歳(明治36年、1903年)ごろから多嘉夫人が作る料理を試食しながら小説『食道楽』を執筆した。もちろん主人公は多嘉夫人がモデルだった。
そのうちに大隈伯爵までが自邸のコックを差し向けるようになり、弦齋もとうとうアメリカ公使舘で働いていた加藤というコックを雇うことにし、和洋中の六百数十種の料理を『食道楽』で披露した。『食道楽』は大人気だった。
【大隈伯爵邸の台所と花壇食卓☆岩波文庫『食道楽』の表紙より】
【大隈重信・生家の台所(生家は幕末・明治時代、台所は大正時代)☆佐賀市・大隈記念館】
もちろんその本には、われらが「蕎麦」についてもちゃんと触れているし、「つゆ」が大切であることをきちんと押さえてある。
明治37年、弦齋は平塚に1万6400坪もの広大な土地を購入し、家屋、野菜園、果樹園、鶏舎、山羊舎、温室などを作って、自給自足にちかい生活を実践した。多嘉と結婚や『食道楽』の人気によって、彼の人脈はかなり広がっていた。森永製菓の創業者森永太一郎、味の素の創業者・鈴木三郎助、料亭八百善の栗山善四郎らも出入りしていたという。
☆弦齋の「食育論」
『食道楽』は 題名に「道楽」という言葉は使っているが、明らかに日本人の食生活の啓蒙のために書いた小説である。だから、弦齋が「食育論」に達するのは当然だったのかもしれない。
弦齋 曰く、「知育、体育、徳育より食育が大切だ。動物を飼っていると、それがよく解る」。
その意味は1825年にブリア-サヴァランが述べた「禽獣はくらい、人間は食べる。教養ある人にして初めて食べ方を知る。」(『美味礼讃』)と同じではないだろうか。
弦齋は、サンフランシスコへ行って、本物の西洋料理を知った。一方で、勉学好きなところから、多くの書や外国の書を読んだ。その結果、先進国には食を楽しむ文化があることを知った。そのため、弦齋は食の啓蒙の必要性を感じたであろうことは十分想像できる。
そんな折、大隈重信の縁者多嘉との結婚によって和洋中の料理に接する機会が増え、かねてからの思いが実行できたということではないだろうか。
晩年、弦齋は美食家から断食研究家へと転身した。第一次世界大戦の勃発に物質文明の幻滅を感じ、「自然に還れ」と唱え始めたのである。そのとき彼は蕎麦粉、豆、木の実などを用意して断食をしたという。
彼は、食と人間の関係を自ら追求し続けるという、まことに奇特な一生をおくったといえよう。
今、平塚の村井弦齋の屋敷跡(現在:村井弦齋公園)では、毎年9月に「村井弦齋まつり」が催されている。
【平塚市・村井弦齋公園】
参考:村井弦齋『食道楽』(岩波文庫)、村井弦齋『食道楽の献立』(角川ランティエ叢書)、村井弦齋まつり(平塚市)、大隈記念館(佐賀市)、火坂雅志『美食探偵』(講談社文庫)、ブリア-サヴァラン著『美味礼讃』(岩波文庫)、
〔蕎麦エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員 ☆ ほしひかる〕