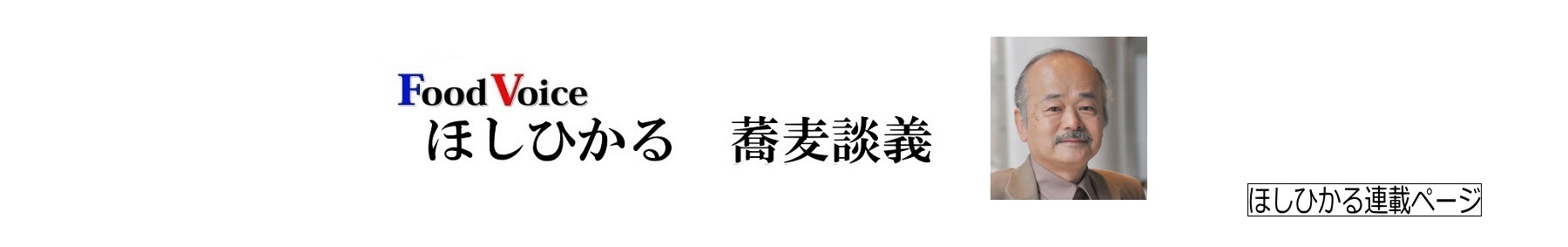第833話 「ごちそうさまでした」を言いたくない店
2025/12/06
ある人と打合せをするために銀座へ行った。
約束は13時。時計を見ると12時40分。昼食はまだだった。真向かいに立ち食い蕎麦の「吉そば」がある。〝福〟の予感をさせる「吉」の字にひかれ、「まだ間に合う」とそこに入った。
初めて入る店だった。清潔感があった。販売機で食券を買う。見回すと半分は女性客だった。すぐに出された《春菊の天婦羅のかけ蕎麦》を持って、カウンターに置いた。目の前に「国産蕎麦粉使用・・・」「国産野菜使用・・・」「無添加の美味しいつゆ・・・」と書いたものが置いてあった。何か安心感のする文言だが、そのことよりも寒かったので《かけ蕎麦》の温かさがたいへん美味しかった。帰り際、食器を運ぶと、おばちゃんが「ありがとね」と言ってくれた。速くて、安くて、温かい蕎麦に、「ごちそうさま」という挨拶が口から出た。

打ち合わせが終わってから、先刻の立ち食い蕎麦の店の前を通った。このとき、外食店にも自然に「ごちそうさま」を言いたくなる店と、言いたくない店があると思った。
ある街に行ったときだった。名の通った定食屋があった。神保町店で時々利用しているから、入った。でも席に座っても店員さんは来てくれない。隣の席の人を見ると、デジタル化してある注文機を操作している。そうかと思いながら、やってみたが面倒くさい。メニュー表なら全体が一目で分かるが、デジタルはそうはいかない。阿弥陀クジのように進めなければいけない。もう店を出ようかと思ったが、辛抱して、操作してやっと「注文」まで辿り着いた。その後に食べた食事も、何か虚しくて美味しくなかった。神保町店は注文を取りにきてくれる店だったけれど、店舗によってちがうようである。
しかもこの店は、支払う時も自分で支払い機に入金しなければならなかった。レジの担当者はまるで検閲官のように無表情で立ったままである。外食店側は、客を集金マシーンと思って機械化を推進しているのだろう。昔は「お客様は神様」というのが経営の根幹だったというのに、現代の客はブロイラーだろうかと嘆かわしくなった。作家の椎名誠が別のことで「帰るとき、ドアを後足で蹴りたくなるような店がある。もちろん実際は蹴らないけど、」と書いていたが、その情景はよく分かる。
和食文化の心は、「いただきます」「ごちそうさま」にあるいわれている。だから拙著『小説から読み解く和食文化』では、「はじめに」を「いただきます」、「あとがき」を「ごちそうさま」とした。
しかし、機械に対して「ごちそうさまでした」と挨拶をする者は誰もいない。皆さん黙って無口のまま帰って行く。たとえ定食という和食を食べても、和食の心は喪失してゆく。
今日は北風が寒い。その北風に日本の食文化もさらされて乾燥してきている。そんななかだから、おばちゃんの「ありがとね」は〝人間味〟という希望の味のような気がした。
〔江戸ソバリエ ほし☆ひかる〕