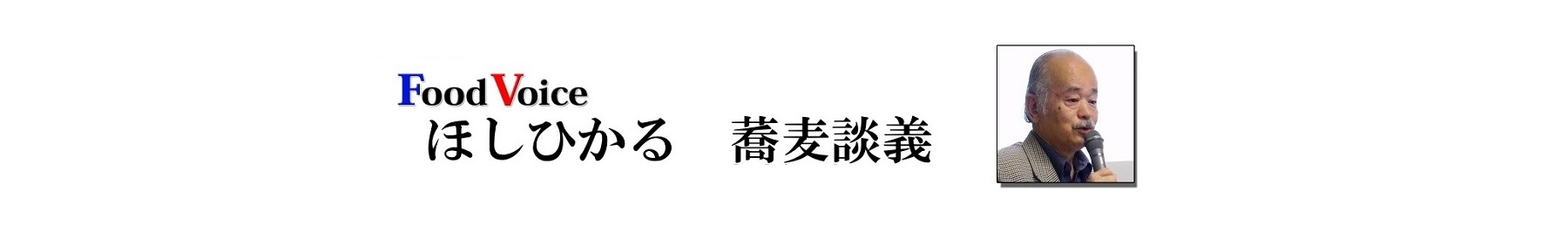第113話 満漢全席で驢も駝も食べた!
~ 中国麺紀行⑤ ~
☆乾隆帝
中国は豚肉王国である。世界の50-60%を生産しており、2位アメリカの10%弱を完全に引き離している。古い時代はそうでもなかったらしく、中国の豚肉がトップに躍り出たのは豚を飼育していた満族が北京入りしてからであるという。
豚というのは、人間にとって実に効率のいい動物らしい。食べた餌のほとんどが肉になり、子供も一度にたくさん産む。牛馬は労働することもあるが、豚は肉になるためにだけこの世に生まれてくる。そんなことを言うと豚サンが憐れに思えてくるから、人間を助けるために生まれてくるのだと感謝したい。いえばブッダである。
そんな豚であるが、時々引用している『韃靼漂流記』にはそれを神に捧げるのを見聞した、貴重な報告がなされている。拙文『紫禁城の夜明け』では主人公に「気持わるい」と言わせたが、異文化とは所詮「気持わるい」か、「憧れ」かのどちらかであろう。
しかし、考えてみれば、日本人も古代には馬を神に捧げていた。それを執行するのが巫女であった。だから満族にも、日本民族にも、巫女がいる。もうひとつ加えれば朝鮮民族にも巫女がいる。だが漢族に巫女はいない。思い切った言い方をすれば漢族は神をもたないのである。だから、華北、朝鮮、日本は≪巫女文化 加盟国≫を結成しているといえよう。ここら辺が「日本人の祖=騎馬民族説」の成り立つ所以であるが、いつしか、日本人は「かわいそう」とか、「もったいない」とかの理由によって生贄の代わりに馬の絵を奉納するようになった。それが今の「絵馬」であることは周知の通りであるが、絵馬にしたところが日本人の知恵でもある。
とにかく、清国は初代ヌルハチの建国に始まり、ドルゴン王の北京に入りを経て、4代目康熙帝は強力な中央集権国家を作り上げ、5代目の雍正帝は倹約して国庫を豊かにした。その累積の結果、清国は世界最強の帝国となろうとしていた。その矢先に、6代皇帝に就いたのが乾隆帝である。
世界の歴史を見ていると〝生まれながらの幸運児〟というのがいるが、この乾隆帝もその一人である。
本人の努力、博学のせいもあっただろうが、祖父康熙帝は孫乾隆帝の才を愛し、早くから後継者として認めていた。
そういう乾隆帝だから文武両面全政策については偉大なる祖父に倣った。
祖父康熙帝という人は尚武精神をかきたててくれる狩猟には特に燃えた。その狩猟は、同時に外藩を慰撫するに必要な軍事演習にもなった。だから、避暑山荘と木蘭には毎年のようにやって来た。
当然、優等生の乾隆帝も毎回木蘭で狩をした。そして、その途中の張三営で白蕎麦と出会うわけである。
そのころ避暑山荘には、すでに溥仁寺、溥善寺、普寧寺、安遠廟が建立されていた。いずれもエキゾチックな建物ばかりである。
戦前、承徳を訪れた画家の安井曾太郎は異国情緒あふれる外八廟を絵にしたが、その気持はよくわかる。私も倣って下手な絵を描いてみた。
 【喇嘛廟 ☆ ほしひかる 絵】
【喇嘛廟 ☆ ほしひかる 絵】
ここ避暑山荘に来ると、乾隆帝に会うことができる。といっても壁にコピーされた肖像画である。原画はG.カスティリオーネというイタリアの宣教師&画家が描いたものだ。カスティリオーネは郎世寧という中国名をもらって、康熙帝、雍正帝、乾隆帝に仕えたという。
私事であるが、わが家に郎世寧が描いた絵の中国の切手があった。誰がどうしたのか全く不明だが、「郎世寧って何者だ?」というわけで調べたら、上記のようなことだった。そんな縁のあるカスティリオーネが描いた乾隆帝だから、つい繁繁と見入ってしまった。
その乾隆帝は、玄宗皇帝が寵愛した楊貴妃と並び賞される、世紀の美女をいつも伴っていた。「香妃」という。その名は、彼女が美しいばかりでなく、身体からも芳しい香りを放っていたことから付いたという。
この麗しき伝説に多くの人が興味をもち、魅惑の謎にいどんだ。
井上靖は、カシュガルを訪ねて妃の香りは「沙棗(グミ科)」のそれであることを突き止めた。執念の小説家だと思う。その井上は、こんな詩を残した。
天山とパミールの見える町。
タクラマカン沙漠の西南の隅っこの町。
香妃が生まれ、育った町。
東トルキスタン最大の回教寺院のある町。
ウイグル人ひしめく大バザールの町。
五月には沙棗の花の匂いでむんむんする町。
往古の疏勒国の故地。
極めて当然なことながら、私がまる一日、原因不明の高熱で意識を失っていた町。
― 井上靖「カシュガル」―
それを機に、高砂香料と資生堂は共同で沙棗の調査隊を派遣した。
中国の小説家金庸氏は『書剣恩仇録』の中で、芳香は幼いころから花を食べていたせいとした。「雪中蓮」という香り高い花も描かれている。
私は・・・・・・、彼女の故郷ウイグルは瓜、西瓜、葡萄などフルーツが豊かであるところから、幼いころから好んで芳しいフルーツを食べている香妃の姿を妄想してみた。
蕎麦人からみて、「香妃は乾隆帝と共に白蕎麦を食べたか?」という問題があるが、おそらく口にしていないだろう。豚肉を禁じられている回教徒は、豚肉を使う撥御麺は食べてはいけないものだったのである。
ともあれ、権力者はどんなものにも頭を下げることはないだろうが、美女にだけは平伏するときがある。そんな美人を「傾城の美女」という。
乾隆帝はといえば、香妃に相当入れ込んだが溺れはしなかったようだ。乾隆帝についてはもう1つ、こんなエピソードもある。乾隆帝は尊敬する康熙帝の在位期間61年を越えてはならないとして、60年で退位したのである。これらの伝説は重要なことだ。思うに、乾隆帝という人は美女にも、部下にも負けない、そして最も重要なことは自分で自分を律する強い何かをもっていた。だから、彼の優等生ぶりは本物だったのではないかと想像する。
そうでなければ、逆に60年間の権力は維持できないであろう。
☆満漢全席メニュー
国の黄金期は、側面から見れば帝王の在位期間の長さからもうかがえる。ちなみに、史上ベスト4は、清の康熙帝(在位1661-1722)、乾隆帝(1745-96)、イギリスのヴィクトリア女王(1837-1901)、日本の昭和天皇(1926-89)であるから、いかに清が盛大だったかが分かる。
清の盛大さを食から見た場合、宮廷料理「満漢全席」がその象徴として挙げられるだろう。
では、その「満漢全席」とは何か? 元々は、地方の漢族がその地に赴任して来た満族の官吏を接待する宴の方法であった。そのうちに、量が増え、質が高まり、乾隆帝が巡幸する時代には満漢全席の形式が決まり、北菜南菜54種ずつの108種の大小の料理、それに満族の点心44種を加えた規模が普通になっていたという。
その献立の中身は別にして、「満漢全席」の意義について『中国料理の迷宮』の著者勝見洋一氏はこう述べている。
― 満族は漢族の持つ高度な料理文化に接し、それを嚥下し咀嚼し吸収した。そして満漢全席の完成によって、清朝の質素だった祝宴は従来の点心に「菜」が加わり、豪華絢爛なものになった。それは慎重に満族の料理を浸透させることの完成でもあった。―
これが、食から見た、国の隆盛、そして文化ということであろう。
前おきはこのくらいにして、いざ満漢全席に着こうとしても、とても本格的な晩餐会は量的にも資金的にも大変だ。そこで、私たちは午餐にすることにした。お店は昨日の昼食をとった店の隣だった。
午餐といえども献立はご覧の通り、何が何だかわからないほど次から次に卓に上がった。
《満漢全席》
①濃汁紅雁、②叫花子山鶏、③満漢一品駝筋、④香椿芽炒飛竜、⑤茴花地鵲、⑥紅扒大雁翅、⑦鮮肉葱爆鹿肉、⑧白葱扒菜芯、
冷菜 ①白切驢肉、②醤爆腱子、③上海酔鶏、④丁香魚、⑤拌糸瓜尖、⑥拌金針菇、⑦養心菜、⑧拌香椿芽、
冷点 ①栗羊羹、②豌豆点、③山楂糕、④杏仁糕、
小吃 ①黄金餅、②鍋貼、
私は、献立表というのは地図のようなものだと思っている。初めて口にする外国料理の場合、いま自分は何を食べているのか? 初めて訪れた外国旅行の場合、いま自分は何処にいるのか? が分からないので、きちんと味わうために必要だと思う。さらにそれは記念にもなるし、資料にもなる。だから、李先生に頼んで、無理して係の方に書いていただいたものが上記である。
お蔭さまで、「サンフランシスコ総領事館 蕎麦パーティ」、「蕎麦喰地蔵講」、「深大寺そばを味わう集い」、「蕎話会」などの、これまでの「私の記念献立集」に新顔が一つ増えた。
ところで、その中にある「満漢一品駝筋」「白切驢肉」とは駱駝と驢馬の肉のことである。これは日本人には馴染みがない。だが、中国では「山八珍」とか、「陸八珍」とかいう場合必ず駱駝の肉は出てくるし、また、華北では一般的、「上有龍肉、下有驢肉」(天に龍の肉あり、地上に驢馬の肉あり)といって美味しい肉の代表のように云うらしい。そんなものを口にすることができると思うと、胸が高鳴る。そして「お、旨いではないか」と歓声を上げる。
人間は、本能的に近い動物と遠い動物は口にしない。近いというのは人間とペットのことであり、遠いというのはその民族が住む地に棲息しない動物のことである。日本人なら、キリンやカンガルーを見ても食べたいとは思わない。
だから、他の民族が鯨や犬を食べるからといって、環境問題などがなければ無闇に責めてはいけない。自分が食べなければいい。
そうそう、大切なことがあった。主食に何か選ぶことができることになっている。当然迷わず蕎麦にしたが、それは押し出し麺であった。
やはり中国では、昨晩のような「撥御麺」は珍しく貴重であり、一般的には「押し出し麺」が多いようである。
ところが、≪麺文化 加盟国≫であるわが国は、この「押し出し麺」部会には加わらなかった。
参考:井上靖詩・大塚清吾写真『シルクロード詩集』(日本放送出版協会)、金庸『書剣恩仇録』(徳間文庫)、勝見洋一著『中国料理の迷宮』(講談社新書)、
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員 ☆ ほしひかる〕