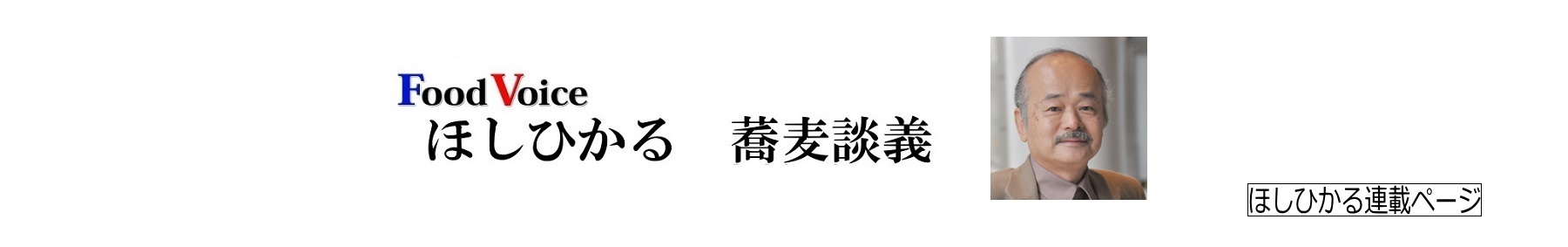第321話小説「コーヒー・ブルース-XIII」
2021/11/12
~ Still I Love You ♪ ~
恵子がニューヨークへ発つ日、健は恵子を成田まで見送りに行った。
途中、二人とも下を向きがちで、まだ「行ってらっしゃい。」「行ってきます。」が言えなかった。だからといって、ここまで来て「行かないでくれ。」「行きたくない。」とも言えなかった。
二人は言葉を交わすきっかけを見つけようとして、お互の眼を見た。二人とも目から涙が零れている。健と恵子はともに小さく笑い合ってから、恵子がハンカチで健の涙を拭いて上げた。健もそのハンカチを取って、恵子の涙を拭いてやった。そして二人はしぜんと抱き合った。いざ抱き合ってしまうと、堪え切れない衝動に見舞われ、二人は互の唇を激しく求め合った。今の二人には他人の目など何ともなかった。それよりも、この感触、この温もりを永遠に忘れまい、そんな気持でいっぱいだった。しばらくしてから二人は離れた。
そのとき恵子は健の手をとりながら、小さな声で言った。「お願いだから、浮気なんかしないでね。」当初恵子は、あの博多織の女性だけは嫌だと思っていたが、出発が近づくにつれ、(留守中、健に恋人ができたらどうしよう。) そんな心配が広がっていった。
不安そうな眼で弱音を吐く恵子を見て、健は恵子をいじらしく思った。こんな眼をするのは、〔小竹〕で泣き崩れた夜以来のことだった。あのときに、(可愛い女だ) と思ってから、今の健と恵子がある。それからの恵子は、甘えることはあってもだいたい大人の女であった。しかし、今日はちがっていた。少女のような眼で訴えている。健は恵子の肩を強く抱いて、言った。「今は恵子だけだよ。」
「今は、なの? いやん。」
「ごめん。ずっとだよ。」
「よかった。ありがとう。」やっと恵子は微笑んだ。
時々、健は覚悟しなければならないかもしれないと思うことがある。 (恵子は、おれにはもったいないほどの女性だ。NYへ行ってしまったら、もう会えなくなるような気がする。もしそうなったときは、優しさと幸せをくれた恵子にありがとうと自分に言い聞かせるしかない) と。
しかし、【恵子ママ ありがとう】デーの最後の日、恵子に言われて迎えに行ってみると、恵子から息も止まるほどの長い長いキッスを贈られた。店の者が拍手をしてくれたので、やっと二人は離れたが、おそらく10分以上は続いただろう。
健は、恵子の痺れるような長いキッスは (必ず恵子は帰ってきます) の強いメッセージだと受け取った。
それが今、恵子の気弱そうな眼を見たとき、ある強い気持がわいてきた。(いま探している自分の道が見つかったら、恵子とのことを決断しよう。)
恵子は握っていた手に力を込め、「NYに着いたら、電話するね。」そう言い残し、何度も何度も何度も振り返りながら、ゲートの向こうに消えて行った。
健は恵子が見えなくなっても、飛行機が飛び立っても、なおもその場に佇んでいた。
NYの空港に到着した恵子は契約していたセントラルパーク近くのアパートメントへ直行した。恵子は、健のこと以外はすべてテキパキとこなしていた。自分の住むアパートメント、日本人のお手伝いさん、通う産科の病院、勤めるブティックなど、すべてを東京にいるときから手配していた。
アパートメントでは不動産屋が待っていた。鍵をもらって、「部屋は今日から使えます」の説明と、「お手伝いさんは、いつから寄こしますか?」との質問をもらった。
「明朝、お会いしたいわ。」
「承知しました。アメリカでは、日本人にかぎるという条件付の募集はできないので、応募してきた人の中から日本人を選んだ」と言って、不動産屋は帰っていった。
部屋に入った恵子は、カバンから〔小竹〕の女将にもらった対の杯と、写真を取り出して、ベッドの枕元に大事そうに置いた。写真は健と恵子が仲良く並んでいた。
翌日、恵子はNY・東京の時間差を見計らって、電話で健に無事に着いたことを知らせた。
この日からお手伝いさんも来てくれた。60歳ちかくの頑丈そうな女性だった。彼女は「アメリカに来てから40年になる。孫もできたけど、閑だから軽いアルバイトをしている」と明るい声で言って、よく働いてくれた。
その翌日は病院へ行ってみた。グランドセントラル駅の近くだった。紹介された担当女医は「順調ですよ」と言ってくれた。
その帰りに、生活に必要な品を購入するためにメルシー・デパートに立ち寄った。菓子、ケーキの売場を通ったとき、「Still I Love You」という文字が眼に入った。チョコレートの宣伝のようだった。恵子は、いい言葉だと思った。見ているだけで音楽でも聞こえてくるようである。
https://www.youtube.com/watch?v=MwQ4BXLdRD4
そのチョコは真っ赤なバラと一緒に飾ってあった。そのバラを見て、恵子は胸がキュンとなった。
〔クラブ恵子〕のママをやめるとき、健は365本のバラの花を贈ってくれた。恵子は瞬間 (もしかしたら、あの人は別れを覚悟しているのではないかしら) そう直感した。(どこかの国の若者が、せめてもの思い出にと、去ってゆく恋人に百万本のバラの花を贈ったという話を聞いたことがある。あの人がその話を知ってるのかどうか分からないけれど、愛の渦中にある人間なら同じことをするかもしれない。恵子だって立場が変われば、そうする。) 恵子は悩んだが、どうしようもなかった。しかし、いざ健が現れたとき、恵子は無意識に健に飛びかかるように抱きついていた。本当なら、女の子の手前、ママとしては絶対やってはいけないことだったが、(今日から恵子は、もうママじゃないんだ) と自分に言訳して、死んでもいいと思うほどにキスを続けた。長い長い時間だったが、健も力強く反応してくれた・・・。
恵子は眼が覚めたように、チョコを見なおした。(「Still I Love You♪」今の恵子の心情だわ。) 恵子はチョコレートを健に贈ろうと思って、買った。
それからブラブラ歩いていると、コーヒーの香りがしてきた。誘われるようにしてコーヒー豆の売場へ近づいて見てみると、奥のケースの中に〔ジャコウネコ コーヒー〕が置いてあった。「幻のコーヒー」と呼ばれるスマトラ産の希少コーヒーだということは知っていた。まだ日本では手に入りにくいということも聞いていた。恵子は〔らんぶる〕や〔キャラバン〕でのことを思い出した。恵子は、〔ジャコウネコ コーヒー〕に「Still I Love You♪」の言葉を付けて、健に贈って上げようと思って、チョコレートと一緒に日本に送る手続をした。
それから恵子はアパートメントへ戻って、健に手紙を書いた。
それ以来、恵子は一カ月に二度、健に手紙を出し続けた。封は必ず「Still I Love You」か「Lovin’You」のサインで〆た。
恵子は、明日から五番街のブティックに通うことにしていた。一従業員として仕事をするのは、明子ママについていたころからみると十数年振りである。何か新入生にでもなったような気分がしてきた。
それから恵子は様子を見ながら、デザインも勉強するつもりでいた。それも健が言ってくれた言葉がヒントだった。
〔クラブ恵子〕の最後の三日間、恵子の着物姿を撮った写真を健に見せたところ、「へえ。恵子の着物ファッションはすごい」と感動してくれた。もっとも二日目の嫉妬めいた様相の話はしなかったが、その発想のベースとなったのは、「高畠華宵の『情炎』がヒントだった」ということは言った。それは健と一緒に行った本郷の弥生美術館に展示してあった八百屋お七の絵だった。その絵を観たとき恵子は (これは今の私だ) と思ったものだった。だから、あのようなファションを思い付いたのであった。そんな話をしたところ、「ふーん。おれとしてはかなり照れるけれど、ストーリー性をもってプロデュースしたところは舞台演出家か、画家のようだよ。やっぱりお父さんの血だね」としきりに感心してくれた。
「お父さんの血。」健がそう言ったことに恵子は衝撃を受けた。
「母に似ている」とは子どものころから、親戚や近所の人からよくいわれていたことだったが、父に似ているとは、今まであまり思っていなかった。思い出すと、実家の倉庫に亡父の絵があったような気がする。恵子は、秋田の従妹に、もし亡き父が描いた絵があったら、至急送ってほしいと頼んだ。
すぐに従妹から、父が描いた5枚の油絵が送られてきた。開けてみると、3枚は花の絵、2枚は亡き母を描いた対の絵だった。恵子はその絵を見て、呆然となった。母の顔はいまの恵子と瓜二つだった。しかもその絵の1枚は母の着物姿の絵、もう1枚は全く同じポーズの母の全裸像、まるでゴヤの「着衣のマハ」と「裸のマハ」のような対だった。人が観たら奇異に感じるだろう。
しかし、恵子には理解できた。子どものころの恵子は母とばかり話をしていて、父と話した憶えはあまりなかった。その数少ない記憶の中で、父は利休の視野の広さを語ったことがあったが、着物姿と裸婦像はそれと同じ思想から描いたものだろうと想われた。健が指摘してくれたことから恵子はデザインも勉強してみようかと考えるようになった。
(母に似ている。祖父に似ている。父に似ている。そして、この児は健に似ている。)
恵子は、出産の、もしものときの覚悟はできていた。そのために、「吐かなければならない嘘もある」と自分を説得し、健と離れた所で産もうとしている。しかし、だんだんと強い自信もわいてきていた。恵子はお腹に手を当てながら、思った。(無事にこの児を産んで、必ずあの人の所に戻るのよ。)
会社における、小田社長の特訓は激しさを増していた。
「どうなってる?」
「なかなか思うようにいきません。」
「今週までに必ずやると言ったんじゃないのか。」
「努力してみたんですが・・・・・・、も少し待っていただけないでしょうか、」
「いいねえ、君たちサラリーマンは、約束を破っても平気で済ませられるからね。」
「平気なわけではないんですが、」
「そうじゃないか。僕も今月の給料の支払を待ってもらいたいって言おうか。努力したけど、払えない、って言おうか。」
「・・・・・・、」
「いいかい。給料はお上が自動的に支払ってくれるものじゃないだろう。僕は君たちに毎月支給しますと、約束しているんだ。僕は君たちとの約束を死んでも破ることはできない。破れば、君たち本人だけじゃない、君たちの家族が路頭に迷う。それが社長の責任だよ。僕は君たちの後に家族がいることを知っている。それが経営者だよ。だから、社長というのは日頃から、あらゆる約束事を守る癖を付けておく。約束の時間に遅れたら、当人だけではなく数名の関係者に迷惑をかける。返事をしなかったら、当人だけではなく数名の関係者に迷惑をかける。いつも約束者の後には数名の関係者がいる。約束を守らなければ、その人たちが困る。会社の仕事だって同じだ。君が今週中に10個売ると約束したとしたら、工場の人間は徹夜して10個製造する。ところが、君たちは売れなかったと平気で言う。徹夜した工場の者は「仕方ない」と言うか、怒るか、どっちだ?」
「・・・・・・、」
「だから約束を守れない者をいいかげんな人間だという、ちがうかい。」
皆はグーの音も出ない。社長に報告するということになっているが、相変わらず社長の話は取調べ同然だ。
新規事業部員たちが社長の叱咤にグッタリなっても、お構いなしに社長の檄は飛ぶ。「約束は守れ。」「約束通りやるにはどうしたらいいかを考えろ。」「約束通りできなかったら、なぜできなかったかを考えろ。」「また自分の仕事を見つけていない者は、さぼってるのと同じだ。外に出て、自分の脚で探せ。」そして最後の台詞はこれだ。「僕のような勉強嫌いな男でも、できたんだ。優秀な君たちにできないはずはない。行け、外に行け。チャンスはどこにでもある。それを見つけて来い!」
皆、ヘトヘトになりながら、社長の言葉を聴いて、忘れないように必死でノートに書いている。
それを見て、また社長はさらに追い打ちをかける。「僕の言葉を書くのはいい、右から左に聞き流すよりは。しかしナ、君たちはなぜ僕の話を聞いてくれるのか。」
「社長は、この会社を作った方からです。」
「そうだろう。そうでなければ、いくら立派なことを言っても聞いちゃくれないだろう。」
「・・・・・・、」
「僕の言うことは会社を作って、育てた経緯から生まれた僕の血と汗の結晶だ。だから、みんな聞いてくれる。君たちも、君たちの脚と汗から生まれた君たちの言葉を見つけろ。その中身によってトップとしてのカラーも出てくる。」
社長の態度は厳しかったが、皆はやる気に燃えていた。
社内の雰囲気も変わってきた。最初の落ちこぼれ軍団でも見るような視線は、
少なくなり、興味津々、面白がって近寄って来る者も出始めた。
老人マンションの企画を持ってきた西村は、それから医療機関の備わったマンション構想を描き、マンション業者と医療機関の橋渡し事業に着手しようとしていた。
さらには、林という北海道支店から転勤してきた男が、「水を売る事業を始めたい」と言ってきた。
社長は、「いいだろう。僕は水道水で構わない、個人的にはそんな物は買おうと思わないが、しかし社会は健康志向で進んでいく。やがては多くの人がそういう水も買うようになるだろう。だから、それを事業とするなら、先ずは自分から率先して、売りまくれ。しかしいつまでもそれではいかん。自分の販売経験を営業ノウハウにするんだ。社長というのは従業員が走りやすいようにグランドを造るのが仕事だ。皆が泳げるように池を造るのが仕事だ。ノウハウもグランドだ、池だ。」
また、関西支店からやって来た境井は「健康機器を売りたい」と言った。
社長は、境井に対しても。林とまったく同じよう「先ず、売ってみろ」と言った。
そして、ある時期、林と境井は一緒になって、健康機器販売チームとして事業を立ち上げた。
野中は、そうした既存製品の販売ではなく、新製品の開発を手掛けたいと思っていた。
野中は、あちこちの展示会に顔を出しているうちに、塩分の取り過ぎが国民的な問題として俎上に乗っているにもかかわらず、それを計測する塩分計がないことに気付き、何とかして製造してみたいと思うようになった。小田社長の紹介状をもって社長の知人である町工場をかなり歩いたが、「アイディアは面白いが、難しい」との回答ばかりであった。そのうちに「貴方の会社で作る理由がきちんとしてなければ、ダメだ。そのうちに計測メーカーに話が伝わって、開発されたら、販売だって、そちらが有利だろうから」と言われ、野中は自分や会社に合わない思い付きだったと考え、手を引くことにした。
それを野中は、消防病院の山本先生流に、ワードプロセッサーを使って文章にしてまとめた。
そのころは東芝、沖電気、シャープなどが発売されていた。野中はシャープを使っていたが、理系あるいは事務職系の人間は、ワードプロセッサーを使う者はたまにいたが、営業出身の人間は、珍しい方だった。
そういう理系の後輩に工場から来た古賀という者がいた。同じ九州出身で、九州大学卒の優秀な男であった。古賀は当時売り出された8ビットのパーソナルコンピューターで、何かできないかと研究していた。
野中はコンピューターにはほとんど関心がなかったが、気の合う古賀と展示会や講演会を聞きに行ったりしていた。そのうちに【美と健康】の他に、【情報化社会】というキーワードで時代が鳴動していることに気が付き始めた。
「情報とは?」「人、物、金の三資源に、これからは情報も資源の一つになる」というような解説記事が、新聞、経済誌にあふれるようになったが、いまひとつ野中には理解できなかった。
そんなとき、医薬品の開発部長から「消防病院の山本部長に、参考ご意見をうかがいたいので、紹介しほしい」という依頼が入った。
病院の玄関で開発部長を待っていると、彼はカバンを持って現れた。
見ると、入り切れないためにカバンの上に大きな通信機みたいな物を挟むようにして置いている。野中はてっきり今日相談する医療機器か何かだと思いながら「それは何?」と訊いた。
部長は「移動式電話だよ」と答えた。
「電話?」
「そう。便利だよ。何処に居ても電話を受けられる。」
「・・・・・、」野中はバカバカしいと思った。 (ジャングルの奥地ならともかくも、普通の街は見渡せば公衆電話ばかりじゃないか。こんな重い物を持ち歩くとは、気がしれない) と思ったが、同時にこういう機器が登場する時代性と、またそういうものに関心を示す者がいるということが何かしら気になった。
この日は土曜日だった。消防病院から野中はその足で恵子のマンションに帰った。ニューヨークへ行った恵子は、野中にマンションを自由に使ってほしいと言い残していたから、土・日は恵子のマンション、月~金は自分のアパートで生活するようにしていた。
マンションに入ると、食堂にはお手伝いの洋子が用意してくれた夕飯が置いてあった。
恵子は洋子に、部屋の掃除と、健の下着などの洗濯を仕事として頼んでいたが、健から土・日はここに泊ることにすると聞いたので、洋子も土・日は、夕飯の支度をして帰るようにしていた。
もちろん洋子は、恵子が何のためにニューヨークへ行っているかを知っていた。知っていても、恵子に堅く口止めされていたため、健には何も言わずに口を噤んでいた。そして、自宅の子どもの位牌に向かって、恵子の安産を祈っていたのであった。
健は一人で食事をする前に、風呂に入った。そして上がってから、下着を取り替えるため下着ダンスの引出しを開けた。下着ダンスには恵子の下着がそのまま残っていた。健は深い溜息を吐いた。「ああ・・・、」(恵子に会いたい!) 下着ダンスを引出せば恵子の下着、洋服ダンスを開ければ恵子の服・・・、ベッドに入れば恵子の香り・・・。(どうにかなりそうだ。)
恵子が去った直ぐのころは、恵子の布団で眠るのは恵子に包まれているようで、心地よかった。しかし、段々と日数が過ぎてくると、それが寂しくもあり、辛くもあった。
健は「ここは、夜はダメだな」と苦笑しながら、服を着た。食事を済ませたら、自分のアパートに帰ろうと思った。
健は、車を運転し、アパートに着いた。駐車場に車を置いてから、外階段を上って2階に出た。するとドアの前に女がいる。健は脚を止めた。ショートヘアの女、(絵美だ!) 絵美は週刊誌を尻に敷いて膝小僧を抱いて坐っていた。(何でおれの家を知っている? そうか、佐藤に訊いたのか!)
健は、そっと後退りして、駐車場に戻って、車の中に入った。(どうしよう?) このまま、ここを去るのは何か気が引けた。(あのままじゃ、風邪をひく。可愛そうだから、声をかけようか?) 健は煙草に火を点けた。(しかし声をかけたら、今まで待っていたくらいだ、いくら言っても黙って帰らないだろう。だからといって、家の中に入れてやったら、今のおれは何をするか分からない。ちょっとだけ付合ってみるか・・・。) そんな迷いが浮かんだとき、「浮気なんかしないでね。」恵子の言葉が痺れるような舌の感覚と共に、耳に聞こえてきた。
(いま新しい道を探ろうとしているときに、恵子を裏切るような後めたいことはしたくない。) 健は胸が痛んだ。
このとき、誰かが階段を下りてくる足音がした。
(もしかしたら、) そう思って、健は座席に身体を沈めた。暫くして身体を起こしてみると、去ってゆく絵美の後姿が見えた。(絵美、それがいい。君はふつうの大学生。もうスナックも辞めた方がいい。) そう心の中で呼びかけ、暫くしてエンジンをかけた。(おれはやっぱり恵子を愛してる。恵子のマンションに戻ろう。) そう思った。
(XIV.〔Lilac Wine〕へ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕