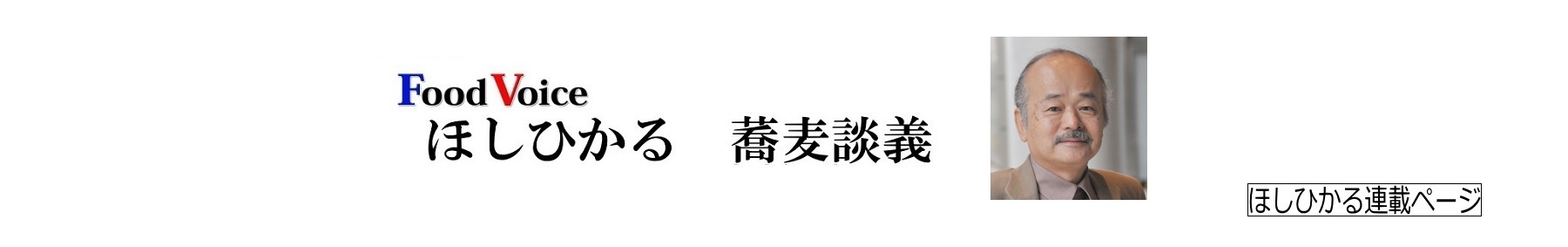第280話 怖い小説「陰翳礼讃」
2025/12/06
私たち蕎麦仲間は定期的に集まって蕎麦会をやっています。
いつもは公共施設を借りての練習会ですが、今日は特別に鎌倉の法念寺というお寺です。石段を九つ上がると、茅葺の大きな門がありました。
「ずいぶん立派なお寺だなあ」と南田さんが感心しながら言いました。他の皆さんも苔生した門を見上げながら、肯きます。
今日集まったのは、南田さん、西川さん、東島さん、中山さん、私 ― 北村の5名です。私たちは南田さんのことを「ミナミさん」、西川さんは「カバさん」―〔西〕の字が学生鞄のようなので、学生時代は「カバン」と呼ばれていたそうなんですが、大人になってから「カバさん」になったそうですので、私たちもそう言ってます。東島さんはあや子といいますので「アヤちゃん」、それに私 ― 北村は「キタさん」と呼ばれています。このうちの4名は長いお付合をしていますが、実は中山さんは新しく入られたばかりで、お会いするのは今日が2度目。この法念寺も中山さんのご縁で利用させてもらうことになりました。
といいますのは、今日の催しも中山さんのご提案なんです。
谷崎潤一郎の『陰翳礼讃』を読んだ彼は、まだ電灯がなかった時代に生まれた伝統食=蕎麦切を、その時代の中で体験しようと提案されたのです。中山さんによると、能の面や歌舞伎の派手な化粧は蝋燭の灯の中で生まれた芸術だ、同じように江戸時代に完成した江戸蕎麦切も蝋燭のもとで味わってみるべきだというのです。
物好きな私たちは諸手を挙げて賛成し、そして先ほどお寺の茅葺門をくぐったというわけです。
初めに中山さんは本堂へ案内してくれました。そこで私たちはそろってご本尊さまにお参りをし、廊下に出て隣の座敷に行きました。廊下の右側にある窓ガラスは手作りガラスのようです。左側の障子をあけると十畳ほどの座敷がありました。その真ん中に燭台が置いてあります。もちろんまだ火は点いておりません。入ると、すこし寒気のする部屋でした。
「この部屋で食事をいただきます」と中山さんが断言するように言うと、皆は「お~」と意味もなく感嘆の声を漏らしました。
床の間には、掛軸が掛かっています。
近づいて拝見しますと、4人が1本の大きな蝋燭のもとに集まって、麺類を食べている場面が墨で描いてありました。
「中山さん、これ何?」とアヤちゃんが訊きますと、中山さんは瞼を下げて視線を落とし、「さあ、何でしょう? 親鸞の蕎麦喰伝説でも描いたのでしょうか」と低い声で呟きました。
「これが、伝説の・・・・・・、」皆は驚きました。
しかし中山さんは、皆の驚嘆を気にもとめずに「庫裏へ行きましょう」と言って先頭に立ちました。
振り向くと、殿のカバさんがその掛軸をスマホで撮っています。
私は「はやく」と手招きしました。
彼は歩きながらスマホを操作し、「しまったな」と舌打ちをしました。
「どうした?」
「ちょうど写すとき、一瞬風が吹いてきてさ、お軸が捲れたから、絵が隠れたのだよ。」
覘くと、たしかに絵の部分が捲れて見えません。
「きっと、描かれた人物が嫌がったんだよ」と冗談を言いながらも、風なんかいつ吹いたのだろうと、私は疑問に思いました。
「もう一度撮るか、」
「よせよ。お寺さんには文化財もあるから、勝手に撮っちゃだめだよ。」
「それもそうだな。キタさんの言う通りだ。」
それから二人は、みんなの後に続いて厨房に入りました。庫裏は別棟になっているので一旦外に出ます。といってもほんの五歩ていどです。
それでも少し離れた所から見ると、白壁に焦茶色の柱の構成がまるで着物の縞模様のように美しいのです。
土間は懐かしい敲土のままでした。
柱も黒くてでかいし、おまけに天井の梁組も大きいのです。少年の身体ぐらいの太さはあるでしょう。
皆は手早く作務衣に着換え、手拭を頭に被りました。
設置してある麺台は広いし、釜も大きいものです。それに流場はビジネス・ホテルのシングル用バスのように広いのです。
「これはすごいや。思い切って暴れられるぞ、」とカバさんが言ったので、皆が笑いましたが、蕎麦打ちはミナミさんが一番上手いのです。
さて、今日の蕎麦粉は常陸産、それを2kg用意しました。1kgは更科、これはミナミさんが打ちました。あとの1kgは二八、これはカバさんが打ちます。
そこへアヤちゃんが「これ微粉だから、蕎麦掻にしようか」って、私に言うのです。その私は蕎麦打が一番下手なので、いつも雑用係を引受けているのです。だから「はいはい」と言いながら、カバさんの蕎麦粉を少し分けてもらい、蕎麦掻作りに精を出しました。
お摘みはアヤちゃんが手際よく用意しています。白い小皿には焼海苔、黒い小皿には蒲鉾、黒い小鉢に豆腐、そしてアヤちゃんの手作の蕎麦味噌は大きな笹の葉の上に盛りました。
一方、中山さんが銘々膳を運んできました。しかし、生憎とお膳は四個しかないというのです。
アヤちゃんが自分の分を譲ると言いますが、中山さんは「今日は私が接待役ですから」と遠慮するのです。
そうこうしている途中で陽が落ちましたので、厨房の電気を点けました。お寺は蛍光灯はなく、全部屋が電灯でした。
その間に、ミナミさんとカバさんが蕎麦粉を練って、延して、トントントンと切った蕎麦切が出来上がりました。
お酒は、中山さんが昨夜から厨房の涼しい場所に置いていたようです。
「サッ、できたぞ。先ずは向こうに行って、飲もうか、」とミナミさんが声をかけます。
4人は各々自分の膳を持って座敷に行きました。
中山さんが、すぐに蠟燭に火を点けます。
蝋燭の炎が、青い芯の先で柿色と鬱金色にゆらゆらと揺れました。
「お~、」皆さんは感動の声を出します。
皆は、白い小皿の焼海苔、黒い小皿の蒲鉾、黒い小鉢の豆腐をしげしげと見つめます。
「ほ~。」
黒い小皿や黒い小鉢、それに黒い焼海苔が重厚に感じます。そしてその器に盛られている白い蒲鉾や豆腐がすごく立体的に見えるのです。
そうなんです。蝋燭の炎が陰翳を強調し、黒白の妙を見事に演出しているのです。
小皿に醤油を差すと醤油がねっとりと光っています。
杯にトクトクと注いだお酒は、さながら大海のようです。
皆はいつもより口数少なく、存分に料理の妙を味わっていました。
「中山さんも憎い提案をしてくれますね」とミナミさんが感嘆したように言うと、「ほんと」とアヤちゃんが相槌を打ちました。
カバさんが「どれ、そろそろ茹でてくるか」と立ち上がったので、アヤちゃんも「手伝うわ」と言って、後に続こうとします。
すると、中山さんが行く手を遮るように、手を横に振りながら「いえいえ、今日は私が全部やります」と言うのです。
それを見てミナミさんが「じゃあ、お願いしよか」と言ったので、カバさんとアヤちゃんも「何かあったら、呼んで、」と腰を下ろしました。
ほどなくして、中山さんが笊を運んできてくれました。
「お待ちどうさま。」
「お~、」
蕎麦切とつゆが蝋燭の光を浴びてにぶく光っています。
「つるつるつる」と皆が啜ります。
「旨いな~。」
「そうかい」とカバさん。
「いや、何というか、しみじみと旨いや。」
「蝋燭の炎のお蔭ね。」
「いや、まいったな。こんな世界があったんだ」と言いながら、今度はミナミさんが茹でに行こうとしますが、やっぱり今度も中山さんが茹でました。
二枚目の《更科》も、うっとりするほどきれいな色艶をしています。
「いい体験をさせてもらったな、」
「ほんと、ほんと。」
「おい、何か少し寒くなったな。そういえば、蕎麦湯がないや。」
「私が持ってきます」と、またもや中山さんが厨房へ行こうとします。
このとき、中山さんを見ると、一瞬だけ口が歪み、ゾッとするような蔭のある表情を見せたのです。
皆は、蕎麦の余韻を味わっているのかのように、黙っています。
私は、中山さんのあの恐ろしげな表情は蠟燭の陰翳のせいだろうと思いながらも、段々心配になってきました。
その中山さんは蕎麦湯を取りに行ったまま、いつまで経っても戻ってきません。
私は不思議に思いました。どうも、中山さんは、私たちがこの部屋から出て行こうとするのを嫌がっているように思えるのです。それに彼は今、席を立ったばかりなのに、時間感覚はもう一カ月も一年も経ってしまったような気がするのです。
そのとき私は、ふっと谷崎潤一郎にはもうひとつ『美食倶楽部』という妄想小説があったことを思い出しました。
「もしかしたら、中山さんは『陰翳礼讃』ではなく、『美食倶楽部』を再現しようとしたのではないだろうか。」
そう思い始めると、急に不安になってきました。
私は「アヤちゃん」と声をかけました。
彼女は返事をしません。
「ミナミさん、」「カバさん、」二人とも黙っています。
全員、急速に冷却されたかのように動きが止まっているのです。
思い出してみると、中山さんという人は、私たちと目を合わせて話すようなことがなかったような気がします。その怪しさに私は恐怖を感じました。
「もしかしたら・・・・・・、この部屋は何かの仕掛で冥界へ通じているのではないのか。彼はその案内人ではないのか。あ~!」
気付いたのが遅すぎました。
そのとき、4~5人の人たちが部屋に入って来ました。そしてそのうちの一人がスマホで私たちを撮ろうとしています。
そうなのです。掛け軸に描かれている4人は私たちだったのです。
私は必至になって「助けてくださ~い!」と叫びましたが、声になりません。その代わりに掛軸が揺れて壁に当たり、コトンと虚しい音がするたけでした。
〔☆ほしひかる〕