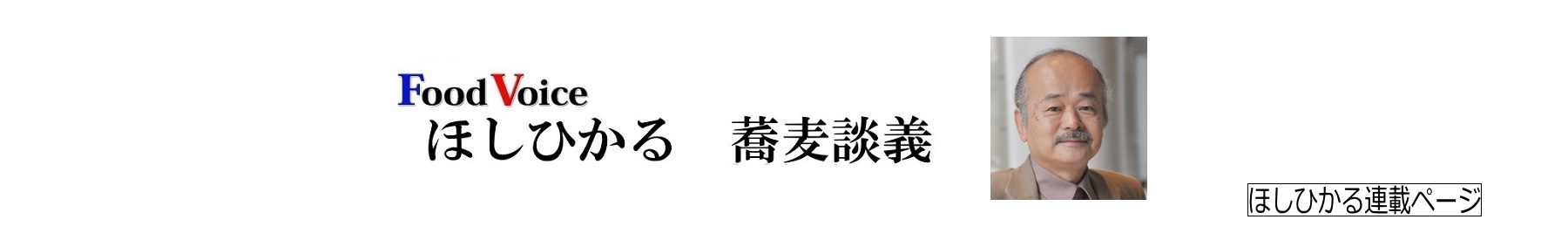第316話 小説「コーヒー・ブルース-XI」
2025/12/06
~ I’ve Lost You〔去りし君へのバラード〕♪ ~
野中が異動になってから、現在や前に担当していたドクターたちが歓送会をやってやると言ってくれた。
「別に、退職するわけじゃないんだけどな」と言いながら、野中は大村病院の陣内副院長のご好意にお付合した。
それから後輩の佐藤が「中村病院の高橋薬局長が会いたがっているから、何とかしてくれ」と言ってきた。佐藤はラブコールじゃないかと言う。
野中はこれには弱った。
佐藤はからかう。「向こうがその気になってるんだから、覚悟を決めて抱いてやったらどうですか。」
「ただ懐かしがっているだけだよ。」
「そりゃそうですよ。ただ、チャンスですよといつているんですよ。」
「お前、簡単に言うなよ。」
「おかしいなあ、昔の先輩とちがって妙に真面目だな。もしかしたら、これがいるんですか?」佐藤は小指を立てて言う。
「まあ、いないでもないかな。」健が恵子のことを他人に匂わせたのは初めてであった。
「なんだ、それならそうと早く言ってくださいよ。そうすりゃ先生に、僕が代わってお付合しますって言ったのに、ハハ」
「じゃ頼むよ。」
「冗談ですよ。それより紹介してくださいよ。」
「嫌だ。お前に紹介したら、盗られるから、」
「何ということを、ハハハ。とにかく高橋先生にははっきり言っておきますよ。野中先輩は彼女がいるのに、思わせ振りな態度ばかりとってひどい人ですよ、ってね。こういうことはそうした方がいいんですよ。変に気をもたせると可愛そうですからね。」
「余計なことを言うなよ。柱の陰から、先生のことをそっと見守っていますってぐらい言っといてくれ。」
「よく言いますよ。それじゃ、安っぽい演歌じゃないですか。」
佐藤は口では冗談を言っているけれど、一旦営業に出るとキチッとした男である。野中は心配していなかった。高橋先生のことは上手くやってくれるだろう。
東京消防病院の山本部長からも「どうだ」と言われたが、「今後もいろいろ相談したいことがありますから、そのときにしましょう」と返事をした。実際、野中の気持はそうであった。
代わりに、山本部長との間をつないでくれた遠藤ドクターと池袋の〔生粉打ち亭〕で一杯飲んだ。
遠藤医師は野中よりかなり背が高い。
「先生は学生時代に運動やってたんですか?」
「中学、高校時代は、バレーボールよ」
(なるほど) 脚が長くて、健康で、溌剌とした女子高生の姿が浮かぶようである。
「このでかい身体のおかげで、オトコが誰も近寄ってこないの、それでとうとう40歳。」遠藤医師はけらけらと笑う。
遠藤医師は、板わさ、鴨、天麩羅を肴に日本酒をよく飲んだ。そして締めにはこの店の名物〔江戸蕎麦〕。
蕎麦湯を飲んでいるときに、店主が挨拶に来た。
遠藤医師が「美味しかったわ。やっぱり手打ちは美味しいわね」と言ったのを皮切りに、店主がいろいろと蕎麦打ちのコツを話してくれたが、蕎麦打ちをやったことのない野中にはよく理解できなかった。ただ、店主はこう言った。「蕎麦打ちの世界で〔蕎聖〕と呼ばれた人がいたんだよ。片倉康雄という人なんだけど、この人が〝たかが蕎麦〟を〝されど蕎麦〟にまで高めた人なんだ。まあその人が出てこなければ、蕎麦は駄物で終わっていただろうな。」
「ああ、そう。どの世界にもそういう偉い人がいるのね。」遠藤医師が応じた。
野中も肯いていた。(ジャズ界のアルフレド・ライオンみたいな人なんだ。ブルーノート・レーベルを創立して、〝たかがジャズ〟を〝されどジャズ〟にまで高めた人だと、よく言われている。)
二人は店を出た。
「先生、ご馳走になりまして、すみません。」
「何言ってんのよ。野中さんの、歓送会じゃない。もう一軒行こうか、何処か知ってる?」
「はい。スナックでよかったら。」野中は新宿のケロンパ・ママの店に連れて行くために、タクシーを拾った。先にドクターを乗せ、後から乗り込んだが、遠藤医師が真ん中寄りに座っているので、彼女の長い脚と野中の脚の大腿部がピッタリくっついてしまった。女医先生の体温が伝わってくる。(困ったな) と思ったが、気付いているのか、いないのか、遠藤医師は外を見ながら言った。「山本先生も、偉い先生なのよ。」
「はい?」
「〔蕎聖〕じゃないけどね、平凡な医局を〔山本学校〕と呼ばれるまでに立派な医局にしたのよ。今ではうちのやり方を真似るところも出てきたわ。」
野中は(なるほど)と思ったが、遠藤先生が、いま何を言いたいのかがよく分からなかった。それより野中は〔キャラバン〕の親父が言っていたことを思い出していた。「日本の珈琲界には、名人はたくさんいるけれど、〔珈琲の神様〕がいないから、もうひとつ高い所まで上っていない。」
(どの世界にも、神様や聖人と呼ばれる人がいるんだ) と思った。
この度の健たちの異動は、会社ではまだ内定段階であったが、小田社長はそういうことは一切構わない。「顔を出せる者は、私の所に顔を出せ」と命じ、「事業化できる仕事を探し出せ、見つけ出せ。そしてそれを事業化するのがお前たちのやることだ。お前たちは社長になるんだ」と発破をかけていた。
野中は「探し出せ、見つけ出せ」という言葉に魅力を感じていた。今日の〔蕎聖〕にしても、社会の真実を見つけ出したようで、勉強になったと野中は思った。
店に着いたら、若い女の子が野中の隣に座って、お絞りを差し出した。野中は「先生が先だ」という風に手で示した。
「今日はピアノさんはまだ?」と女の子に訊いたとき、ケロンパ・ママが、「絵美ちゃん」と呼んだので、「はい。まだなんです」と言いながら、一旦席を外した。それから戻ると、今度は遠藤医師の隣に座って、水割の支度を始めた。
遠藤医師はそんな絵美がほとんど目に入らなかったようで、「会津の父が、私に帰ってこいと言ってるのよ。」
遠藤医師の実家は内科医院らしい。おそらく冨士子ドクターを呼び戻して、跡を継げというのだろう。(ああ、そうか。) 野中は先刻の遠藤医師の台詞の意味が分かった。(山本部長に付いて行くか、実家に戻るべきかを、悩んでらっしゃるのか、)
「野中君、どうしたらいい?」
「と申されても、私は詳しいご事情を知りませんから、」
「そうよね。そのうち私のグチでもゆっくり聞いてよ。」遠藤医師はそう言うと、いつものように笑った。
そんな二人を絵美はなぜか不満そうな目で見ている。
野中は、この子は何でこんな顔をするんだと不思議に思った。
暫く飲んでから、ピアノ弾きの清水が入ってきた。「先生、どうですか、歌ってくださいよ。
「恥かかせないで、私は体育会系なのよ。」
と言われれば、野中もそれ以上は押せない。
「野中さん、今度の部署は何をやるの?」
「会社をつくれって言われてます。」
「何の会社?」
「それを自分で探すんです。」
「へえ、変わった会社ね。それで見通しは?」
「全くなし。ハハハ。でも、何か見つかれば、山本先生から教わった企画立案のノウハウを活かしたいと思っていますよ。」
そんな話を小一時間ぐらいした後、遠藤医師は「明日は忙しいから」と言って帰った。
野中は残った。
「ノナちゃん。あんた、近ごろ目がイキイキしてるよ。モテモテでしょう。」年齢不詳のママは相変わらず、友達みたいな口調である。
「そんなことないよ。」
「何言ってんのよ、いまの女医さん、押せば落ちるよ。」
「おれは・・・」
「分かってるよ。お客さんはお客さんでしょ。まったく製薬会社の人はお品がいいからね。でもね、女医さんだってオンナだからね、しっかりしてるようでも悩みがあるんだよ。ノナちゃん、ベッドの中でそれを聞いて上げなよ。」
「よく言うよ、人ごとだと思って。」
「あんた、も少し若けりゃ、ホストになれたのにね。」
「ひどいこと言うな。オレは自分でオトコっぽい性格だと思ってたけど、」
「それは認めるよ。後輩の面倒見もいいしね。だけどね、あんたにはもう一ついいところがあるんだよ。ね、絵美ちゃん。」
若い子は肯く。
野中はあらためてその子を見てみたが、最近入った子で、前に来たときもいたような気がする。まだ20歳そこそこ、ショートヘアでシャープな眼に、精悍な顔をしていたが、勝気なようで、脆そうにも見える。
「何? いいとこって、」
「絵美、どう?」
「野中さんの隣に座りたくなる。」
「え?」
「そうそう、それだよ。だから、さっきも注意して、女医さんの隣に座りなさいって言ったんだよ。」
「そうだったのか。さすがにママだな。」
「ノナちゃんは誠実で、あったかそうでさ、付き合ってみると頼り甲斐がある、ワルじゃない優しさもいいな、っていうところがあるんだよ。ま、特別にいい男だというわけではないけどさ。なにしろ偽物のヤサ男や脳味噌が空っぽのイイ男はいっぱいいるからね。」
「何だ、それじゃただ人がいいだけで、モテるとかいう話じゃないじゃないか。」
「そんことないよ。心に深~い傷をもった女たちが羽根を休めにやって来たときは、それが一番大切なことなんだよ。」
「勘弁してくれよ。それじゃ、慰め役じゃないか、」
「マ、それもあるね。そんな中から抱かれてもいいかナ、って女も偶にはいるかもね。ははは。」
「偶にかよ。ハハハ。」
「偶だっていいんだよ。私なんか、ずっとご無沙汰なんだから。蜘蛛の巣だわ、ははは。」
「そうですか。」
「それにノナちゃん、喜びな。まだ19歳のこの絵美が、ノナちゃんに気があるみたいだから、でしょう?」
絵美は照れたようにして肯いた。
「ほらほらほら・・・・・・。」
「からかうなよ。」
「あら、私はほんとうのことしか言わないよ。夜の世界、酒の世界はね、女と男の、男どうしの、女どうしの、本音の世界だからね。」
ピアノの清水が曲を弾いている。
「あの曲、聞いたことがあるな。何っだっけ?」野中は絵美に訊いたが、絵美は「知らない」と言いながら。清水の所に行って戻って来た。「プレスリーの【去りし君へのバラード】だって。」
「あっそうか。去れって言うから、帰ろっ、」
清水が笑いながら、「違う違う」と手を横に振っている。
野中は「じゃ」っと、右手を上げて立ち上がった。
「はい、一丁上がり。絵美ちゃん、お送りして。今度はノナちゃんだけだから、はっきり言うんだよ。好きだとか、嫌いだとか。ははは。」
エレベータに乗ったとたん、絵美は野中の手を握ってきた。
「きみは学生?」
「そう」と言うと、今度は野中の腕を両腕でしっかり組んできた。絵美は、外に出ても腕を離さなかった。
それを見て、(恵子も学生時代から水商売に入ったと言っていた) と胸が痛んだ。野中は恵子の所へ行きたくなった。「ちょっと電話してくる。」野中は絵美の腕を外して公衆電話の方へ行った。時計を見ると1時である。恵子に電話した。恵子は帰っていた。野中はホッとした。いつもの声で「うん。待ってます」と言ってくれた。
振り向くと、絵美が睨むような顔をして立っている。「どこ行くの?」
「どこも、ただ電話しただけ。」
「うそ。オンナのとこでしょ、」
(オンナ! こんな小娘がおれの大事な恵子のことを、) 野中は腹が立った。(冗談じゃない、よく知りもしないお前からそんな風に言われる筋合いはない)と言おうかと思ったが、(まだ若い子だ) と思って気持を押さえた。しかしその怒りは19歳の絵美と若いころの恵子の姿が重なって、恵子の過去に嫉妬したせいかもしれなかった。
絵美はお構いなしに「今度、誘って」と言ってきた。
野中は返事をしないで、タクシーを捕まえた。早く恵子の所へ行きたかった。
タクシーに乗ってから、「今日は何という日だ」と呟きながら、野中はポケットから煙草を取り出し、火を点けた。
(でも、モテる時期とモテない時期があるのは確かだな。) 思い出すと、真知子に振られたころはまったくモテなかった。
しかし由利子と付合っていたころは、今日のような機会が何回かあった。現に何度か浮気したこともあった。
そして由利子と別れた後、恵子と出会うまではまたサッパリだった。そんな野中も今は前とちがっていた。恵子以外の女性にはまったく関心がもてなかった。それよりか久し振りに心配に火が点いていた。(営業用でも、恵子には他の男の手を握ってほしくない。昼間の仕事のお世辞とちがい、夜の世界のお世辞は危険だ。早く恵子に水商売から足を洗ってもらいたい) と思った。
それに、健には悩みがあった。それは、どうしても狭い1Kのアパートに恵子を連れて来れないことだった。前の恋人由利子とは互のアパートに行ったり、泊ったりしていた。しかし、恵子の部屋の調度品、彼女の持っている着物の数、宝石の数から見ても、由利子とも、自分とも、レベルが格段に違っていた。それが男として情ないし、辛かった。
恵子のマンションに着いた。健はマンションの入口で上着を脱いで、叩いた。やましいことをしたわけではなかったが、絵美の化粧品の匂いでも残っていたら恵子に悪いと心配だった。
迎えてくれた恵子の菩薩のような優しい笑みを見たとたん、健の今までのイライラはスーと消えた。健は (やっぱり恵子がいい。) そう思った。
「ね。今日とってもいいことがあったのよ。」
「何?」恵子の声を聞いた健はさらに落ち着いてきた。
「洋子さんのこと。別れたご主人が訪ねてみえたんですって。」
「・・・・・・?」
「彼女、30年ほど前に離婚していたのよ。そのご主人が『すまなかった』とおっしゃって、見えたんですって。」
「へえ、それは凄い。オトコだね。」
「ね。」
「そういえば、〔キャラバン〕の親父もさ、店と自宅を担保にして、痴呆の奥さんの入院費を作ってたんだって、」
「それも凄いわ。」
(健は言わなかったが、思えば、真知子の父親だって養子の道を貫いていたんだ。)「だろう。みんなオトコだよ。おれだけダメ、」
「何を言ってるの、あたなもオトコよ。恵子を守ってくれてるわ。」
「洋子さんの旦那さんや〔キャラバン〕の親父さんの人生を賭けた優しさに比べりゃ、たいしたことないよ。」
「ううん。あなたは恵子にとって大切な人よ。」恵子は健の手を握った。
「ほんとに、恵子は優しいな。泣けてくるよ。」と言いながら、「今日は、一緒に風呂に入りたい気分」と言った。
恵子はニッコリ笑って、「うん」と肯いた。
「ニューヨークでは毎晩一緒だったな。」
「ふふふ」
「NEW YORK、入浴!」
「ンもう。」恵子はバスルームに健の背中を押して行った。
先に入った健は、思い切り背伸びして、(ああ、おれはいつも恵子から優しさをもらっているだけ、恵子に何もしてやってないな。) と一人嘆いていた。
健たち新規事業部員たちは小田社長の特訓を受けていた。
野中は、日本でも登場したばかりのワードプロセッサーなるものを習いに行っていた。ある者は各界のトップクラスの人物に会って話を聞いたり、ある者は経済セミナーを聴講したり、ある者は一番流行っている店を見に行ったりしていたが、たいていはその日のことを社長に報告しなければならなかった。
そのときは、社長の机の上に必ず大学ノートが開かれていた。頁を捲ると「健康と美容」と大きな字で書かれていた。要するに、近い将来は「健康」か「美容」という要素のビジネスがものになる、という意味である。
企画部から来た西村という男は、老人マンションの話を持ってきた。普通のマンションですら、高嶺の花である。それが老人専用のマンション? そんな話、今まで誰も聞いたことがない。
ところが社長は「面白いじゃないか。誰から聴いてきた?」と言う。
「○○病院の老人科の医師です。」と西村は答えた。
「そうか。何て言ってたんだ。」
「健康時代のその先には、老人社会が見えてくる。だから将来、老人マンションなんかが必要になるだろう、って言ってました。」
「そうか。孫の世話は金を出してでもするけど、年寄の面倒は金をもらってもイヤだ、と言うだろう。人間というのは勝手なんだ。その勝手がビジネスの種になる。」
小田社長というのは、そういう人だった。人間の本質から判断する。それから情報先も現場発でないとダメだった。「セミナーの講師が・・・」なんて答えようものなら、「大きな流れとしては、いい。でもな、セミナーなんていうのは所詮カルチャーだ。飾りだよ。」と言って信用しない。
社長は西村に「お前に何ができるか、考えろ」と付け加えた。
健は部署が変わってから、イキイキしていた。まるで子どものように新しいこと、未開拓的なことに好奇心を示していた。
(今、この人は大事な時期なんだわ。) そんな目で健を眺めている恵子も幸せだった。それに営業でなくなった健は接待がなくなったため、毎週土・日に泊ってくれるようになった。パジャマ、歯ブラシ、髭剃りは前から置いていたが、恵子の下着ダンスに健の下着が増えていった。洋服ダンスには健のシャツやネクタイがぶらさがるようになった。恵子は同棲生活とほとんど変わらなくなった日々を楽しんでいた。
恵子は、健を愛するようになってから、「ますますきれいになった。」「こぼれるような色気にあふれている。」としょっちゅう言われるようになった。男の客は蔭で「一度でいいから恵子ママを抱いてみたいナ」なんて言っているのも聞こえていた。店の女の子は「ママとキスしたい」と冗談を言う子もいた。
鏡を見て恵子は、前より優しい顔付になっていることに気付いていた。これも心を満たす健との愛のせいだと思った。
日曜日の午後だった。外出のために恵子は顔にクリームを塗っていた。鏡にはベッドで横になっている健が映っている。
健は恵子を眺めていた。
恵子は鏡の中の健に向かって言った。「いやだわ。何を見てるの。」
「うん。化粧する恵子を見ている。」
「どうして?」
「社長は、『美と健康』と言ってるんだけど、美のビジネスってよく分からないんだ。」
「何だ、恵子のことを見てくれているのかと思ったら、がっかり。」
「怒った?」
「うん、怒った。なんてウソ。美のビジネスって山ほどあるわよ。化粧品、ヘア、ファッション、下着、バッグ、装飾品。雑誌もあるし、ジムなんかもそうじゃないの。」
「そうか。でも、恵子は化粧しなくても、きれいじゃない。」
「まあ、嬉しいことを言ってくれますこと。でもね、お化粧は楽しいわよ。」
「楽しい?」
「そうよ。化けられますからね。」
「どういう風に?」
「お化粧で、一番変えられないのは鼻、次は口かな。せいぜい口紅の色で変えられるくらい。でもね、お化粧で眉と目は変えられるの。鼻と口は立体でしょ、それに比べて目と眉は平面だから、描けるのよ。」
「はあ、なるほどね。恵子のお父上は画家だったと聞いたけど、さすがだね。顔の中の立体と平面をとらまえるなんて、」
「そうお。お化粧法によって髪型も変えられるでしょう。そしてそのヘアスタイルに合わせてお洋服も決めるの。そうするとね、気持まで変わっちゃうの。」
「気持も?」
「そうよ。恵子は和服のときと、お洋服のときは気分が違うの。」
「どんなに?」
「和服のときはあなたを愛して上げたくなるの。お洋服のときはあなたに愛されたいの、なんてね。」
「まあ、嬉しいことを言ってくれますね。」
「ふふふ。でもね、その逆もあるわよ。」
「え?」
「優しい気持をもっているときは、優しい化粧になるの。きつい心のときは張り合うような化粧をしているの。恵子はあなたを愛するようになってから、ゆとりが出たのね、優しい化粧をするようになったわ。そうしたら、女の子たちに慕われるようになったの。」
「へえ。お化粧の世界も奥が深いんだ。これじゃ、男は手が出ないよ。」
「そうね。クレオパトラよりもっともっと昔から、女性はお化粧をしているものね。」
「そういえばさ、ニューヨークで五番街とかを回ったじゃない。あのときの恵子はお店によく合っていたよ。何かお店のオーナーみたいだった。恵子のお母さんはデザイナーだったんだよね。やはり血筋だな。」
「ううん、デザイナーの玉子のそのまたタマゴぐらいよ。」
「それでも血筋だよ。お父さんとお母さんのセンス・・・、恵子は美の世界が合ってるんだ。」
(えっ! あなたは私のことを考えてくれてたの。) 化粧が済んだ恵子は、嬉しくなって、ベッドに寝転んでいる健の両手を取って起こして上げたが、その勢いで口紅が頬に付いた。
「ふふ、付いちゃった。」恵子はそれをハンカチで拭いて上げて、「さ、出かけましょうよ」と言って、健の上着を持ってきた。
健は少し胸が痛かった。(こんなに優しくしてもらって、おれは幸せ者だな。)
二人は車で、恵子の知り合いの画家が展示しているという八重洲の美術館に行った。先に贈っていた花束が飾ってあったが、幸い美術館には知人はいなかったので、記帳だけした。そしてちょっと間をおいてから、隣に「健」と併記した。恵子はニューヨークから帰ってから、心境が変化していた。以前は健のことを秘密にしていた。仕事上、当然であった。それが最近は今日のような行為をよくとるようになった。ささやかながらも夫婦ごっこの雰囲気だけでも味わいたくなったのである。
二人は、展示してある花や裸婦の絵を見て回った。
恵子は裸婦像を見ながら、高校生のころ母が言っていたことを思い出していた。「モデルはね、ただ呆として座ってるだけじゃないのよ。絵描きさんが、いい絵を描いてくれるようなモデルにならないとだめなのよ。」
(父と母は、信頼し合ってたんだわ。) そう思いながら、恵子は健と腕を組んだ。そして恵子は、今が人生で最高に幸せのときだと思った。健がいないときにはちょっと不安になったり、余計な心配をしたり、涙したりしているが、それも幸せの裏返しだと分かっていた。
(私は恵まれすぎているわ。この人から幸せをもらう一方、なのに私はこの人にまだ何もして上げていない。) 恵子はそれだけがちょっぴり辛かった。
それから二人はまた車に乗って、神楽坂の天ぷら屋〔金とら〕へ行った。
店は毘沙門天で知られる〔善國寺〕の裏にあった。そのために店の名前を「毘沙門天の虎」をとって〔金とら〕としていた。
健は近くの駐車場に車を止めた。
長い黒塀の料亭の、その隣の店の戸を開けると、「いらっしゃいませ」と声がかかった。
「まあ、恵子ママ。いらっしゃい。今日は珍しくお洋服で、」と女将が挨拶をする。
「そう。今日はプライベートだから」と恵子が言うと、女将が健の方を見て、「あら、こちらは確か野中さん、」
健が軽く頭を下げると、女将は「二度ほどお見えいただきましたよね。お久しぶりでございます」と言いながら、カウンターの端に二人を案内した。
女将はお絞りを渡し、「恵子さん。あなたがますますきれいになってるわけが、分かりましたよ。」
「え~?」と笑いながらも、恵子は否定しなかった。
それよりか女将の前で「あなた。女将の桃子さん、恵子と仲がいいのよ」と言って、女将を紹介した。
恵子が「あなた」と言ったとき、女将は (まあ) というような顔をしていたが、「いつの間にかしっかり彼氏を捕まえていたのね。野中さん、恵子さんは可愛いでしょう。女の私でもそう思うわ」とお酌をしてくれた。
恵子も一口お酒を飲んだ。
恵子は常連のようで、黙って座っているだけで、恵子の好きな物が揚げられてくる。
「金とら」の天ぷら油は場所柄、芸者衆の着物に匂いが付かないように、匂いの少ない綿実油を使っていることで知られている。それから衣液には白身を使う「銀ぷら」と、黄身だけを使う「金ぷら」があるけど「うちは〔金ぷら〕だ」と前に来たときご主人が言っていた。
「今は〝江戸前〟はなくなって、〝日本前〟だ」とはどこの天ぷら屋も鮨屋もよく言うことだが、二人の目の前に〝日本前〟の魚介類がきれいに揚がってきて、サックリと美味しそうである。
ところが、今日の恵子は食欲がなさそうだった。出てきたものにほとんど箸を付けていない。
女将が、それをじっと見ていて「恵子さん。表に出て、外の風にでもあたりましょうか」と言って、誘い出した。
二人は、15分ぐらい外で休んで、戻ってきた。
そして「あなた。今日はすこし疲れたみたいだから、帰っていいかしら?」と恵子が言った。
健は驚いたが、女将も「そうした方がいいわよ」と言う。健は慌てて席を立った。
女将が見送ってくれた。「野中さん、恵子さんのこと宜しくお願いしますね」と頭を下げた。
恵子は「桃子さん、ありがとうね。」そう言って、女将の前で健の腕を取って健の身体に寄りそった。
女将はそれを見てにっこり笑った。
翌日だった。お茶の水にある大学病院の会計の前に、大きなサングラスをかけた恵子が座っていた。
ここ数日、恵子は身体の変調が気になっていた。それが「金とら」の女将に「恵子さん、もしかしたら妊娠しているんじゃないの? 野中さんに言わなくていいの?」と言われたが、「今日は待って、明日病院で診てもらうから」と頼んでいた。
恵子の店には、産科医の客はあまり来なかったが、用心して大きなサングラスを掛けて来た。診てくれたのは若い女医だった。女医さんは「おめでたですね、三カ月に入ろうとしているところです。順調ですよ」と若いわりには落ち着いた声で言った。
恵子は、妊娠が初めてだったにもかかわらず、それを告げられても心は穏やかだった。 (妊娠したのは、日数からいってニューヨークにいるころ。当然だわ) とさえ思った。海外旅行中ということもあったのだろうか、それともニューヨークという自由な雰囲気のせいだろうか、水着を着けずに裸で大海を自由に泳ぎ回ったような日々だった。恵子は、(妊娠したのは、きっとあの満月を見たあの夜だわ) とわけもなく確信し、嬉しく思った。
このとき、恵子の隣の椅子に赤児を抱いた若い女性が座った。
恵子はサングラスを外して、赤児を見た。
赤児は黒い大きな眼で恵子をじっと見つめている。
「まあ、可愛い。」恵子は思わず声を出して、ちっちゃな手をそっと握ってやった。
若い母親は嬉しそうな顔をして、にっこり笑った。
この時になって初めて恵子は胸がドキドキし始めた。(私は何ておバカさんなんだろう) と思った。(妊娠というのは赤ん坊を産むということなんだ) と赤ん坊の小さな手を通し、初めて思い知った。そうなんだ。この私も子供を産むことができるんだという実感を初めてもった。
(どうしよう。) 「どうしよう」というのは、健への報告である。「妊娠した」ことはすぐにでも言おうと思っていた。しかし「赤ちゃんができた」とはとても言えないような気がした。「妊娠」というのは男女のセックスだけの感じがする。だが「赤ちゃん」という言葉のなかには家族という雰囲気がそなわっている。
健にどう言おうか?
(それでも健には真っ先に電話しなくてはならない) と思って、一度電話の所へ行ったが、また戻ってきた。
赤ちゃんが、またじっと見つめている。
恵子は、にっこり笑ってそっと頬を指で擦って、また電話の所へ行った。そして受話器を外して健の自宅の電話番号を回した。「ツー・ツー・ツー・・・」今の時間、健は会社である。家にいるはずがない。
恵子は受話器を下ろした。(やはり、あの人に赤ちゃんのことは言えない。健のご両親にさえお会いしていないのに、)
このとき、名前を呼ばれたので、そのまま窓口に行って支払を済ませ、また椅子に腰を下ろした。
が、再び電話の所へ戻って、ダイアルを回した。「ツー・ツー・ツー・・・」 呼出音は続く。しかし恵子は、その呼出音に向かって「あなた。今日、病院に行ってきました。恵子はあなたの赤ちゃんを授かりました。恵子は産みます。」そう言って、受話器をそっと元に戻した。
恵子はもう一度赤ちゃんの所へ行って、「ありがとう。お元気でね」と声をかけて、外に出た。恵子はさっきの空電話で決心していた。(私はこの子を産むわ。)
恵子は車を拾った。決心した恵子の決断は素早かった。(店を売ろう。あとは徳子がふさわしい。) 恵子はサングラスをかけた。 (この児のために夜の仕事は卒業しよう。そういう気持をもつようになってのは、あの人と付き合ったおかげ。だから、あの人に絶対迷惑はかけられない。迷惑をかけないためには、あの人と別れることになる!) 恵子は唇を噛んだ。(私は、あの人からもらう一方、とうとう赤ちゃんまでもらってしまった。なのに私はあの人に何もして上げられなかった。) そう思ったとたん、サングラスの下から涙がポロポロ流れ出て止まらなかった。「うううう・・・・」、恵子は声を出して泣き始めた。運転手がびっくりして車を停めた。恵子は「行って」と命じた。恵子は嗚咽を抑えようとしたが、抑えきれなかった。
マンションに帰っても、嗚咽はよけいに激しくなった。(健と別れることになるなんて!) 恵子はベッドの上で小学生のように声を出して泣きじゃくった。
(XII.〔ムーンリバー〕へ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕