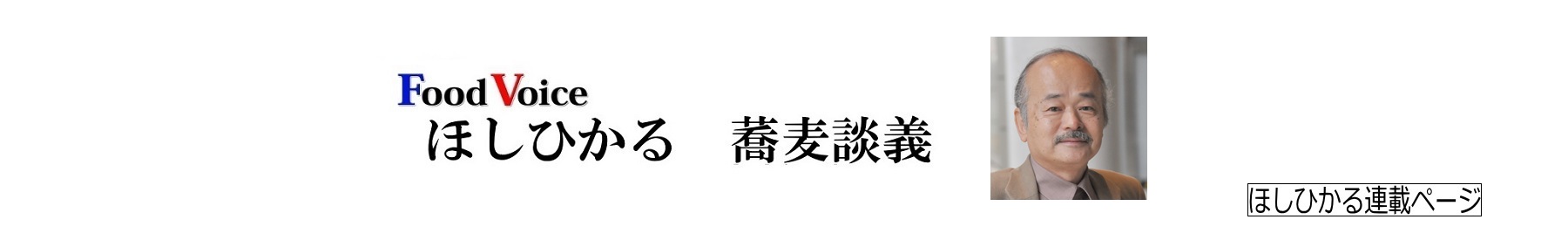第331話 小説「コーヒー・ブルース- XV」
2025/12/06
~ Bridge Over Troubled Water ♪ ~
(〝インフォームド・コンセント〟って、いったい何だ?) 野中は気になって仕方がないので、東京消防中央病院の山本部長に尋ねに行こうと思った。
その前に、西銀座クリニックの遠藤医師を訪ねた。お会いしたのは昼過ぎ、例の〔生粉打ち亭〕だった。
「そうね。私も『説明と同意』ぐらいしか知らないわね。欧米の考え方だから、日本の医者に訊くより、アメリカに行ってみたらどう。」
「アメリカですか。」やっぱり、明解は得られない。野中はとりあえず、(大学病院やそれに匹敵する病院の医師は、〝インフォームド・コンセント〟ということは知っているが、あまり関心はなさそう。しかし街の開業医はさらに言葉すらも聞いたことがないようだ) という認識をもった。
そして翌日、古賀を伴って消防病院の山本医師を訪ねた。
山本医師は「うん。〝インフォームド・コンセント〟の考え方が日本に上陸することは間違いない。医療技術や考え方というのは、昔はドイツ主義だったけど、今はアメリカ主義だからね。僕はできるだけアメリカの学会を見ているけど、何年か経ったら、必ず日本もそうなっている。だから、その方向で何かしよういうのは、面白いじゃないか。」
全医師が懐疑的だったというのに、(やはり、山本先生は違ったな) と野中は感心した。
「またコンピューターのことは詳しくないが、その波も押し寄せてくるのは間違いない。」
古賀は嬉しそうな顔をしている。というよりかやや興奮気味である。
山本医師は、ちょっと思案してから、英語で書いたメモを野中に渡した。
【Better Living As Human】 メモにはそう書いてあった。
「僕の理念だ。君たちだって、同じ医療人だ。この言葉を上げるよ。」
ソウルに行ったとき、「銃で遊びたくない」と拒否した山本医師を思い出し、野中は深く肯いた。
会社に戻って、野中と古賀は小田社長に報告するために社長室の戸を叩いた。
部屋ではすでに他の新規事業部員が社長節を聞かされていた。
「社長というのは身体丸ごと会社なんだ。そこがサラリーマンとは違う。」
だいたいこれまで聞いてきたことと同じだが、社長は何回も繰り返して説く。
「君たちは、仕事も上手くやらなければ! ゴルフも上達しなければ! とあれもこれも大事だと思うだろうが、それは考え違いだ。社長は仕事が一番、ゴルフは二番だ。そこから、覚悟も、判断基準も違ってくる。」
「ゴルフの上達も仕事に役立つと思いますが、」
「それは本末転倒だ。その原因は、右か、左かを選ぼうという方法がまちがっている。基準は、縦に一番、二番と判断しなければなら。そういう癖を付けるのだ。」
「一番、二番・・・、ですか。」
「そうだ。社長の第一の仕事は何だ?」
「黒字にすることです、」
「なぜだ?」
「・・・・・・。」
「社長の責任の一つは給料を払うことだ。きみの家族は何人だ?」
「4人です。」
「そうか、じゃ一家4人いる君に僕は、どうか今月の給料は待ってくれとか、勘弁してくれというわけにはいかんだろう。だから黒字にしなければならん。社長にとってゴルフの上達は二番目だ。」
「・・・・・・。」
「黒字か、ゴルフ上達かという具合に、右か、左かじゃないだろう。僕がゴルフ上達を選んだら、君たちは堪らんだろう。」
「はい。」
「会社は先ず黒字だよ。だから、営業成績の未達成者はダメだと言うのだ。Aができているのに、なぜBが達成しない。原因があるだろう。それを探し出して、解決するのが営業マンの仕事だ。その解決を手伝ってやるのが、上司や社長の仕事だ。社長は池を造ることをいつも考えていなければならん。」
皆。グーの音も出ない。
そんなとき、野中と古賀が社長室に入って行った。
小田社長は野中の方に向いて「何だ?」という顔をした。
野中と古賀は、山本先生から言われたことを報告した。
「〝説明と同意〟? 難しい言葉を使うなよ。ようするに僕がここでしゃべっているように分かってもらうことだろう。それがアメリカのやり方だというのだろう。だとしたら、山本先生がおっしゃる通りだよ。戦後の日本はアメリカ一辺倒だから、そういう考え方も必ず日本に上陸する。それからコンピューターのことはよく分からんけど、それも先生の言う通りだと思う。人間は機械を信用するものだよ。なぜなら人間は横着なんだから。だから、流れはいい。あとは、君たちがコンピューターで何をやるか、早く決めろ。悠長なことをしていると、他所がやるぞ。人手が要るなら、そう言いなさい。必要があれば、増やす。どうなんだ、古賀。」
「はい、人出は要ります。」
「何人だ?」
「3人は欲しいです。」
「じゃ、野中、人事部に交渉してこい。」
「はい。」
「それから、【Better Living As Human】という考え方ね、まあいいだろうよ。物だけ造ることを『仏造って魂入れず』と言うからな。ただし、それは山本先生の言葉だ。野中の身体から生まれた言葉じゃないだろう。だから、偽の魂だ。」
「・・・!」
「使うなら、お前の言葉として使えるようになったとき、使え。」
「ハイ。」
野中は、社長の言う通りだと思った。
そのとき昼刻になった。社長室に居た者は社長と一緒に外に出た。行先は、近くの蕎麦屋である。
蕎麦屋で社長が言う。「さ、君たちの好きな物を頼みなさい。僕は狐うどん。」
これには皆、苦笑する。「好きな物を食べていい」と言われるけど、先に社長に「狐うどん」と言われてしまえば、あまり高い物は頼めない。だから、僕も、おれも、私も同じ物となって、社長と別れた後「やっぱり、おれたちはサラリーマンだな」と嘆くことになる。
しかし、この光景が他の部署の者から見れば、羨ましくてたまらない。社長の話を聞きながらの昼食は、今までは取締役か、部長クラスでしかありえなかったからである。
社長はといえば、そんな社員の心理はお構いなし。社長自身もいわゆる「経営塾」を楽しんでいた。
「さっき、戦後日本はアメリカ一辺倒になったと言っただろう。戦争が終わったとき、南方に行っていたわれわれは運が良かった。アメリカ軍はわれわれを日本に帰してくれた。北へ行っていた友人は不幸だった。ロシアが帰還を許さなかった。だから、日本人はアメリカ一辺倒になったのだ。」
昼食後、野中と古賀は話し合った。
「3人補充すれば、5人体制。プロジェクトの発足ですね!」
「やってみるか!」
古賀は素直に「はい!」と返事をしていたが、野中は映画か小説かで言っていたような台詞「偶には勇気や無謀も必要だ。成功すれば勇気といわれるが、失敗すれば無謀と非難される」という言葉を思い出した。
その脚で野中は、コンピューターのできそうな理科系の人間を3名、ほしいと人事部長に申入れに行った。
部長は、「社長に通している」と言ったら、二つ返事で「候補を上げる」と返答してくれた。ただ、そう言いながらもちょっぴり皮肉めいたことも付け加えた。「小田社長は、よく『一番、二番という思考法を取れ』とおっしゃるけど、うちは薬屋だ。薬が一番じゃないのかね。」
「それは私もわきまえていますよ。」
「そうかね。社長のお墨付をもらって、大手を振っているように見えなくもないけどね。」
「その大出は気概だと理解してください。」
「そうか、なるほどね。」
野中は人事部長に皮肉を言われたせいか、かえってヤル気がわいてきていた。健は、数日前にきていた恵子からの手紙の内容を頭に浮かべた。
何とかというファッション雑誌の編集者と会ったとき、「毎号の雑誌を一つの作品だと思って創っている」と言われたと、書いてあった。
野中は、(そういう風にも考えられるな) と思った。(古賀とのブロジェクトもまさに一つの作品だ。山本先生方式のまとめ方でいうなら、タイトルが【情報医療システム】、サブタイトルが【Better Living As Human】という作品なんだ。しかし、残念ながらまだタイトルとサブタイトルでしかない。そのタイトルの「情報医療」は自分で思い付いた概念であるが、【Better Living As Human】というサブタイトルは自分の言葉ではない。それに、本でいえば大事な各章立てがまだできていない。)
野中は、それこそ「社長のお墨付」が効く間に何とかしたい! との決意をもった。
この事業部に来てからの野中は、薬剤や医学の雑誌より、医療経営関係の雑誌に目を通すことが多くなった。そんなとき、世田谷の個人病院、木村産婦人科で、先進的な取組みをやっているとの記事を見つけた。
(院長木村肇・・・、そういえばベンチャービジネス交流会で名刺交換をしていたな。) それを思い出しながら、野中はすぐにアポを入れた。名刺は交換していたが、ふだんから「製薬会社」というキップがあれば医療機関は理由も訊かずにアポはオーケーである。社内の担当者にだけ「調査のために面談する」と伝えておけばいい。
病院は小田急沿線の高級住宅街にあった。周りには樹木が多く繁っており、病院の外観はモダンだった。そして院内は清潔で、患者さんも多かった。
さっそく木村院長に会ってから話を聞くと、「患者さんに病気の説明と治療方針を丁寧に説明している」と言う。
(それは今までの治療でもなされていたのではないだろうか。) 野中はまだ十分に理解できなかった。
「実はね、ハワイに行ってたとき、階段から落ちて骨折したんだよ。日本では安静第一、ベッドで寝てなければならないけれど、アメリカではすぐリハビリに入るんだよ。それが患者さんのためと言うんだ。それで、帰国してから今までの考え方を変えようと思った。」
野中は木村院長が言う「患者さん」という言葉に新鮮さ感じた。医療機関ではたいていの人が「患者」と言っているが、院長は「さん」を付けている。そう思いながら、「治療法が違うんですね。」と返した。
「そう。安静第一か、直ぐリハか、というのは治療法だけど、日本に帰ってから患者さんと接しているうちに、その根底にあるものも違うなと気付き始めたんだ。」
「・・・・・・、」
「欧米人は自律、自立、自力ということを大切にしているが、日本人は、他律、他立、他力だということはよくいわれているね。」
「はい。」
「人間の身体は再生する力があるがあるんだけれど、その部分を信頼しようということなんだよ。」
「・・・・・・。」
「ところが、日本の場合、その前に患者さんが医師を信頼し切っている、というより頼り切っている。一部の渡鳥の患者は別としてね、」
「そうですよ。」
「だから私も、最初は頼り切っている日本の患者さんには説明とか、納得とかは不要だと思った。」
「なるほど。」
「しかし、医者から見れば、間の合う患者さんと、合わない患者さんがいるんだよ。医療技術や治療法云々の前にね。」
「それはよく聞きます。」
「そう、ここが重要だと思うのだが、われわれは間の合わない患者さんとこそ、コミュニケーションを欠かしてはならないと思うんだ。」
「欧米では自立性のある患者さんのために説明と同意が必要不可欠な医療行為だけれど、日本の場合は他力的な患者さんを相手にする医療機関のために、というわけですか?」
「そうだよ。だけどね、医師会なんかでも話してもね、皆さんは患者に余計なことを言って不安を与えてはならないと言うんだね。」
「癌は告知しない方がいいというわけでしょう。」
「そう。だけど、芥川龍之介の『蜘蛛の糸』、知ってるよね。」
「はい。」
「今、天井から蜘蛛の糸が下りてきたとしたら、野中君はそれに捕まって自力で登るかね? それとも、助けが来るまで黙って待つかね?」
「うーん。今は、自力で上がっていきたいですね。」
「そうだろう。若い人がそう言うのだから、これからは待つだけではダメという考え方に変化してゆくと思うよ。リハビリがそうなんだ。患者さんは自力で治していく。医者はその手助けをする。という風に考え方が変わってゆくよ。」
「そうでしょうか? と今は思います。」
「今はね! でも、将来の日本人は自力型になっていくと思うよ。そのときはお産の入院日数や、産後の考え方なんかも変わってくる。」
「ちょっと信じられないですけれど、おそらくそうなるだろうなという気もします。」
「一旦考え方を逆転させるとね、アイディアというものは次々と沸いてくるもんだよ。たとえば食事なんか、優秀なシェフを招いて、美味しい食事にした。それが好評だったから、食堂をレストランにして、一般の人も食べられるようにした。」
「はあ。病院と学校の食事は安いけど美味しくないものでしたね。」
それから木村院長は「日本の医療を改革していきたい」というようなことを熱っぽく語ってくれたが、そういう考え方に関心をもってくれた野中に対しても、院長は信頼感をもってくれたようで、「これから一緒にやって行こう」と言ってくれた。
野中は、木村院長といい、情報医療システムを手掛けている岩崎さんといい、明日を見つめている人たちの存在を知った。ただし、60代後半の木村院長、30代半ばの岩崎さんのお二人は、アメリカで先取性の洗礼を受けたところが、社長の言う「日本はアメリカ一辺倒」、山本先生の言う「現代医療はアメリカ主義」ということだろうかと思った。
(そういえば、ニューヨークの恵子は今ごろどうしているのだろう?) そう思った野中は新宿へ出てところで、中央線に乗り換え、吉祥寺で下車した。(久しぶりに〔もか〕に行ってみようか) という気になった。
野中は、井の頭公園の方へ歩いて行って〔もか〕の戸を開けて椅子に座った。
隣には常連らしい客が店主と話していたが、あの日は隣の席に恵子がいた。
健は、〔もか〕の、格調高い珈琲に負けぬほどの、上品な芳しさを漂わせていた恵子に、もう何というか参ってしまった。店を出てから歩いていると、旅館があった。健は抑えきれなくなって恵子の身体を押した。だが恵子に軽く拒まれてしまった。と思ったら、「ね、恵子のうちに、来てくださらない。」と優しく誘われた・・・。断られて、誘われたことによって、健は不思議な気持に陥った。けっして姉さんぶったりしないのに、恵子には〝年上の女〟のもつ優しい雰囲気があった。そこに健は至福を感じるようになったのである。
今、こうして遠く離れていると寂しくてしかたがない。これから先も離したくないという気持が強くなってくる。健は碗を傾けて珈琲を飲んだ。
隣の席にいた客と店主が話している。
「マスター、ウィーンに行ってたんだって、コーヒーはどうだった?」
世界のコーヒーを飲み歩いているマスターを〔キャラバン〕の亡き親父は敬愛しつつもライバル視していたことを思い出しながら、健も聞くともなく聞いていた。
「もちろんおいしかったですよ。でも、自分で淹れるのが一番かな。ははは」とマスターが笑う。
「いやいや、さすがにマスターだ、誇りをもってるね。」
「でもね、コーヒー文化はあちらが本物ですね。」
「どういうこと?」
「ウィーンに〔カフェ・ミュージアム〕という店があったんですよ。そこに、車椅子に乗った高齢の女性がいらっしゃったんです。きちっとした身なりのね。その方は毎日お見えになり、5時間ほど座っていらっしゃるというのですよ。」
「え~! 店としては勘弁してくれじゃないの?」
「そうじゃないんですよ。お店も歓迎しているのですよ、誠意をもって。で、時間になったら、施設の車が迎えに来るのです。そして、翌日も、そのまた翌日も、入所してから三年間、毎日。」
「へえ、すごいな!」
「なぜ、その方がそのお店に見えるか、分かりますか?」
「・・・・・・?」
マスターは野中の顔も見た。
野中も顔を横に振った。
「亡きご主人に60年前、そのお店でプロポーズされたからだというのです。」
「・・・・・・、絶句だな!」隣の客は、野中に了解を求めるようにして呟いた。
「店も、施設も、そしてウィーンの街中が、その方の人生を尊んでいるんだなと思いました。私も〔もか〕をそういうお店にしたいですよ。ご縁のあるお客さまの、お一人お一人の人生に寄り添ったコーヒーを・・・・・・、」
隣の男は「マスターも偉いけど、きっとその人のご主人はそれだけのことをやってあげたんだろうな。ああ、反省、反省。」そう言って、帰って行った。
(恵子・・・、) 健はまた恵子のことを想った。
健は、コーヒーをもう一杯頼んだ。
マスターは丁寧にコーヒーを淹れる。
それを眺めながら、健は思った。(少しだけだけど、新規事業の、形にならない形のようなものがボンヤリと見えてきた。も少し頑張ったら、恵子のことを真剣に考えよう。そのときは、あの1Kのアパートに連れて行って、おれの一部を見せてあげた方がいいだろう。いつまでも恵子に甘えちゃいけないナ。)
恵子は桃子の手紙が小躍りしたくなるほど嬉しかった。どうしても外国での一人暮らしにはプレッシャーが多い。その上、アメリカという国は、性別、年齢、学歴、社歴、人種、言語、宗教が自由すぎて、かえって煩わしさを感じることがある。日本のような単一性による安堵感がない。なかにはパニックに陥って、帰国しようにもそれすらできなくなってしまう日本人たちもいるという。
恵子は、エリザベスの心遣いにどんなに救われていることか、と感謝している。しかし昼間はまだいいとしても、夜になるとやはり切なくなることもある。そういうとき、親しい日本人が来てくれる。こんなに嬉しいことはない。
恵子は桃子姐さんの来訪を心待ちにしながら、今日はトーマス・ウィルソンというファッション専門のジャーナリストと会っていた。もちろん、いつものようにエリザベスも一緒である。
恵子は自分のことを「銀座で飲食店を経営していたけれど、ハズバンドがファッションのセンスがあると言ってくれたから、ファッションの勉強のためにNYへやって来た。」と言った。お腹が大きくなった今、健のことを何と言おうかと思ったが、迷わず「夫が・・・、」と言った自分に恵子は満足していた。
そんな恵子の顔をエリザベスはニコニコしながら見ていた。
ウィルソンは饒舌だった。「それはいい。ニューヨークは、パリ、ロンドン、ミラノに続く、世界のファッションのメッカみたいな所だ。勉強になるだろう。ファッションは、この四大都市が流行発信の源だ。文化を創造し、世界に向けて発信する都会こそ、世界の都市だ。東京も早くそういう都市にならなければ、世界からは認められない。」
「映画のハリウッド、歴史の京都、ファッションのミラノ、音楽のウィーン・・・、みたいな特色をもつ都市もあるわよ、トーマス。」エリザベスが付け加えた。
「もちろん、そうだが、ぼくが話しているのは、日本が認められるためには東京が文化都市になるのが早道だということだ。」
(このような話、何処かで聞いたことがある) と恵子は思った。思い出すと、たしか彼が小田社長から聞いたこととして話してくれたことだった。あの夜は、はやくベッドに入りたくて、熱心に聞いてなかったことを思い出し、恵子は一人で微笑んだ。
ウィルソンは続ける。「そういえば、最近は日本人モデルたちも世界で注目されるようになった、サヨコヤマグチ、シュウカ、トコ。ジャーナリストの目から見れば、それは東洋ブームがやってくる前兆だと思う。それに女性は、イヤ女性こそが、平和産業の旗手として相応しいと思う。男は、どうしてもギリシャ神話の昔から、ゼウス、ヘラクレス・・・、と闘う戦士だけが活躍する。そうすれば、軍事都市、軍港が増えるだろう、どうする? エリザベス。」
「ファションの話を聞くつもりだったけれど、すごいことになったわね。」
「ははは。終戦を待っていたクリスチャン・ディオールは、花のような、女らしいシルエットのファッションをデザインした。」
「そうね。」
「15世紀イタリアの画家ボッティチェリが描いた『春』は知っている?」
「『ラ・プリマヴェーラ』でしょ、フィレンツェのウフィツィ美術館で見たわ。」
「うん。あの絵にはファッションの原点がある。」
「えっ? 愛と美の女神ヴィーナスを中心に、右は春の女神プリマヴェーラと花の女神フローラ、左に三美神・・・、」とエリザベスが目を丸くしながら言う。
「そう、そのヴィーナスだよ。同じボッティチェリの『ヴィーナス誕生』の方は〝天上のヴィーナス〟とよばれている。ヴィーナスが裸体だからだ。でも、『春』のヴィーナスは〝世俗のヴィーナス〟といわれている。着衣のヴィーナスだからだ。これがファションの原点だよ。春のような衣装を纏わせた。ディオールの出発にもそれがある。」
恵子も思い出した。「そういわれれば、ディオールは、『世界の動乱が大嫌い』って言ってたのを何かの雑誌で見たことがあるわ。」
「そう。イヴ・サンローランも兵役のときに精神を病んだ。軍需産業と平和産業が相容れぬ証拠だ。女性は平和の象徴だ。その平和産業は、ファッションばかりではない。デザイン、音楽、食、映画・・・、たくさんの舞台で女性は主役を踊れる。そしてニューヨーク、パリ、ロンドン、ローマ、東京といった世界的平和産業都市が増えれば、地球には平和がやってくる。ケイコのハズバンドは正しいことを言ってくれた。そうだろう。」
健のことがこのような形で評価されるとは思いもしなかったから、恵子は自分のことのように嬉しくなって、にっこり笑った。
恵子は、その夜もウィルソンと会ったことを健に手紙で報告した。(こうしてあの人に手紙を書けば、いつもあの人と一緒にいられる。) 恵子はそう思った。
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕