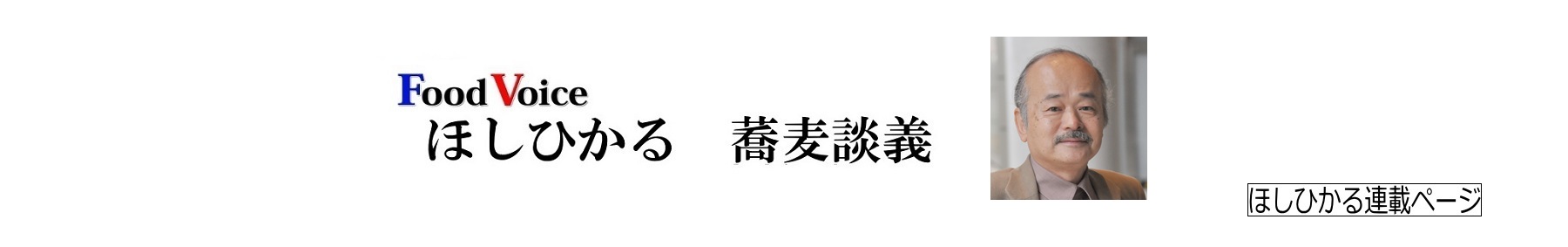第347話 小説「コーヒー・ブルース- XVIII」
2025/12/06
~ Sarai Qui ♪ ~
健は桃子が指定した神楽坂の喫茶店に向かったが、足が重かった。何でもない土産話なら「お店に顔を出したら」ぐらいの誘いだろうけど、「喫茶店に来い」と言う。恵子に何かあったのだろうか? 健は約束の時間より早めに着いた。なのに、店内を見るともう桃子の顔があった。健はますます不安になった。
「あ、野中さん、」桃子は健を見つけて、手を挙げた。
近寄ると、「ほんとうにお久しぶりね。」桃子が立って挨拶をした。
健も、「ごぶさたしています」と頭を下げてから、席に座った。
店員が直ぐ来たので、「珈琲」と言ってから、健は桃子を見つめながら「恵子と会って来たそうで、」と切り出した。
「そうなの。」
「どうしてました? 元気でした?」
「大丈夫よ。元気よ。」
健は少しほっとした。
「野中さんは?」
「僕は相変わらずです。」
「恵子さんのマンションには?」
「ええ、時々行くようにしています。」
「それはよかったわ。」
健は、桃子さんの「よかったわ。」の返事に少し安堵した。しかし、桃子の顔を見ると、何か大事な話を隠しているような感じがする。健は営業出身だから、そういうことが分かる。
そこへ桃子が言った。「これから話すことは、あたしの独断で野中さんに言ってしまうことなの。恵子さんは知らないことよ。」
「・・・?」
「でね・・・、」
「・・・・・・、」
「恵子さんのお腹の中には野中さんの赤ちゃんがいるのよ。」
「!!!」健は思わず立ち上がってしまった。
「大丈夫よ」桃子はそう言ったが、何が大丈夫なのか、意味がよく分からない。でも、健はその言葉でまた席に座りなおし、コップの中のお冷を飲み干した。
「恵子さんはね。野中さんに迷惑をかけまいと思って、貴方との思い出のニューヨークで一人で産むつもりなの。分かってあげて、」
桃子も水を飲んだ。桃子は今日の台詞を夫を相手に練習して臨んでいた。
恵子に「任せて」と言ったものの、話が失敗に終われば、恵子と野中さんの人生を狂わせることになる。思い出せば、若いころはよく喧嘩をしていたが、今回のような平和な話し合いはあまり経験がない。責任重大だった。
それを夫に言うと、「野中さんはまだ若い。不安がらせちゃいけないナ。赤ちゃんが野中さんの児だということを分かってもらうことが先だ」と言った。
(そうか。) 喧嘩をするときは、相手の弱味を見つけて、そこを攻めて優位に立った。しかし平和交渉は一瞬でも不安を与えてはならない・・・。「恵子さんのお腹の中には赤ちゃんがいるのよ。」より、「恵子さんのお腹の中には野中さんの赤ちゃんがいるのよ。」がいい。桃子はコツがつかめたような気がした。
「そうだったんですか。」やっと健は返事をしたが、嬉しいのか? 困ったのか? あまりにも唐突な話だったので、自分でも分からない。
「おめでとうございます。よかったわね。」桃子がニコニコしながら頭を下げた。
「あ、ありがとうございます。」健も、つられて頭を下げた。
「まだ、実感がわかないでしょう。当然よね、うちの亭主もそうだったわ。」
「恵子は・・・・・・?」
「もちろん大喜びよ、女にとって大好きな人の子供が産めることは一番幸せなことよ。」
「大好き」という言葉に、健は照れながら「予定はいつなんでしょうか?」と訊いた。
「あと三カ月よ。あの銀座一の美人が横綱よ。ふふふ。」
健もつられて笑ったが、まったく想像がつかない。
桃子は野中が少し平常心に戻ったように感じたので、ひとまず胸をなでおろした。ただ、「これからどうする」ということを健はまだ口にしない。
二人とも珈琲はまだ残っている。
桃子は、赤ちゃんが野中さんの児ということを分かってもらえて、認めてもらえることが、私の役目だ。それ以上の性急は禁物だろうと思って、とりあえず野中と別れることにした。
「今度、お店にいらっしゃい。恵子さんはあたしの妹も同然なの。だから野中さんは弟よ。」
「はい。」と言いながらも、健はまだ混乱していた。社長には「子会社にしろ」と煽られ、桃子姐さんには「貴方には子供がいる」と言われた。何という日だと思った。(しかし、「一人で」とは、よく決心したものだ。恵子の方が大人だな。)と感心もした。
翌日は、本社の経営会議だった。新規事業の各子会社、各部、各プロジェクトチームも、営業成績や進捗状況を報告しなければならない。
野中は、システム・テストの現時点での状況と、発売時期について報告した。商品名としては〔レオネス・ケア・システム〕を予定していることも話した。
すると、牧田常務が口を開いた。「ケアっていうのは何だ? 今まで聞いたことがないぞ。」常務はみんなを見回しながら言ったので、皆は「そうだ」と首を縦に振っている。
「世話とか、看護とかいう意味です。」
「みんな知ってるか?」皆も「知らない」と返事をする。オーナーの小田社長は建前や手続的なことが大嫌いだから、会議にはめったに顔を出さない。だから、経営会議は牧田常務の独断場になっていた。
「わが社は医療で飯を食っている。なぜ、メディカル・システムじゃいけないのかね?」
野中が答えようとしたとき、総務部長が追い打ちをかけてきた。「野中君、常務がおっしゃる通りだよ。わが社の基本理念に関わることだ。それを君は分かっていない。ケアなんて訳が分からない言葉を持ち出すことは、どうかな。もう一度考え直したまえ。」
野中は会議室から出るとき、危うくドアを蹴飛ばすところだった。(分かってないのは、あ奴らだ!)
失敗だった。社長に言えば「根回しをやらなかった野中が甘い」と言われるにきまっている。野中は、自分自身に腹が立った。面白くない。外廻りでもするかとばかりに、電車に乗って、小川医師と遠藤医師の所へ行った。
システムの感想を聞くと、二人とも「面倒だけど、面白い。もっと使い道を考えてみる」といい反応である。
健はまた電車に乗った。車内では、今までは気にもとまらなかったのに、赤ん坊を抱いた若い夫婦が目に入った。夫婦は何か話している。妻は夫に信頼し切った眼差しを送っている。(あれが、夫婦なのか!) 健は、胸が締め付けられた。 (半年間、恵子は一人で我慢していたのだ!) そう思うと、居ても立ってもいられない。これまでの社長との会話の中で、「やっています」と答えると、「結果が出てないのは、本気になってない証拠だ。逃げているのだ。」と言われることがよくあった。(おれに真剣さが足りなかった。だから恵子は一人で苦しんでいたのだろう。恵子に会いたい。会って、謝らなければ、) 健は唇を噛み締めていた。
野中は今日の経営会議のことで、腹を決めた。(本社から離れよう。子会社にしよう。そして、恵子に結婚を申し込もう。)
夕方、マンションに戻ってから、健は桃子に電話をした。
「昨日はありがとうございました。近いうちに恵子を迎えに行きます。」
「ほんと! よかったわ。ね、行く前にお店にいらっしゃいよ。祝杯を上げなきゃ。」そう言うと、桃子は嬉しさの笑顔から涙を零した。そして夫に向って「あんた、野中さんがニューヨークへ行くって、」と涙顔で伝えた。
「よかったな。」亭主は冷蔵庫からビールを取り出し、栓を思いっ切り開けた。そしてカウンターに座っていた三人の客に「お客さん。あいつの妹分の結婚が決まったんで、わたしの奢りです」と言いながら、コップのビールを注いだ。
健は、NYが夜の時間になるころを見計らって、恵子に電話を入れた。
恵子の手は緊張していた。
「恵子。桃子さんから、話を聞いた。一人にしてしまって済まなかった。」
「ううん。恵子こそ・・・、貴方に言わないで・・・、」
「身体はどう?」
「母子ともに順調です。♪」と言うしか、言葉が見つからない。
健には「母子」という言葉がまだピンとこない。「会社の休みをとって、そっちへ行くから・・・、」
恵子は緊張が抜けてほっとした。「ありがとう。でも、お仕事は大丈夫?」
「大丈夫。それより会いたいから、行くよ。それから・・・、おれと結婚してほしい、」健は一気に言ってしまった。
「・・・、」堪え切れずに、恵子は電話を持ったまま、座り込んだ。涙が溢れ出してきた。
「どう・・・?」
「うん。恵子からもお願いしたいくらい。」
「よかった。ありがとう。」
恵子は声を出して泣き始めた。「ううう・・・。」(もう一人じゃない。) そう思うと喜びと安堵と、そして何よりも健への信頼感がわき上がってきた。
「恵子、すまなかった。ほんとうに済まなかった。」
「ううん。大丈夫。今の恵子にはあなたが百人力よ。」
(さて、10日間ぐらい会社を休まなければならない。どう切り出そうか。) かつて牧田常務は、「おれはお得意様の接待を約束していたから、親の葬式も出なかった」と自慢気に話したことがある。だから会社にはまだそんな雰囲気がある。
しかし、小田社長が言ったことがある。「右か、左か、そのどちらかを選ぶのではなく、一番、二番と優先順位で決めるのだ」と。そうだとすれば、牧田常務の考え方は間違っているじゃないか。おれは恵子も、会社も選ぶ。その優先順位からいえば、今は恵子は取るべきだ。恵子を守ることが、【Better Living As Human】を自分のものにすることなのだ。そう考えれば、社長からの宿題も果たすことができる。小田社長に休暇願いも出せる。
しかしそうした場合、あの方には嘘は通用しない。それと、仕事のこともキチンとしていなければならない。そうしないと、藪蛇になる。野中は先ず、古賀に話した。
古賀は驚きと笑顔を向けながら、「もちろん協力しますよ」と言ってくれた。テストは一ケ月ぐらいかかるけど、できれはもう一軒テスト先を作ってほしいと言った。「よし、木下病院の院長に頼もう。あの院長にユースウェアを相談するんだ。古賀、それを含めてやってくれるか。」
「分かりました。」
そうした上で、社長に会おうと思った。ただし、社長と交渉するときは堂々としていないと、嫌われる。野中は少し胸を張って、古賀と共に社長室の戸を叩いた。
「社長、公私共に報告と相談があります。」
「何だ。」
システム・テストの方は、古賀と一緒になって報告した。要は、10日ほど野中がいなくても仕事は進むということの説明であった。
話が終わってから、古賀が下がると、野中が「実は、アメリカにファションの勉強に行っている彼女がいるのですが、」と前置きをして、妊娠したまま行って、もうすぐ生まれそうなこと、会社を休ませてほしいことを頼んだ。
すると社長は「行ってこい。製造物責任は取らなきゃナ」と言った。
「セ、製造物責任!」野中は面食らったが、社長は「そうじゃないか。ははは」と高笑いをする。
「はあ。」
「その代わり、アメリカの医療機関を見て来い。どうせ病院に行くんだろう。いいか、お前の事業関係ばかりじゃないぞ。全部見てくるのだ。」
「はい。ありがとうございます。」
恵子は朝から、落ち着かなかった。部屋の掃除をした。シャワーを浴びて、下着を取り換えた。洋服は2度も着替えた。1度は和服を着てみたが、やはりお腹の膨らみで様にならないから、また洋服にした。鏡の前に行って、髪をブラッシングし、口紅の色を変えたりした。
健のためのパジャマと下着を買い揃えた。お酒を用意し、コーヒーを淹れ、フルーツを買ってきた。
(あの人と会える。半年ぶりに。) 健が恵子のアパートメントに着くのは夜遅くなってから。しかし恵子は朝早くから待っていた。
「空港まで迎えに行きます」と言ったが、「夜は危ないから、一人で行く」と言ってくれた。
時計を見るとまだ夕方。
でも、あの人が乗った飛行機は、もうアメリカ大陸の上空を飛んでいると思った。恵子は何度も窓際に行って、空を見上げた。
それから恵子はレコードを取り出し、回した。
サラ・ボーンの「My One and Only Love ♪」だった。
銀座で健と偶然に会ってお茶を飲んだとき、〔らんぶる〕の店内にはペギー・リーの「ブラック・コーヒー」が流れていた。恵子は最初に会ったときから真面目そうな健に好感をもっていた。それが、あるとき健に無償に会いたくなった。〔らんぶる〕に行けば会える。恵子はそう思った。直感は当たっていた。健がいた。恵子は、この邂逅は神様の采配だと思った。ところが健は「もう会うことはないだろう」と言った。すかさず恵子は健を昼食に誘った。恵子は本気だった。だからなのだろうか、神の采配がまた起こった。亡き母のことを思い出し、恵子は健の腕の中で泣き崩れてしまった。そのあと神様が現れた。その神は言った。「どんな死でも神は許してくれます。」母や明子ママなど近しい者の死に罪の意識をもっていた恵子は、この言葉で救われた。そして思った。この人と一緒なら幸せになれるかもしれない。数日後、吉祥寺へデートした夜に二人は結ばれた。その日は桜咲く満月の夜だった。
それからの恵子は健に対し、少女時代に戻ったように素直になった。
ある日のこと、〔クラブ恵子〕の女の子たちがお客が来る前に雑談をしていた。「オトコに素直になる幸せってあるよね~。」女の子たちははしゃぎながら話していた。
ママの恵子は話には加わっていなかったが、「今の恵子がそうよ」と胸の中で応えていた。
それから、二人はNYで遊んだ。ハネムーンのように楽しく、幸せだった。二人は愛し合った。その結果、恵子は健の児を身籠った。奇しくも、その夜も満月だった。
恵子は待っていた。夜になった。電話が鳴った。空港からだった。健が無事に着いた。恵子はほっとした。それからまた待った。午前零時を過ぎた。
健が恵子の部屋のドアを開けた。
「あなた!」恵子は健に飛びついた。
「恵子。」健は恵子の身体を抱きしめ、頬摺りしてから、「そんなに動いて大丈夫か?」と言った。
そして離れてから、お腹をしげしげと見ながら「やっと会えた。恵子にも、おれの児にも。」そう言って、健は恵子のお腹を擦った。
(ああ、この人は今の恵子を受け入れてくれた。) そんな気がして、恵子はやっと安心した。そして「時々、お腹を蹴るのよ、この児は。」と恥ずかしそうに微笑んだ。
「そうかあ。」健はそう言って、もう一度恵子を抱いた。
「疲れたでしょう、バスに入りますか?」
「うん。一緒に入ろうか?」
「でも今日は、恥ずかしいわ。」
「そうか。」
「パジャマと、下着は用意しています。」
健は、バスルームに行った。
恵子はまたレコードを回した。
すると、健は5分も経たないうちに出てきた。
「えっ、もう。」
「そう、やっと会えたんだもんな。」
「ンもう。」
レコードから、透き通るようなヴァイオリンとトランペットの音が流れてきた。綺麗な曲だったが、甘く切ない旋律の中に激しさをも秘していた。それでいて二人の奏者は見事に呼吸が合っていた。
「いい曲だ。踊ろうか。」健は、デュオを選んでくれた恵子の気持が、嬉しかった。
恵子は肯いた。
二人は抱き合い、曲に合わせてゆっくりと身体を動かし始めた。
恵子は健の身体に触れてみて、前より男らしくなったような気がした。
「会いたかった!」そう言うと、健はいきなり激しく唇を求めてきた。
恵子は、【恵子ママ ありがとう】デーの最後の日に皆の前で健と長いキッスをしたときのことが蘇ってきた。健から届けられた365本の真っ赤な薔薇。カードには【Lovin’you】とあった。恵子は健のパジャマをしっかりつかんだ。瞼からどっと涙が溢れてきた。
その涙を健は口で吸い取ってくれた。
恵子は、日本を離れるとき、遺書まで書いたことも思い出した。その上になぜか病院でちらりと見かけた健の昔の恋人らしき女性のことまで思い出したりした。
恵子はちょっと拗ねたくなった。そしてその思いを持て余し、思わず健の唇を噛んでしまった。
健は動じなかった。唇から血が流れてきた。「一人にして、悪かった。」健が囁いた。
恵子は健の身体にすがりながら、血を飲み込んだ。そして顔を健の身体に預け、甘えたような声で「許して上げる」と言った。
恵子が甘えるとき、必ず甘い吐息が発散される。
それに健は弱かった。健は自分の額を恵子の額にくっつけて、恵子の鼻を軽くかじった。
「ふふふ。いやん。」身体をくねらせながらも恵子は嬉しかった。(半年も離れ離れになっていたというのに、僅かの時間で元に戻ることができた。ほんとうによかった♪) そう思うと安堵の涙が流れてくる。
このとき、健が言った。「結婚、いいだろう!」
恵子は何度も何度も肯いた。
健が「寝室は、何処?」と囁いた。
「向こうよ。でも、血は止まった?」
「大丈夫だよ。」
「ほんと?」
「それより、抱っこして連れて行ってやろう。」健は恵子の身体を抱き上げた。
「いやん。二人分だから、重いわよ。」
「そうか。二人分か、」健は、二人分という言葉に感慨深げな表情をした。
恵子は嬉しかった。「バスに入ろう」「踊ろう」「抱っこしてやろう」という健の優しい態度に、愛する人と二人でいる幸せを感じていた。
翌日の午前中、二人は恵子が通院しているGYN病院へ行った。病院はセントラル駅の近くだった。その病院は高級ホテルのようなVIPばかりの産科病院だった。(日本にはこんな病院はめったにない。) 健は驚いた。
玄関には、【A Patient's Bill of Rights】と記した大きな額が掲示してあった。それを見た健は、雷に打たれたような衝撃を受けた。
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕