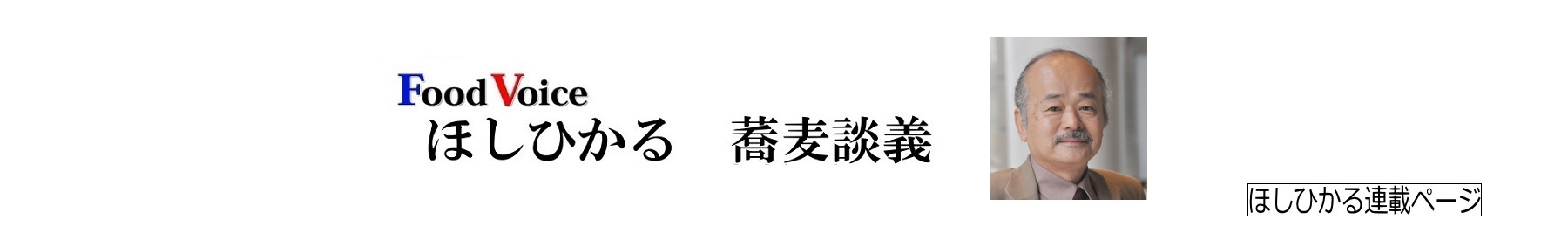第96話 都鄙の研究Ⅰ
2025/12/06
☆安房高家神社 料理の祖神
ここは安房の千倉町、太平洋の波の音が聞こえる小高い丘、鎮座するのは古式ゆたかな高家神社。祭神は料理祖神の磐鹿六雁命である。
記紀神話では、景行天皇(和風諡号:オオタラシヒコオシロワケ)が東国巡行で安房の水門に渡ったとき、イワカムツカリという土地の者が蛤の膾を奉ったと伝えている。
景行天皇は英雄ヤマトタケルの父であるが、この父子の実在は疑問視されている。もし実在したとすれば4世紀ごろだろうか。
そういえば、わが故郷「佐賀」の名も、ヤマトタケルの呟きに由来するらしい。『魏志倭人伝』にも記載してあるように、佐賀は古代から楠の巨木が林立していた。その楠が朝日、夕日を受けると影は15km先の西に東に達していた。それを見たタケルは「この国を栄の国と謂うべし」と言ったと『肥前国風土記』にある。その「サカエの国」から「佐嘉 → 佐賀」となったのである。
『風土記』を編集したのは藤原不比等の息子宇合であるが、宇合はスケールの大きな話が好きだったのだろうかと思ったりする。
 【肥前国風土記☆ほしひかる絵】
【肥前国風土記☆ほしひかる絵】
ところがである。この神話に注目した古代史学者の横尾文子氏は朝日、夕日で伸びる楠の影東西30kmは現代の国会議員の選挙区とほぼ一致しているとみた。つまりこれが佐賀の生活圏=当時の国の範囲を示していると解読したのである。そんな横尾説に、また「成程」と感心することしきりである。
故郷の話だと、ついつい横道に逸れる悪い癖のある私であるが、要するに「伝承の裏に潜んでいる真実を探ろう」と言いたかったのである。
それもこれもふくめて、一般的にはオオタラシヒコオシロワケとヤマトタケルの父子を記紀に登場させて言わんとしているところは、ヤマトタケルの西征東征の物語を創出しつつ、大和朝廷が北の蝦夷を除いた日本(西国・東国)を統一したのがこの時期であるということである。
だとすれば、「安房の何某が○○を奉った」ということは安房が大和朝廷の軍門に下ったということを指している。その結果、大和へ連行されたイワカムツカリには、膳氏という姓が与えられ、代々宮廷料理部の管理部長になるのである。この膳氏の子孫が天武朝廷の料理を一手に仕切るようになったとき、高橋(奈良市?or天理市?)という所に住んでいたことから新たに高橋氏の姓を賜り、また先祖のイワカムツカリは料理の祖神として祀られることになるのである。
ところで、この安房のイワカムツカリ伝説の意味するところは何だろうか? それをもう一度考えてみたい。
先ず、安房の何某が大和朝廷の料理部長に任じられたという事実である。
その前に、当地には大昔から外房を発祥とする漁師料理「沖膾」というものがあることを知っておかなければならない。
漁師が沖へ出たとき、揺れる船の上で捕れ立ての魚介を粗造りする。頭と尾を切り落として腸を取り除き、鱗は引いて皮は付けたまま、それを塩味か味噌味で食べるものである。それを表すものが神話の「膾」である。
3世紀の九州ヤマタイ国では、夏冬かかわらず高坏に盛った生野菜などを手で食べるという食習慣であった。だが、4世紀の大和朝廷では、安房の何某を宮廷の料理部長に任じようとまでしている。つまり、食文化レベルの違いから見て、九州と近畿では異なる部族であった可能性が感じられる。
そのことはさて措き、魚介を〝切って〟作る安房の料理法を朝廷の正式の料理法として採用するということは、料理においても国としての統一を図ろうとするようなものである。そこで創られていったことは、世界中で見られる〝煮る〟〝焼く〟〝揚げる〟という料理法だけではなく、そこに〝見事に切る〟という安房の料理法が中心に加わったことである。
次に、大和の都へ連行された地方の人材という点に注視したい。朝廷にスカウトされた彼は大和の都人の厳しいニーズに応えるために、必死になって努めたであろう。大和の都は人材を吸収し、育てたのである。その結果、自分のクニでは彼が作った物は単なる喰い物でしかなかったのに、ここでは旨い物は旨い、美しい物は美しいと賞讃された。だから彼らは料理人としてさらに腕を磨いた。その結果、文化の花が咲くのである。
そうして、こうした過程における苦労談、物語、伝説にこそ、実は中央(都)と地方(鄙)、そして両者を結ぶ官僚という構図確立の片鱗が読みとれるのである。これがただ敵を討ち滅ぼすというのではなく、創像的な全国統一の手法ではないだろうか。イワカムツカリ伝説とはそういうことだったのである。
☆「見返り美人」に見るファションの系譜
繰り返し波打つ海辺に菱川師宣記念館(千葉県鋸南町保田)が建っている。絵が好きな私である。「せっかく房総までやって来たから」と、ここ保田で途中下車をした。
浮世絵師菱川師宣は、今からおよそ350年の昔に、ここ保田 ― 母の郷であったらしい ― の金箔刺繍を営んでいる家に生まれた。
日本の刺繍の歴史というのはかなり古く、飛鳥時代には始まっていた。奈良の中宮寺に伝わる「天寿国曼荼羅繍帳」は有名だ。聞くところによると、当時の日本の刺繍には、京風、江戸風があったという。それ以上の詳しいことは知らないが、師宣の父も場所がら江戸風の刺繍を手掛けていたのであろう。だが、それにしても生臭い漁村で、洒落た金箔刺繍をやっていたというのがよくわからない。
しかし、小説風に想像すれば、この矛盾が師宣にとってバネになったのだろう。師宣は魚臭い漁村を捨てて洒落た金箔刺繍が相応しい江戸の都に出た、というストーリーが描かれてくる。歳はすでに40ちかく、明暦の大火(1657年)の後のことだったらしい。
目前に広がる海の右手向こうがすぐ東京である。鼻にまとわりついてくる潮の匂いを嗅いでいると、船に乗って海を渡って江戸へ行った師宣の姿が浮かんでくるようだ。
江戸での師宣は狩野派、土佐派、長谷川派の絵師たちの技法を学んだ後、師宣らしさを確立し、それまで単なる挿絵でしかなかった浮世絵を独立した絵画にした。師宣は都で花を咲かせたのである。それ故に菱川師宣は「浮世絵の祖」と称される。
その師宣の代表作といえば「見返り美人」(17世紀)である。
モデルの女性は、17世紀末期当時の流行であった女帯の結び方「吉弥結び」と、紅色の地に菊と桜の刺繍を施した着物を身に着けている。それらを美しく見せる演出法として師宣は、歩みの途中で首を右に向けて後方を見る姿を描いた。すると、観る者に後姿を見せることになる。
話は脇道に逸れるが、この絵から連想するのは、フェルメールの「真珠の耳飾りの少女」である。フェルメールは真珠の耳飾りを強調するために、少女を肩越しにやや左へ振り返らせている。
師宣が「見返り美人」を描いた年は不明だが、フェルメールが「真珠の耳飾りの少女」を描いたのは1665年頃。しかも菱川師宣(1618?1630?~1694)とヨハネス・フェルメール(1632~1675)はほぼ同年齢というところが面白い。
地球の東西で同時期に二人の天才画家が、「振り返り」という全く同じ発想をして「美人」を描いている。ただ、師宣が「後帯」、フェルメールが「耳飾り」を描こうとしたため、振り返る角度が違っていた。
この話は一旦措くとして、女帯のことをも少し見てみよう。
それまでの和服の帯は幅17cm程度の細い物で、紐が使われることもあった。女帯も規格品であり結び方も一種類しかなかったという。ところが平和な時代になると華美を競うようにして女帯の長大化が進んでいった。そのきっかけとなったのが、延宝年間(1673-81)の女形、初代上村吉弥であった。吉弥は大幅の帯に重りを縫い付け、結び目の両端をダラリと垂らした新型の帯結びを考案し、後の広幅帯の流行の端緒を開いた。こうした帯の長大化に伴って帯を後結びにする風習が若い娘から堅気の女性一般にまで広まり、日本の服飾史にとっては大きな転回点となったことはいうまでもない。
縫箔師の家に生まれた師宣は、今風にいえば着物ファッションを絵にして、それまで挿絵でしかなかった浮世絵を独立した世界に仕立てたのである。
見方を変えれば、師宣は「見返り美人」を描くために江戸に出てきたといってもいい。
そして、日本の美術界は「見返り美人」によって女性の「後姿」に光が当てられたのである。
さて、人間にとっての基本的な生活条件とは「衣食住」の完備であることはいうまでもない。そして文化とは、その「衣食住」をより高度なものにしようとする活動である。
今日、私が安房の千倉と保田で見たことは、そのうちの「衣食」の文化事業は文化の花咲く都でしかできない仕事であったということではないだろうか。
参考:ほしひかる「蕎麦談義」 (第11、31、43、72、73、74話)、ほしひかる『天平龍虎伝』(コスモス文学)、『古事記』、『日本書紀』、『魏志倭人伝』、志の島忠・浪川寛治『にほん料理名ものしり辞典』(PHP文庫)、菱川師宣記念館(千葉県鋸南町保田)、フェルメール画「真珠の耳飾りの少女」、トレイシー・シュヴァリエ著『真珠の耳飾りの少女』(白水社)、ピーター・ウェーバー監督『真珠の耳飾りの少女』、横尾文子『新・肥前風土記』(NHKブックス)、
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕