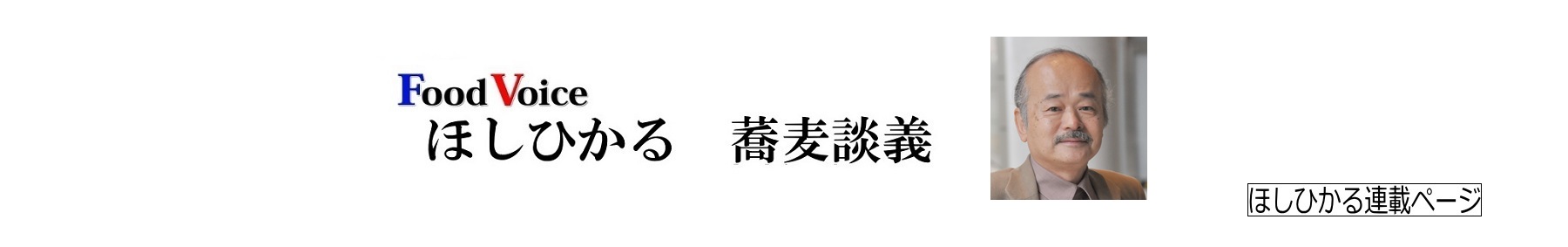第154話 八百善の七月「朝茶の献立」
《 蕎麦膳 》三
☆深大寺茶室
緑の風がそよと吹いてきた。遠くで鳩笛の音がする♪ ここは深大寺の裏庭に佇つ茶室である。
前以てもらっていた今日の献立を見ると、流れるような字で「朝茶の献立」が書かれてあった。
汁 六郷蜆、田舎味噌、粉山椒、
向附 姫百合、梅肉あえ、
椀盛 深大寺蕎麦、もみ海苔、さらし葱、
焼物 かしわ水煮、
強肴 茄子皮付煮立
八寸 小鮎風干、隠元黒胡麻あえ、青唐辛子塩煎り、
香の物 白瓜印籠漬、新生姜一夜漬
菓子 葛素麺
「何と粋な献立であろうか」。私はそう思った。それは江戸近郊の食材のみを使った料理からくる、姿勢からくるものであろう。
深大寺蕎麦はむろんのこと、多摩川下流の六郷川口の蜆といい、おそらく卵、茄子、白瓜、人参、生姜、葛などもいわゆる江戸野菜だろう。たとえば、茄子なら駒込か、雑司ヶ谷か、寺島。瓜は鳴子か、本田か、大越。人参は滝野川か、馬込。生姜は谷中、と。
そう思いながら、室内を見回すと、大田南畝がいる。亀田鵬斎、葛飾北斎、酒井抱一、谷文晁もいる。栗山善四郎の顔もある!
ト、ここまで書けばこの場面が嘘、いや夢想であることがおわかりであろう。
☆八百善
日本の外食産業は、茶粥の「奈良茶」、蕎麦の「けんどん屋」など簡単な食事を提供する店の登場から始まり、段々に高級料理店が営業されるようになったことは、これまで度々述べてきた。
そうした高級料亭の最初は何という店だったのかということは明らかではないが、享保年間(1716-35)に顔を出した「八百善」も早い時期の料亭の一つであったことはまちがいない。とくに4代目の栗山善四郎は、大田南畝、亀田鵬斎、葛飾北斎、酒井抱一、谷文晁ら文化人と交流し、『江戸流行料理通』を刊行したことでよく知られている。また、6代目善四郎は、ペリー来航の際の響応料理を料亭「百川」とともに担当したことも日本食文化史上、忘れてはならないことである。
そんなことから、「八百善」関係の書を捲っていたら、毎月の献立を記載してある頁が目に入った。
すなわち、正月の献立、二月の献立、三月の献立、四月花見茶の献立、晩春の献立(5月)、初風炉の献立(6月)、朝茶の献立(7月)、八月の献立、月見の献立(9月)、名残茶の献立(10月)、口切茶の献立(11月)、歳暮の献立(12月)、である。
そのうちの、7月の「朝茶の献立」には椀盛として《深大寺蕎麦》が加えられているので、ご紹介したいと思って、冒頭のフィクションから入ってみた。
☆八百善「朝茶の献立」
もう一度、献立をじっくり見てみよう。
・汁=六郷川口の蜆を前夜より水に浸けておいて田舎味噌で仕立て、椀に盛ってから粉山椒を添える。
・向附=姫百合は百合根を三、四分水煮して、あとで薄い砂糖味して、美濃紙を上からかけて煮上げる。それに梅肉は梅干の塩を抜いて砂糖で甘味をつけて、これを姫百合にあえる。
・椀盛=深大寺蕎麦を自然薯と玉子でつないで手打ちにし、もみ海苔とさらし葱を薬味にする。
・焼物=田舎近傍の若鶏を水煮にして汁張りにして使う。
・強肴=茄子を皮付のまま煮立る。
江戸野菜研究家の大竹道茂先生によると、昔の茄子は皮が硬いから必ず皮を剥いて料理したが、この「強肴」という料理だけは、皮付のまま煮たという。
・八寸=小鮎を三枚におろして塩水にちょっと入れて串に刺して風干にする。隠元をちょっと茹でて黒胡麻あえにする。京都の青唐辛子をフライパンで油で煎り上げ塩をふる。
・香の物=白瓜印籠漬。印籠漬とは、白瓜や胡瓜の両端を切って種を掻き出し、しそ、唐辛子、にんじんなどを詰めて、塩漬けまたは味噌漬けしたもの。 新生姜一夜漬
・菓子=葛素麺
これを見ていると考えさせられることがある。
もちろん江戸時代であるから、江戸圏内だけでの生産と消費の世界は普通であり、小規模生産は至極当然のことである。
だが今、あらためてこの献立表を手にしてみると、地球の裏側からまで食材を運ぼうとする現代人の、便利さや豊かさを手放せなくなった欲望の姿も同時に見えてくるではないか。
参考:四代目善四郎『江戸流行料理通』、九代目善四郎『八百善料理通「江戸のおそうざい」』(中央公論社)、九代目善四郎の妻栗山恵津子『食前方丈 八百善ものがたり』(講談社)、江守奈比古『八百善物語』(新文明社)、宮尾登美子『菊亭八百善の人びと』(新潮文庫)、
《 蕎麦膳 》シリーズ(第154、153、150話、)
〔江戸ソバリエ認定委員長、 伝統江戸蕎麦料理編集委員 ☆ ほしひかる〕