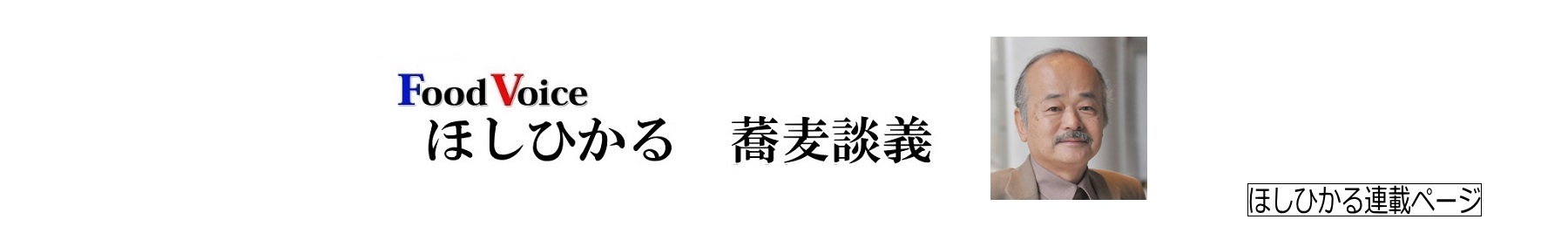第150話 なべ家の五月「昔の料理ぶらり散歩」
2025/12/06
《 蕎麦膳 》一
NHKの人気番組「ブラタモリ」で再現した江戸料理をコースとして楽しむ「遊食会」を企画したから来ないか、と「なべ家」のご主人福田浩先生に誘われた。
伺うと、その日は一階も二階も、粋な江戸料理を味わいたいというお客さんでいっぱいだった。
季節は五月末、初夏はすぐそこ。部屋の戸は空け放たれていた。塀の前に小さな石灯籠が見えていた。
卓上には御品書が置いてある。題して「昔の料理ぶらり散歩」。
座付 玉子焼 初鰹
汁 五月汁
刺身 掻き鯛
焼物 川鱒
猪口 なまり 青柳 わけぎ
煮物 筍羹 蕎麦麩
飯 胡椒飯
香物 大根味噌漬
甘味 人寄せ
先ずは、「玉子焼」と「初鰹」が迎えてくれる。二品ともどこか骨太い。
玉子焼は全国で見られるけど、江戸の厚焼玉子はちょっと焦げ目があって、甘い。でも、こんな風になったのは江戸末期か、明治になってのことらしい。出汁巻き玉子は温かいうちが華、厚焼玉子は冷めた方が味が馴染んでくる。
そして、初鰹。江戸っ子と五月の初鰹については多くを語る必要はないだろう。私はもともと九州の出身だから白身の魚を好むが、鰹は食べる。ただし、九州人は脂がのらない〝若い〟鰹を美味しいと言い、関東人は脂がのった鰹が旨いと言う。さらに大通は〝熟女〟のような戻鰹を絶品だと叫ぶ。いずれにしろ、鰹節の旨味が、鮮魚のときから感じられるからか、日本人は鰹が好きである。
そんなわけで、座付は江戸料理の通過門のような二品だ。
「五月汁」のお椀がきれいだ。まるで大名屋敷の膳のようである。福田先生は「料理再現の手始めは器探しから。先ずは骨董屋へ通え」と言われる。一方では新たな蕎麦料理を提供する「ほそ川」の主人はよく陶器漆器の新進作家展に行くという。魯山人も「器は料理の着物」と言った。要は、丸ごと「自分の世界を創れ」ということだろう。
そう思いながら、椀の蓋を取る。味噌汁だ。江戸の料理は味噌汁とご飯の後に酒が出た。その方が身体にいい。だから今日も初めに汁である。現在のような酒が主流というのは維新後からである。食文化がなかった土佐や薩摩の下級武士たちが無知なるがゆえに江戸の食文化を破壊してしまったことは、児玉定子さんらの研究によって指摘されている。というような、粋ではない話は抜きにして、汁の底を見れば鉄皮が沈んでいる。五月汁には季節の野菜と、必ず鉄皮が入っている。河豚の旬のころに皮を干しておき、使う前に水で戻して汁の具にする。河豚は俗に「鉄砲」と呼ぶ。「当たったら死ぬぜ」という危険なシャレからだ。そういえば、「なべ家」さんはふぐ料理が看板のひとつだ。
「掻き鯛」― これも今日の目玉のひとつだろう。ある統計によると、私の故郷佐賀は全国で一番鯛を食べる県だという。そのせいか私も寿司屋では鯛は欠かしたことがない。むろん刺身や煮付も大好きだ。春は真鯛、金目鯛(実は鯛ではないらしいが)。夏は石鯛、石垣鯛、黒鯛、いぼ鯛(これも鯛ではないらしいが)。秋は甘鯛、と。先日、寿司屋さんで鯛に似た魚がいた。訊くと「おじさん」という変な名のスズキ科の白身だったが、頂いた。
「掻き」は今では刺身のひとつだが、元はといえば刺身の前身だろう。庖丁の先で身をこそげとる掻きや、細かく切られている和え物などは、醤油より煎り酒や久年母などがよく合う。逆にいえば、醤油普及以前の刺身が掻きや和え物、醤油普及後は刺身ということになる。それは醤油による麺つゆの時代と、それ以前の垂れ味噌による汁の時代の関係とよく似ているのである。
掻き鯛には白い燕巣と黒い岩茸も添えてある。和食で燕巣を頂くのは初めてだ。これも煎り酒で食する。
「皐月鱒」― 5月頃に遡上することからその名があるが、木曾川の鱒も今日の目玉だ。なにせ「なべ家」さんは、5月が川鱒、6月は鮎が看板だ。どれも香がいい。鱒も、鮎も、そしてどこか似ている山女魚も、岩魚も日本人は好きだ。
箸を置いて壁に目をやると、妙な軸が飾ってある。女将さんに尋ねると、チャールス・ロイドというアメリカのジャズ奏者が見えたとき、色紙に描いてくれたのを誰かが軸にしてくれたので、飾ってみたとのこと。それには「Truth is One」と筆で書いてあり、そのとき食べた鱒の絵が描いてあったが、何か妙である。鰭が足のようになっているから、子犬のように見える。拙いのではなく、基本的に変なのである。向席の林さんが「魚食民族ではない人間が描いたから(変なんだ)」と言った。「なるほど。」さすがに料理研究家だけあって深読みされる。
とにかくわれわれは「白身だ、赤身だ、青魚だ」といいつつ、海の魚はむろんのこと、川魚まで食べる。それは日本が海に囲まれ、近海には2~3万種もの魚がいるという環境のせいだろう。
想い浮かべれば、肉食民族が描いたアルタミラ洞窟の牛の絵は迫力がある。そして、よく見る日本家屋の床の間の掛け軸の「鯉」は生きているようだ。肉食の民が描いた魚の絵を「妙だ」と思うわれわれは、「やはり魚食民族なんだ」と悟らせるために飾ったのは福田先生の戦略だろうか。
「筍羹」― 五月料理の楽しみのひとつに筍がある。焼いても茹でても美味しい。筍は、香り、味もさることながら、何といっても歯触りがいい。もしかしたら、日本人しか食べないというあの午旁だって歯触りを楽しむ料理かもしれない。硬くもなく、軟らかくもなく、という具合に・・・。ン! 硬くもなく、軟らかくもなくとは! これはコシのある蕎麦を美味しいとするところと通じるものではないか?
煮物の中を見ると、「蕎麦麩」も入っている。蕎麦米入り生麩を煮たものだ。 初めて口にする。麩は西日本ではよく見かけるが、関東はあまりお目にかからない。本来、茶道では利休が好んだという「麩の焼き」というのがある。福田先生も「蕎麦粉を入れて皮を焼いて、蕎麦味噌をくるんで出してもいいのでは」と提案されたりしているが、「蕎麦麩」なるものは珍しい。大切にしたい。
今日は尊敬する福田先生のお料理を食べたくて伺ったものの、実はこの《蕎麦膳》シリーズでご紹介する予定はなかった。しかし、「蕎麦麩」を知って、これはもう皆さんにもお知らせすべきだと思ったわけである。
「胡椒飯」― さて、後段ではないが、締めの胡椒飯だ。名飯中の名飯といわれる。胡椒がわが国に上陸したのは大昔だ。だから、昔は肉にも魚にも大いに使っていたらしい。そういえば、われわれ九州人は胡椒も、唐辛子も、共に「胡椒」と言う。それは唐辛子が胡椒の代理品として入ってきたため当初「南蛮胡椒」と呼んでいたのだが、いつのまにか南蛮が外れて「胡椒」になったからである。そのうちに種類が違うことが分かっても、「唐辛子は唐枯らし」に通じるとして「「唐辛子」と呼ぶのを嫌った。やがて唐辛子は都に上り、醤油文化と合致して、先輩格の胡椒を追い越した。だから、それ以前に食べられていた今日の「胡椒飯」は江戸初期の味がするはずである。啜ると、胡椒の刺激が心地よく、出汁も旨い。
古式の器のせいもあるだろうが、概して江戸料理は渋い。だから江戸時代の雰囲気が座敷に漂う。まるで私自身が、江戸に出てきた肥前鍋島藩の中年の武士のようだ。思わず、腰に手を当て二本差を確認したくなる。
最後の甘味のことを江戸では「寄せ物」と言うらしい。いわゆる口取、折詰などに使う羊羹、金団、蒲鉾、伊達巻などを指し、料理の一部も入っている。関西の方では「練り物」といってお菓子類が多い。
昔は蕎麦がお菓子屋で作られていたこともあるという説があるが、この「練り物」屋の歴史を調べれば、蕎麦史解明の一助にもなると思うが・・・。
さて、その寄せ物だが、イザ出てきたお菓子を見てご一緒した仲間はみな笑った。それは何とパンダの顔なのである。私は「寄せ ⇒ 人寄せパンダ」という言葉がチラついたのだが・・・、これも江戸っ子福田先生のダジャレだろうか。
参考:なべ家「昔の料理ぶらり散歩」、NHK 第19回「ブラタモリスペシャル― 江戸の食」、福田浩『大江戸料理帖』(新潮社)、福田浩『そば蕎麦百珍』(柴田書店)、
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕