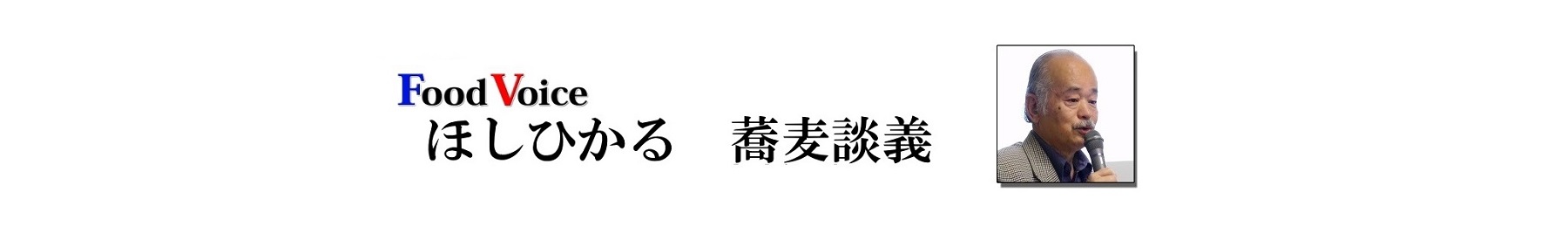第301話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅰ」
2021/11/11
~ Mr.Wonderful ♪ ~
名前の由来は定かではないが、東京の下町に稲荷通りという道路が通っていた。道路のメインは手前で右手にカーブしていたため、車はみんなそちらの方へ流れていたが、道路は直線にも伸びていた。ただ、その道の先は行止になっているので、車はこの道には入って来ない。
その稲荷通りの銀杏並樹の緑の木陰で、野中健は車を停めて休んでいた。新宿を担当している営業マンは「柳町の交差点を通るときはハンカチで鼻や口を押さえながらノロノロ運転している」と言っていたが、この街は比較的排気ガスの少なかった。
車のフロントガラスの少し先には東映の映画館があった。高倉健の「昭和残侠伝」と藤純子の「緋牡丹博徒」のポスターが見えた。面白いことに二枚共、いや二人共まるで「兄貴!」「姉御!」と呼ばれた瞬間に後を振向いたときのようなポーズだった。野中もシリーズの何本かは観たことがあるが、その粗筋といえば、最初は我慢していた正義漢の強い主人公が、最後にはあくどいワルに刃向かっていくというものだった。本来なら無茶な話であるが、映画の中ではきちんと筋が通っていて、見ていても納得がいくため、その心情と勇気に拍手をおくりたくなる。
そんなことを思い出したところにタクシーが一台、野中の後に付けた。緑蔭で一休するためだろう。ここは一種の穴場だから、みんな考えることは同じだ。
バックミラーで見るともなく眺めてみると、ナンバーは練馬、車種は〔クラウン〕であった。野中の車といえば前から見ると、蝦蟇みたいな顔をした白い〔コルト〕。あまり格好いいとはいえないが、先輩たちは、「最近はみんな車を与えられ、営業が楽になった」と喜んでいた。
「兄さん! 火、持っている?」
タクシーの運転手が車から下りて、〔いこい〕を銜えながら声をかけてきた。
野中は、グレーのスーツの左のポケットに入っている銀のライターを取り出そうとしたが、用心して、昨夜行った新宿の寿司屋のマッチの方を差し出した。考えてみると、車にもライターは付いているから、何のために火を求めたのかと疑問に思ったからである。
ずっと前にも病院の駐車場に車を停めていたとき、やはりタクシーの運転手が近づいて来て「当たり馬券を知りたくないか?」みたいなことを言われたことがあった。もちろん端からそんなことを言われれば、誰でも怪しいと思うが、世間話をしながら、「オレのダチがジョッキーで、今度は○○が勝つ番で、その次がオレの番だと言っていた」と、筋の通った話をしてくるから、ついホントだと思ってしまいそうになる。野中が「危ない、危ない」と我に返ったのは、その男が分厚い札束を見せたからである。男は信憑性を高めるための知恵のつもりだったのだろうが、野中には逆効果だった。かえって目を覚まさせてくれたのである。
そんな経験のある野中は、話に乗せられないように、逆に訊いた。「この辺りで病院へ行くとしたら、何処に行く?」それは先輩から「煙草買うときでも無駄に買うな。その町で流行っている医者ぐらい、訊いておけ」と教わっていたのが頭にあったからである。
まさか質問されるとは思っていなかったのか、男は、何? という顔付をしたが、「そうだナ。中学校の門の前にあるだろう。何とかクリニックっていうのが、あそこはいつも混んでるな。兄さん、どっか悪いの?」
野中は「いや」と首を振り、「あそこか。やっぱり地元でも評判か」と心の中で思った。
「じゃあ兄さんは、クスリ屋さんかい」と男は言う。
「イヤ、器械、」
「ふ~ん。とにかく、あそこにはよくお客さんを運ぶよ。」
野中は医療器械屋ではなく製薬会社の営業員だったが、それを言うと「儲かっているだろう」とか言って後がうるさいから、「医療器械屋だ」と言うことにしている。そうすると何か難しそうな感じがするのか、追打ちがないのを知っていたからである。
「さて、行くか」。男は、それこそポスターの高倉健か、石原裕次郎になったようなつもりでチョット格好付けながらタバコを道に落として足で火を踏み消し、車に戻って行った。
たぶん、「何となく話しかけたかっただけなのだろう」と思っていると、5分もしないうちにタクシーはその場を走り去った。
野中はカーラジオのボタンを押した。
エルヴィス・プレスリーが「この胸のときめき」を歌っている。
野中は、左胸から〔ハイライト〕とライターを取り出した。ライターは「カキン!」と音を出して開いた。野中が火を点けて吹かすと煙が車内から窓の外に流れる。ライターは香港で買った自慢のデュポンだったが、本物か、偽物かはわからない。
野中は煙草を吹かしながら、もしマッチではなくてライターを出していたら、あるいは質問をしたりしなければ、どういう話の展開になっていただろうか、と思ったりした。野中は営業だから、話が右へ行くか、左へ行くか、そんな展開に関心をもっていたのである。
曲が、サイモン&ガーファンクルの「明日に架ける橋」に変わった。
野中はもう一本、火を点けた。
製薬会社の営業は、水商売みたいなもので、お得意先が働いている時間は暇になり、お得意先の休憩時間が仕事時である。
朝一番に薬問屋に顔を出して問屋のセールスと相談し、彼らが一斉に営業へ出かけた後は、お昼前まで少し時間がある。もちろん午前中は医療機関も診察に大忙しだ。その間、営業所にいる自分の課長に電話したり、セールスから耳にした情報を得てから、一日の訪問先を練り直すこともある。
先刻も、赤電話から、課長に連絡した。
「ノナさん、頼むよ。売上いかないと、ウチの会社、潰れるよ。」野中は、会社で「ノナさん」と呼ばれていた。毎日毎日「根性だ、根性だ」と課長の発破が続く。そして最後の怒りの台詞は「そんな数字で恥ずかしくないのか。辞めちまえ」だ。これも毎月末のマンネリ文句だ。たいていの部下は、それが聞こえ始めると受話器から耳を遠ざけて、生返事をしている。
野中も馬耳東風。それよりか、先ずは昨夜接待した田中整形外科へ顔を出すつもりだ。新宿の寿司屋とクラブとスナックに連れて行った。田中先生はビール党だった。何処に行っても女の子たちは、CMの「男は黙ってサッポロビール」を決まり文句のように使いながら注いだ。
最後に行ったスナックのママさんはケロンパみたいな顔をしていて、年齢不詳だ。常連の野中もママが若いのか、いい齢なのか今もって知らない。店には清水という若いピアノ弾きがいて、どんな曲でも伴奏できたから、客はマイクを握って、よく歌った。田中先生も歌った。
カウターの奥でママさんが「今度お店の女の子たちと沖縄に行こうって話してたの」と言った。
「へえ、」
「だって、日本に返還されて沖縄県になったのよ。パスポート、いらないじゃない。」このママは客をお客様扱しない。まるで友達のように話してくる。そこがこの店の良さだった。
そのケロンパ・ママがさらに何か言おうとしたとき、田中先生が「オイ野中、何をコソコソ話してるんだ、行くゾ」と言って倒れてきた。
野村はまだ他の店に行くのかと思い、「先生、何処へ行くんですか?」と訊いた。
「沖縄だ。」
「あら、先生聞いていたの!」ママが笑う。
「知ってるか。日本では、人は右、車は左。アメリカは反対。人が左、車が右。名前もそうだ。日本で私は田中義雄、アメリカではヨシオ・タナカだっ。フランク・シナトラだってそうだ。日本に来れば、シナトラ・フランクだ。」
「へぇ、シナトラ・フランク。何かおかしわね」とママはクックッと笑ったが、先生は完全にノックアウト。こうなると、田中院長は背が高いから厄介である。やっとの思いで、タクシーを拾って送ったのが、4時ちかかった。
だから、眠い。しかし見返りをもらわなくては。そのタイミングは接待の翌日である今日がいい。
野中の会社では、営業所は地区割になっていて、その地域の中クラスの病院と開業医を担当し、病床数100ベッド以上の大病院は病院部が担当していた。
地区は重要なお得意先が必ずある。それが多ければ多いほど安定した売上を確保できるのはいうまでもないが、少なくとも5~10軒はないと情ない数字になる。
昨夜お付合した田中整形外科も重要得意先の一つである。営業所は病院部のように派手に接待する機会は少ないが、それでも重点得意先は接待することもある。
もっとも田中整形外科は昔からのお得意先であって、野中が開拓したわけではない。どちらかといえば、営業所として大事に守っていかなければならないところであった。
「やっぱり、先ずは田中先生の所に行こう。」野中は車のエンジンをかけた。
「おはようございます。」野中はネクタイの緩みを直して、田中整形外科の玄関てスリッパに履き替え、診察室の隣にある事務室に入った。とはいっても机と椅子があるだけの休憩室のようなものだ。廊下は暑かったが、この部屋には冷房が入っていた。
たとえ事務室でも、診察中の部屋への出入りは許可がない限りマナー違反であろうが、一方では営業マンなら出入り自由でないと優秀とはいえない。とくに接待した翌日は敢えてルール破りをした方がいいときもある。
事務室には誰もいなかった。テーブルの上に新聞が開いたまま置いてあった。野中は新聞を取り上げた。セ・リーグの川上監督や長嶋や王の写真、パ・リーグの野村の写真が載っていた。競馬の欄には、ランドプリンスやベルワイドなどの活躍記事が踊っている。近ごろは競馬がますます過熱してきて、野球を上回るほどの人気だ。野中が目を通そうとしたとき、医院長が顔を出した。患者さんが途切れたのだろう。
「おう。昨日はどうも。」
「こちらこそ、ありがとうございました。」
「あの寿司屋はいいな、旨かったよ。天然物しか出さないって言ってたな、たいしたもんだ。高かったろう。」
「え、まあ」と何となくごまかしているところに、看護婦さんが顔を出し、野中に「おはようございます」と言いながら、机の上の新聞を片付けて「先生、患者さんですよ」と追い立てる。
医院長は立ち上がって、言う。「また行こう。」
「はい。」野中はそう言いながらも、「まずい、魚を逃すかもしれない」と思ったとき、「あれ、持って来ていいよ。」と院長が言ってくれた。
「ありがとうございます。」
「あれ」とは、来月出る新製品だ。前々から頼んでいたものである。野中は立ち上がって、院長の背中に向かって頭を深々と下げた。
それから、三軒ほど訪問したが、空振り同然だった。こういうときは気持を取り戻すために、自分好みの得意先へ行くに限る。それが中村病院だった。それは野中が開拓した得意先だった。とはいっても、振り返るとたいしたことはやってない。最初は薬局へケーキを持参したことだった。病院には若い女性の薬剤師が三名いた。前任の薬局長が退職したばかりだったためか、彼女らは学生のように伸び伸びと仕事をしていた。それに彼女らが自分と年齢が近かったので、野中も気楽に顔を出した。
三人の薬剤師は大学が同じで、各々一学年ずつ後輩ということだった。一番上は「高橋先生」、竹を割ったようにサッパリしていた。二番目は「松本先生」、温和な人柄だった。三番目が「由美ちゃん先生」、美人の上に、赤ん坊のように大きな黒い瞳をしていた。「由美ちゃん、由美ちゃん」と全職員から呼ばれ、掃除の小母さんでさえ「由美ちゃんは可愛いお嫁さんになるよね」と可愛いがっていた。
「甘い物と、お酒と、趣味は、営業マンとお得意様をつなぐ架け橋だ」とは野中の課長がよく言う台詞であるが、なるほど女性に甘い物はクスリよりよく効く。
三人は姉妹のように仲が良かった。午後の休み時間にチーズ・ケーキなどを持って行っては、お茶を飲みながら、楽しく談笑した。たいていはネスカフェのインスタントだったけど、甘すぎるコーヒーを飲みながら野中は「若い女性たちの中にいるこんな心地よい時間はとても仕事とは呼べないナ」なんて思うほどであった。
ところがある日、ここにこうして座っていると医師の処方が手に取るように分かることに気が付いた。まるで、見てはならない麻雀の牌を背後から見るようなものである。
それから野中は医局に顔を出して、医者らの麻雀に付合い、ここぞというときに医師に自社の薬剤を使用してもらうよう頼んだ。その依頼は的を得ていたので、どんどん実績を伸ばしていって、野中の重点お得意先にまでなった。
この病院の薬局は野中にとって天国だった。そんな天国になぜ他のメーカーはあまり立ち入らないかというと、薬品の採用、購入権が院長にあったからである。だからあまり重要視してなかったのだろう。
野中は薬局の先生たちとうまくいっていた。ただ、若い野中である。可愛い由美ちゃん先生が近くに来ると胸が幸福感に満ちてくることもある。だが、必要以上に接近し、高橋先生や松本先生たちの間を崩すことを懸念した。
そんなとき、社内の他課の男だったが、長井という後輩が会社を辞めた。理由は女医さんとの浮気だった。
半年ぐらい前に「昨日は子供を肩車してやったせいで、肩が凝って・・・・・・、」なんて言ったりしていた。長井は野中より三級後輩の独身だ。てっきり甥っ子か何かのことだろうと思って気にもしてなかった。
ところが先月、長井が「某眼科クリニックの女性院長と結婚することになった」と課長に言ってきた。訊くと、ご主人だった人も医師だという。ただし大学病院の命令で地方の病院勤務の身、いわゆる単身赴任だ。そこへ偶々長井が院長の自宅の引越の手伝いに行ったりするうちに段々と、そういう関係になったらしい。女医さんは、離婚して、子連れで十歳若い長井と再婚することにしたわけだ。
「あのバカが・・・・・・、辞めさせろ!」
本社の部長は激怒したが、所内の若手たちは面白がっていた。
「長井も、某眼科クリニックの事務長か。」
「毎日が数字、数字だ。一転して、それもいいか。」
「しかし長井もよくやるよな。」
「営業マンだって人間だ。情がわいてくるのも分かるよ」。
そんな話していたところを課長が耳にして、「お前たちはどうしようもないな。営業は仕事上の人間関係を構築するもんだ。会社のカネで仲良くなってんだ、勘違いするな」と怒鳴った。
長井が厄介な問題を持ち込んだためか、営業所は一時期、調子を狂わせられた感じだった。それも長井がいなくなるとまた元に戻った。
野中が、得意先としてもうひとつ狙っているところは齋藤胃腸科クリニックだった。ここも患者数は多かった。
卸の担当セールス渡辺も「何とか落としたい」と言っていた。
野中は渡辺と仲が良かった。月に1回ていどは二人で安いゴルフコースで汗を流し、その後の風呂でバカを言いながら遊ぶ仲だった。
齋藤胃腸科の情報を持ってきたのもその渡辺だった。
「ノナさん、シルヴィ・ヴァルタンのチケット手に入る?」
「なにそれ!」
「京子先生は学生時代、パリに行ったときシルヴィ・ヴァルタンを聞いたことがあるらしい。いま来日していて、懐かしいからもう一度聞きたいっていってたんだ。」
齋藤胃腸科の薬局長は院長の娘であったから「京子先生」と呼ばれていた。
「おう、そういうことか。じゃ何とかするよ。で、ナベさんも一緒に行くかい。」
「え、おれもいいのかい。所長に相談しとくよ。」ナベさんは嬉しそうだった。
翌日、「チケットは手に入る」と言ったとき、渡辺はちょっとがっかりしたようにして「所長に十年早いって言われたよ。京子先生と行きたかったけどな」と小さな声で言った。
そうか、ナベさんは薬局長が好きだったんだ。女性の医師や薬剤師には頭の良さと育ちの良さからくる美しさをそなえている人が多い。京子先生もそうだったが、そんな先生とちょっとデイトなんて、いい感じだ。渡辺の気持も分かる。
しかし渡辺は、その日も、翌日も、いつもより口数が少なかった。
「こまったナ。」野中がそう思っていたとき、渡辺の上司の村井所長が「野中さん、ちょっと。それから、ナベも来いッ」と会議室に呼び入れた。
「気遣ってもらってすみませんが、齋藤さんの薬局長の件は野中さんにお願いします。われわれ卸はメーカーさんを立てながら仕事をしなきゃならん、だからお前が楽しんじゃいかん、とナベに言ったんですよ。ですから、」
「は」
各メーカーの営業員は、病医院で自社の薬品を採用してもらったり、採用されたその薬品の消化活動を行ったりするが、実際にその薬品を配達したり、集金したりするのは卸である。だから「メーカーと卸は夫婦のように」と言う者もいるくらいである。
村井所長が「メーカーさんを立てながら」と言ったのは、そういう意味であった。
「ナベ。お前も野中さんの気持を組んで頑張れよ。」
所長にそう言われて、ナベさんもやっとふっ切れたような顔をして、「はい」と頷いた。
野中は所長の顔を見ながら、「良かった」と思った。
「知ってるでしょうが、薬局長は院長の一人娘だから薬剤の件は任されているけど、やっぱり院長にも会っておいた方がいいよ。将来は医者のお婿さんを迎えて、ということになるだろうけどね」。
「・・・・・・。」
「ちょうどいいや、今度の日曜日に齋藤さんとゴルフに行くことになっているから、おれからも言っとくよ。野中さんというのが頑張っているから、すこし面倒見てください、って。」
月曜日の朝、卸の営業所に顔を出したとき、村井所長は他のメーカーの人間と話していたが、野中の方に顔を向け、オーケーのサインを送ってきた。昨日のゴルフで、うまく言っておいたという意味である。
野中は所長に向かって頭を下げ、渡辺の所に行って軽く肩に手を置いた。
渡辺は机の上に置いていた新聞を開いて見せた。シルヴィ・ヴァルタンのディナーショウの広告が載っていた。
それを見ながら、野中は渡辺の肩を二、三度叩いた。
午後になって、齋藤胃腸科の薬局を訪ねたとき、その新聞が置いてあった。渡辺が置いたことは間違いがないが、彼が何を言ったかは判らない。
それでも野中は壁に掛けてあるカレンダーの写真を眺めながら、パリの話題を持ち出した。前から、カレンダーの写真がフランスの風景だったことに気づいていたからである。
薬局長は表情をいちいち露わにするような人ではなかったが、それでもフランスの話をすると頬あたりに懐かしそうな感情を浮かべていた。
「友達とね、アルザスのワイン農家にホームステイしたの。パリは日本へ帰るとき、二泊しただけなのよ。」
「へえ、」
野中は思い切ってシルヴィ・ヴァルタンのコンサートに誘った。そしてYesかnoを聞く前に、「行くとしたら何曜日が都合いいですか?」とも訊いた。ノーの回答を口にされないような会話の運びは営業マンなら定石だ。「やはり、週末でしょうね。」野中は壁のカレンダーを見ながら、たたみかけるようにして呟いた。
「そうね」
「月半ばの週末、17日に取りますか?」
「ええ。」
野中は京子先生の返事をもらうと、齋藤院長にも会った。院長は野中が差し出した名刺を手にしながら「分かりました」と言った。
野中は病院の外に出て、ネクタイを少し緩めた。何気ない会話でも、囲碁や将棋をしているように緊張する。京子先生が「はい」と言ってくれて、よかった。ゼロからのスタートだったけど、ここまでくればゴールも見えているだろう。野中は心の中で「やった!」と思った。ナベさんと、村井所長の顔も浮かんできた。
野中は駐車場に停めていた自分の車に戻った。ドアを開けると、ものスゴイ熱気が襲ってきた。空いていたから、大きな樹木の下に停めていたが、それでもこの熱気だ。まだ梅雨前だというのに、真夏のような暑さだった。時計を見ると遅い昼食時にはちょうどいい。野中はまたドアを閉めて、通りを渡った所にある中華屋に入った。
店内には、なぜだか江波杏子の「女賭博師」のポスターが貼ってあった。しかも中華屋独特の油と熱風で汚れている。それでもポスターの江波杏子は藤純子のポーズと違って、正面を真っ直ぐ見つめていた。そのしっかりとした視線はどこかの女医さんのようだと思った。
隣には《冷やし中華180円》の貼紙があった。野中は何も考えずに「冷やし中華」を頼んだ。
すぐにおばちゃんが皿に指を突っ込むようにしてそれを持ってきた。野中は箸立から箸を抜き取り、麺を啜った。
夏になると、よく《冷やし中華》のおしながきが貼ってある。客も「冷やし」の文字に誘われてついつい頼む。しかし野中はこの《冷やし中華》というものを旨いと思ったことは一度もなかった。そんな話をある医師と雑談で話したとき、「神保町の〔揚菜館〕は旨いよ」と教えてくれた。野中は行ってみた。たしかに、そこら辺の店より酸味と甘味が効いていて、旨かった。しかしだからといって感動するほどのものでもなかった。
店の角の棚の上にのせてあるテレビが、ニクソン大統領がソ連を訪問し、ブレジネフ書記長と会談したというニュースを報じていた。そして関連して、ニクソンが去る2月に中国を訪問し、毛沢東主席、周恩来首相などと会談したときの映像も映し出していた。
うちわをパタパタさせていた中年の客が「オイ、野球やってんだろう。変えろよ」と、ちょうど出前から帰ってきたばかりのアンチャンに大きな声で言った。
よく見ると、テレビはチャンネルの部品が壊れていて付いてなかった。アンチャンは椅子を持ってきて乗って、ペンチでチャンネルを回した。みんなゲラゲラ笑った。
そのアンチャンはまた小型バイクに乗って次の出前先に走り去った。
野中は中華屋を出たが、暑い。ジリジリ、ジリジリとうるさく鳴く油蝉の声にたまらず、たまたま目には入った喫茶店に飛び込んだ。飛び込みながら、今日は大きな仕事をしたから休憩してもいいだろう、と心の中で言訳もしていた。
さっきの中華屋は冷房はなかったが、ここは珍しく涼しかった。
「いらっしゃいませ。」珈琲の香り漂う中、店の奥さんだろうか、おとなしそうな人が席へお冷を運んできてくれた。
野中は水を一気に飲干し、「あゝ、旨い!」と一息ついた。それから「珈琲を
ください」と言った。
店主は四十代だろうか、俳優の殿山泰司によく似ていた。惚けたような、怖
いような目で私をジロリと見ただけで何も言わなかった。
すぐに珈琲が運ばれてきた。野中はそれを見て「しまった」と思った。アイス珈琲を頼まなかったことを悔みながら、ホット珈琲を頂いた。
ところが意外にも飲むとスッキリした感覚で、さらに一口含むと珈琲のコクが舌に滲みてきた。珈琲といえばインスタントしか飲んだことのない野中は、美味しいと思った。
野中は、あらためて店内を見回してみた。幾つかのラクダの置物が飾ってあった。そのとき初めて店名が〔キャラバン〕であることに気が付いた。
「ご馳走さま。」野中は汗がひいたところで代金120円を払って店を出た。
翌日も、近所を回る日だった。野中は昼食後にまた〔キャラバン〕に寄った。
「いらっしゃい。」今日は店主が声をかけてくれた。そして惚けたような顔で、こう言った。「お兄さん、珈琲が好きなんだね。アイスなんて、冷たいだけで、珈琲の味わいはないんだよ」。
「・・・・・・!」 野中はこの店ではホット珈琲しか頼めないなと思って苦笑した。それから話をしていたら、野中が昨日「ご馳走さま」と言ったのが、店主が野中のことを覚えてくれた理由らしかった。逆にいえば、気に入らなければたとえお客さんでも口を利かないという頑固な面がこの店主にはあるようだった。
とにかく、相手が好感をもってくれるということは、こちらも気分がいい。そんなきっかけで、それから野中は〔キャラバン〕に通うことになった。 (Ⅱへ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる:作〕