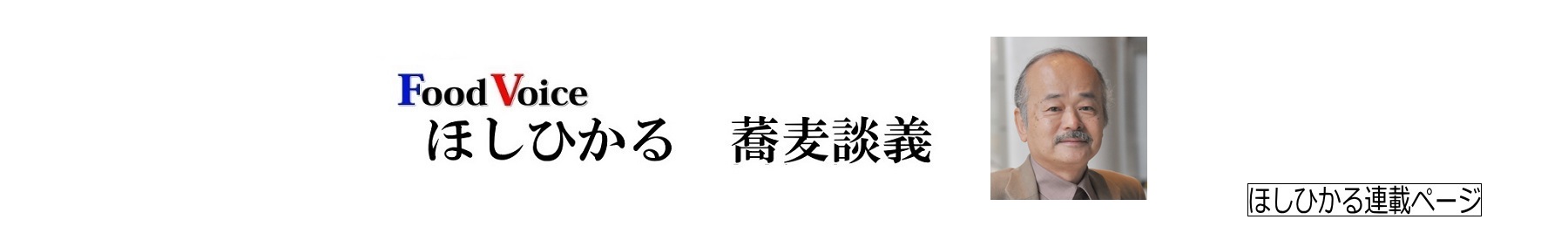第307話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅴ」
2025/12/06
~ Lovin’you♪ ~
自宅のマンションで、恵子はシャワーを浴びていた。
今日は、恵子の人生にとって、一番大切な日となった。特に晴海埠頭にいた時間は、ほとんど話をしていないというのに、野中の心と深く交わり、堅く結ばれた、と思った。恵子は幸せを感じていた。
美容院の予約は鮨屋の女将がキャンセルを入れてくれ、「今は彼と一緒に行きなさい」と背中を押してくれた。
そして先ほど野中に車でマンションまで送ってもらったとき、本当はこのまま野中を部屋に招き入れたかったが、野中はまだ仕事の途中、恵子も夜の仕事が控えていた。
「仕事だけは絶対さぼってはダメ。」明子ママが恵子に「これだけは何が何でも守りなさい」と教えてくれたことだった。いわば、明子ママは「夜の学校」の教師、恵子はその優秀な生徒だった。
シャワーの音が浴室に響いていた。そんな中でもあのラジオの声は今も耳に残っていた。「神様は、人間のどんな死でも許してくれます。」
この言葉によって、恵子は2年間の苦しみからやっと解放された思いだった。
そのとき母の優しい声も聞こえてきた。「恵子ちゃん。お母さんは平気だよ。あなたが幸せになってくれれば、何もいらないよ。」
恵子は母の声で泣いてしまった。
それを野中が黙って受け止めてくれた。
シャワーの心地よいお湯が恵子の身体を跳ね、滑らかな肌を滑り落ちていった。まるで罪を流してくれるかのように・・・
2年前、マスコミに叩かれ、世間からは「悪女」と呼ばれた恵子を救ってくれたのは、恵子の「育ての親」の明子ママだった。
事件が起きたころ、大西明子は自分の実家である大月の病院に入院していた。
テレビで見ていた報道番組で恵子の姿が映っていたときは、ほんとうにびっくりした。すぐに人に頼んでスポーツ紙を買ってきてもらうと、トップページにはいい加減な記事が溢れていた。
怒った明子は、病院の早い夕食後、看護婦に「東京へ行きたいから、許可してほしい」と頼んだ。看護婦は婦長を連れて飛んで来た。
「大西さん、貴女はご自分のことを分かっているのですか?」
「分かってますよ。あと1年もないと言われたのに、お蔭さまで1年半も生き長らえている癌患者です。」
「・・・・・・。何しに行くのですか?」
「それはお話できません。ただ、遊びに行くわけではありません。人助けです。どうしてもお許しいただけないというならば、退院させてください。」
明子は頑として譲りそうもない。若い看護婦は院長を呼びに行った。
院長がやって来た。事情はすでに看護婦から報告を受けていたが、先ず耳を傾けることにした。
明子もさすがに院長に隠しておくわけにはいかないと思った。
「それじゃお話します」と言って新聞を開き、「この子、恵子っていうんですけど、子供のいない私にとってたった一人の愛娘なんです。21歳の学生のとき、私のクラブにアルバイトにやって来たのが最初でした。ご覧の通り女優やモデルしても負けないほどの飛びっ切りの美人で、しかも凛とした容姿です。だからあの娘は女の子たちからも一目おかれるという長所をもっていました。
私は、この子は銀座一のママになれると思いました。大学を卒業して、ちょっとだけ証券会社のOLになったんですけど、また戻って来ましたから、私の店のチーママにして、教育を始めたのです。」
婦長と看護婦は興味深そうな目になった。
「まずは銀座の街の人たちを大事にしなさい。そして仕事は絶対さぼってはダメ。初めて見えたお客様には手紙を出しなさい。そのためにペン字を習いなさい。美しいお辞儀の仕方も勉強しなさい。お店のお掃除は手を抜かないで、飾るお花は豪華にしなさい。ファッションを勉強しなさい。着物の着付も学びなさい。一流の衣装を身に付けなさい。新聞は隅から隅まで3紙は読みなさい。ベストセラーも読みなさい。経済セミナーを聴きに行きなさい。英会話も身に付けなさい、ってね。向島にも連れて行って、踊りも習わせましたよ。別に踊りのお師匠さんにするというのじゃないんですよ。玄人の踊りで〝玄人の美〟ということを恵子に教えたかったの。」
「〝玄人の美〟か、いい言葉ですね。」院長が感心しながら呟く。
「ありがとうございます。それは一流クラブの経営信条みたいなものなんです。各界のトップレベルのお客さまをお迎えするための。だから間違っても法にふれるようなことには絶対手を出しちゃダメだと厳しく言いました。それから、美しい身体を維持するために、ジムに通いなさい。美容クラブにも入りなさい、とね。」
明子はちょっと目を閉じた。「先生、横になっていいですか? 少しおしゃべりが過ぎたかしら。」
「もうその辺にしますか。」婦長が布団を整えてくれた。
「大丈夫です。娘を助けなくっちゃね、婦長さん。まだまだ教えたことはたくさんあるんですよ。お客様にとってお酒は楽しい潤滑油、でも私たちはそれが商売道具、だからお酒に飲まれちゃダメ。それを知るために酒造会社、ビール、ワイン、ウイスキーの会社に行って製造も見学しなさい。そういう会社のお客さんはウンといたからね。そして・・・、恋多き女はいいけれど、オトコ漁りは駄目、とブレーキも掛けましたよ。あれほどの美人ですから、中学・高校生のころから周りの男たちが放っておかなかったらしいのよ。でもね、どんな美人でも乱れた女の末路は哀れなものよ。私は何人もそういう女を見てきたからね。その点、あの子は優等生だったわ。そうしてるうちに、とうとう縁あって25歳で独立したお店を持てたの。と思ったら、3年もしないうちに、銀座で指折の店になったわ。そういう子なの、あの娘は。」
院長と婦長は、明子の物語を感心して聞いていた。
「そうですか、分かりました。それで大西さんは東京へ行って、その娘さんを励まそうというのですか?」
「励ますっていえばそうでしょうけどね。私たちは世間様にお世話になっているけど、だからといって、世間に負けるなっていうことだけを分かってもらいたいのよ。ですけど、その前に先ずあの娘を抱きしめて、あんたは悪くないよって言ってやりたいんですよ。先生も医者だから、お分かりでしょうけど、本当のところ、他人は本人とちがうから、手助けできるかどうか分かりませんよ。」
「そうですね。」
「ただね、娘があんな目にあっているというのに、テレビを黙って見ているわけにはいかないのよ。親だったら、娘に代わって私をぶってくれって言いたいものでしょ。私の命を差し出しますから、どうか娘を助けてほしいと思うものでしょ。」
若い看護婦の方は目に涙を浮かべている。
「分かりましたよ。」院長は許可した。「娘さんのお住まいはどちらですか?」
「築地です。先生、ありがとうございます。」
「いいえ。このままでは死んでも死ぬに切れないという思いなんでしょう。止めたら、大西さんの病状は悪化するかもしれない。医者としてはそれは避けなければなりませんよ。築地に後輩の医者がいますので、大西さんのことは連絡しておきます。ここに電話と住所と、紹介状を書いておきますから、持って行ってください。」
翌日、明子は大月からタクシーに乗って、恵子のマンションへやって来た。
恵子がマスコミに叩かれ始めて三日目だった。ちょうど気持が折れる寸前だったから、ほんとうにほんとうに恵子は嬉しかった。
しかし、それはそれとして明子が異常に痩せていることにも驚いた。
「胃潰瘍だよ。大丈夫。」明子は事もなげに言ってのけ、「それよりね、人の噂も75日、切り抜けるのよ。こういうときも原理原則は同じよ。仕事は絶対さぼってはダメ。お客様には手紙を出しなさい。お辞儀の仕方は崩れていないの? お店のお掃除は手を抜いてないの? お花はちゃんと飾ってるの? こういうときこそ、貴女の健康が大事よ。身体を動かしなさい、規律ある生活をしなさい。向島の絹江姐さんも言ってたでしょ。ここ一番というときは、あそこをギュッと引き閉めて、女の意地を見せるのよ。」
思わず恵子は苦笑いをこぼした。そして「75日、やってみよう」と何とか行動目標をもつことができた。
続けて、明子は言った。「この布団と枕、私には合わないのよ。デパートの外商部に言って、替えてもらっていい?」
恵子はピンときた。「滝川が使った枕なんか捨てなさい。もう過去とは決別しなさい」と明子ママは言ってくれているのだと。恵子はあっさり頷いたが、そういう自分に少々驚きながら「私は本当に滝川を愛していたのだろうか?」とも思ったりした。
そんなころ、店にマスコミから電話が入った。「○○の記者です。ママさんお願いします。」
店の者が、ママに電話を代わるわけがない。「いません。」
「何処にいますか?」
「分かりません。」答えるはずがない。
「そうですか。」と電話は切れた。
店の者は「いったい何なんだ」とも思えないほど簡単な電話だった。
翌日のスポーツ紙の、見出しと記事は、こうなっていた。
【恵子ママ行方不明!! 逃亡か? 後追い心中か?― 本紙記者が従業員に確認したところ、「ママの行方は分からない」と言う。某専門家は「後追い心中のおそれがありますね」とコメントした。】
「エー! あの電話一本で、こうなっちゃうわけ。」
「みんな、鵜呑みするよね。」
「ママ、かわいそすぎる。」
徳子は怒って新聞をテーブルに叩き付けた。「私たちをいったい何だと思ってんのよ!」
他の女の子が囃した。「徳ちゃん、いい根性してるわよっ!」
店の者は、このハプニングで恵子ママを守るようになった。
翌日になると銀座の商店会の店主たちが、会合の帰りだと言って10名が来てくれた。
その夜、恵子はお得意様50名の名簿を持って、商店会の会長である老舗和菓子屋に行って、和菓子50名分を送るように頼んだ。
会長は「恵子ちゃん、無理することないよ。困っているときぱお互いさまだよ。」と言ってくれたが、「いいえ、今こうしないと私がだめになるような気がしますから」と返事した。
それから、店にはお客が戻り始めた。恵子は一人ひとりに頭を下げ、丁寧な接客を続けた。そうしているうち、明子が予告したように二ケ月も経たないうちに火は消えた。とはいっても、恵子の気持としては針の山に登るような毎日だった。
家に戻ったとたんに、バタン。着物を脱ぐ気力も失せていた。それを明子が手伝った何とか過ごしてきた。
店が休みの日、昼までぐっすり眠っていた恵子がシャワー室から裸のままで出てきた。
明子は恵子のヴィーナスのような裸身が眩しかった。「あんたの身体は20代のころとちっとも変っていないのね。」
入院中、親の見舞いに赤児を連れた若夫婦が来ていたことがよくあった。明子は、赤児を見ると生命の輝きに胸がドキドキするのであった。院内で子供や若い看護婦を見るのも楽しみであった。そしていま、恵子を見ても同じような感動をいだいた。「生きているって、若いって素晴らしい。」明日には死ぬかもしれない身だから、痛感することだった。
そんな明子だから、恵子に対して親として責任のようなものを感じ始めていた。それは「この娘を、いつまでもクラブのママしておいていいのだろうか?」ということだった。
ここを切り抜けたら、恵子は銀座一のママへと登ってゆくだろう。しかし、それでも所詮はクラブのママ。この私とあまり変わりはない。恵子は私の優等生。それ故に普通の恋愛なんか経験してないだろう。恵子が付合った男は、映画一筋、歌舞伎一筋といえば聞こえはいいが、自分のことしか考えない男が多かった。それは恵子自身を愛するというより、恵子の美貌だけが目的だった。だからといって、サラリーマン族とは生活環境が違いすぎて、本気で付合うのは難しい。これまでの個性的な男が向いていたといえばそれまでだが、一人の女としてそれでいいのか? と一人者の明子は胸が痛む。恵子はもう34歳、普通の結婚や出産はもう縁遠くなってしまった。しかし、あの美貌、あの才能が・・・・・・、惜しい。
明子は、「闇将軍」といわれていた相場師三木茂吉の愛人だった。茂吉が第一線を退いたころ、恵子に会わせた。経済の仕組や株のことを学ばせるためにであった。いつのころからか恵子は茂吉の指導下で信用取引を始めた。紹介したものの、その世界に弱い明子は、恵子が何をどうやったかは知らないが、結果的には、一生何もしなくても食べていける分ぐらいは稼いだらしい。あの茂吉が「恵子の勘は女彪のようだ」と舌を巻いていた。「特にカイ時の決断力がいい」と言っていた。お蔭で、恵子は店を持つことができたが、茂吉はこうも言ったことがある。「あの娘はもっともっと化ける。お前も楽しみだな」と。あの人の言葉をよくよく考えて上げなければ、私はあの世であの人と合わせる顔がない。
東京に来たといっても、明日の命も分からぬ明子が店に出るわけにはいかない。食事の支度はお手伝いさんがやってくれる。むしろ邪魔みたいなものだ。でも、恵子の一生について、何かを投げかけてやってこそ「母」ではないか。しかしそれを言うにはタイミングがいる。今のこの火事場で言うのは難しい。
そうこうしているうちに三週間経って、事件は鎮火の気配を見せ始めた。明子は大月に帰る前に言おうと思ったが、やはりまだ雰囲気としてはまずかった。
ただこれだけは言った。「恵子、このくらいで済んで良かったと思いなさい。」(下手すれば、滝川の奥さんに訴えられることもあったけど、幸か不幸か滝川さんが亡くなったから、それはなかった。)とまでは言わなかったが、「『法にふれるようなことはしてはいけない』と言った言葉の中には、『浮気もダメ』ということも入っていたはずだよ。一人者のあんたは浮気じゃないと思っただろうけど、相手はそうじゃないんだ。とか何とか、立派なことを言うようだけどさ、失敗するのが人間さ。あんたにとっては、これくらいで良かったと思いなさい。」
気丈な明子だったが、大月に戻ってから、彼女の身体はみるみる痩せていった。明子は自分の死期を悟り、恵子を呼んでもらった。
恵子が東京から飛んで来た。
明子は恵子の手を弱々しく握って弱い声で言った。「恵子、よくがんばったね。もうこれであんたは、私の学校は卒業だよ。あの人が言ってたよ、あんたはもっと大きなことをやれる力があるんだって、楽しみだって。もうクラブのママは卒業して、そのうちに世界に飛び出してみたら・・・・・・、」
明子は、女彪のように跳躍する恵子を想いながら、旅立っていった。
その一ヶ月後に、恵子の実の母佳子が倒れたとの知らせがきた。
恵子はすぐ秋田へ発った。心臓が弱かった上に娘を思う心労がたたったのであろう。母の最期は間に合わなかった。
恵子の姿を見る前までは親類の者や近所の人たちは、恵子の親不孝ぶりを口ぐちに言っていたが、恵子の姿を見るやピタリと口を閉じた。恵子の美しさは母親ゆずりであることは皆も承知していたが、何年ぶりかに帰って来た恵子の、息を飲むほどに洗練された美貌にすっかり威圧されてしまった。その上、告別式になったとき、献花の名前を見て、皆は驚いた。政界、財界、芸能人の名前がズラリと並んでいたのである。
恵子は思った。近所の人たちもお客さんも同じだ。こちらが縁を切れば、この人たちも縁を切る。私が誠意を尽くせば迎えてくれる。恵子は親不孝を詫びるつもりで、弔問客一人ひとりに丁寧に頭を下げ続けた。
一度に二人の母を失ってしまった恵子であったが、仕事だけは何とか乗り越えた。それは二人の母の教えのせいだった。母佳子は若いころ、田舎のしがない画家だった父のモデルをしていたという。それについて、中学生の恵子は母に尋ねたことがあった。
母は言った。「モデルは画家(お父さん)のことを絶対信頼しているけれど、モデルはモデルとして画家と勝負しているのよ。ただ呆として座っているだけじゃないのよ」母のその言葉が、お客と対峙する恵子の心構えとなっていた。母の言葉を思い出した日から、恵子は自分の店に入るとき、一礼して入ることにした。明子ママや、花柳流の絹江師匠にも女の生き方を教わった。
しかしながら、「二人の母の死は私のせい。」そう思うと恵子は打ちひしがれた。「不徳のいたすところ」というおざなりな言葉が、こんなに重いものだと思いもしなかった。
恵子は心に深い穴をいだくようになった。「不徳」という深い穴を。それを塞ぐにはどうしたらよいの? それを教えてくれるママや母はもういない。自分で見つけなければならない。
でも、それを野中さんが持ってるような気がする。現に、あの人といるときは、今までの空気と何か違う。あの人は違った色をもっている。
恵子はシャワーを止めて、身体を拭きながら、女学生のように聞き耳を立てていた。
別れ際、恵子は紙に電話番号を書いて野中に渡した。今日か明日、電話がかかってくれば、私とあの人のお付合は続く。電話がないときは、彼は去っていくだろう。でも、あの人は私が渡したメモを大事そうにして財布にしまってくれた。きっとあの人は電話をくれる。もしかけてくれるならあなたの温もりが残っている今日の内にしてほしい。恵子は夜中でも待ってます。
恵子は浴室のドアを開けた。珈琲の香りが漂ってくる。お手伝いの洋子さんが淹れてくれている。
恵子が顔を出すとお手伝いさんが「おじゃましています」と挨拶をしながら、珈琲を持ってきてくれた。
お手伝いの洋子は、もう5年も通ってくれている。最初は、お掃除とお洗濯を頼んでいたが、彼女は元美容室で働いていたことが分かって、着付も手伝ってもらうようになり、それから恵子は和服一辺倒になった。
「今日はねえ、美容院へ行く時間がなかったの。だから髪の方もちょっと手伝ってね。」
「分かりました。」
恵子は鏡の前に座った。そしてチラチラと電話の方を見る。
「お電話がかかってくるんですか?」
「たぶんね。」
「恋人ですか?」
「エッ! どうして?」
「お仕事でしたら『かかってくる』でしょう。『たぶん』でしたらお友達か、・・・・・・でしょう。ですから、言ってみたんです。」
「ふふふ。」
「当たってましたでしょう。」
「さあ、どうかしら。洋子さん、今日はこちらのお着物にしたいわ。」
恵子が迷わず指差したのは、花嫁衣装のような純白の綸子だった。京都の着物屋に作らせてから、まだ一度も袖を通していない。
恵子は襦袢を着た。伊達襟には紅の線が小粋にスーと入っている。そして洋子に手伝ってもらいながら、純白の綸子を身にまとい始めた。帯は濃紺、純白の綸子によく合っていた。
恵子は鏡を見ながら、今日のために作った着物のような気がした。
洋子が言った。「かわいらしくて、よくお似合いですよ。」それはお世辞でも何でもなかった。「こんなにきれいな方に着てもらえて、お着物も喜んでいますよ。きっと。」
「嬉しいわ。」恵子は素直に喜んでいた。
しかし支度をしている間、電話のベルは鳴らなかった。
恵子はすこしだけ不安をいだきながら、7時過ぎにマンションを出た。
出て行く恵子に洋子が娘でも見るように優しく声をかけた。「恵子さん、」
「はい?」
「今日は特におきれいですよ。行ってらっしゃいませ。」
「ありがと。」恵子は洋子の見送りの言葉を「吉」と感じた。
恵子が出勤した後、お手伝いの洋子は部屋の掃除と洗濯、洗い物などをして帰って行く。これが彼女の日課だった。
野中は自宅でレポート用紙に対していた。山本先生から言われた「詰めが甘い」というのは、どういうことだろうか?
そう考えながらも、心の半分以上は恵子に奪われていた。起き上ってレポートを眺めたり、また寝転んでは恵子の姿を思い浮かべたり。時計を見ると、まだ12時前、彼女があのマンションに帰るのは、早くて1時過ぎだろう。
野中は恵子のことを想っているうちに、珈琲を飲みたくなった。野中は湯を沸かすために台所に行って、ガスに火を点け、キャラバン珈琲の豆をミルで挽いた。〔キャラバン〕の親父は「珈琲好きは、飲むこと、淹れること、知識を学ぶこと、全部マスターしなくては」と言って。淹れ方も教えてくれた。親父の淹れ方はアクを出さない方法だった。だから味はスッキリしていた。
香りが狭い部屋に渦となった。野中は一口含んで、「ふゝ」と吐息をついた。〔らんぶる珈琲〕と自分が淹れた〔キャラバン珈琲〕はまったく別物の味がする。それでも、これからは珈琲を飲む度に恵子のことを想うだろうと思った。
野中は時計を見た。まだ12時半だ。野中はまたレポートに目を移した。先生は、最初の時『タテ社会の人間関係』を提示してくれた。もしかしたら、ヒントは優れた著書にあるのではないかと思った。野中は本棚を見た。オー・ヘンリーの短編集が目にとまったので、頁をめくった。「詰めが甘い」と言われたので、結末だけに目を通してみた。いずれの短編も、唸るほどにキチッと締まっていた。
「これか・・・・・・」タイトルとエンドが直結していた。これが作者の言いたいことかと思ったとき、何かが見えてきた。
野中は時計を見た。1時10分。野中は受話器をとってダイアルを回した。「30歳にもなって、オレは何をしているんだろう」との迷いが過った。呼び出し音が鳴っている。胸が高鳴る。これは間違いなくオレの三度目の恋だと野中は思った。
恵子はいつもより早めに帰宅した。お手伝いさんが淹れておいてくれた珈琲を少し飲んで、それから帯を解き、裸になってゆったりとバスに横たわっていた。
浴室のドアは開けたままにしていた。
そこへ電話が鳴った。りりん・りりん・りりん・・・。
恵子は濡れたまま飛び出し、奪うようにして受話器を取って耳に当てた。
「もしもし、」「野中さん、」
「もしもし、」「恵子さん、」
(やっぱり今日中に電話をくれた! よかった♪)
「野中です。」「今、何してたの?」
「恵子です。」「お風呂に入った後、休んでいたの。」さすがに裸のままだとはまだ野中には言えなかった。「ちょっと待ってもらっていい? 電話を寝室に持って行くから、」
「いいよ。」
恵子は大急ぎでバスタオルを取ってきて、電話をベッドまで持っていった。「ごめんね。」
ベッドの頭の棚には、〔小竹〕の杯が二つ仲良く並んでいた。恵子は杯の縁をそっと指で摩りながら、「お電話をくれてありがとう」と言った。
それから二人は今日一日の出来事を語り合った。それは今日という日を記憶に深く留めたいという気持からくるのかもしれなかったが、とくに恵子とっては「今日から、もう泣かない」と密かに決めた日でもあった。
「神様は、どんな死でも許してくれます。」野中さんと一緒だったから、この救いの言葉に出会うことができた。恵子は、そう信じていた。だから、電話がかかってきたら、野中に告白しなければならない言葉をかかえていた。
恵子への思いが強くなっていた野中であるが、まだ気持の方は整理がついていなかった。それでも恵子の気持に応えなければならないことは分かっていた。
恵子は電話番号を書いたメモを渡してくれた。それは「電話をしてほしい」という気持の表れだ。野中は恵子と唇を合わせた。だったら今日のうちにきちんと「好きだ」と伝えなければ、と思っていた。
野中はかつての苦い経験が頭をかすめた。5年前の由利子との失敗は彼女の気持を汲まず、自分が逃げたところにあった。
由利子はダンス教室の教師であった。彼女と野中は2年ほど付合っていた。気持の中では、そろそろ一緒になってもいいと思っていた。
その年の夏、田舎の柳川に帰ろうと思ったとき、唐津出身の由利子にも「一緒に行こうか」と誘った。由利子は承諾し、野中の前に晴れやかな笑顔で現れた。幅広い白の帽子、白いワンピース、真珠のネックレスに白いハイヒール。羽田の客がみんな見ていた。野中は満足だった。機内の2時間も楽しかった。由利子に約束こそしていなかったが、このまま実家に連れて行こうかとも考えた。迷ったまま、飛行機は福岡空港に着いた。ここでもみんな由利子のことを見ていた。そんなとき、高校の同級だった女性とばったりあった。「あ、野中くん。」彼女は幼子の手を握り、背中には赤児を負ぶっていた。弟の帰郷を迎えに来たのだという。野中は由利子を紹介した。同級生だった彼女は頭を軽く動かしたものの「何、この女」という目でチラリと見ただけだった。野中はショックを受けた。空港で由利子とお茶を飲んだとき、「田舎の市役所勤めの両親が、この由利子を認めてくれるだろうか?」そう思うと、西洋人の血が入っていると言っていた由利子の存在が段々遠く見えてきた。野中は福岡空港で由利子と別れた。東京に戻ってから由利子に電話しても由利子はもう電話口には出てくれなかった。由利子は「裏切られた」と思ったにちがいなかった。
「ね。ラジオで、『神様は、どんな死でも許してくれます。』って言ってたでしょう?」電話から恵子の声が聞こえる。
「うん。」
「私、あのとき、深い言葉だなって思ったの。」
野中は恵子を初めて見たとき、遠くて手の届きそうにもない女だと思った。しかし、〔バッハ〕で珈琲を飲んだとき、〔小竹〕のカウンターに並んで座っているとき、野中は恵子に温もり以上のものを感じ初め、そして鮨屋ではあんな姉さんぶってた彼女が、すっかりしおれて車に乗ってきたときは「何て可愛い女だ」と思うようになっていた。
野中は、車の中で嗚咽していた恵子の姿を想い浮かべた。あのとき野中は、恵子に対して尊敬心のようなものとたまらない愛おしさを感じた。そして見つめる恵子の瞳に吸い込まれるままに抱きしめた。そのとたん、自分は最初から恵子が好きだったのだと気付いた。野中は、25歳のとき由利子から逃げた。もっと遡れば実ることのなかった20歳の初恋では、投げやりになったこともあった。だから、長い時間、恵子と抱き合っているうちに、恵子と気持が通じ合えた喜びを感じていた。そして救われたのは自分の方だと思った。
野中は電話口で言った。「ぼくはきみを離したくない!」本気だった。
「・・・・・・、」
「もしもし、聞いてる?」
恵子は目頭を指で押さえていた。「はい。ちゃんと聞いています。」恵子は野中と気持が通じ合えたことで舞い上がりたいほどだった。
恵子は受話器を抱きしめながら甘えるようにして言った。「ンもう、私が言おうと思っていたのに、」
「えっ!」
「恵子は野中さんのことが、大好きって♪」これまで恵子は男に愛を告白したことなど一度もなかった。
「・・・・・・。」
「ねえ、いつから?」
「ん?」
「私のことを好きになったのは?」
「初めて〔バッハ〕で珈琲を飲んだとき、」
「そう。私は最初にお店でお会いした時からよ、」
「えっ、」
「ふふ、」
電話だからできる他愛もない話、それが今の二人には大切であった。34歳と30歳の遅い恋、時間を埋め合わせるかのように二人は夜明けまで受話器を離さなかった。外には春がもうそこまできていた。
(Ⅵへ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる 作〕