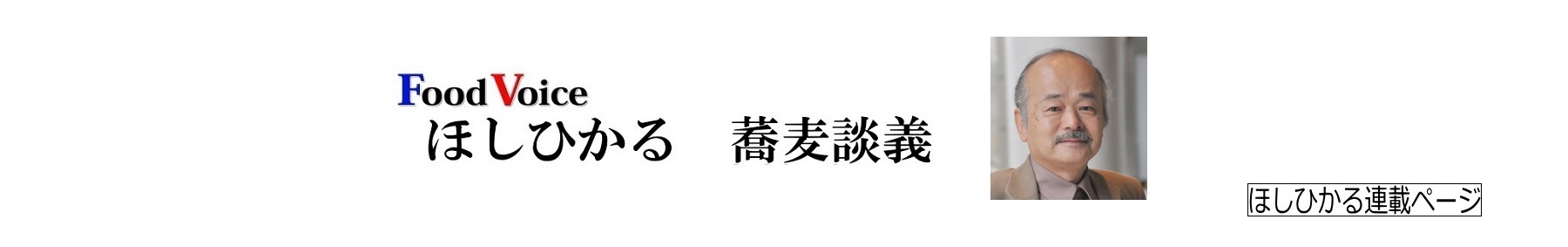第309話 小説「コーヒー・ブルース-Ⅵ」
2025/12/06
~ Mr.Wonderful♪ ~
野中健は眠い目を擦りながら、アパートを出た。といっても、不愉快さはなくむしろ幸せな寝不足だった。ただ、東京消防病院の山本部長との約束のレポートの最後の詰めができていなかった。
野中は、まず会社に顔を出した。
後輩の鈴木が「ノナ課長、助けて」と言ってきた。
「何だよ。」
「キリスト大の数字がサッパリなんですよ。」
「そうか。じゃ、オレに戻せよ。」
「ほんとですか。でもな~、まだ代わって間もないですから、も少しやってみますよ。」
「そうか。」
「山田教授も、野中さんはどうしている? っておっしゃってますよ。」
(〔クラブ恵子〕には行ったか?) と野中は訊きたくもあったが、止めた。恵子は野中に仕事のことは一切話をしない。その姿勢を尊重しなければと思っていたからだった。
鈴木の同期の佐藤もやって来た。「ノナ先輩、久しぶりじゃないですか。」
「お、調子はどうだい。」
「バッチリですよ。先輩、中村病院の由美ちゃん先生、覚えてますか?」
「覚えているさ、可愛子ちゃんだろ。」
「あの子、結婚するそうですよ。」
「やっぱりな。」
「課長、好みだったでしょ。」
「まあな。」
「誰、だれ、ダレ?」と鈴木が間に入ってくる。
「高橋先生や松本先生は、相変わらずか?」
佐藤がそうだと首を振り「先輩、どうですか、ひとつ、」
「オレはお得意様はお得意様だよ。」
「そんな硬いこと言ってるから、ヨメさんが来ないですよ。」
「まあな、それは認める。」
「え~、課長、今日はえらく素直ですね。」
「ハハハ、」
皆、バカを言い合ってから外に出る。そしてお客さんの前に出たら、真剣勝負となる。
野中は他の担当病院を巡ってから、消防病院へ向かった。
〔スカイライン〕のハンドルを握りながら、鈴木が困っているキリスト大病院をどうしよかとも考えた。これで少しはオレの言うことを病院部長は分かってくれただろうかとも思ったが、無理だなと思い直した。牧田常務はどうだろうか? なんてことも考えてみた。
このとき「ン!」と一瞬閃いたことがあった。
「何のために、山本部長はレポートを会社に出せと言ってるのだろうか? このレポートの内容はアメリカ学会のことだけではない。将来の疾病予測がメインである。医者でありながら、そういう面にも視点をもっている医師=人材を会社の役に立たせろと言ってるのだろうか。だったら、オレが書くレポートは、オレが会社に山本先生を利用しろ、と提案することになる。そうか。それがレポートの目的なのか!」
野中は喫茶店を探して車を停め、書きかけのレポート用紙を持って店に入り、考察の箇所を書き直した。野中の書いたことは、当社は〔大学病院戦略プロジェクト〕のようなチーム結成が必須で、そこでは日本の医療界を牛耳るようなトップクラスの医師などを登録し、その活用を練るいわば頂上攻略を企画するというものであった。たとえば、キリスト大病院とか、あの河村医師の問題とかは、営業マン個人の問題ではなく、会社として取り組むべきだ。そんなことだが、その全てを書くわけにはいかなかったが、背景にはそのようなニュアンスを滲ませた。
すぐに病院の部長室の戸を叩いた。午前中の診療が終わったばかりの山本部長は部屋にいた。
野中はレポートを出した。
山本はレポートに目を通して「いいじゃないか。レポートは、いやエッセイや、小説だって、作者は何を言いたいか、何をやりたいかが大事だ」と言った。
「はい。」
「ところで、このレポートは会社の誰に出すつもりかね?」
「は?」
「ぼくは君の会社の人を知らない。しかし、せっかくの意見だが、たいていの人はこれをもらってもすぐ屑箱行きだよ。聞き入れてくれそうな人を探さなければ。もちろん組織というものがあるから、それを無視するわけにはいかないだろう。それに提出したからといって、すぐに実現できると思ったら大間違いだ。それが現実だ。だからこそ遣り甲斐がある。」
そう言い残して、部長は病室へ行った。
(何というドクターか。) 野中は舌を巻いた。
野中は遠藤医師を探した。休憩室を覘くと彼女は秘書の上村といた。
「何を話していたんですか?」
「秘密の話よ。」遠藤医師が笑う。
「お茶飲みますか?」上村も笑いながら、支度をしてくれる。
「先日、たまたま銀座に行きましたから〔生粉打ち亭〕でお蕎麦を食べてきましたよ。」
「美味しかったでしょ。」
上村が言う。「〔生粉打ち亭〕? どこかで聞いたことがありますよ。」
「池袋でしょ。」
「そうそう、東池袋にありました。」
「銀座の菊地さんの師匠らしいわ。ところで、野中さん!」
「はい。」
「上村さんに、誰かいい人いない? 早くお嫁に行きなさいって言ってたの。私みたいに行きそびれないうちに、」
こういう話は、独身の営業マンにはタブーである。
なのに、遠藤医師はかまわず続ける。「出産適齢は20歳から25歳、せいぜい30歳まで、なんて厳しい話をしてたわけよ。」
野中は (女性どうしの話はシビアだな) と思ったが、口は出せない。
上村が照れたように言う。「私、クリスマス(25歳)はとうに過ぎたんです。」
野中は黙っていた。下手をすれば、火の粉が飛んでくる。タイミングを見て、帰った方がよさそうだと思ったとき、直球が飛んできた。
「野中さん、どう?」
(そら来た。)「いやいや、」と言って、ごまかすしかない。
それを聞いた上村は、「エーン、また振られたあ」と泣き真似しながら、部屋から出て行った。
(助かった。)
遠藤医師は大笑いしている。
野中は何となく恵子に電話したい気持になったが、公衆電話の前には2人が順番を待っている。(また夜にするか。)
野中は病院を出て、池袋にあるという〔生粉打ち亭〕に向かった。住所は、先ほど公衆電話の所に置いてある電話帳で確認していた。
小さいことでも拾っていく。これが野中の営業のやり方の一つだった。似たような台詞を松本清張の小説に出会ったことがあるが、そのときに刑事と営業は同じだと思ったこともあった。
店は分かりづらい所ではあったが、野中はすぐ分かった。営業マンは番地探しには慣れている。都内の場合、皇居から若い番地が始まる。
昼時が過ぎていたから、店は空いていた。お品書を見ると、この店も〔江戸蕎麦〕〔津軽蕎麦〕とある。
遠藤先生はここの店主が師匠だといっていたが、なるほどコシと喉越しがいい。野中はいつものようにツル・ツル・ツル・・・と見事に啜った。
店主が湯桶を持って出てきた。
野中は、銀座の菊地さんと同じじゃないかと思うと可笑しかった。
「お客さん、気持よさそうに喰ってくれるね。」
野中は苦笑しながら頷いて、「菊地さんの所へ行ったら、こちらが師匠と聞いたから、」と応えた。
「ああ、あいつの店に行ってくれたの。」
「この〔江戸蕎麦〕と〔津軽蕎麦〕って何ですか?」
「オレは人形町の生まれ、細くて、喉越しがいい二八の、江戸の蕎麦を〔江戸蕎麦〕って名付けたわけよ。で、津軽は女房の田舎、そこに呉汁といって大豆でつないだ〔津軽蕎麦〕が風前の灯みたいに生き残っているのよ。だから、オレが命をつないでやってるわけさ。」
「へえ、えらいね。」
「褒められちゃ、放っとけないな。サービスしてやるから、喰ってみるかい。」
「えっ、いいんですか。」
そんなことから、ときどき通うようになったが、野中は〔江戸蕎麦〕の方が好みだった。店主にそれを言うと、「そりゃ、当たりめえだ。〔江戸蕎麦〕が世界で一番だよ」と高笑いし、急に声を落として〔津軽蕎麦〕は女房の親父にならったから、親孝行でやってるのさ」と囁いた。
店を出た野中は、やはりレポートは牧田常務に出した方がいいなと思った。ただし、組織を無視するわけにはいかない。だから常務が病院部に見えたときに部長に渡そう。
そのときはすぐにきた。2日後、野中がいるとき、牧田常務が病院部に顔を出した。野中はこれまでの経緯を報告してレポートを鞄から取り出し、病院部長に差し出した。部長はすぐに常務へ渡した。
「分かった。じっくり読ませてもらうよ。だが、読まなくても分かっていることがある。このレポートを書くにあたっては、野中君はずいぶん勉強しただろうから、一番実になったのは野中君自身だ。それが大きいと思うよ。ナ、部長。」
「はい。おっしゃる通りだと思います。」部長はニコニコ顔で相槌を打った。
しかし野中は、自分の方を向いたときの部長の目が、あの大村病院の事務局長に似て妙に湿気を帯びていたのを見逃さなかった。
(Ⅶ. Lovin’you へ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕