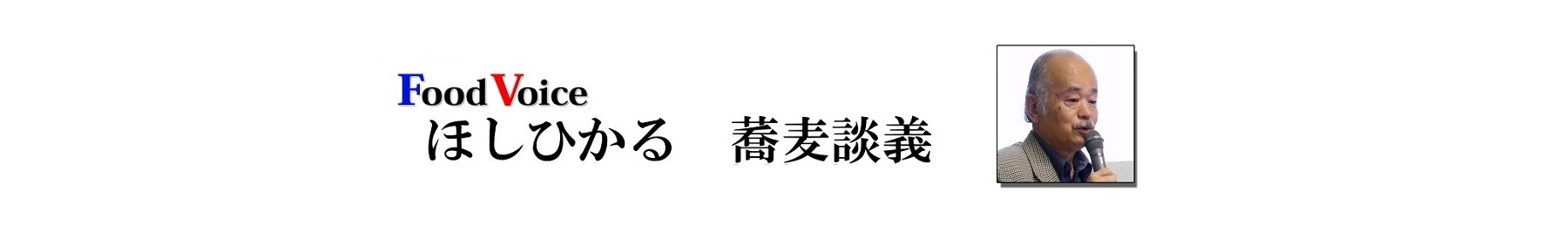第340話 小説「コーヒー・ブルース- XVI」
2021/11/12
~ Bridge Over Troubled Water ♪ ~
昼の時間になっても、古賀はコンピューターの画面に集中していた。野中は声を掛けるのを躊躇い、一人で外へ出た。
すると、「野中さ~ん。」後から女子社員の小林が明るい声で呼ぶ。
野中は足を止めて、振り向いた。
それを見て、小林は転がるように走って来た。「お昼でしょ、何処で食べるんですか?」
「別に決めてないよ。」野中はそう言って、小林と並んで歩き始めた。
「社長とご一緒のときはいつも蕎麦屋さんでしょう。」
「小林さんはどこで?」
「いつもはお弁当。今朝は子供が熱を出したので、作る時間がなかったの。」
「あらら、お子さん大丈夫?」
「ええ、母が見てくれていますから、安心です。」
「そう。」小林はいつも明るい。だからなのか、「安心です」という言葉も本当に安心に聞こえる。
「そこの喫茶店のランチにしましょうか。」
二人は店に入って席に座った。
他にも社員が何組か入っていた。
「社長さんのお相手も大変ね。」
「そんなことないよ。面白いよ。」
「あの社長さんを面白いって言うのは、さすがね。」
「そうお?」
「見ていると営業畑の人は、事務系と何か違うね。」
「そうかね。」
「楽観的っていうか、余裕があるというか、そんな感じの人が多いわ。」
「はは。営業なんて内勤に入ったら、陸の上の河童みたいなもんだよ。」
「河童! おかしいッ」
「おれは小林さんみたいに、経理のできる人がうらやましいよ。内勤してみて分かったけど、営業出身の人間ってさ、何もできないんだなと思ったよ。」
「う~ん。そう言われればそうかもしれないけれど、内勤の人はみな自分のことで精いっぱいっていう感じで、営業出身の方たちのように話が上手じゃないわよ。」
「別に話上手でもないんだけどね。ただ聞いて、頷いているだけだよ。それが仕事みたいなもんだ。ま、たまに分からないときは質問するけれどね。」
「それだけ、そうかな? 私、営業経験できなくて10年損したって感じがしているのよ。」
「そりゃ、嬉しいこと言ってくれるな。そういえば、営業的勘というか、チャンスに飛び付く能力はあるかもしれないな。」
「それ、私が言いたかったのは、それよ。それって大切なことでしょ。だから、営業を経験しなくて、人生の10年損したって思うのよ。」
「へえ!」野中は、面白いことを言う女性だと思った。何かのときはスカウトしようか。と、そんな考えさえもった。
スカウトしたい人間がもう一人いた。それは後輩の佐藤である。野中は佐藤を飯に誘った。
古賀もそうだが、佐藤も野中を信頼してくれているところがある。そしてそれが野中に伝わってくる。だから野中もまた古賀や佐藤が信頼できる。
その佐藤が口を開いた。「ノナさん、何か見つかりましたか?」
「気にかけてくれてんのかい。」
「もちろんですよ。」
「ま、面白そうなのがあるけどな。」
「へえ。」
「コンピューターだよ。」
「え? ノナさんが、コンピューターですか?」
「そう思うだろ。おれ自身もよくそんなものに関心をもったな、と驚いている。」
「まったく縁がないような顔ですわ。」
「そう言うなよ。おれはサ、内勤になってから営業出身の者は何もできないということがよく分かった。もちろん技術的なことはわからない、薬事法もわからない、経理も分からない。」
「・・・・・・。」
「だけどな、世の中のことを勉強してると、その流れに乗っかる勘みたいなものが必要だと思うけど、営業員にはそれがある。と、小林さんが言っていた。」
「小林さんって、経理の?」
「そう。はは。」
「何ですか、それは。」
「うん。彼女は『営業を経験しなくて、10年損したって』って言っていた。」
「そりゃ、営業が重要っていうことじゃないですか。」
「うん。だけど、それは営業を離れたから、よく分かるっていうことなんだ。それを小林さんは女の直感みたいなことから言ったのかもしれない。」
「へえ。」
「とにかく、その勘から、コンピューター事業でもって医療界に役立てたいなと思っている。」
「へえ、野中先輩。役立てたいなんていう高尚な台詞使うようになったんですね。」
「高尚か、」
「格調高いな。」
「そうかい。佐藤、一回営業から出てみろよ。世の中面白いぞ。」
「そうですね。経理の女性の能力にまで目を向けるようになったノナさんもたいしたもんだと思いますよ。たしかに営業なんて何もできないくせにプライトだけは高く、内勤の人をバカにしているところがありますからね。」
「佐藤も冷静な目を持っているな。感心だ。」
「ノナさんは、オレに新規事業部へ来いって言ってるんですか?」
「はやい話、そういうことだよ。」
「何だ。マ、考えておきますよ。」佐藤はなぜかニヤリと笑いながら答えた。
古賀たちが進めているシステムのうちのレセプト・システムは最終詰の段階にきていた。しかしその最終段階というのが曲者で、『最終段階』そのモノが見えないのだそうだ。何百回もテストをやって、バグという欠陥を見つけては、修正していくのだが、何回テストをすれば終了だということが判らないという。
野中は聞いて、呆れ顔になった。「終わりが見えない、なんて。見切りは付けられないのか?」
「これで終わったかなと思ったら、またドドドッって出てくるんですよ。」古賀も少々イラつき気味である。
「グラフッィスック・システムもそうなのか?」
「いや、そっちは絵ですから、完成が見えます。」
「じゃ、そっちはテストしなけりゃな。」
「そうなんです。ですけど、レセプトも医療機関で実際、動かしてみた方がいいでしょう。」
「どうすりゃいい?」
「野中さんの顔の利く医療機関を紹介してください。」
「そりゃ簡単だよ。日数は?」
「少なくとも2週間、できれば3週間。」
「担当者を決めなきゃいかんだろ」
「最初だから、私が担当します。」
「それから、本当は多くのデータが取れる医療機関がいいだろうけど、最初だから少な目でやってみよう。日数も2週間でいいかい。」
「はい。」
「明日、心当たりを回ってみるよ。」
「お願いします。」
野中はテストに入ることを報告するために、社長室に入った。
小田社長は、野中の報告を聴いてから、ノートを開いた。
そこには「お客様は誰?」と大きく書いてあった。もちろん社長の字である。
「野中。『われわれの商売のお客様は誰だ』ということを念頭においておかなければならんぞ。」
いつも言われていることである。
「製薬会社のお客は医者ではない。『病人だ』と言えば『そんなことは分かっています』と言いたいだろうが、もっといえば製薬会社のお客は、病気だと思えばいい。分かるな。」
「はい。」
「仕事にはいつもお客がいることを忘れるな。飛行機、電車、バス、タクシー会社のお客は乗客や旅行者ではない。『尊い人命』がお客だ。だから危険な運転はしてはいけない。それじゃ、野中たちが、これからやろうとしている事業のお客は何だ?」
「・・・・・・!」
「患者だ、というのは当たり前だ。患者の何なのだ。納得か? 安心か? それを医者と共有するのだ!」
「共有?」
「そうだ。野中は新しいことをやろうとしているのだ。今までのような製薬会社と医者の関係は捨てろ。製薬会社と医者の新しい関係を創るのだ。それが見つかれば成功する。やれ!」
ここが社長の凄さである。新しい事業には、新しい商品以外に、何か新しい関係とか、新しいシステムを開発しろというのである。これは責任者である自分の仕事だろう。野中はそう思った。
「いいか。できそこないの僕だって、この会社を立派に創ることができた。優秀な君たちなら、必ずできる。」
社長に「できそない」と言われると困るが、勇気づけようとしている気持は痛いほど分かる。
「人生や世の中や仕事は困難ではない。君たちが困難だと思っているに過ぎん。君たちがそうした考えを変えるなら、絶対できる。やれ!」
社長室に入った新規事業部の者は、社長に檄を飛ばされ、勇気を得て社長室から出てくる。まるで勇者の映画を観たあとのような顔をして出て来る。他の部署の人間たちはそれが羨ましくもあるから、わざと冷やかな視線をおくったりする。
サラーマンの野中もそうしたみんなの感情は理解できる。だが今は、人から何と思われようとも、走り始めた道を走るしかない。
野中は、アルバイト先の遠藤医師を訪ねた。まだテスト段階であるから小規模な医療機関が望ましいと考え、遠藤医師のアルバイト先の院長に開発中のシステムを預けられるかどうかを探ったのであるが、やはり野中たちの考えを理解してもらうのは無理なようであった。木村病院の院長のように先進的な考えをもった医師はまだ少ない。
野中は、遠藤医師と一緒に〔生粉打ち亭〕で蕎麦を食べてから、〔ぱうりすた〕に行って一人で珈琲を飲んだ。
ここも恵子と立ち寄った珈琲店の一つであった。恵子と健のデイトは美術館巡りかコンサート、そしてその後に行くのは食事か、珈琲の店であった。水商売の女性と営業員の男は酒が仕事だともいえるせいか、二人が外で飲むことはあまりなかった。
店内の壁には、コーヒー農園で働く農夫を画いた銅盤が飾ってあった。画のタッチはゴッホのようで、雰囲気はコーギャンの世界のようだった。
(恵子に、会いたい。) 健は珈琲碗の縁が恵子の唇に思えてきた。
野中は、煙草一本吸ってから、店を出た。
進取的な医師でなくとも、システムのテストをしてくれそうな親しい医師は何人もいる。今度は彼らを訪ねてみよう。そして説得してみようと思った。小田社長の言う新しい関係も作らなければならない・・・・・・。
恵子はトミーというカメラマンとエリザベスの三人でランチをとっていた。
トミーはまだ20代、ややアナーキーな風貌をしていた。彼は多くのファション誌と契約を結んでいたが、まだトップページを飾るまでにはいたっていなかった。
「トミーは写真の腕はいいけれど、ちょっと変人だから、ディナーではなくランチにしましょう。」そう言って、エリザベスは南米系のレストランへ案内してくれた。
店の壁には、農園で働く農夫の油画が飾ってあった。筆のタッチは土俗的だ。
恵子は思った。 (この画は、健と行った銀座の珈琲店に飾ってあった画と似ているわ。) 画に見入りながら恵子は呟いた。「ああ、あの人は今ごろどうしているのだろう。会いたいなあ。」
そんな恵子に、エリザベスが声を掛ける。「もし、トミーが『ケイコの写真を撮りたい』なんてと言ったら、断るのよ。」
「え!」恵子はわれにかえって、頷いた。エリザベスの心遣いは日本人より細やかだ。恵子はありがたいと思った。
トミーが来て、食事が始まった。
エリザベスがトミーに語りかける。「トミーの世界は美的にリアルよね。」
「そうさ、ファション写真では、カメラマンは主張できない。ファッションが主役だからね。とはいっても現実生活の写真ではつまらない。そこでオレは、夢の世界と現実の世界の境界線をなくすところを工夫したのさ。」
恵子にも、ファション写真は芸術じゃないことぐらいは分かっていた。だから、 (すごくまともな答ではないか) と思った。
ところが、トミーは「女の一番美しい姿はファッションじゃない。ヌードだ」ときた。
すかさずエリザベスが「ケイコはダメよ。今が一番大事なときだから」とピシッとトミーを制した。そして付け加えた。「そうであっても、トミーのような素晴らしいカメラマンがいて、ファッションは世界に広がるのよ。」
エリザベスも上手い。トミーは満更でもないような顔をして頷く。
(雑誌のエディターと同じように、カメラマンも流行をつくる人たちなんだ。) 恵子はエリザベスがカメラマンと会わせてくれた意味を理解した。
「トミーはね、レンズに映るファションモデルの、その奥のヌードを想像しながら撮っているのよ。」
「え~!」
「ファッションは素晴らしいわ。だけれどファッションって何だろう? ということも頭に入れておかなければならないのよ。『ヌード、ヌード』と言っている変わり者のトミーは『たかが、ファッションじゃないか』ということを教えてくれるの。ただし彼は危ないから、それだけ知れば、あとは近づかない方がいいわね。ほほほ。」
その夜、トミーというカメラマンと話したことを健への手紙に書いた。後日の、健からの返信には「おれの従兄にカメラマンがいるけど、カメラマンにはプレイボーイが多いと聞いているから、気を付けてくれ」とあった。
恵子は (あの人が妬いてくれている) と嬉しそうに微笑んだ。
今日は、前々からエリザベスと約束をしていたアンダーウェアのショウを見学した。
下着だけのモデルたちが、舞台の上で颯爽と闊歩する。デザインの良さもさることながら、カッコいいとしか言いようがない。(どうして彼女たちはああも誇り高い顔をしているのだろう?) その上、セクシーである。女性でも、見ていて興奮してくる。
夜になって、恵子はアパートメントに戻った。
ポストに桃子姐さんからの手紙が入っていた。開封すると、それには「ニューヨークへ行く」と書いてあった。カレンダーを見ると、もう来週のことである。恵子は嬉しくなった。もちろんエリザベスは親切で信頼できる人であったが、今の恵子にとって日本人の来米は、まるで親類の者が来てくれるような大きな安心感があるのであった。
恵子はバスに入った。鏡に映る裸身、だいぶお腹が大きくなってきた。あと四カ月で出産だ。よく頑張ってきたと思う。桃子姐さんがやって来て、今の恵子を見たら何て言うだろう。イヤ、あの人が今、ここにいたらさぞかし驚くだろう。
恵子はバスタオルで裸身を包んだ。それからバスルームを出て、ベッドの端に座った。このとき、恵子は思わずクスッと微笑んだ。健が言ったことを思い出したからだった。
健は、恵子の下着を脱がせるとき、「女性の着物の下着は男のためだな。」と言ったことがある。
恵子が「どうして?」と尋ねると、「ブラジャーは外すのが大変だけど、長襦袢は簡単、しかも楽しみだよ。」と笑って言った。
「なにそれ!」と恵子は呆れたことがあったのを思い出しながら、健の台詞がいかにポイントを突いているかが、分かったような気がした。
今日のアンダーウェアのショーを振り返っても、和服と洋服はまったく基本がちがっている。ブラジャーは乳房そのものをスッポリ被せるように立体的にデザインされている。ドレスだって肉体の線に合わせて作る。しかし、和服はどうだろう。このバスタオルと同じで、身体を布で巻いているだけだ。ショーの最中に、エリザベスは言った。「蝶のような装いでも、装いは科学なのよ」と。
恵子は「ファッションをやるなら、デザインから勉強しなければ・・・・・・。」との考えがわいてきた。
恵子は、桃子姐さんに「何でも一人で決めてきたのね」と言われたことがあったが、そうでもないと思った。〔クラブ恵子〕を立ち上げるときは、明子ママの言葉をよく聞いた。そして今は、あの人に頼り切っているようなところがあると思った。
恵子は、大事そうにしてお腹をさすりながら、また健のことを考えた。
(あの人は、新規の事業を探していたけど、うまく見つかったかしら。そもそもあの人にはどういうお仕事が似合うのかしら? サラリーマン? 独立? 少なくともあの人は平取は似合わないわ。部下や後輩の面倒見はいいけど、上司へのゴマスリは苦手みたい。) そう思って、恵子はまた微笑んだ。(父と健は似ているのかしら? もし似ているとしたら、あの人も教育者がいいのかしら。)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕