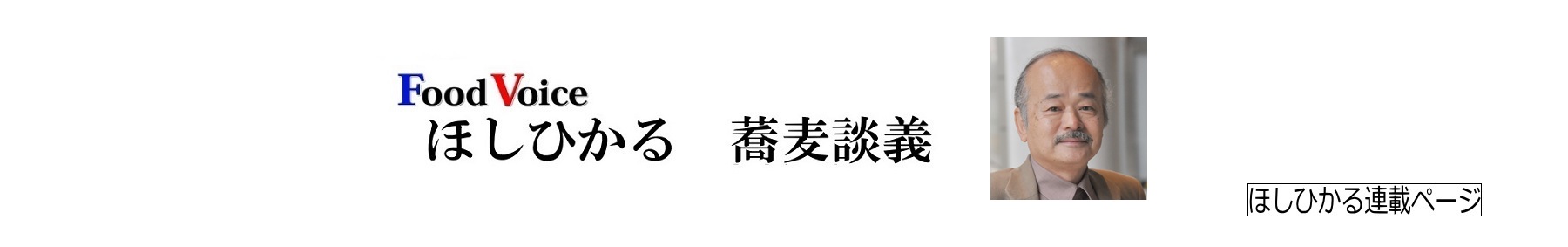第365話 お蕎麦のレストラン
2025/12/06
= 江戸蕎麦+東京蕎麦 =
ずっと以前に、作家の山口瞳(1926~95)が「寿司屋とソバ屋と、酒場(赤提灯)と喫茶店、これを一軒ずつ知っていれば、あとはもういらない」と述べていた。当時の人(男性サラリーマンだろう)の、ごくごく普通の日常生活を上手く描いていると思ったことがあった。
ただし「気楽に無駄話のできる喫茶店があるというのは、とても嬉しいことだ。」と続けてあったが、今のファスト・コーヒー・ショップにはそういう雰囲気はない。そこは友人と無駄話をする所ではなく、スマホを相手に一人で座る店のようである。
ことほどさように、赤提灯、寿司屋、蕎麦屋も中身が変化してきていると思われる。少し前の赤提灯はおでんが多かったけれど、それをコンビニが売るようになってから街のおでん屋は壊滅し、具や味も変わってきた。また寿司は世界的に知られるようになり、高級職人店と大衆チェーン店に二極化してしまった。
さて、蕎麦屋はどうだろう? 先日おじゃました「孤丘」(与野)の店主は「お客さんの数は年々1割ずつ増えている。しかも、恋人どうし、夫婦、家族が多くなってきた」と言われる。この傾向は、「ほそ川」(両国: 江戸ソバリエ講師)や、「一東庵」(東十条)や、「流石」(銀座)などあちこちの蕎麦屋でも同じである。
まさに、蕎麦屋さんが和食レストランの代表に成りつつあるというのが、私の感想である。
そこで、あらためて現代の街を眺めると、以前にも増して全景食事処ばかりであるが、ほとんどが企業経営の店である。その結果、家内事業である鰻屋、天麩羅屋、定食屋、そして寿司屋、和食の店が消えてしまった。そんな中で唯一健在しているのが、蕎麦屋というわけだ。
「家内事業」というのは「錦町更科」(神田錦町)の堀井市朗さん(江戸ソバリエ講師)の考え方であるが、今風にいう「オーナーシェフの店」もそれだろう。
一方の、企業が経営する店は、それなりに味も追及しているだろうが、優先するのは効率である。だから、客までもが合理性の対象になっているようなところがある。それがイヤで、「オーナーシェフの店」=「家内事業」の店に足を運びたくなる。
じゃ、何処へ行こうか? と見回してみると、たとえば蕎麦屋がある。それは400年の伝統に支えられた馴染み性もある。焼海苔や板わさなど簡単な物もある。一品料理もある。天麩羅も美味しい、お酒もいいのを揃えている。最後に蕎麦で〆て、満足。しかも、最近の蕎麦屋さんは小奇麗になってきた。というわけで、人気が出てきているように思う。
そうした蕎麦屋は献立にもリズムがある。たとえば、「大門更科」(大門)「無庵」(立川)「玉江」(駒込)などでは、1. 蕎麦の実、2. 蕎麦粉、3. 蕎麦麺(冷、温、揚)、4. 蕎麦寿司や、様々な蕎麦料理を供してくれる。
蕎麦寿司というのは、いつから登場したのかは明らかではないが、幕末の江戸日本橋の「松露寿し」で《そば寿し》をやっていたというから、こうした「蕎麦尽しの献立」は昔からあったのだろう。
さらに現代では、日本酒ばかりではなく5. 蕎麦焼酎や、6. 蕎麦茶や、7. 甘味まで揃え、「蕎麦尽しの」間に、普通の料理も提供してくれる所もある。
いわば、下記のような移行、これが「お蕎麦のレストラン」の形である。
単品料理の「お品書き」蕎麦屋さん ⇒ コース料理の「お献立」蕎麦屋さん
ところで、こうした絵をとうに描いていた人がいた。「小松庵」(駒込: 江戸ソバリエ講師)の社長だ。
その思いを小松社長は「東京蕎麦」という言葉で表わし、お蕎麦のレストランを目指されていた。
われわれ江戸ソバリエが言う「江戸蕎麦」とは、江戸中期に完成した、現在の日本蕎麦を指しているが、その「江戸蕎麦」を食する現代人のライフスタイルを小松社長は「東京蕎麦」と表現したのであろう。
〔江戸ソバリエ認定委員長 ☆文・絵 ほしひかる〕