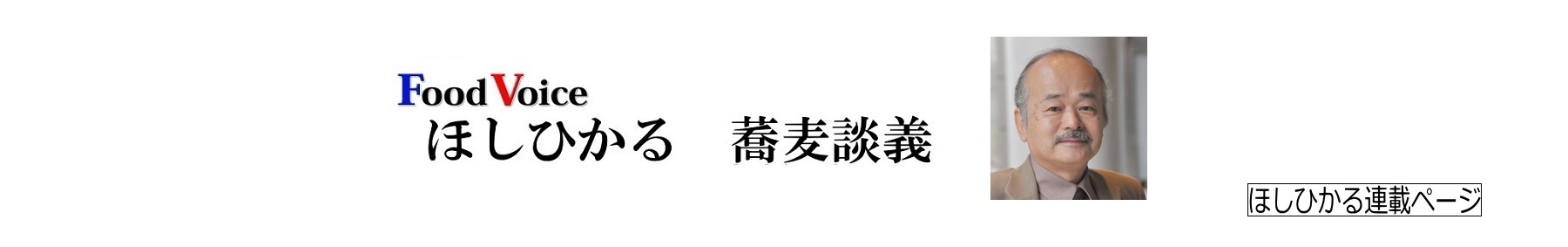第404話 美味しそうな絵を描きたい♪
2025/12/06
拙文の「蕎麦談義」を見ていただいている方から、401話の伊勢鳥居の絵についてコメントを頂いたので、今回は絵についてお話してみたいと思う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
話といっても、たいしたことはないが、言ってしまえば、自分の絵が下手であることを知っているから、できるだけそれ補おうと苦慮しているということだけである。
たとえば、日本の景色や物を描くときは顔彩、欧米のそれを描くときはアクリル絵具を使うようにしている。絵具の性質を利用しようというわけだ。自分では気に入っているが、何てことはない。よく考えれば、それは絵画の基本だろう。
ところで、日本の風景を描いていると、常に樹木や生茂る葉があることに気付いく。やはり、これが「日本」の特色だろうと妙に感心している。
ということで、じゃ、その樹木や葉をもっと自然に見えるように描けないかと思ったとき、偶々手元にコーヒーの飲み残しがあったので、いたずらに筆を付けて塗ってみた。「おっ、木肌の色として使えるじゃないか。しかも、何か、いい。」
それから、何回も重ね塗りをして濃淡を出したり、時にはコーヒーを煮詰めてみたりして、様々な茶色として使い分けるようになった。
笑われるかもしれないけれど、絵具は色が一定しているが、このコーヒーという絵具はその日によって、あるいは煮詰める回数によって違う色が誕生する。いいかえれば、昨日描いた木肌と今日描く木肌は微妙に違うのである。私はすっかり気に入ってしまった。
次は、緑色である。これさえモノにできれば、日本の風景の主役である二つの色を独自に手にすることができる。
そこで、緑色といえば、すぐ思い浮かべるのが、お抹茶である。
さっそく塗ってみた。きれいな緑だ。しかも、艶がある。「やったゾ!」
コーヒーで塗った木肌に、抹茶で塗った葉。自然にある色で自然を表現できたと小躍りして喜んだ。
ところが・・・! 翌日、あらためて見直すと、緑色が茶色に変化しているではないか。もう、がっかりなんでもんじゃない。塗り立ての緑がきれいだったから、かえってその落差は大きかった。夢砕かれた少年のように悄然となってしまった。以来、幻の緑色を探し続けているが、まだ見つからない。
さて、少し前に「コーヒー・ブルース」なる恋愛小説を書いたことがある。題名からしてコーヒーの絵は欠かせないだろうと何度が試みたが、あまり面白い絵ができなかったから、描いては破り捨てたりしていた。もちろん絵具としてコーヒーを使っていたが、何か足りない。
そんなとき偶々お中元にインスタント・コーヒーを頂いた。塗ってみた。すると、「おっ。コクがあって、いい。」
わが家では豆を挽いてドリップで淹れたコーヒーを飲んでいるため、絵具のとしてもそれを今まで使っていた。ところが、インスタント・コーヒーを絵具としたら、絵にコーヒーのコクが表現されたのである。たぶんインスタント豆の脂分が出ているのだろう。しかも、濃い物を使っているから、部屋中にコーヒーの香りがプンプン飛んでいる。美味しそうなコーヒーの絵になったと思った。
このとき、食べ物の絵は美しく描くことも必要だろうが、その前に美味しそうに描かなければということを痛感した。
ところが、世には美味しい絵というものをあまり見かけない。だから、食の世界では写真が多い。
とくにお蕎麦のイラストはひどい。しかもなぜか知らないが、お蕎麦もラーメンと同じように縮れて描いてあるから、なおひどい。まるでミミズである。
さて、このシリーズの402話では生牡蠣を描く必要性があった。
この場合、生牡蠣の何を描くべきか?
ひとつは牡蠣殻のあのゴツゴツした様、コジ開けるのに苦労する頑丈さだ。しかし、これは難しい。拙い技法しかない小生には大きな壁だ。とりあえず、20回ぐらい重塗りをして、その頑丈さを描こうとしたが、いい出来栄えではない。
もうひとつは牡蠣の生身を口に入れたときのヌルンとした感触だ。これを描くことができれば、美味しそうな絵になるかもしれない。
そう思って、「牡蠣は海のミルク」をヒントに、白の絵具を牛乳で溶いて、仕上げにスジャータを塗ってみた。塗立ての一瞬は、望む通りのヌルリとした食感が表現できていた。しかし乾きが速いからか、残念ながら写真ではそうは見えない。成績としては30~40点ぐらいだろうか。
トまあ、これまでは、刺身のつまみたいな挿絵だから、その解説まではあまりしなかったが、素人とはいえど、それなりに結構悪戦苦闘していることだけは事実である。
江戸時代の伊藤若冲は色の鮮やかさや深みを出すために、表からばかりではなく、布の裏からも塗っている。水の景色を描くことを得意とした江戸末期の広重は、当時ヨーロッパから伝来したばかりの「ベロ藍」を駆使して独特の「広重ブルー」を見出した。
若い女性の真珠のような美しい肌を描こうとして、天花粉を塗った藤田嗣治という洋画家もいる。
かように、天才だって苦闘している。ましてや才能のない凡人だ、七転八倒はとうぜんだろう。でも、考えようによってはそれも楽しみのひとつになっている。
〔文・挿絵 ☆ エッセイスト ほしひかる〕