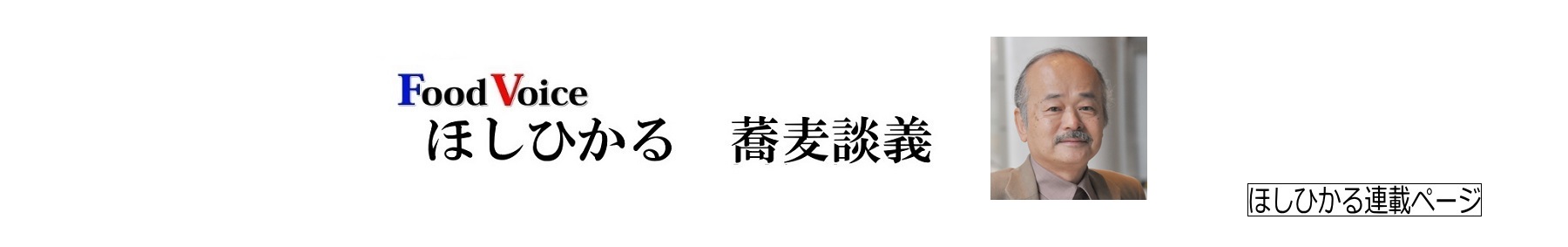第206話 美味しい勉強会
2025/12/06
《 蕎麦膳 》十三
グー先生こと林幸子先生(江戸ソバリエ講師)が、日本橋人形町の「酒亭きく家」で美味しい勉強会を開いた。
魚の切り方と、魚の炭火での焼き方と、盛付を習ってから美味しい料理を頂こうという趣向だった。だから「美味しい勉強会」だ。
細い路地を入ると、三味線の音が・・・と思ったら、猫の鳴き声だった。 でも、お店はいい雰囲気のする所にあった。谷崎潤一郎の生家はすぐ近くだが、彼の文学はこんな空気によって培われたのだろう。
さて、勉強会の方は、切り方組と、焼き方組に別れることになっていた。私は、和食の真髄は「切り」にあると思っているから、切り方組に入った。
☆片刃庖丁
厨房に入ると、見事な鯛が待っていた。
親方が鯛を俎板の上にのせた。そして「切る」とは言わず、「引く」とおっしゃる。そう、これが和食の特徴だ。
江戸ソバリエ協会・正式サイト→「国境なき江戸ソバリエたち」の、 ↓
http://www.edosobalier-kyokai.jp/kokkyou/kokkyou.html
稲澤敏行先生の「蕎麦の縁で出会った世界の庖丁たち」に紹介されているさまざまな片刃・両刃庖丁を見ていると、「日本は引いて切る」「中国は叩き切る」「西洋は押して切る」ということがよく分かる。
日本の料理が「切る」ことを大切にするようになったのは庖丁のお蔭、その庖丁文化は世界一切れる「刀」のお蔭である。
刀(カタ・ナ)の「ナ」は「薙ぐ」、「払って切る」の意であるが、もともとは片(カタ)刃(ハ)が語源である。
だから、日本の刀も庖丁もルーツはひとつで片刃である。
ヨーロッパの剣は鋼作りの両刃、日本の刀は軟鉄と鋼を鍛錬して作る片刃、といった製作から違う。
こうした屁理屈は、若いころから刀が趣味だったから、一通り知っている。
「きく家」の親方は切るところを見せながら、「優しく、引きなさい」と指導される。が、よく切れる庖丁だからこそ「優しく」て、いいのである。これが日本式の切り方となった。どこかの国の切れない刃物であれば、叩っ切るしかないだろう。
屁理屈が得意の私はこうしたことは理解できるが、その割には腕がまるでダメ。切った鯛があまりにも無残であったため、皆さんから笑われた。
☆活き締め
魚屋は「殺す」なんていう物騒な言葉は使わない。「締める」という。
「締める」というのはどちらかといえば、縁起のいい言葉かもしれない。 「閉会」といわずに「中締め」といったり、「一本締め」という言葉もある。「魚河岸の一本締め」という「シャン・シャン・シャン・・・」の一本締めは、売り手、買い手、魚の三者をま~るく一本で締めるということからきているらしい。
そういえば、宴会などでよく、いかにも・・・、という雰囲気まる出しのお兄さんがご指名されて「では、関東一本締めで」とか言って「チョン」とやったりするが、あれは元々は冗談・悪フザケから始まったことで、インチキだ。それを見かねた貫禄のある初老のオジさんが、前に出てきて、「そんなのは江戸にはない。やり直し」と言って「シャン・シャン・シャン、シャン・シャン・シャン、シャン・シャン・シャン・・・」と見事に三本で締めたことがある。
なるほど、これも比較するとよく分かる。 「チョン」のときはファストフードの立ち食いハンバーグのような後味だったが、三本締めの後は辺りが聖域となったような清らかな空気が流れる。だから、締めるのも簡単に考えてはいけない。
話を戻して、締め方は魚によって違うらしい。
平目や真鯛などは後にある魚の急所に手鉤を打込んで気絶させ、延髄や尾の付根に切目を入れて血抜をする。鮪は、延髄に螺旋状の針を入れて神経を壊し、さらに血抜をする。
自然死した魚より、活け締めした魚が長時間鮮度を保ち、味もよくなる方法として、いつのころからか、誰かが編み出した。おそらく、生活の中から自然に考え出されたのだろう。
☆食味
よく美味しさの表現として、五味七味+風味(臭覚)+食味(視覚、聴覚、触覚)を言う。そのうちの五味七味+風味(臭覚)は世界中の人がうるさく言う。
しかし、今日の課題の刺身のプリプリ感や、われわれが求める蕎麦切のコシや、ある種の野菜のシャキシャキ感は、触覚の美味しさを表現しているはずである。
だから、日本人ほど食味(視覚、聴覚、触覚)にうるさい民族はいないのではないかと思う。
今日の締めも触覚が大切なお蕎麦だった。
「締める」とは調理以前の触味の追求、「コシ」とは料理による触味の追求ともいえよう。
《 蕎麦膳 》シリーズ(第206、205、204、190、189、180、176、171、170、166、157、154、153、150話)
〔エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員長 ☆ ほしひかる〕