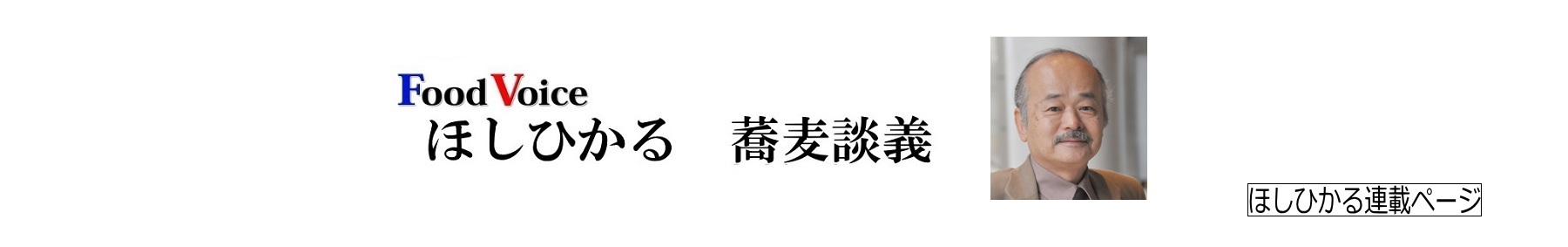第482話 涮羊肉と雑麺のいい関係
2025/12/06
北京紀行-2
昨日、「蕎麦人」北京店で「日中蕎麦学セミナー」が開かれたが、その会をアレンジされた孫前進先生(中日経済技術研究会会長・北京秦藤物流咨询有限公司社長・元北京物流学院教授)に夕食会へ招かれた。
北京市内の道路はいつも大渋滞。そのため1時間半も遅れたというのに、孫先生はニコニコ顔で迎えてくれてすぐ夕食会になった。
卓に着くと先ず中国茶が供された。続く料理は《涮羊肉 シュワーヤンロウ》。分かりやすくいえば、羊肉のシャブシャブである。その羊肉はきれいで、匂いもなく、柔らかで美味しかった。とくに自前だという垂れが羊肉によく合っていた。孫先生は「この辺りには回族の人が多く住んでいるので、いい羊肉が入る」とおっしゃっていた。
賑やかに懇談をしながら時間は経ったが、その間に孫先生は「中日蕎麦学研究会」の設立を熱心に提案され「私はやる気満々です」と何度もおっしゃった。
中国の蕎麦事情について教えてもらいたいことはたくさんあったが、夜も遅くなってきた。私たちは明日も北京外語大のイベントがあるので、そろそろ失礼しようということになった。締めは《ラーメン》だった。《涮羊肉》の汁で茹でて、例の自前の垂れで頂いた。
この「羊+麺」という組み合せで思い出したのが、前に北京に来たとき王府井の『東来順飯荘』で食べた《涮羊肉》と《雑麺 ザーミェン》であった。
《雑麺》― それが応永年間(1394-1428)に成立した『禅林小歌』や、相国寺(京都)の史料『蔭軒日録』の1490年の条に記載されていることを伊藤汎先生(江戸ソバリエ講師)が発見されている。
だから私は「この店の《雑麺》とはいったい何だろう?」と思って、ガイドさんに頼んで『東来順』の厨師(料理人)に尋ねてもらった。すると、緑豆や粟の粉で作った麺だという。伊藤先生は《雑麺》のことを「雑穀麺」だろうと推定されているが、ほぼ同様である。私は興味深々とばかりに啜ってみた。すると個性的な味がする。それに羊肉ともよく合っていた。
それにしても、思いがけないことから『蔭軒日録』に記載されていた《雑麺》を口にすることができて、伊藤先生の弟子を自称する江戸ソバリエとしては謎が解けたような気分になったものだった。
そんな体験から、帰国後に『東来順』のことを調べてみると、『東来順』の創業者は回教徒か、あるいは回族の人だったらしい。最初は清朝末期ごろ屋台で《雑麺》や《蕎麦饅頭》を売っていた。《雑麺⇒粟麺》といえば、青海省民和回族トゥ族自治県の喇家遺跡で、約4000年前の世界最古の麺《粟麺》が出土しているぐらいだから、回族だという創業者がそれを商うのもおかしくはない。そして屋台からテント張の店『東来順』を構えるようになって粥を供するようになった。店主は、さらに漢族にも受け入れられる回族風味の食べ物の開発を思案していた。そんなところに北京で《涮羊肉》が流行り始めた。そこで店主は回族仲間の伝手をつかって北京への羊肉の集積地である河北省の張家口に、臭みのないあっさりして、かつ湯の中でも硬くならない羊肉を手に入れるルートをつくった。その上で漢族にも回族にも好まれるような垂れを開発し、今日に至るということだった。
回族というのはペルシャ人とかアラビア人が源流である。また唐時代にはペルシャ系の胡人による「胡旋舞」というのが流行っていたらしい。その舞がどのようであったかは今となっては分からないというが、作家の井上靖は、その様を「疾きこと旋風の如く、耀くこと火輪の如し、飛星を遂い、流電を牽す、回風乱舞、空に当たって散る」と謳っているから、そうと激しく、かつ優雅に舞うものであったろう。
そんな胡族の食の中には羊肉や粉食があった。当然、粉食のための挽臼も持ち込んでいたであろう。
伊藤先生がいつも言うように「粉食をするためには、挽臼がなければならない」が、その挽臼が中国に伝わったのは、漢代初めのころらしい。なぜ「伝わった」とはっきりいえるかというと、中国の挽臼はいきなり〔溝のある挽き臼〕が登場しているからだ。対して、ギリシャ・ローマは、溝のない挽臼・ある挽臼とその発展過程がわかる挽臼が見られるからだと民俗学者の周達生は述べている。
とにかく、粉の本場、即ち挽臼の本場から、その文化を持ち込んだのは胡族であろうということが、目前の鍋の中の《涮羊肉》と《麺》から伺えたのは、思わぬことだった。
かくて中国は麺王国となって、食の豊かな国となったものと想われる。
〔文 ☆ 江戸ソバリエ北京プロジェクト ほしひかる〕
ほしひかる 絵 「胡旋舞」
ほしひかる 写真「東来順」の《涮羊肉と雑麺》