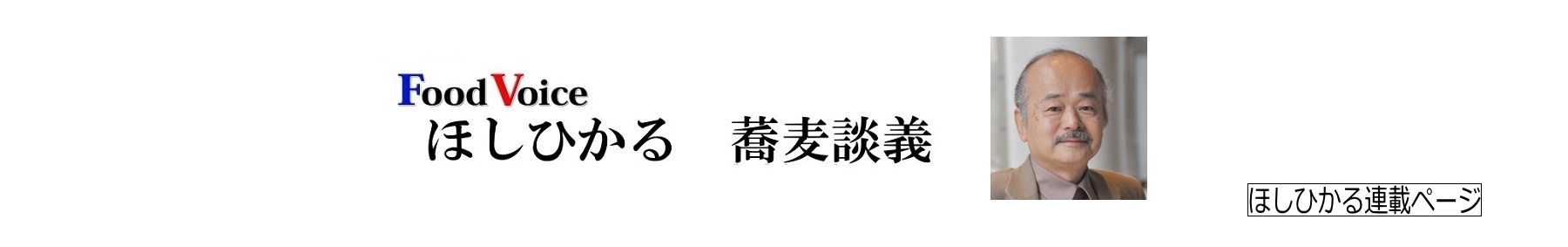第484話 中国茶を喫する
2025/12/06
北京紀行-4
北京市内をタクシーで通っていると「○○茶館」という看板をよく見かける。「お茶と蕎麦は兄弟」ともいうから、ちょっと入ってみるのもいいかなと思わないでもないが、ただ茶界も蕎麦界以上に幅広く奥深い。そう簡単ではなさそうだから、やはり通りすがりにチラリと茶館の看板を流し見るだけだ、
ところで、この度の北京出張は観光する間もなかった。ただ帰国しようという日、ホテルを出てから空港に向かうまでの時間に余裕があった。そこで空港⇔北京市内の送迎を頼んでいたガイドさんに、故宮見学をお願した。それが第481話である。そのガイドさんが故宮を一巡りした後「茶館へ行こうよ」と誘った。「時間はとらない。飛行機は間に合う。お茶が美味しいよ」と云う。これも旅行社の定番コースかもしれないが、中国茶の一端を知りたいと思っていたので誘いにのった。
案内された店は『頤馨茶芸』。名前は北京を旅行した知人から、前に聞いたことがあった。階段を上って部屋に案内されると、若い男性が、目前で丁寧に手際よく小さな碗にお茶を淹れてくれる。彼のその指は、同行の女性たちも感嘆するぐらい、細く長い。そのピアニストのような指先で、茶葉を3~5gぐらい入れて、熱いお湯で1.~2分浸出してくれる。そうして供された烏龍茶+高麗人参、玫瑰花茶、フルーツティなどは、とろけるように美味しかった。いずれも華麗なお茶だから、微妙な甘みと爽やかさが味蕾を刺激する。それは日本茶の旨味とはまったく違うものだった。
頂きながら私は、遠藤周作の「樹の下で茶を楽しむ」というエッセイを思い出した。遠藤は幼いころに育った大連や、長じて旅をしたサマルカンドで見たお茶を飲んでいる老人の姿が忘れないという。それは青い空の宇宙とみごとに調和した光景だったらしい。遠藤はそれからまた旅をした。そして台北で飲んだ烏龍茶の味が「微妙で、舌の先から何ともいえぬ香りと味が広がっていく・・・」と述懐していたが、まさに今日のお茶がそのようだと思った。
中国人も日本人も、お茶が大好きである。先日、孫前進先生に招かれたときもお酒や料理の前は先ずお茶だった。かつての日本でも遠藤周作が目にした光景はよく見られたが、今の日本はペットボトルのお茶以降、これまでみっともないとされてきたラッパ飲み・独り飲み・歩き飲みが普通へと変わってきた。
歴史的に日本のお茶は、中国の各時代の茶が何回も伝わってきた。空海・最澄・永忠ら遣唐使たちは唐の時代の餅茶を伝えた。入宋した栄西・円爾たちは抹茶や茶道具である挽臼(「水磨の図」)を持ち帰った。それから江戸初期に来日した隠元は煎茶を持って来た。
特に、鎌倉時代に入宋した留学僧たちは日本を革命的に変えた。栄西の抹茶から日本の【茶道】が生まれた。道元が説いた「六味」は、日本料理の中の【旨味】になった。円爾が持ち込んだ挽臼は日本に【麺文化】をもたらした。
先述の「茶と蕎麦は兄弟」といわれる所以は、茶木の原産地がソバの故郷と同じ四川・雲南であることと、抹茶も蕎麦も挽臼で挽いて粉にする点だ。
その挽臼は482話で指摘したように漢の時代に胡族によって中国にもたらされたものと思われる。
しかし中国茶史では、唐茶の時代は搗臼を使用しており、宋代になると擂鉢・磨臼・碾を利用して抹茶にしていると中国茶研究家の布目潮風は述べている。
それからすると、漢から唐の時代までは挽臼使用の前期という位置づけで、宋の時代の茶の発展によって、麺の進化が起きたのだろうか。
その宋の時代の食文化を入宋した先の留学僧たちは、ごっそり日本に持ち帰ったのである。
ところで、この『北京紀行』シリーズをお読みになられた方たちから、たくさんのメールを頂いた。
たとえば、北京文化の象徴と感じた483話の【北京ダック】では、北京が好きでここ数年は年に4回ほど北京を訪れているという友人SRさんから、「南方と北方文化」云々はその通り、「だから、北京は魅力がある」とのお声を寄せられた。
しかし、いまひとつわからないのは、やはり胡族文化の浸透である。
メソポタミアで誕生した粉文化(=挽臼文化)は、ヨーロッパではそのまま粉文化を発展させた。一方、アジアにやって来たそれは麺文化に変わった。
なぜか?
それを本当に解明している人はまだいないだろうが、482話の【雑麺】をお読みになったYTさんは「なぜ中国で麺が誕生したのか?」と指摘されたのはさすがである。
それ故に、KTさんは「やはり日本文化のルーツは中国大陸。もっと若いころに気付いておれば、何度も中国へ行けただろうに」。KNさんは「中国・朝鮮の勉強会を開きましょうよ」とのご意見を頂いた。
「東アジアはなぜ麺なのか?」
あらためて、そんな思いを抱くことができたのも、北京の茶館で頂いた異国風味の甘美なお茶のせいだろうか。
〔文・写真 ☆ 江戸ソバリエ北京プロジェクト ほしひかる〕