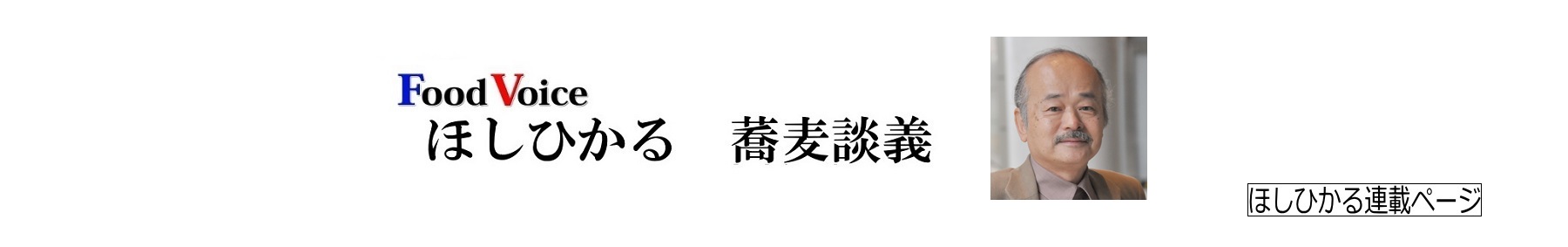第486話 バイカルチャル
2025/12/06
北京紀行-6
☆日本の味
話は484話のお茶に戻るが、茶自身は中国伝来である。それを日本人は「茶道」という独自の芸術に昇華させたことはいうまでもない。
そしてこの「茶道」を参考にして、中国「茶芸」や韓国「茶礼」が生まれた。北京の『頤馨茶芸』もそれだった。
日本人はなぜか「極める」ことが歩むべき最高の「道」だという考えが強い。そこからお持て成しや型が重んじられるようになったことは、これまでも度々述べてきた。
一方の、「茶芸」は「美味しく淹れる」という本来の目的が主となっているという。これは食に関わる人は忘れてはならないことであると思う。
そういう比較文化みたいなことを考えているうちに、美味しい蕎麦を食べたくなったので、両国の「ほそ川」の、例の大きな暖簾をくぐった。すると、目に入ってきたのは、あるソバリエさんご夫婦だった。ちょうど食べ終わったところだという。「美味しかった」という言葉を残して、ご夫婦は帰られた。
私も卓に着いた。相変わらず、《ざる蕎麦》や《煮穴子》など全てが美味しかった。帰国後だけに、これらは日本人の口に合っているという感じを強くもった。
次の日は、北京では《北京ダック》だったから、日本では「鴨だ」というわけで、《鴨なん》発祥の地である日本橋の蕎麦屋へ行った。
《鴨》も美味しかった。肉料理とはいえ、煮ることによって優しい味になる。《煮穴子》や《鴨なん》など煮物は日本人の口に合った日本の味だと思った。
そういえば、これまでお持て成しや型が主だった和食界に「美味しい和食」という考え方を導入したのは北大路魯山人だった。それに倣って片倉康雄は「美味しい蕎麦」を目指した。細川さんは片倉の弟子ではないが、その志は継いでいると思う。
☆日本の料理
そして今日は、江戸ソバリエの金村さんに食事に誘われていたので、約束の六本木のグランド・ハイヤット東京に向かった。
金村さんはソバリエになってから長い。受講された頃は服部料理学校に勤務されていたが、定年後にグランド・ハイヤット東京に再就職された。そこでホテルの鉄板焼レストラン「けやき坂」のシェフ本多さんを「ソバリエ」に誘われた。下記のホームページを飾っている雄姿が本多シェフだ。
今宵は、その「けやき坂」での会食だった。料理は鉄板焼ステーキ、個人的にはある意味懐かしかった。
というのは、私がまだ若造だったころ、六本木の鉄板焼ステーキ店とか、銀座の鮨屋でお客さんをよく接待したものだった。この二つはカウンター席であるからテーブル席より一対一で話せるという利点がある。だからカウンター席というのは、営業員や恋人たちに向いていると今でも思っている。
それはともかく、現在の寿司屋、そして天麩羅屋は江戸の屋台の止まり木がカウンター店舗に発展したものであるが、鉄板焼ステーキというのは、神戸の「みその」が寿司屋のカウンターをヒントに考案した料理システムであるらしい。
この日本独自のカウンター店舗は、旧来のお持て成しや型重視から脱して、「でき立て」料理の提供を第一とするシステムである。同じく大阪で生まれたカウンター割烹というシステムもあるが、鉄板焼ステーキはニューヨークで受けて、世界に広く認められることとなった。
今宵も、野菜・魚・肉がジュッ!と音を立てながらでき上がり、そのでき立てを口にすることができる。ソースも美味しい。野菜は江戸野菜だ。金村さんも本多シェフも、「更科堀井の会 ~ 更科蕎麦と江戸野菜を味わう」の常連だが、そういうことだったかと納得する。さっそく大竹先生(江戸ソバリエ講師)に電話したら、翌日にはこの店を訪れたらしい。
ところで、料理の進歩には革命家が必ずいる。先の魯山人もそうであるが、その前の千利休もそうだ。利休は、茶懐石では「熱い物は熱いうちに、と述べた」と弟子の山上宗二が証言しているが、鉄板焼ステーキも革命だと思う。なぜならば、アメリカ式に肉の匂いがプンプンする肉屋さんもいいが、鉄板焼のステーキというのは優しく、日本人向きだと思うからだ。《すき焼》も日本料理だが、「割烹ばかりが和食ではないヨ」と鉄板の上の賽の目のステーキが云っているようだ。しかも当店のステーキは東京の秋川牛。シェフ自身が餌の世話に行くらしい。それによって自然に牛の体質を得ているのであろう。
さて、目の前を見れば、御飯のガーリックで焼いているところである。御味噌汁と香の物も付いている。
本多シェフは、この御飯の代わりに「蕎麦を」と思っているらしい。これも革新的だ。いま金村さんが蕎麦打ちを指導されているらしい。どんな蕎麦が出てくるか、楽しみだ♪
〆として、この章の話としては余談だが、付いていた香の物が美味しかった。尋ねると塩と砂糖の浅漬らしい。調味料の量を訊くと「秘密です」と笑ってかわされた。やはり日本人は、御飯と御味噌汁と香の物があれば落ち着く。
海外生活をして二重文化に適応していることを【バイカルチャル】というらしい。今回の私たちのようにわずか数日間の滞在体験で、「適応」云々などと大きなことはいえないが、今まで空気のよう当たり前だった日本食の味、あるいは日本の食文化! ということが、帰国直後には鮮明に浮かび上がってくるのも事実である。
このことを申上げて『北京紀行』シリーズは「終」としたい。
肝心の北京でのイベントについては、別の機会で発表していることにしている。
拙文にお付合い頂き、心より感謝しています。
〔文・写真(中国の白茶) 江戸ソバリエ北京プロジェクト ☆ ほしひかる〕