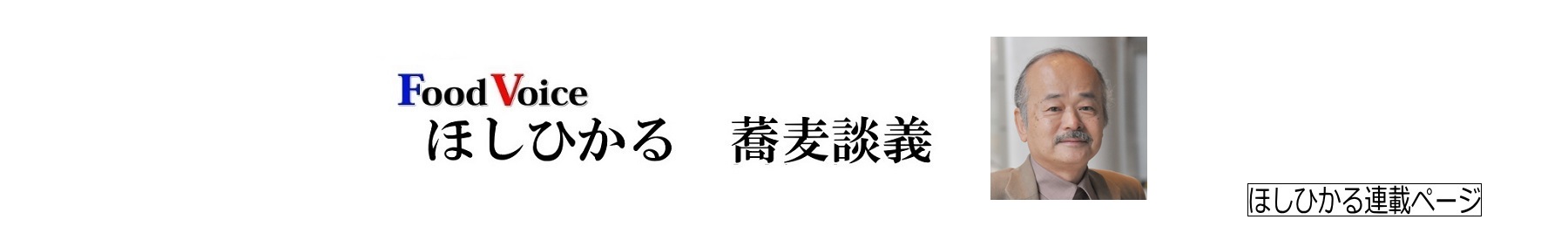第664話 街の蕎麦屋
2025/12/06
~ 『世界蕎麦文学全集』物語6 ~
「突然、おまえから電話がくる♪ あのう、そばでも食わないかあ、ってねえ♪」
これは中島みゆき作詩・作曲の「蕎麦屋」という歌の一節である。力強さと優しさと希望の上に、ちょっぴりの荒っぽさが織り交じったみゆき節は、独特の蕎麦屋に仕上がっている。全曲はYou tubeのカヴァー曲でしか聞けないが、やはり本人のCDの方がいい。
https://www.yamahamusic.co.jp/files/34/ymc/miyuki-cp2019-a/
この歌から見えるのは〝街の蕎麦屋〟の光景である。どこが「街の」かと言うと、「蕎麦でも・・・」というところだ。美味しい蕎麦じゃなければならないという食通の話ではなく、「とりあえず蕎麦にするか」というわけだ。
ところで、小説で蕎麦屋を材にしたものはめったにない。だからといって他の麺屋のものがあるわけではないが、珍しく栗良平の『一杯のかけそば』という童話のような物語が、平成の初めごろブームになった。
舞台は北海道、大晦日の夜遅く、「北海亭」という蕎麦屋の二番テーブルに母と二人の男の子が座って一杯の《かけ蕎麦》を注文した。
オヤジはちらりと客を見て少しサービスする気がわき、玉蕎麦一個に半個足して茹でて出した。
「おいしいね」と10歳ぐらいの兄と、6歳ぐらいの弟が「母さんもお食べよ」と一本の蕎麦を摘まんで季節外れの半コートを着た母の口に持っていった。そして食べ終わると「ごちそうさまでした」と言って立ち上がった。
蕎麦屋の夫婦は声をかけた。「ありがとうございました。どうかよいお年を」。
翌年の大晦日にも去年と同じ半コートを着た母親と子供がやって来て、一杯の《かけ蕎麦》を注文した。
オヤジは今年も玉蕎麦一個半を茹でてやった。
「おいしいね」「今年も北海亭のお蕎麦を食べれたね」「来年も食べれるといいね」。
翌々年も、蕎麦屋のおかみは二番テーブルを空けて待っていた。
色褪せた半コートの母と子供がやって来て、《かけ蕎麦》2杯を注文した。
オヤジは玉蕎麦三個を茹でてやった。
母が子に語り出した。「実はね、死んだお父さんが起こした交通事故で支払できなかった分を毎月払っていたけど、それが今日で終わったの。お兄ちゃんは新聞配達を続けてくれたし、淳ちゃんは毎日お買物や夕飯の支度をやってくれたから。ほんとにありがとうね」
話を聞いていた蕎麦屋の夫婦は、厨房で貰い泣きをしていた。
それから、母子は大晦日になってもなぜか来なかった。蕎麦屋の二番テーブルは空いたままだった。
それが数年経った大晦日、和服の女性と二人の立派な青年がやって来て、丁寧に頭を下げた・・・。と、こんな話だった。
まるで、温かい《かけ蕎麦》を食べたときのように、日本中の人たちの心が温まったのは、もう30年も前のことだろうか。
その後、作者のトラブルによって、小説『一杯のかけそば』も忘れられてしまった。しかし、ここにも日本の〝街の蕎麦屋〟の情景があったことはまちがいなかった。
そういえば、少し前の街の繁華街や駅前などには蕎麦屋、鰻屋、天麩羅屋、握り寿司屋が必ずあった。加えるなら、喫茶店、らーめん店もあった。それが街の風景であった。こうした街の形は、いつから生まれたのだろうか?
話は明治維新に遡る。薩長土肥は徳川文化を否定して「朝廷+舶来志向」を掲げた。そして新政府は西欧列強並みの強国の道へと舵を切った。これがいわゆる欧化政策である。
しかしこれによって民は単純に「舶来品はハイカラ、日本伝統物は野蛮」と認識するようになった。たとえば洋服を着ているだけで尊敬され、和服を着ている者は「古い、遅れている」と軽く見られ、「伝統」は古くて価値がないという判断基準が生まれた。
食においては、江戸四大食は主役の座から下りて、庶民の需要に応えて腹を満たす食堂へと変身しなければならなくなった。かくて蕎麦屋の品書には丼物が増え、続く大正時代になると、蕎麦業界では製麺機が広まり、品書にはカレー南ばん・親子丼・天丼・支那ソバ・かつ丼・カレーライスまで並んだ。また関東大震災後から店内の上がり框は卓・椅子へ変わった。
蕎麦屋は本格的大衆食堂へ変身し、人情味ある〝街の蕎麦屋〟として日本の大衆文化を支えたていったのである。
しかし・・・現在、街から個人経営の、天麩羅屋、鰻屋、握り寿司屋、喫茶店の灯は消えた。代わって登場したのはチェーン展開の回転寿司、外資系のcafe、らーめん店などの企業による外食店である。
そんな中で、街の蕎麦屋をはじめ、老舗蕎麦屋、創作蕎麦屋など頑張っているところを皆さんに、知ってほしいと思う。
【世界蕎麦文学全集】
21.中島みゆき「蕎麦屋」
22.栗良平『一杯のかけそば』
文 ☆ 江戸ソバリエ認定委員長 ほしひかる