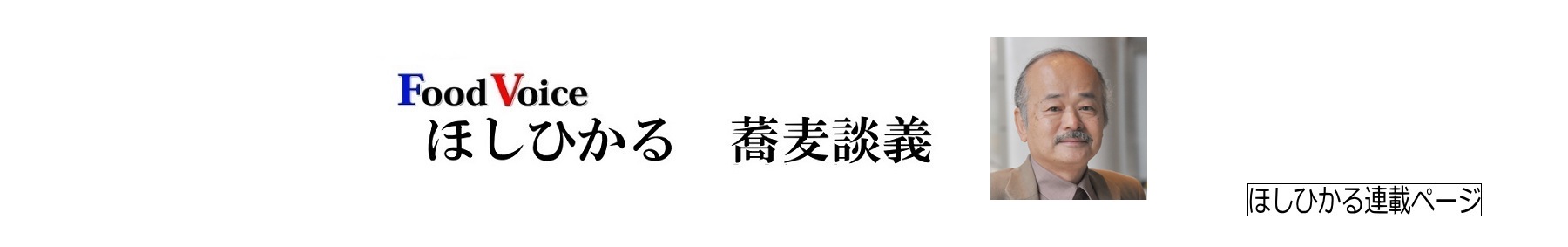第667話 わが猫の思い出から
2025/12/06
『世界蕎麦文学全集』物語9
☆わが猫
わが家はマンションの一階、そのベランダで「ミー・ミー・ミー♪」と子猫の鳴き声がする。覗いてみると三匹の赤チャンが生まれていた。今からおよそ10年以上も前のことだった。その内の一匹はすぐ死んでしまったが、残る兄と妹は庭でママ猫に見守られながら、いつも仲良く戯れ合っていた。ママは気品のある顔立で白色、まるで女王のような美人、イヤ美猫だったから子猫たちも白、すごく可愛い顔をしていた。兄妹はすくすくと育ち、親子猫の行動範囲はわが庭からマンション全体にまで広がって、道行く人たちを振返らせていた。そのうちに、とうとう美猫のママと、血筋を受け継いだ妹は可愛らしく甘え上手だったから、通りかがりの猫好きの人にもらわれていった。おそらく母娘とも、猫可愛がりされたのであろう。「人間も、猫も、美人は得だ」と管理人さんと話したものだった。
残ったお兄ちゃんは、「シロ」という名前をもらい、管理人さんが「猫を嫌がる人もおられるだろうから」と館内に入らないようにと、トイレと食事と睡眠はゴミ収納室内でするようにと躾けくれた。シロは利口でいい子だったから、それを守っていた。だから皆さんから好かれ、マンションの住民として認められるようになった。しかも彼は雄であった。他の雄猫が縄張に入ろうとすると、シロは許さない。猛然と襲いかかった。お蔭で当マンションはシロ王国となった。
その一方では、私がゴミを捨てに行くと、私の足音を耳にしただけで出てきて「ミャオ・ミャオ」と猫撫声で近寄って、私の足を舐めはじめ、そのうちにゴロリと横になり、自分の身体を撫でてくれと要求する。そういうアヤシイ関係をマンションの皆さんは呆れていたものだった。たぶんマンション住民のなかでは一番慕われていたと思う。それが猫でも悪い気はしない。私もシロが気に入って「わが猫」と思って幸せな日々をおくることができた。 シロが来てくれてから15年! 突然、シロの最期のときが訪れた。たぶん病気だったのだろう。管理人さんが涙ながらに、そのことをマンショナンの住民に振回ったため、日ごろシロに癒された人たちがゴミ室に集まった。
弱ったシロは目を閉じていた。「気付かなくてゴメン」みんながそう思った。管理人さんが瞼を広げてやると、私をジッと見つめた。十数年前の赤児のときと同じ目であった。シロは最期の声を出した。「ミャオ!ありがとう」と。そして夜更にあの世へ逝ってしまった。
翌朝、ゴミ室には多くの花束が積まれた。そして昼にささやかなお葬式が行われ、マンションの人に見送られてシロは火葬場に行った。
翌日、お骨となったシロは自分の部屋=ゴミ収納室に戻ってきた。 それから四十九日の間、花だけは供えられていたが、皆さんは歯が欠けたようなモノ足りなさを感じていた。「そうか、もうシロはいないのか」という心境だった。
四十九日が経って、お骨はペット寺に納骨されることになった。だが、管理人さんは「縁のない場所にシロが永眠することに気持的にしっくりこない」と言って、お骨を少し持ち帰った。私も文骨して、シロが生まれたわが家の庭に葬ってやろうと思った。たまたま庭にはお地蔵さんを祀っていたから、そこに埋めてやった。
数日後、私は久しぶりに柏の「竹やぶ」さんを訪れた。店主の阿部孝雄さんは蕎麦屋を越えたアーティストであることは、業界でも知られている。行ってみると、相変わらずお店全体がアート作品の群れである。そんな阿部さんに私はいつも刺激を受ける。言ってみれば、そのために行くようなところがあるのかもしれない。そしていつも私は何かしらのお土産をいただいてしまうのだが、その日に頂いたのは
光背をもった招猫だった。 
☆吾輩ハ福猫デアル
そういえば、あの夏目漱石の家にも子猫が入り込んで来たらしい。漱石夫人と長女の婿松岡の著書『漱石の思い出』によれば、 明治37年の6、7月ごろ何処からともなく生まれて間もない一匹の子猫が、当時夏目家が住んでいた千駄木の家に入って来たらしい。
猫嫌いの夫人はすぐ外へ摘まみ出したが、また「にゃん」と鳴いて入って来て、じゃれついたりした。漱石は「置いてやったらいいじゃないか」と言い、また出入りの按摩に「福猫でございますよ」と言われたためついに飼うようになった。
夫人が言うには、明治36年にロンドンからく帰国した漱石だったが、子猫が住み着いたその年の暮からいきなり原稿を書き始め、『ホトトギス』の明治38年1月号から連載されたという。これが漱石の処女作『吾輩ハ猫デアル』である。
ということは、子猫がやって来なければ文豪夏目漱石は誕生しなかったのだから、按摩の予言は当たったことになる。
後に、漱石の長女夏目筆子と松岡譲の四女である半藤末利子は『夏目家の福猫』というエッセイを書いたぐらいだから、夏目家の人々はやはり〝福猫〟と認識しているようである。ちなみに半藤末利子は作家の半藤一利である。ある年、夫婦は山梨県立文学館で「夏目漱石展」が開催されたとき講演を依頼されたが、山梨の老舗和菓子店「松寿軒」の〝猫〟なる和菓子を振舞われたという挿話を末利子が書いている。
さて、われわれ蕎麦好きにとって『吾猫』の価値はどこにあるかというと、漱石先生が『吾猫』の中で「蕎麦の食べ方」を披露していることである。
漱石は関西落語の「そうめん」をヒントに蕎麦の食べ方を創り上げてたようである。そのことを、漱石と江戸文化の関係を研究した水川隆夫が漱石が落語の「そうめん」からとったことを突き止めている。
落語「そうめん」の内容は、大和の名物「丈長そうめん」を面白半分に切らずに食べようというわけだが、そこで「そうめんが二尺(約60㎝)ならつゆは五寸五分(約16.5㎝)、一尺五寸(約45㎝)なら三寸五分(約10.5㎝)付ける」と講釈を垂れるというもの。
こうして、日本に蕎麦の食べ方が誕生したのである。ということは、それまでに蕎麦の食べ方というのは存在しなかったということであり、また漱石先生が蕎麦の食べ方を考案しなければ、日本には蕎麦の食べ方はないままに終わっていたということになる。蕎麦史にとっては、ここが大事である。さすがは大文豪漱石である。
それを簡単に言うと次のようなことである。
*蕎麦はつゆと薬味で食うもの。
*一尺ばかりの高さにしゃくい上げる。
*むやみにつゆを付けるな、三分の一ぐらいがいい。
*口の内でくちゃくちゃ食うな。
かくて、前の660話で述べたように、河竹黙阿弥が粋な蕎麦の食べ方の雰囲気を作り、それを夏目漱石が具体的に披露したのである。
【世界蕎麦文学全集】
25.夏目鏡子 述+松岡譲 筆録『漱石の思い出』
26.半藤末利子『夏目家の福猫』
27.水川隆夫『漱石と落語~江戸庶民芸能の影響』
28.東大落語会編『落語辞典』
文 ☆ 江戸ソバリエ認定委員長 ほしひかる
写真 阿部孝雄作「招き猫」