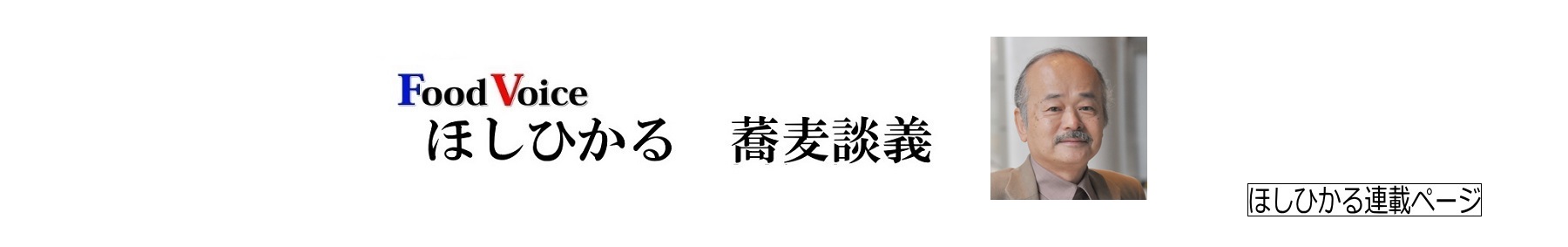第775話 合う、ということ
2025/12/06
あるいは「月の裏側」の舌学
~ 新・美味論Ⅲ ~
☆再びのオリーブオイルの試飲会
小松庵は「蕎麦にオリーブオイル」を供する都内で唯一の蕎麦屋であると思う。
その小松庵銀座店の今日の「森の時間」は小松圭子さんの4回目のオリーブオイルのお話だった。
今日は4種類の新油のオリーブオイルの試飲を中心にして話された。

これまでのお話でも、温かい《かけ蕎麦》にオリーブオイルがよく合うことを学んだ。
今回は、オリーブオイルを数種ブレンドしたものはサッパリ感があるので魚貝料理が合う。シンプルなものはパンチがあるから肉類が合うことを知った。
それを聞きなから《江戸蕎麦》にはブレンド、《田舎蕎麦》にはシンプルなものがいいかもしれないと思った。
なぜ日本の蕎麦なのにイタリアのオリーブオイルに関心をもつかというと、何よりも未知との遭遇感がおいしいからだと思う。
ブリア=サヴァラン(1755~1826)が「新しい御馳走の発見は人類の幸福にとって天体発見以上のものである」と述べていたが、それでなくても人類学者たちは「他の動物とちがって人類は、変化や新しいものに関心をもっている」としている。だから、よく耳にする「笹しか食べないパンダに味覚はあるか?」というジョークは面白い視点だ。
☆合う、ということ
さて、今日の試飲にはオリーブオイルとお摘まみが出て、「両者は、合うか合わないか?」というテストになった。
そして終了後、「フレーバーオリーブオイル チョコレート」を1本頂いたので、翌日からチャレンジした。アイスクリーム、ヨーグルト、湯豆腐、トースト、ホットケーキ、ピザ・・・、どれが合うか?、と。

この「合うか、合わないか?」を強く意識したのは、麻布のイタリアンレストランで食事をしたときからだった。何とかというワインが出されたので一口飲むと、「マズイ!」 舌が麻痺するくらいのひどさだった。ところが続いた《サルーミミスティ(ハムの盛合わせ)》を食べて飲むと、一転しておいしい♪ ハムは世界の三大ハムといわれるパルマ製である。熟成したコッパ(首の肉)、スパッラ(肩の肉)、パンチェッタ(腹の肉)はともに舌にまとわりつくようなあま味がある。それが渋い赤ワインを口にすると拭われるような感じがするのである。
驚きながら、改めてワインのラベルを見るとやはりパルマ産のようである。
聞くところによると、パルマの農民たちは小麦を作る傍らで豚を飼育しているらしいが、その風土と歴史から生まれた生ハムとワインが「合う」ということかと思ったものだった。
ところが、あるときサンフランシスコから、あるフードサイエンスジャーナリストがやって来た。彼は蕎麦も大好きということだったので、ある蕎麦屋に案内した。その店の蕎麦は《常陸秋そば》だったが、彼は「この蕎麦に合う日本酒を選んでくれ」と私に言った。何しろ彼は世界的にも著名な人物であるから、緊張した。とにかく私は茨城のお酒を薦めた。といっても原料米は茨城のものではなかった。パルマの生ハム+ワインは「パルマの地産」であったが、常陸秋そば+茨城酒は「国産」にとどまっていた。
そんなことがあってから私は、ある疑問をもったので「合う」と言う言葉を調べてみた。
一、 先ず『古語大辞典』(角川書店)の、「あふ(合・逢・會)」の項は1頁4段中ほぼ3段を費やして説明している。にもかかわらず目的の解明にあたる説明はない、ただちかいものとして、次があった。
~ 野菜や魚介類などに、塩・味噌・酢・胡麻などを混ぜ合わせて調理する。~
この古語辞典は、大百科事典の大きさで全五巻もあるから、古語のすべてが掲載されていると思ってまちがいない。ということは、古い日本には味覚における「合う」という概念はなかったと思われる。
二、次に現在の『日本国語大辞典』(小学館)。これも同じく大百科事典の大きさで全14巻である。ほとんどの日本語が網羅されているとみてよい。頁を捲ると、「あう(合・会・逢・遭)」の項に次のように掲載されていた。
~ 一つ以上の音や色、味覚などがうまく調和する。
「ビールと日本料理とは合うものだろうかと考えた。」(丸谷才一『笹まくら』1966年)~
「 」内は使用例であるが、他の例から判断してもだいたい初出の例であると考えていい。しかも他の語例は『古事記』『万葉集』や古い時代の史料の引用ばかりである。ところが、この「合う」の引用は1966年である。このことは一の古語辞典に適した解説がないことと符号する。
結論として、私がもつた「ある疑問」は解決された。
つまり、昔の日本人に「合う」という概念はなかったのである。
それが戦後を過ぎたころから「合う」という考え方が必要になってきた。
当時は、高度成長を経て日本人の食卓に海外の飲食物が並んだため、「日本料理つまり和食と西洋の酒」という組み合わせにとまどう日本人の思いを代表して「合うのか?、」という言葉を丸谷才一は発しているのである。
丸谷は作家であり、食通であった。感性で真実に迫るのが文学であるが、この何気ない言葉のなかに、日本の食文化の本質が秘められているかと思うと文学の力の大きさを知る思いである。
ところで、われわれの和食の根底は出汁である。そして日本の出汁の思想は、余計な特徴を出さず、出汁の旨味を基調にした調和だという。
伏木亨先生(江戸ソバリエ講師)も「和食にとってなくてはならない出汁は、奥ゆかしく主張は控えている。けれど揺るぎない強さをもった、要の存在」と定義している。
そう、和食の思想は最初から調和。その調和の使者が〝旨味〟というわけだ。だから、これまで日本では、この食べ物とあの食べ物は〝合うか〟などと考える必要はまったくなかったわけである。
そこが、日本の食文化の面白さだと思う。
「料理の三角形」を提示したとして有名な人類学者レヴィ=ストロース(1908~2009)は、『月の裏側』という著書で日本文化を論じている。
彼は毎日、パリの自宅では電気釜でご飯を炊いて海苔で食べるほど、異文化日本のファンだったらしいが、それでも日本人は「月の裏側」の生命体のように映っていたのかもしれない。そこが面白いところである。
私たちの味覚の故郷は母乳である。つまり母乳は旨味、甘味、油脂味によって成り立っているが、欧米人の味覚は甘味、油脂味が際立っている。ところがわれわれ日本人の味覚の根底は旨味である。この相異が西洋人には「月の裏側」と映ったのだろう。
それをわれわれは良い方に受け取って、西洋とも東洋とも一線を画した、日本でありたいと願うところである。
〔江戸ソバリエ ほし☆ひかる〕