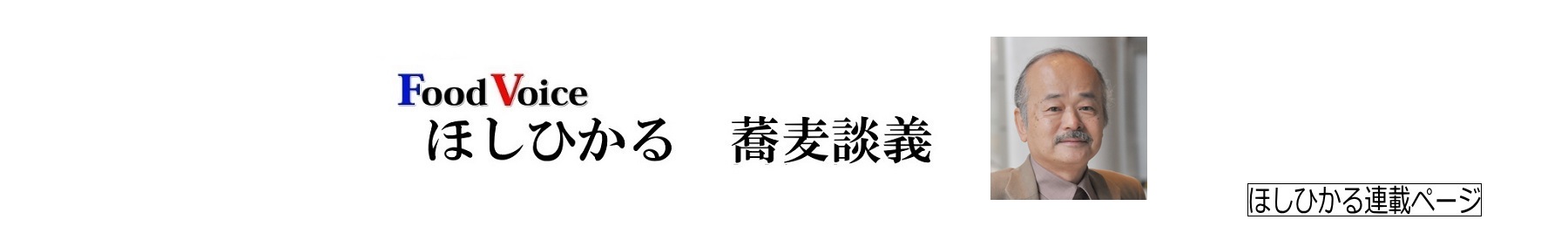第935話 美味しさの秘密
2025/03/23
ソバリエの北川さんや美季さんたちに誘われて、江戸ソバリエ十楚の会の蕎麦会に参加した
蕎麦は十楚の会の会員さんが打ち、料理のほとんどは北川育子さんが準備された。
並んだ料理は、ご覧の通り日本、韓国、中国、タイ、メキシコと、多国籍というか、無国籍というか、料理がずらり。

皆さんが先ず箸をつけるのは鮮やかな色物か、珍しい物。
そのなかに《辣白菜(ラーパイツアイ)》という中国料理があったが、これが非常に美味しい逸品。
白菜のシャキッとした触感とともに香りがよく、舌には甘酸っぱく、辛く、やや油っぽく、隠れたような鹹味、旨味が感じる。
スゴイと思った。なぜかというと、だった一品に五味(甘味・酸味・辛味・旨味・鹹味)+油味=六味が詰め込められているからである。だから、煮て焼いてとか、蒸して炒めてとかの、ダブルで調理する、いかにも中国料理らしいと感心した。
中国に詳しい小島さんによると、お金がないときは、この《辣白菜》一品でご飯が食べられると言われるが、たしかに一品で六味がするならそうだろうと思った。そこら辺にこの逸品の誕生秘話があるのかもしれない。
そこに北川さんが声をかけた。「いやだ~、《高湯豆腐》は売れないのね。地味だから?」と。男どもは慌てて《高野豆腐》に箸を付けたところ、今日までにこんな美味しい《高野豆腐》を食べたことがない。これぞ和の味と皆さんが感動した。
たかが《高野豆腐》、どうしてこんなに美味しく作れるのだろう?
コツは必ず砂糖から入れることにらしい。つまりサシスセソ(砂糖・塩・酢・醤油・味噌)、この順を崩してはいけないというわけだ。
思えば、世界で砂糖を調味料として使うのは日本ぐらいだろう。それも最初に入れろという。誰がそのようなことを発見したかは知るよしもないが、日本語では「甘い」と書いて「ウマイ」と読むこともあるのは、このあたりの事情と無縁ではないだろう。
とにかく今日は、《辣白菜》の複雑な五味+油味=六味と、《高湯豆腐》の単純な甘味(砂糖)>塩味・旨味(醤油)の、二つの味覚の世界を楽しむことができた。
江戸ソバリエ十楚の会の皆さま、ごちそうさまでした。
江戸ソバリエ協会
ほし☆ひかる