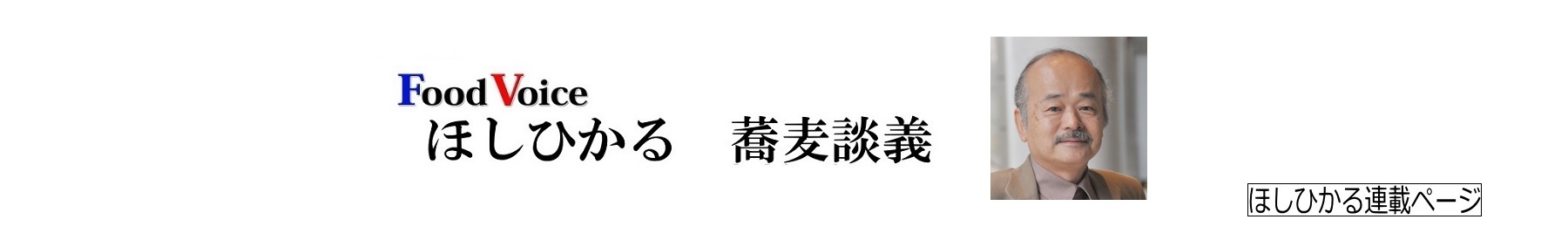第949話 美味しい三麺:記事
2025/12/06
☆一麺:大分の《やせうま》
ソバリエのrさんから、大分名物だんご麺《やせうま》というのを頂きました。
市販されている《やせうま》はたいてい製麺機による乾麺ですが、本来は庖丁で切らないで、練った小麦粉の塊を指で引きちぎるようにして作る、いわゆる餺飥(ほうとう)系でしょう。
発祥は由布市狭間町古野あたりらしく、市内にある天台宗青雲山妙蓮寺に《やせうま》発祥の地の看板が立っているそうです。
伝説によりますと、平安時代に当地へ落ちて来た藤原氏の若君に従った女中の八瀬(やせ)が作ってくれたおやつがうまかったところから、《やせうま》とよばれるようになったと言い伝えられています。ですから、本来は伝説にあるようにおやつですから、黄な粉をまぶして食べるのがいいでしょうが(農水省HPに写真)、今日は《笊うどん》風にして食べました。
https://www.maff.go.jp/j/keikaku/syokubunka/k_ryouri/search_menu/menu/yaseuma_oita.html
ご覧の通りかなりの幅広麺ですから、独特の触感です。

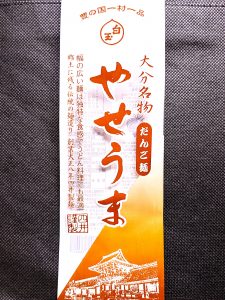
冬でしたら、山梨風の《ほうとう》のようにして頂くのもいいかもしれませんが、やはり一度は古代の藤原の君を想って、《おやつ》として頂かなければなりませんから、次回はそうします。
ところで、その日はrさんの娘さんnちゃんも一緒でした。nちゃんと最初に会ったのは小学2年生、今日の彼女は中学1年生になっていました。驚きながら「大人になったね」と言ってあげると「ウン」とはっきり言います。ママさんが「そうなの!」とおっしゃると、「小学6年生と中学1年生は1才差だけど、全然ちがうよ。大人だって、29才と30才は全然ちがうでしょ」。「なるほど」。賢い子に一本やられました。
☆二麺:備中《鴨方手延べそうめん》
私の故郷佐賀は麺類王国です。よく、そうめん、うどん、らーめん、皿うどん、チャンポンを食べます。とくに夏の《そうめん》、冬の《うどん》は日常食で、実家では神崎麺を定番としていたため、東京で生活するようになっても佐賀神崎からずっと取り寄せ、故郷時代と同様に日常食にしていました。
神崎というところは、小麦の産地であり、島原の乱(1637, 38年)以前から神崎麺は作られていたといいます。
現在、私が《蕎麦》と関係しているのも、《そうめん》の1.3㎜の細さと、コシというところが、蕎麦の特色と合致していたせいもあります。そして、《神崎そうめん》の栞には「室町時代ごろまでは麺類は、点心といって、禅林の僧侶が食べる間食を指し、茶の普及にともなって一般化したもの」と記載されていることが、蕎麦史の理解に一役も二役もかってくれたのでした。
ところが、最近そのそうめん屋さんから跡継がいないから廃業するという連絡をいただき、困っていました。何しろほぼ一生をお付き合いした《そうめん》ですから、ほんとうに困っていたのです。
そこへ、この夏のモンゴル国旅行中、お世話になった岡山のTさんから、《鴨方手延べそうめん》を送っていただきました。
Tさんからは幼いころは水車が回っていたこと、そこらじゅうそうめんの天日干しがしてあったことなどを聞いていましたが、麺好きからいえば羨ましい光景です。さらには水車製粉の復元に尽力されたことなども伺っていました。
昔から、播磨・備中・讃岐は小麦の産地のうえに良質な塩が生産されているところから、製麺が盛んだったことは教科書にもありますが、備中麺は初めてでした。しかも鴨方は300年前のから製麺を行っていたといいます。
さっそく頂いたところ、その感触は《故郷のそうめん》と同じだったのです。「わが故郷と同じ」と言えば、頂いたTさんに失礼になるかもしれませんので、言い方を変えれば、伝統の味わいといったところが共通していたのでしょう。
頂いた物には麺線の端も入っていました。蕎麦でいえば切り端のようなものです。これもすっかり忘れていたほどに懐かしいものでしてた。Tさんは「これをバチという」とおっしゃっていました。私の故郷では何と言ったのか忘れてしまいましたが、フシと言ってような気がします。これを味噌汁の具のようにした食べたものでした。


そうだ。とこのとき思いついて、《やせうま》でできなかった黄な粉をまぶしをやってみようと思いました。
でき上がりは、「うん。まあ、こんなもんだろう」です。
そんなことで、とうとう一箱食べ終わってしまいました。そこで箱に書いてあった製造元に電話して、次の注文をした次第です。たぶんこれからもお世話になるかもしれません。
☆三麺:雄武の《韃靼そば 満天きらり》
先日、仲間のMさんが北海道雄武町にある㈱神門の《韃靼そば 満天きらり》の乾麺を頂いたからといって、小生にも回してくれました。
十数年前に、江戸ソバリエ協会が、北海道の農研機構で開発中の《韃靼そば 満天きらり》のアンケートに協力したことがありましたので、それを機にIさんとMさんと三人で雄武町の㈱神門を訪ねたことがあったのです。
たぶん、12年前の2月のことだったと思います。
農研機構のSさんに案内されて、雪の道を日本のトッ外れに近い雄武町まで行って、工場と雪におおわれた畠を見学させていただいたりしました。宿泊は日の出岬ホテルでしたが、コース料理の最後に《韃靼そば》が少し出ていたことに「まさに地産地消。こうであるべきだ」と嬉しくなったものでした。

それから数年後、中国南部、貴州省を訪れました。
そのとき、中国は南部が韃靼蕎麦、中部は韃靼蕎麦と普通蕎麦、北部は普通蕎麦を中心に栽培していると教えられ、はじめて中国蕎麦の実情を知ったのでした。また韃靼蕎麦は麺よりも、お茶、スープや、焼いたりとして食されていることを知りました。
ほんとうは生産量も知りたかったのですが、言葉が通じないので、そうした情報を得ることはできませんでした。
そんなことを思い出しながら、頂いた韃靼蕎麦を《ざる蕎麦》でいただきましたが、食べやすい蕎麦でした。
ところで、元来、江戸の蕎麦屋はお茶(緑茶)を出す風習はありませんでした。
それが最近は《蕎麦茶》を出すようになりました。「茶」というキーワードではなく「蕎麦」つながりから、納得されてのことでしょう。そのきっかけは日本では《韃靼そば茶》は美味しいとの評判が定着し始めたころからだと思います。それだけ韃靼蕎麦はインパクトがありました。これからも韃靼蕎麦の拡がりを期待したいものだと思います。
江戸ソバリエ
ほし☆ひかる