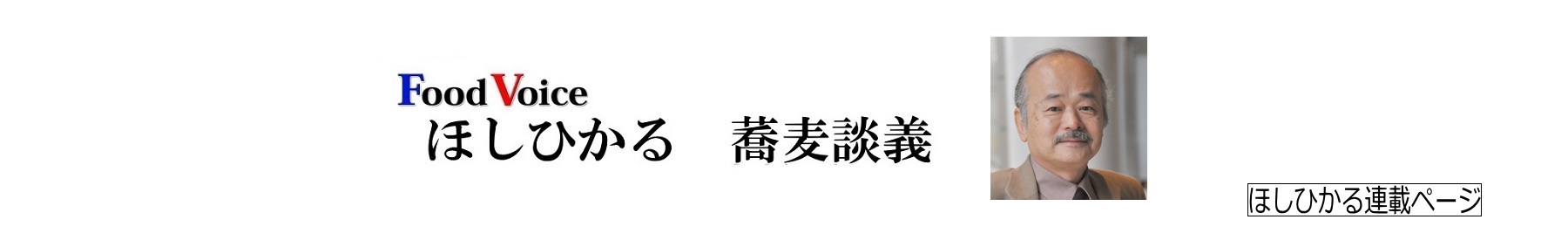第952話 美味しさと、自信と
☆《昆布と低温調理の牡蠣蕎麦》
ソバリエの眞澄さんから「ご近所蕎麦会」に招かれました。同区内にお住まいの眞澄さんと美季さんと陣内さんご夫婦でおやりになるところを、ついでに隣の区に居る私も入れてやろうというわけでした。
蕎麦会のテーマは、NHK『激突メシあがれ~ 自作グルメ頂上決戦 ~』で彼女が出演して披露された「低温調理した牡蠣蕎麦をめし上がれ」というわけです。
眞澄さんのマンションに伺うと、竹を割ったような性格で面倒見のいい美季さん、蕎麦打ちユーチューバーの陣内さんとその奥さま、他にもうお一人、彼女のご友人である都内の大学で哲学を教えておられる先生も遅れてご参加とのことでした。
皆さん、ビール、ワインがすすみます。その間に眞澄さんが次から次へと料理を運んでくれます。
私の大好きな《筍》(町田産)。
初めて食べた《厚岸草》(海のアスパラガス)と《氷下魚の一夜干し》。《厚岸草》は気風のいい触感がします。《氷下魚》は海の魚なのに淡水魚のようにあっさりしています。マヨネーズと唐辛子と醤油を混ぜて垂れにして食べるそうです。


組み合わせの妙も見事です。《鴨肉に酢橘》や《茗荷の甘酢漬け》や《桃とモッツァレラ》。
《鴨肉に酢橘》は鴨がさらに上品になります。



でも何と言っても、今宵の蕎麦会の主役は、焼・蒸・煮に続く第四の調理法とよばれる「低温調理法の、牡蠣」です。


私は少年のころから、生牡蠣が好きで、熱を通した牡蠣は気持わるくて食べられなかったのです。でも、東京に住むようになって、みんなが気持わるい《牡蠣フライ》が好きなのには驚きました。それに私は衣が硬すぎるのが嫌でしたからしばらくは避けていたのです。でも最近は慣れてきて優しい衣の牡蠣フライは食べるようになりました。それでも好きか嫌いか問われれば牡蠣フライは△なのです。
しかし、今日初めて口にした低温調理の《牡蠣フライ》は口に入れたときから、美味しいと思いました。噛んで牡蠣が崩れていくとき、生ではない味が染みてくるのです。
続くは《昆布と低温調理の牡蠣蕎麦》です。汁で和えて食べます。蕎麦切と昆布の細さが同じなので、食べやすいのです。低温調理の牡蠣の滋味が美味しかったです。
☆江戸の数学
ところで、眞澄さんが紹介された哲学の先生ですが、お話はAIのことが多いのです。なので確認ではないのですが、「失礼ですがご専門は?」とお尋ねしたところ、やはり「哲学」とのこと、ただアメリカ哲学なので、哲学を数学で考えるのです。そこからAIにつながるとおっしゃいます。
そう、うかがってもやはりチンブンカンプンでついていけない。だけれど、何となくアメリカといえばプラグマティズムという思想があったので、それから発展したのだろうかと思ったりしていたところに、陣内さんが「企業の社長はAIの方がよいのでは」という実に的を得た質問をされました。すると先生は「AIは責任を取れないから、社長にはなれない」とおっしゃるのです。納得です。お蔭さまで、私もAIというものの本質がわかったような気がしました。先生はさすがは教育者です。
それから、最近私は、蕎麦と数字のことを書いたり、講演したりしているので、そのことについて話してみました。
どういうことかといいますと、史料を見ていると江戸中期から急に日本は数字表現が増えたように思えるのです。蕎麦界でいえば、江戸初期の史料は蕎麦の作り方、汁の作り方が文字で書いてありますが、江戸中期になりますと、それがまったくありません。代わって二八蕎麦、切りベラ23本、饂飩一尺蕎麦八寸などなどが言われるようになります。
それは和算の発達の影響だろうかと申し上げたところ、それは面白い見方だとおっしゃってくださいました。
先日も、全麺協首都圏のシンポジウムでそんな話をしてきたばかりですが、お蔭さまでこれからももっとこの持論を展開していきたいと思ったわけです。
というわけで、今夜の蕎麦会は美味しさと自信を得た楽しい会で、自宅に帰り着いたのは11時過ぎでした。
眞澄さん、美季さん、陣内さんご夫婦に、アメリカ哲学の先生、ありがとうございました。
江戸ソバリエ協会
ほし☆ひかる