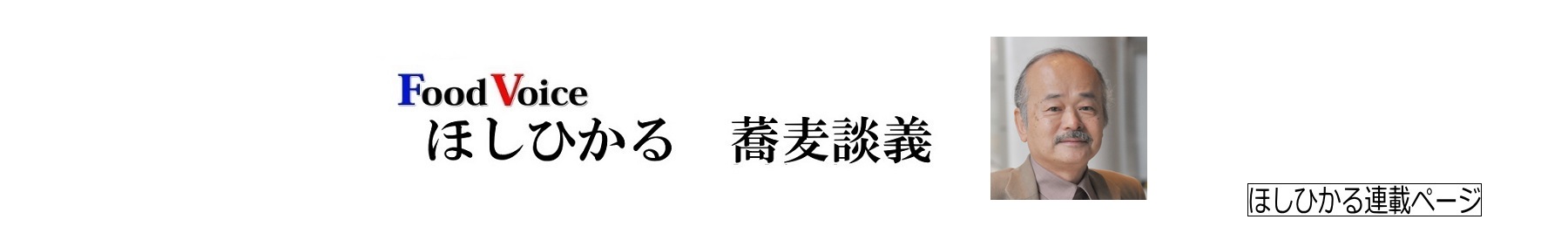第317話 小説「コーヒー・ブルース- XII」
2025/12/06
~ Moon Rever ♪ ~
お手伝いの洋子が来る時間になった。鏡を見ると、泣きじゃくった恵子の瞼はひどく腫れている。ちょっとやそっとで回復しそうもない。 (この顔でお店に出るわけにはいかないわ。) そう思って、徳子に電話して休むことを伝えた。そして、近いうちに恵子のマンションに来るようにとも付け加えた。恵子が店を休むのは、ママ人生の中で、母と明子ママの葬儀以外初めてのことだった。
夕方になって、いつものように洋子がやって来た。洋子は恵子の顔を見て、驚いていた。先週ぐらいから別れたご主人と一緒に住むようになったという洋子は、少し若返ってきた。
恵子は、そんな洋子夫婦の30年ぶりの再会を心から喜んでいたせいか、洋子の顔を見たとたん、つい「洋子さん、私に赤ちゃんができたのよ♪」と口にした。
洋子は目をいっぱいに見開いて、喜んだ。「お願いですから、お身体を大切にしてくださいね。母子ともにですよ。」洋子は自分の過去は触れぬまま、恵子の母体を気遣って念を押した。
「ありがとう。」恵子は素直に喜び、初めて母になるような感覚を味わった。ただし、あくまで「ような」であって、まだ本当の実感はなかった。
洋子が帰った直後、〔金とら〕の女将が電話をくれた。
恵子は妊娠だったことを伝えた
「そう。恵子さんに赤ちゃんがねえ、よかったわね。」桃子が明るい声で、そう言った。
「うん。恵子も嬉しい。」
「明日は居る? ちょっと顔を出すわ、」
「桃子さん。心配してくれて、ありがとう。」
洋子や桃子との会話によって、恵子は段々実感がわいてきていた。(ああ、私に赤ちゃんができたんだわ。あなた、ありがとう!) 恵子は一晩中、健や生まれてくる子や亡き両親のことなどを想っていた。(恵子って、普通の女性とは反対の道を歩いてきたのね。30歳をとうに過ぎてからあなたを好きになって、結婚しないであなたの赤ちゃんを授かって、普通の人なら喜びを両親にも知らせるのでしょうけど、私はお墓に報告しなくてはいけないの。そうだわ、もうすぐ母の三回忌、そのときはあなたも一緒に秋田に来てくれない? まだ生まれてはいないけど、三人揃って、墓前に報告したいの、お願い。お母さん、ごめんね。遅くなったけど恵子に赤ちゃんができたのよ。お母さんともう一度話したいな、生まれてくる赤ちゃんのことについてたくさん教えてよ。そういえば、高校生のとき亡くなったお父さんとはほとんど話した憶えがないのが残念だわ。えっ、あの人がお父さんと似てるんですって? そうか、〔Birdland〕の舞台から彼に飛び付いたのは・・・、彼がお父さんに見えたからかしら。ふふふ、〔らんぶる〕であなたに飛びかかったのも、あなたが父と似ていたせいなのね。だから恵子はあなたが好きになったのよ。そしてあなたの赤ちゃんまで授かっちゃったのね。恵子はやっぱり幸せなんだわ。)
恵子は窓辺に立って外を見た。今夜は生憎、曇っていたが、恵子の瞼には満月が映っていた。恵子は、まだ大きくなっていないお腹を撫でながら、【Moon Rever】を口ずさんだ。(もし女の子だったら、名前は〔月〕ちゃんがいいわ。もし男の子だったら、あなたの名前をちょうだい。〔健〕くんよ。)
それから恵子はレコードを取り出して【Lovin’you】を何回も回した。
No one else can make me feel
The colors that you bring
Stay with me while we grow old
And we will live each day in the springtime
Cause lovin' you has made my life so beautiful
And every day my life is filled with lovin' you
Lovin' you I see your soul come shinin' through
And every time that we oooooh
I'm more in love with you
La la la la la...
Doot-n-doot-n do doo
Ah...
聴いていると、「おれの最高の音楽は、恵子の〔Lovin’you〕だよ。」NYで言ってくれた健の言葉が聞こえてくる。
翌日、〔金とら〕の女将がケーキを持って来てくれた。
「よかったわね、野中さんも、喜んだでしょう。」
「ンー、」
「まだ言ってないの?」
「あの人はまだ30歳よ、自由にしてあげたいの。恵子は、あの人より年上なんだから、私が引き受けなければ・・・・・・。」
「エッ! 一人で産むつもり?」
「ええ。」
「やっぱり、そうきたか。」
「やっぱりって、そう思っていたの?」
「うん。ママというのはトップだからね。これまでも恵子さんは何事もずっと一人で決めてきたんでしょう。だから、最後には一人で決めるんだろうなっていう気がしないでもなかったの。」
「・・・・・・、」
「あたしたち料理屋は夫婦そろって一人前の〝夫婦善哉〟だからね、亭主の板前だけでも、女将だけでも決められないの。そこが違うのよ。」
「・・・・・・。」
「あたしは親が八百屋だったでしょ。父と母がいつも居るの、十代のころはそれが嫌でね。サラリーマンなんかに憧れてさ、一時期はそういう彼がいたわ。あのころのあたしはモテてたなあ。〔神楽坂の八百屋お七〕なんていわれてね。」
「桃子さんは、今もきれいよ。お店の女の子たちもそう言ってるわよ。」
「いやいや、神楽坂の桃子姐さんも、銀座の恵子ママにはかなわないよ。最初会ったときは恵子さんは、凛として近寄りがたいほどの美人でさ、徳ちゃんや店の若い子は恵子ママにスターみたいに憧れているし、この女には負けたと思ったよ。それがさ、最近はすっかり可愛らしくなっちゃって。どうしたの?って思ってたら、彼のせいだったのね。昨日の様子では、恵子さんは完ぺきに野中さんに甘え切ってたのにね。あたしも、まるで自分の娘がボーイフレンドを連れて来たようにあなたが可愛らしく見えたわ。あたしはあなたよりたった三つだけ上だというのに、昨日は母親のような気分になっちゃったわ。でも、心の中では苦しんでたのね。まったくあなたっていう人は偉いのか、おバカさんなのか。心底から野中さんが大好きなんだということだけは分かったけど、困ったわね。」
「恵子もほんとうに困ってるの。」
「自分で言ってりゃ世話ないけど、恵子さんは純なのよ。あなたに女の敵がいないのもそのせいよ。」
「そんな、」
「でも野中さんはサラリーマンだよね。サラリーマンというのはね、昔の彼のことでいえば、そこそこ頭はいいの。そうして競争相手がいないようで、実はいるの。だから、しっかりしてないようで、実はしっかりしているの。わけの分からないようなことを言ってるようだけど、分かる? サラリーマンのお客さんなんか見ても、うちの単細胞亭主なんかと違う人種なの。そう、違う人種なの。それで、あたしも段々と彼と肌が合わなくなってきて、結局は親と同じで、今の亭主と、父ちゃん母ちゃん稼業をやってるわけよ。ははは。」
「夫婦善哉が羨ましいわ。」恵子は目頭を押さえる。
「あたしはそれがいいんだけど、恵子さんはトップ役がお似合いだよ。でもさ、いいじゃない。この世で一番惚れたオトコの子供を産めるんだから。ある意味、生まれてくる子も幸せかもしれないよ。とにかくさ、何かあったら言ってちょうだい。応援するから。」
「ありがとう。桃子さんとお話してるうちに勇気がわいてきたわ。」
恵子はたしかに勇気もわいていたが、一方では桃子を見送った後も桃子の言葉にショックを受けていた。「ずっと一人で決めてきた。」 (あの人がプロポーズの素振り一つ見せなかったのは、そういう恵子に抵抗があったからなのかなあ。やっぱり恵子の責任なんだわ。) 「ふう。」恵子は思わず、長い溜息を吐いた。
そのとき、徳子が電話で「今から行きます」と言ってきた。
徳子は例の事件のとき、新聞を叩きつけて怒ったことがあった。それから恵子は徳子のことを負けん気の強い子だと見ていた。その後も、徳子は恵子のノウハウを吸収している様子だった。店に入るときはたいていの女の子は恵子ママに倣って一礼してから入ってくるが、徳子は自分ばかりか若い子にもそれを指示していた。店の清掃や花にも注視していた。だから、彼女ならママとしてやっていけると見ていた。
恵子は、やって来た徳子に「徳ちゃん、ママをやってみたくない?」との話を持ち出した。
徳子は言った。「ママになりたいです。」
「私の店を買わない?」
「エっ!」
「ママはどうするんですか?」
「そうね。少し休憩しようかしらと思っているのよ。」
「お店って、幾らですか?」
「あなたが出せるだけでいいわ。」
「少し考えさせてください。」
「もちろん、いいわよ。」恵子は徳子と話すうちに、ママの姿勢になっていた。「ところで徳ちゃん、あなた彼氏は?」
徳子は外人のように彫りのある美人である。男たちにもてるはずだ。
「彼というか、ボーイフレンドというか、一応います。」
「そう、よかったわね。」どんな人?と訊くのも野暮だと思いながら、恵子は続けた。「よく、お客様が冗談をおっしゃるでしょ。『女房次第で亭主は良くもなる、悪くもなる』って。でも、それは女だって同じよね。『男次第で女は良くもなる、悪くもなる』って。ふふ、」恵子は笑って言ったが、恵子はそれを身をもって体験した。(健に救われ、健のお蔭で幅のある女になり、健のお蔭で幸せを味わった。最後には健から赤ちゃんまでもらって、生まれてくるこの子と生きていける自信をもらった。そんな守護神みたいな人、それがほんとの男じゃないの!)
恵子は、徳子の彼がどういう男か想像もつかないが、徳子が店をやるとしたら、うまくいってほしい。そのためにはゆとりのあるママにならなければ。まちがっても、店の女の子と張り合うようなことはしていけない。だから、いい恋人を持ってほしい。しかし、それを直接言っては説教じみてくる。ここは自分のことを話した方がいいと思った。「私には、いま愛する人がいるの。その人のために休憩したいの。」
徳子は驚きながら、恵子ママのことを穴のあくほど見詰めてから訊いた。「結婚するんですか?」
「さあ、どうかしら。私はその人のためにどうしたらいいかだけを考えたいの。そして決めたことは絶対彼のためになると信じて、」
(恵子が見るかぎり、徳子は私のやり方をかなり吸収している。きっと男性観についてもそうしてくれるだろう。) 恵子はそう信じた。
夜になって、恵子は健に「秋田に一緒に行ってほしい」と電話をした。
実家は母方の従妹夫婦に貸していた。健が了解してくれたので、恵子は恋人と一緒に帰郷する旨を伝えた。
秋田では父方、母方の僅かな親類だけを招き三回忌を行った。お墓で眠る亡き両親には、子供ができたことを恵子だけが胸の内で報告し、預けていたお位牌も東京へ連れて行くことにした。
その夜、実家の座敷に二つの布団が敷かれていた。健は布団に入って間もなくして、恵子の布団に入ってきた。
恵子は健を一つ布団に迎え入れながらも、「ここでは許して」と健の耳に囁いた。健も素直に聞き入れてくれた。しかし恵子は (困ったな) と心の中で小さな溜息を吐いた。これから半年ちかくも健の求めを断わらなければならないことに気が付いたからであった。夫婦なら労り、協力し合うこともできるが、健は恵子が妊娠したことを知らない。恵子は (私は何をしているんだろう) と思った。(「一人で産む」「健と別れなければならない」と思いながらも、この人を秋田まで連れて来てしまった。いつか桃子さんは「未練も愛なのよ」と言ってくれたが、お腹が目立つ前に、この人と別れなければならない) そう思いながら、眠る健の手を取って恵子は自分のお腹の上に健の手を置いた。(この人と、近いうちに離れなければならない。そのためにはこの秋田で出産するということもあるかもしれない。) そう思って障子の向こうの廊下を見やると、明るい。月の光でも射しているのだろうか? 恵子はハッとして呟いた。「ニューヨーク! そうだわ、ニューヨークで妊娠したんだから、ニューヨークで出産しようかしら!」
東京に戻った恵子は、アメリカ留学から帰国して間もないと聞いていた、店のお客の医師に電話して、「ニューヨークで出産する友人がいるので、いい病院を紹介してほしい」と依頼した。そのドクターは「だったら、自分がいた病院がいい」と即答で産科の女医まで教えてくれた。
それを聞いてて恵子はにゅーよーくでの出産を決意した。
いざ決断してみると、新たな道筋も見えてきた。健が言ってくれた「ファションか、化粧品をふくめた美関係」をニューヨークで勉強してみようという考えもわいてきた。そうなると、自分を自分で納得させる理由かもしれなかったが、店を打って夜の世界を卒業し、新たな事業を手掛ければ、あの人の住む世界に近づくことができる。(私は、別れるのではない。一時、離れるだけかしら。) そんな新しい気持に切り変わっていった。そして新しい道を歩むために、秋田の実家はもう従妹夫婦に上げようと思った。
ただ、恵子には耐えなければならない不安があった。(母子とも無事でありたい。しかし、病院で私の生年月日を見て、女医も、婦長も「大丈夫ですか?」と声をかけてきた。あれは私の高齢出産を心配してのことだろう。
(もしももしも、私がいなくなったら、この子はどうなるの? そのときは、恵子に代わってあなたにお願いするしかないわ。恵子のわがままを恨んでもいいから、罪のないこの子だけはあなた! どうかお願いします。)
翌日、恵子は知り合いの弁護士に会って、遺言状のようなものを書いて、あずけた。
一、美薗恵子が死んだときは、全財産の二分の一を野中健へ、二分の一を美薗恵子と野中健との間にできこの子に遺す。ただし、その子が成人するまで、野中健に見守ってほしい。
一、美薗恵子と生まれてきた子が共に死んだときは、野中健に全財産を譲る。
遺言は、この二つのケースしかなかった。
ほんとうはもう一つのケースがあった。しかし、もし赤ん坊だけがダメだったときは、私は生きてはいない。私が健に内緒で勝手なことをした罰は受けなければならない。これが恵子の覚悟だった。
さらに恵子には、女として拭い切れない心配があった。(半年間、健と離れているとき、健に新しい恋人ができたらどうしよう。)
何か月か前に偶然見かけた、消防病院で健と話していた和服の女性、ああいう普通の善き女性に恵子は弱かった。そして普通の善き男性を好きになった恵子は弱かった。
前に店にいた子のお見舞いに、店の女の子と一緒に消防病院を訪れたとき、待合室でその女性は健と向かい合っていた。健は背中を、女性は顔を、恵子の方に向けていたが、二人とも紳士、淑女のように誠実な態度だった。二人は別れるときも握手ひとつしなかったが、博多織を着た女性の健を見る慈しみにあふれた眼差しに、恵子は激しく嫉妬した。たぶん二人は昔の恋人どうしだったのだろうが、ああいう女性こそが健にはふさわしいのかもしれない。だからこそ、ああいう女性は健の前に現れてほしくない。恵子はこれだけは考えるのも嫌だった。
徳子が「ママになりたい」と言ってきた。ただし「店を購入する額は相場の三分の一ぐらいしか用意できない。残りは借金したい」と言う。
恵子は、これで儲けようとは思っていなかったから「そう。じゃ相場の三分の二でいいわ」と返答した。
つまり三分の一は現金、三分の一は借金で手を打ったのである。
その夜、やって来た健にも恵子はそのことを報告した。
健は喜んだ。
「徳ちゃんがね、最後の三日間を〔恵子ママ、ありがとう〕のサービスデーにすると言ってくれてるの。」
「おお、恵子の晴れの舞台だな。」
このとき、恵子はふっと思った。「ね、あなた。最後の日に恵子をお迎えに来て頂戴。」
「え~! おれはそういうキザな役は似合わないよ。」
「そういうことではなくて、」
「いやいや、」
「恵子の一生のお願いよ。」恵子は健の膝の上に乗って甘えるように言いながらも、一方では (ああ、ニューヨーク行きはどう切り出したら、いいだろう) と胸を痛めていた。
翌、日曜日のこと、健が「何年か前の映画だけど、『ニューヨーク・ニューヨーク』を観に行こう」と言い出した。
ライザ・ミネリとロバート・デ・ニーロの音楽物語だった。ジャズバンド付のシンガーだった人たちが、ジャズシンガーとして独立してゆく過程が描かれている映画だった。
帰りの車の中、恵子は言った。
「ねえ、前にあなたが『恵子は、ブティックなんかの店主が似合うかもしれない』って言ってくれたでしょ。」
「うん、今でもそう思っている。おれは恵子がママをやめてくれる決心してくれたことがすごく嬉しい。だからといって、これから何をやれっていうのは分からないが、そんな道はあると思う。」
「ほんと。」
「うん。」
「もしもよ、もし外国へ行ってそういう勉強をしてみたいと言ったら、あなた許してくれる?」
「何処へ?」
「分からない。何処へ行っていいか判らないもの。常識的には、パリとか、ミラノとか、ニューヨークかなっていうぐらい。」
「何か月ぐらい?」
「それも分からない。だって恵子はあなたと離れたくないもの。」まだ一部の迷いを捨て切れないでいる恵子は、「離れる」とか「別れる」とかの言葉が出ただけで、あやうく涙が零れそうになる。「もう、こんな話はやめましょう。」恵子は辛くなって話を打ち切った。
健は、「女性ジャズ・ボーカルの草分け的なエラ・フィツジェラルドやダイアナ・ロス、ここら辺まではラジオの方がレトロな音調にピッタリだな。その後の、声量豊かなサラ・ボーン、〝ニューヨークのため息〟と呼ばれたヘレン・メリル、クールなペギー・リーやハスキー・ボイスのジュリー・ロンドン・・・・・・、これらはステレオの方がその雰囲気によく合っていると思うよ」なんて話を口にしていたが、どこか話が上滑りしている。
と思ったら、突然、車を停めて、言った。「恵子、ニューヨークに行ってみたら。」
(この人は、私のニューヨーク行きのことをずっと考えてくれていたんだ!)
恵子は健の首に抱きついた。もう堪らなかった。赤ちゃんができたことを健に内緒にしていることが。恵子は堪え切れずに泣き出した。(正直に言わなければ) そういう思いが喉まで出かかったが、必死で押さえた。(私がやって上げられることは、この人を自由にしてやることだけ。それに、この人はいま自分の道を探している大事な時期。そんなときに、「妊娠、赤ちゃん」を言ってしまえば、二人の関係が壊れ、永遠の別れが襲ってくるようで、怖い!!)
〔クラブ恵子〕改め〔クラブ徳子〕において、【恵子ママ ありがとう】デーが三日間、華やかに開催された。これまでの〔クラブ恵子〕のお客様総勢600名をご招待するというものであったが、恵子は「ご恩返しだから、完全無料にする」と言った。そのためか、かえって御祝儀が集まり、そして部屋には豪華な花束がびっしりと埋まった。花には全て贈り主の名前が明記してあったが、ほとんどが有名人ばかりであった。そんな中に最後に届けられたのが、365本の真っ赤な薔薇だった。カードには【Lovin’you】とだけあって、贈り主の名はなかった。そのカードを見て、恵子は大きな花弁に優しく口づけをして、部屋の真ん中に飾るように若い子に指示した。
それを見ていた徳子は、それが恵子ママの恋人から贈られた薔薇だということがピンときた。徳子は恵子ママの恋人に強い関心をもっていた。恵子ママを水商売から足を洗わせるほどの男とは一体誰だろう? 実業家? 芸術家? 芸能人? それが誰であっても、恵子ママにはよく似合う。そう思った。
恵子は三日間の着物を自分でプロデュースした。それは健への思いを込めたものであった。
一日目は〔歓び〕をイメージした。健と初めて結ばれた日は満月と桜の花が満開の夜だった。着物の模様も桜の花が満開だった。髪には本物の桜の花を取り寄せて飾った。女の子たちが口を揃えて「ママ可愛い」と称えた。
二日目は一転して〔嫉妬〕をイメージした。紫紺の襦袢に真っ赤な炎色の着物、髪は紅蓮に染めて逆立てて、(あの博多織の女の人が現れたら、私は鬼になるかもしれない) と思いながら、目と眉を激しく描いた。お客たちは炎の恵子を見て、異口同音に「スゲー」と感嘆した。
三日目はさらに一転し〔祈り〕をイメージした。健が迎えに来てくれることから、恵子にとっては思い出の純白の綸子を装うことにした。口紅とマニュキュアの色を伊達襟の紅の色と全く同じにした。恵子は鏡に映る花嫁に似た自分の姿に健との再会と安産を祈った。それを知らぬお客たちは、色香漂う恵子の姿にうっとりしているのであった。
三日間、客は恵子と並んで写真を撮った。女の子たちも撮った。
徳子は、ピアノの弾き語りの女性から、【Lovin’you】が歌の題名だということを聞いて、ママの恋人が現れたら、その曲を弾くように頼んだ。
三日目の夜中の1時半、お客がすべて帰ったころ、健が恵子を迎えに来た。
女の子たちは野中を見て不思議な顔をした。
(まさか?) 徳子は戸惑った。徳子は野中のことをほとんど知らない。ただ、しっかりした人だという印象はもっていた。
恵子ママが、健の首に抱きついて深いキスをした。
店の者は(エッ!恵子ママが)と、呆然となった。
徳子も驚きながら、合図した。ピアノが【Lovin’you】を弾き始めた。
恵子は健の首から腕を外そうとはしなかった。恵子は薔薇に込めた健のメッセージを感じとって泣いていた。
それを見て、女の子たちももらい泣きした。
徳子には分かった。(恵子ママの涙は、自分のためではない。ママは、恋人のために泣いている。) 徳子は背筋に戦慄が走るほどの感動を覚えた。(ママってやっぱりすごい! わたしなんかのようにミーハーじゃないんだ。自分の道を自分の脚で歩いてる。わたしも今日から恵子ママのように生きていきたい!)
(XIII.〔Still I Love You〕へ続く)
*この作品はフィクションです。仮に同姓、同団体の名前がありましても、この小説とは全く関係ありませんので、あらかじめご承知おきいただきたいと思います。ただ、一部の商品名につきましては、時代性を表現するために表記しましたので、併せてご理解いただきますようお願いいたします。
〔ほしひかる☆作〕