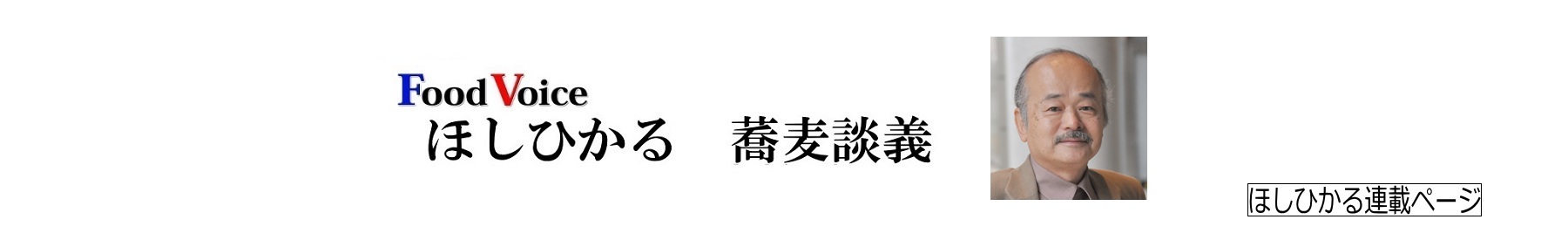第438話 目黒の秋刀魚
2025/12/06
~ 落語模様 ~
「上方落語と江戸落語」というテーマの落語会の、ご招待に甘えることにした。
なぜかというと、前のときも上方落語に大笑いして楽しんだことがあったからだ。
そのときは、桂ざこば師匠の身体ごと客にぶっつかってくるようにして会場を笑いの渦にする上方落語のサービス精神にほんとうに感心したものだった。
今日はといえば、上方落語は笑福亭たま師匠、桂まん我師匠、江戸の方は立川こはる師匠、ものまねの江戸家まねき猫師匠が出演するという。いわば「西・東の落語を聞き比べてみてはいかがですか」というのが、会を企画した南大塚ホールの意図である。
上方の、笑福亭たま師匠は全身で笑いを表現し、皆は腹を抱えて笑い狂った。
そもそも上方の人間にはそういうところがある。
今夏の14回江戸ソバリエ認定講座を受講されている三遊亭金也師匠にそんな話をしたところ、「ほんとうに上方の人はコワイくらいの迫力がありますよ」とおっしゃっていた。
そういえば、ソバリエ講師の林幸子先生も関西出身だけあって大の落語ファンだけど、先生の母上様は一日一回は人様を笑わせないとその日一日が無駄に生きているような気がするというくらいだというが、とにかく上方落語は滅茶苦茶に面白い。
かといって、無茶苦茶だけでは名人にはなれないのは当たり前だ。人情話なら心から泣かせるくらい、怪談ならほんとうに背筋を寒くさせるくらいの磨かれた話芸を持った人が名人と呼ばれるのだろう。そんなことから、怪談噺をするとき、冷房を一段と効かせたなんていう笑い話を桂まん我師匠が披露していたが、それはともかく、落語に古典とか名作とかいうときもあるが、それは結果であって、それだけ話芸が優れていたからこそ伝説となったということだろう。
そんなことを考えていると、たまに拙い講演などをしている者としては、少しぐらいお客さんを笑わせたり、「そうだったのか」という落ちをつくって納得してもらうように、もっと勉強しなくてはと反省した・・・。
さて江戸の方の、江戸家まねき猫さんは亡き猫八師匠の娘さんだという。そういう血筋のよさと女性らしさもあってか、大きな声の上方落語の後だけにほっとする。もちろん芸も巧い。
もう一人の、こはるさんは「私は少年ではありません。これでも女です」から始まったが、とにかく元気がいい。
お題は「目黒の秋刀魚」。
こはるさんは、秋刀魚を焼くとき飛び散る脂、そして焼き立ての熱々の魚を口にするあたりを、精一杯演技してくれるから、聞いている私たちも秋刀魚を食べたくなったほどだ。
この噺の落ちは、よく知られているように「秋刀魚は目黒にかぎる」だが、それよりも、当時庶民は青身魚の焼立てを食べていたけれど、殿様クラスは食べていなかったことが、この落語の背景にあるようだ。
話は変わるが、テレビ番組関係の調査会社から電話で度々尋ねられることがある。
「落語で、『死ぬまで一回、蕎麦をどっぷり付けて食べたかった』って言うじゃないですか。あれは蕎麦好きの本音ですか?」 「・・・・・・!」
「・・・・・・!」
これはだナ。「落語で、『秋刀魚は目黒にかぎる』って言うじゃないですか。昔は目黒の秋刀魚は有名だったんですか?」って訊いてくるようなもんだ。
どうして、話の背景としての、「江戸の蕎麦つゆは濃い」というところに目がいかないのか?
「江戸で必然的に生まれた濃いつゆだ。江戸っ子は決してそんなことは思わねえ。」と言いたいところだが、気を取り直して「あれはお笑いですよ」と申上げることにしている。
しかしながら、それはおそらく!
「秋刀魚は目黒にかぎる。」
「死ぬまで一回、蕎麦をどっぷり付けて食べたかった。」
という‘落ち’があまりにも効きすぎたせいだろう。
つまりは、名作すぎる落語は世間の認識までも変えてしまうのかもしれない。
〔文・写真(ざる蕎麦) ☆ 江戸ソバリエ認定委員長 ほしひかる〕