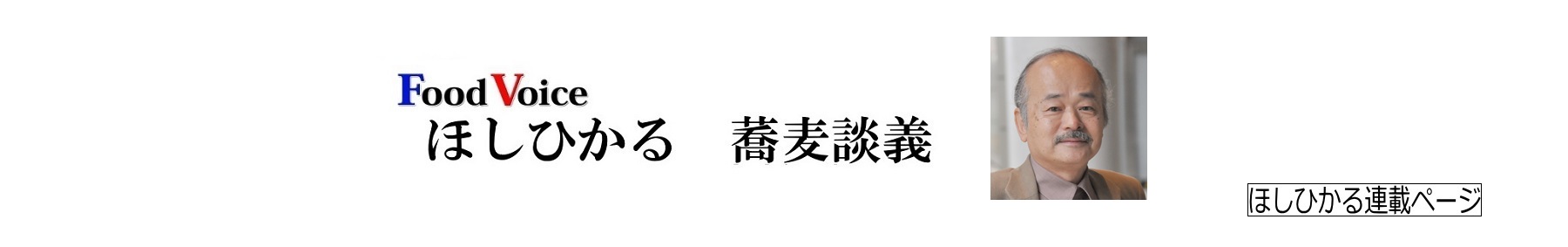第483話 花鴨を愛でる
2025/12/06
北京紀行-3
蕎麦に関わっている者は北京名物《北京ダック》を食べるべきだと思うようなことがあった。
それというのは、以前にテレビで「蕎麦屋で鴨と言っているのは、実はアヒルだった」というようなことを放映していた。
実を言うと、この番組から江戸ソバリエ協会へ事前の問合せがあった。「蕎麦屋で鴨と言っているのはアヒルだと聞いたが、ほんとうか?」と。私は「蕎麦屋で使うのは『合鴨』といって、『真鴨』と『家鴨=アヒル』の交配種だ」と答えたが、調査員は「でも、ある蕎麦屋に訊いたところ、アヒルだと言われた」と頑固だった。私の云うことより、蕎麦屋さんが正しいというのだろうか。それとも電話やメールなどの調査は往々にして理解不足が生じるから、消化不良のまま番組が制作されてしまったのだろうか。とにかく、番組は「実はアヒルだった」で仕上がっていた。したがって、コメンテーターも「そうだったんですか。がっかりですね」みたいなコメントを発している。
「がっかり」とはどういうことか? そこで海外に目を向けてみよう。
たとえば、北京市内をタクシーに乗っていて回っていると、街のいたるところに《烤鴨 カオヤー》店の看板が目に入る。いわずと知れた《北京ダック》のことである。
「なぜ、ダックが鴨なのか」というと、日本語では「アヒル=家鴨」、「カモ=鴨」と書き分けているが、中国語では「アヒル=鴨」、「カモ=野鴨」なのである。だから「北京ダック=北京鴨」でいいわけだ。
要するに、日本字では「家鴨」であるため、ペットのように思われているせいか、可愛いペットを食べるとは何事かということになってしまった。しかし世界では「アヒル」も、名物とされるぐらい盛んに食べられていることをあらためて認識していただきたいと思う。
ついでながら、なぜ「烤」の字かというと、当初の《北京ダック》は南京の料理だった。その南方では炙るは「焼」の字を使うから、南京のころは《焼鴨》だった。それが明代の永楽帝が北京を首都としてから、北方で使う「烤」が正式になった。だから《烤鴨》なのである。
北京ダックは「填鴨」つまり餌を無理して詰め込んで太らせるということはよく知られているが、それだけではない。元となる鴨の品質が大事で、そのうえ肥育法もなかなか難しく、下手をすれば死んでしまうらしい。だから他の所で真似できないのである。
この鴨の焼き方については、モノの本によると二通りあるらしい。
一つは明朝時代に考案された扉付の炉で蒸し焼にする南方流。アヒルの腹の中には香味野菜と調味料、スープが詰め物として入れられていて、余熱で蒸し上げられることで詰め物の風味が肉にゆき渡って肉が柔らかく仕上がるという。
もう一つは清朝末期に考案された扉のない炉で直火に炙る北方流。とうぜん皮がこんがりと香ばしく焼かれる。
老舗の、『便宜坊』系の店は前者の焼き方、『全聚徳』は後者のやり方を受け継いでいるという。日本では西日本の料理と東日本は大きく違うが、中国・北京では南方と北方の違いがあるようである。
ところで、私たちは、北京最後の晩餐会は《北京烤鴨》にしようと決めていた。選んだのは『全聚徳』。創業は清朝10代皇帝同治帝のころというから、150年は経っている。
北京を訪れて北京の代表的食《北京烤鴨》《満漢全席》《涮羊肉》などを頂くとしたら、各々の老舗『全聚徳』『仿膳飯荘』『東来順』などだろう。
たとえて言えば、来日した外国人が、《蕎麦》を食べたいと云ったなら、それは日本の伝統食文化に触れたいという意味だから、やはり《江戸蕎麦》の老舗に案内すべきということと同じだろう。老舗というのはその存在そのものがすでに文化なのである。
さて《北京烤鴨》の店に行くと、たいてい厨師(料理人)がお客の卓の近くまで来て、初めに短冊(簽)に切った鴨肉をきれいに並べて花状に飾ってくれる。写真がそれだが、これが話に聞く南宋時代の孟元老の著『東京夢華録』にある「入炉細項 蓮花鴨簽」というやり方だろうか。
日本では江戸初期になってやっと外食店が誕生しているが、中国では宋の時代に外食店の花が開いている。そんな中での「鴨店」で見られた「蓮花鴨簽」の技は、すでに宋の時代の人が食に美的な楽しみを見出していたということだろう。
続けて、厨師は客のために鴨肉を切る。それを客は、細切りの葱や胡瓜とともに「甜麺醤」という味噌状のものを塗って小麦粉製の「荷葉餅」で巻いて食べる。
北京の《ダック》と蕎麦屋の《鴨》はまったく違う。とても「実はアヒルだった」とは言えない。
それにしても、「厨師が客のために鴨肉を切る」という行為はいつから始まったのだろうか? まるで皇帝のように、客を贅沢な気分にしてくれるではないか。その始まりをちょっと調べてみたくなった・・・!
〔文・写真《蓮花鴨簽》 ☆ 江戸ソバリエ北京プロジェクト ほしひかる〕