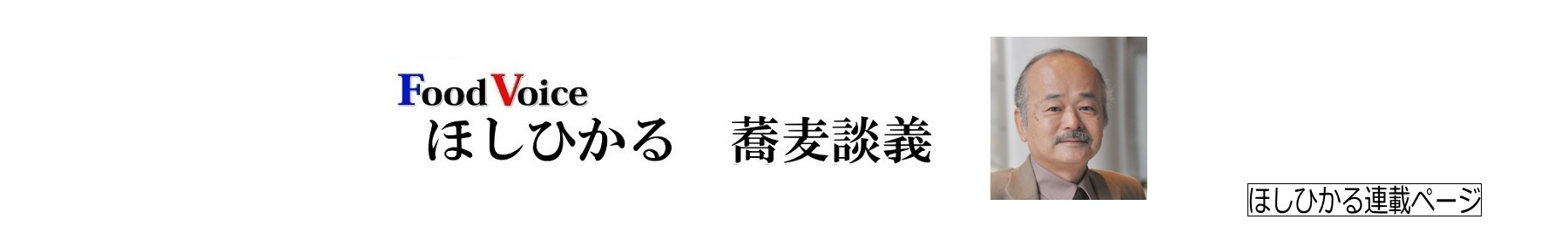第487話 人間の七味
2025/12/06
北京紀行-終
『紀行』は前回で終わったが、ある人が「もう終わりですか」と言ってくれた。もちろんただの儀礼的言葉だと分かってはいたが、図にのってもう一回だけ延長してみた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お蕎麦の話をするときに「薬味」についてもお話するが、その余談として「人間にも七味がありますヨ」なんて冗談を言うことがある。
「それは、嫌み・蔑み・恨み・嫉み・妬み・僻み、弱みの七味です」と。
皆さんは失笑しながらも、「なるほど」と肯いたような表情をされることもある。
小説や映画というのは、このような七味を扱った物語が多い。とくにこの七味をミステリー仕立てにすれば、面白い作品になる。
たとえば、五、六年前に放映された『北のカナリヤたち』(原作:湊かなえ・監督:阪本順治・主演:吉永小百合)という映画があった。
人間の弱みが一度スパイラルに陥ってしまうと、不幸がさらに重なってまた堕ちていくという人間社会を縮図のように描いた重い物語であった。
それでも制作者はそんな中に日本人らしい情けと優しさを用意してくれており、それによって観客はホッとして涙する。そんな映画だった。
今回は、この度の中国紀行のご縁から、中国のそういう傾向をもつ小説を少しご紹介しよう。
紹介したい中国小説は中島敦の『山月記』である。
唐時代にある秀才が官僚試験に合格して役人になった。ただ彼は優秀すぎたためか、身分の低い役人のまま甘んじるつもはなかった。
その上、彼は他の者と協調しようという気持が全くない。そのため誇り高い彼は周りとうまくいかず、官を退いて故郷の山で余生をおくることになった。そういうことになっても、彼は相変わらず人との交わりを絶ってひたすら詩作に耽っていた。しかし、彼の詩は世の評価を全く受けなかった。日増しに貧乏になっていった彼は、家族のために屈辱のまま再び小役人となったものの、彼の秀才としての自尊心は昔のままであった。だから彼は、そこでも浮上しなかった。ついに彼は絶望し、発狂した。
ここまでは私の云う、「人間の七味」剥き出しの物語であるが、小説の後半がすごい。
発狂した彼が猛獣の虎になるのである。そして一日のうち数時間だけ人間の心が戻ってくるという。そうした時に彼が悟ったのは、人には誰も獣の心があるということであった。その描写に哀しさと詩情があり、芸術性豊かなファンタジーとなっている。文を書く者なら、こんな小説を構想したいと思わせるほどだ。
もう一つご紹介したいのが魯迅の『阿Q正伝』である。題名がユニークだから人に「どんな内容の本だろう?」と思わせるところがある。
そこで「阿Q」という主人公の名前だが、「彼は確か、阿という姓だった。しかし名前が桂だったのか、貴だったのか」、誰も気にもしていないし、誰も知らなかった。要するに名前すらはっきりしない男が主人公というわけである。だからといって、その男について書く場合、「某という男」じゃ面白くない。そこで魯迅は「阿Q」としたというわけである。
しかも、その男は貧乏で、頭が悪くて、グズ、その上なさけない性格で、どうしようもない男だったが、とうとう泥棒の濡れ衣を着せられた。しかし彼なら当然だと皆から見られ、無実にも関わらず死刑になってしまう。それでも人々はその男のことを気にかけなかったという話である。
何という小説かと思うだろうが、ただ作者の魯迅だけが無名の男の味方をし、「正伝」とはとてもいえないような彼の虫けら以下のような一生に、わざわざ「正伝」として記録してくれたのである。魯迅は、どんな人間でも救われると云いたかったのだろう。「善人なおもって往生を遂ぐ いわんや悪人をや」の精神であろうか。
この度、このシリーズでご紹介したように、北京の中学校で蕎麦教室を開いた。
「そのときの中学生の中に、魯迅の伝記を読んでいた子がいた」とメンバーの高橋さんが感心していた。私はその子を見ていないが、人間の七味を題材にして書いた魯迅に関心をもっている子がいることに、中国の確かな将来を感じたのだった。
〔文・挿絵 ☆ 江戸ソバリエ北京プロジェクト ほしひかる〕