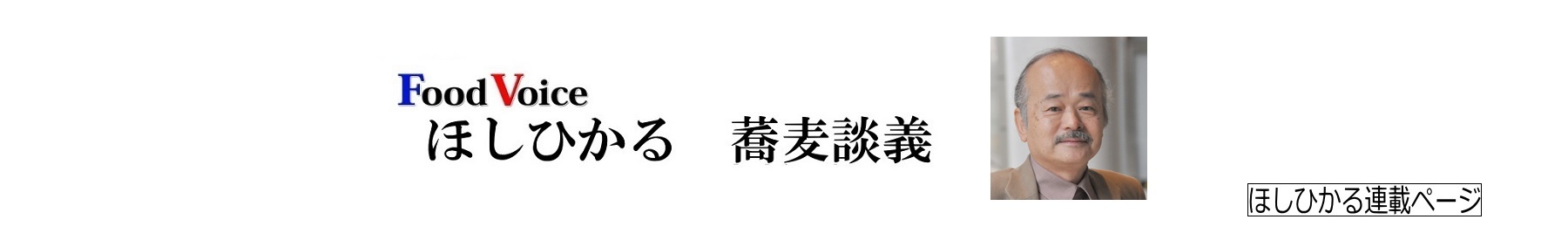第496話 明治42年へ時間移動
2025/12/06
蕎麦文学を残した作家の中で気になる人物が幾人かいる。その一人が田山花袋だ。そんなわけで思い立ち、彼の代表作『田舎教師』ゆかりの地である羽生に行ってみた。
☆建福寺
小説は「四里の道は長かった」で始まっていることで有名だが、東武鉄道に乗って着いた羽生はけっこう遠かった。
駅を下りると、すぐ近くに「田舎教師」が下宿していた建福寺があった。立派な山門を通ると、左側に『田舎教師』のモデルになった小林秀三の墓(狩野徳次郎筆)と、「田舎教師」という墓(小杉放庵筆)があった。
当寺の23世住職と花袋は交流があった。花袋は住職から、21歳の若さで病死した田舎教師小林秀三の日記を見せてもらって読んでから、小説『田舎教師』が誕生したという。発刊は明治42年だった。ちなみに、花袋の細君はこの住職の妹である。
ソバリエとして見逃せないのが、『田舎教師』に出てくる「寺では夷講に新蕎麦をかみさんが手ずから打って」という一文である。
「手打ち蕎麦」のことを機械打ちではなく手(Hand)で作る蕎麦だと思っている人がいるが、現代ではまあ間違ってはいないかもしれない。しかし「手打ち蕎麦」という言葉は、機械打ちのなかった江戸時代から使っている。だから、元々は「自ら=手(テ)ずから打った蕎麦」が「手打ち蕎麦」だったのである。
蕎麦好きだった花袋は、作家らしく蕎麦のことをきちんととらまえて創作をしていたことが伺える。
☆「小川ゆでめん店」の自家製《ひもかわ》
さて、時計を見るとちょうど昼時である。ぶらぶら歩いて行くと、「小川ゆでめん店」という看板が目に入った。
「ここで昼食をとろう」と思って店に入ると、お客さんが何組も入っている。
壁に掛かっている調理責任者は「小川菊二」とある。なぜ名前まで書いたかというと、同姓同名のソバリエさんがいらっしゃるので、つい書いてしまった。でも、店主らしき人の姿は見えず、女将さんが一人で働いているだけだ。
「何になさいますか?」
「何がおすすめですか?」
「そうですね。《ひもかわ》がね、当店の逸品といってますけど、」
「じゃ。それでお願いします。」
《ひもかわ》はすぐ運ばれてきた。
「頂きます」と言って噛むと、自家製麺の味わいがした。
食べながら店内を見回すと、焼酎やビールの箱や、なぜか中華麺の箱までが山積み、小上がりの所や卓の下には、週刊誌・マンガ・スポーツ新聞が重なっている。卓の上に置いてある品書も、箸入や薬味入もかなり古い。
小説『田舎教師』では、蕎麦屋の場面が幾度も描かれているが、もしかしたら昔の蕎麦屋や食堂はこんな雰囲気ではなかったろうかと想った。
食べ終わってから、代金420円を支払って、これから行こうとする弥勒地区までは「歩いて遠いですか?」と訊いたところ、「歩きでは無理ですよ、ねえ」と、女将は目の前で食べていたご夫婦に投げかけた。
「え~、かなりありますよ。食べ終わったら、車に乗せて行ってあげます。」
「えっ!いや~、申訳ないですよ、」と言いながら、私は親切に甘えた。
☆日照寺
車中で、ご夫婦のお名前を伺うと、Iさんとおっしゃった。
時々お店に見えるらしく、「小川ゆでめん店」の主人はもう92歳になられるという。小規模ながら製麺業も営んでおり、他の店舗へも卸しているらしい。
私は「だから自家製の味わいがあったのか」と得心がいった。
Iさんの車は田園の中を走る。小説によると、弥勒辺りでも明治時代頃には蕎麦が穫れていたらしい。その広い風景を見ながら、歩いていたらとんでもないことになっていたことを思い知った。
しばらく行くと、田舎教師の銅像が立っていた。教師が勤めていた弥勒高等小学校の跡もあった。そしてすぐ近くに日照寺があった。木造建ての古い寺である。
『田舎教師』では「小川屋」という料理屋が登場し、その店にはお種さんという若い女性が働いていたらしい。この日照寺にはそのお種さん資料館というのがあると聞いていたので、来てみたかったのである。
車を下りると、山門が迎えてくれる。
私は、いつも寺の山門が気になるのだが、この寺の木造の山門は一見の価値があると思った。Iさんご夫婦はいつもは通過するだけで、寺内に入ったことはないらしく、やはり山門に感心されていた
小さい寺であるから、資料館はすぐ分かった。寺の境内も資料館の中も、人は誰もいない。
館のガラスケースの中には、「小川屋」で使用していた白磁の蕎麦猪口が陳列してあった。主人公は、《ざる蕎麦》や《天麩羅蕎麦》いわゆる「江戸蕎麦」をよく食べているが、こんな猪口で啜ったのだろうかと想ったりした。それだけでも「貴重な物を拝見できて、よかった」と思った。
それから、Iさんは図書館にも連れて行ってくれて、最後は羽生駅で下ろしてくれた。結局は、「小川ゆでめん店」 → 日照寺 → 図書館 → 羽生駅とご案内していただいたのである。何とまあ、親切な方だろうとありがたく思った。
東武線の羽生駅に入った。高くなったホームから建福寺が見えた。
小説は、若くして亡くなった田舎教師が教えた女生徒がやがて教師になり、そして「秋の末になると、いつも赤城おろしが吹きわたって、寺の裏の森は潮のように鳴った。その森のそばを足利まで連絡した東武鉄道の汽車が朝に夕べにすざましい響きを立てて通った。」と、明日への期待が込められて終わっている。
私は電車に乗ってから、「いつかまた『小川ゆでめん店』を訪ねたい」と思った。そうすれば、また時間移動して、明治40年代の弥勒の風景と、Iさんのような温かい人情に出会うことができるかもしれない・・・。
〔文・写真(日照寺山門・「小川屋」の蕎麦猪口) ☆ エッセイスト ほしひかる〕