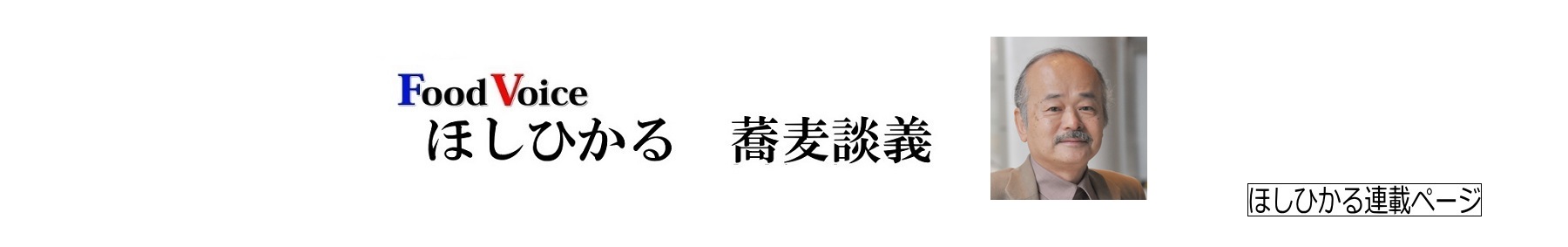第614話 人の橋、人の道
2025/12/06
待ち合わせの時間より30分早く着いたので、隣の古本屋に入ってみた。本棚を眺めているうちに内田康夫の『黄金の石橋』というのが目に留まったので買ってみた。そして用件を済ませ、喫茶店に入ってその本を読んだ。
本と珈琲はよく合うと思う。僅かなカフェインだけで覚醒作用を起こすとは思えないが、珈琲の苦みが読書には都合いいのだろうか。
読書といえば、私の竹馬の友であるTクンの、親父さんは煙草と酒と本が大好きだった。いつも煙を吹かせながら、盃を傾け、よく本を読んでいた。なかでも推理作家のクロフツのファンだったようだが、その親父さんはチェーンスモーカーならぬチェーンリーダーだった。何しろ本を手放したことがなかった。
私はといえば、酒を飲むと眠くなるからとても読書どころではない。
そんな昔話をしたいところだが、その親父さんはむろんのこと、竹馬の友のTも先に逝った。彼とは小学生になる前から一緒に遊んでいた幼馴染みだった。周りの人たちからは「兄弟のようだ」と言われていた。だからTの訃報を聞いたとき、ついつい嗚咽が止まらなかった。
チェーンリーダーといえば、昔、在職していたころに本の虫の先輩が二人いた。一人は開発部長、もう一人は総務部長だった。二人とも仕事中でも本を読んでいた。本の虫の親父さんと先輩たちに共通していたのは‘判断力’であった。アナログの読書量というのはデジタルの情報量には及ばぬことを後で知って、私は舌を巻いたものだった。
さて、『黄金の石橋』の方は、埋蔵金か何かが石橋の何処かに隠されているのではないかということに殺人事件が絡んでいる話で、例によって素人探偵の浅見光彦が解決するという筋である。
舞台は鹿児島、だから甲突川の五石橋(玉江橋、新上橋、西田橋、高麗橋、武之橋)も登場するし、長崎の眼鏡橋や、熊本の通潤橋という名橋も出てくる。みんな有名な眼鏡橋だ。
この石の眼鏡橋やさらには古い木の橋などは‘景色’がいいから、みな名所になっている。ただし、これらは地方である。
保田與重郎の『日本の橋』には、宇佐の呉橋、岩国の錦帯橋、日吉神社の本宮橋、木曽の桟橋、甲州の猿橋、日光の山菅橋など景色のいい橋が紹介されている。
しかし、東京にだって有名な橋はたくさんある。石橋でいえば、皇居の二重橋、日本橋、万世橋、浅草橋、蓬莱橋、江戸橋、京橋、鍛冶橋、呉服橋・・・。
でも、皇居の二重橋は別格として、都会の石橋はあまり注目されない。それは石橋が‘景色’になってないからである。それゆえに都会の石橋は段々と消滅していって交差点の名前ぐらいに堕ちているといった具合だ。
昔の都会の橋はそうではなかった。それぞれに物語があった。
たとえば、藤沢周平の『橋ものがたり』は江戸時代の萬年橋、思案橋、両国橋、永代橋、大川橋が描かれており、人と人との別れ、出会い、しがらみの舞台になっている。三島由紀夫の『橋づくし』は、三吉橋(三叉橋なので二つに数える)、築地橋、入船橋、暁橋、堺橋、備前橋の七つ橋を巡り渡ると願い事が叶うという話である。橋は、ここから未来へ橋渡しをしてくれるから縁起がいいというわけである。
しかしながら、それらの橋を訪ねると、いずれも現在は無残な姿となって機能している。どこが「無残な機能」かといえば、それらはもはや人の渡る橋ではなく、車の、物流の通路でしかない。もはや物語も景色も生まれないだろう。
須賀敦子は『橋』の中でヴェネチアのグリエの橋を渡るとき、靴のヒールの音の違いを描写している。まさに、これが人の渡る橋である。
そして今、橋ばかりではなく、とうぜん道路もまた同じ運命にある。道路は車道になって、人間の道ではなくなっている。交通事故の悲劇はそこから派生している。橋も道路も悲鳴をあげている。人の道、人の橋にする法はないものだろうか、と。サスペンス『黄金の石橋』に似合わないことを思ってしまった。
〔文 ☆ エッセイスト ほしひかる〕
写真:懐かしく素朴な木の橋