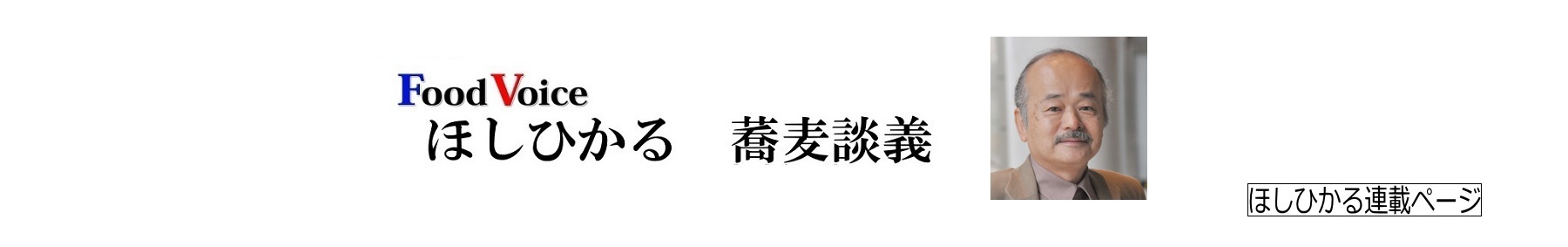第801話 映画『駅馬車』のコーヒー
2025/12/06
谷中の街を歩いていたら、「旬のアイスコーヒー」と謳った店がありました。

「暑いからアイスという旬はないだろう」と苦笑いをしたくなりましたが、意表を突いた発想は面白いと思いました。
ですから、隣のレストランで食事をしてから、立ち寄ろうかと思っていましたが、そのレストランでもコーヒーが出ましたので、残念ということになりました。ま、とにかく現在では食事の後はほとんどの人がコーヒーを飲みます。特に肉や脂物を食べた後は欲しくなります。
これほどコーヒーが広まったのには多くの理由があるでしょうが、私が思い浮かべるのは、かつての喫茶店文化、インスタントコーヒーの流行、そして珈琲専門店の登場などの影響が大きいかと思います。
しかし、いま街ではアメリカ流のチェーン店があふれています。アメリカへ、コーヒーはヨーロッパから伝わってきました。当初、ヨーロッパではコーヒーハウスが人気でした。そこではバッハ作曲の「コーヒー・カンタータ」などが歌われていたそうです。
そのコーヒーがアメリカに伝わってきても、高級な飲み物でしたので、大衆は紅茶を飲んでいました。それがボストン茶会事件(1772年)という植民地への嫌がらせみたいな事件が起きてからアメリカ人は紅茶を飲まなくなりコーヒー一点になったらしいです。
アメリカのコーヒーといえば、若いころに観た西部劇映画で、カウボーイたちが焚き火をしながらコーヒーを沸かして飲んでいたシーンがあったことを思い出しました。とくに映画『駅馬車』がそうであったような気がしたので、ひさしぶりに『駅馬車』をDVDで見直してみました。
『駅馬車』の、時代設定は南北戦争からしばらくした1885年ということになっています。駅馬車はアリゾナ州トントからニューメキシコ州ローズバーグへ向かって走るのですが、ほとんど疾走する場面ばかりです。だからスピード感のある映画になっています。
乗客は、牢破りでお尋ね者のリンゴ・キッド(ジョン・ウェイン)、街を追われた娼婦ダラス、妊婦の貴婦人、元は上流階級出で今は流れの賭博師、昔は名医だったというアル中男、人の好い洋酒販売の男、怪し気な銀行員、正義感と人情のある保安官の8名と、小心者ではありますが仕事に責任感をもっている御者1人。そんな乗客の素性が走る馬車の中で徐々明らかになってきます。そのなかからリンゴ・キッドとダラスの恋が芽生えます。そこへインディアンの襲撃がありますから、目が離せません。しかし戦いの中、男たちは男ぶりを発揮します。
ニューメキシコ州のドライフィールド駅に着いたとき、貴婦人が産気づきます。アル中の医師は濃いコーヒーをたくさん飲んで脳を覚ませて無事に赤児を取り出します。出産騒動後、ダラスが皆にコーヒーを淹れてあげます。ミルで粉を挽いて、その粉をお湯の入ったポットに入れて沸騰させます。当時はすでにドリップも、サイフォンも登場していましたが、まだ未開拓のアメリカ大陸の片田舎は、こんな淹れ方だったのでしょうか。そういえば、この映画は「長旅で疲れたでしょう。コーヒーでも飲みましょう」という台詞から始まっていました。ある駅馬車が到着したとき、馬車から降りた客を迎えに来た人物がそう言うのです。今さらながら、あれは今のこの場面のための布石だったのかと思います。とにかく、コーヒーのおかげでアル中の医師は男になりました。それから、落ちぶれた賭博師は中世の騎士のように貴婦人を守り切って最後はインデアンの弾で命を落としました。主人公のキッドはローズバーグに着いたとき、父と弟の仇を見つけます。キッドは牢破りの罰は受けるから10分だけ時間をくれと頼み、保安官は目をつぶります。それから仇をとったキッドは、1年経ったら罪を償って戻るからとあらためてダラスに求婚し、御者に自分の牧場までダラスを送り届けてくれるよう頼みます。
男たちによる西部開拓時代のアメリカらしい映画でしたが、そのなかでコーヒーが大事な役割をもっていました。
そこで、駅馬車流にコーヒーを淹れてみました。一般的に1人分はコーヒー10g、水120㎖で淹れます。そうしてできたコーヒーは、緑茶や紅茶と違って、解放的に西部劇流に飲むのが合っているような気がします。
〔エッセイスト ほし☆ひかる〕