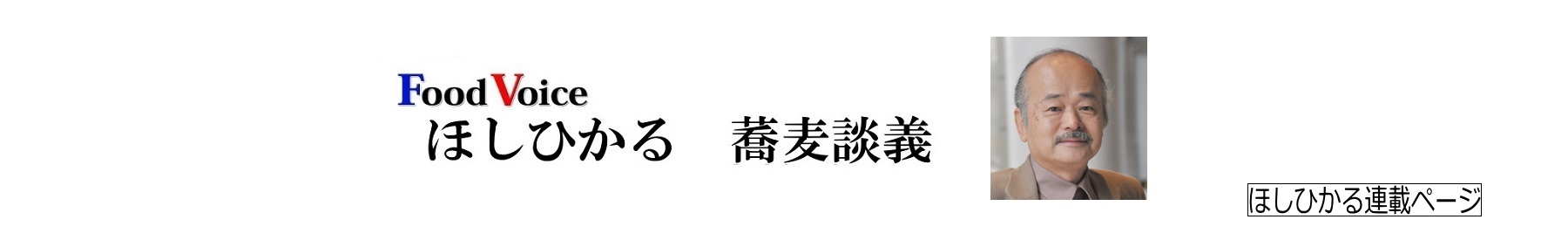第850話 岡本かの子の『鮨』の時代から
2025/12/06
ソバリエの小池ともさんから、インターネットラジオ放送局「ゆめのたね」の、ノコさんの対談番組『花咲くだんす』でソバリエの話をしないかと誘われた。
今日が収録日なので、「ゆめのたね」の神奈川スタジオへ向かった。
駅はみなとみらい線の元町・中華街、池袋から直通で行ける。
駅を右手に出てアメリカ公園の中を通って、みなとのみえる丘公園を観ながら右折するとイギリス館の前を通る、と前もってノコさんから伺っていた。
ン、すると見覚えのある所に出た。神奈川近代文学館前の信号・・・、文学館へはずいぶん前に来たことがあったことを思い出した。目指す「ゆめのたね」の神奈川スタジオは直ぐ近くだった。時計を見ると12時。実は初めての訪問先ということと、収録は13時からということだったので、早めの12時に到着し、どこかで軽く昼食をとってスタジオ入するつもりで自宅を出たのであったが、辺りは住所が山手町というだけあって住宅しかない。どうしようと思ったとき、思い出した。あの文学館にカフェらしきものがあったはずだ。そこで何か入れておこう。
文学館はレンガ造りの霧笛橋の右に建っている。正面は港だ。
 この「霧笛橋」を見るだけで、ボウ♪という霧笛の音が呼んでいるような気がする。
この「霧笛橋」を見るだけで、ボウ♪という霧笛の音が呼んでいるような気がする。
さっそく入館した。右手は展示室、左手がカフェ。前に訪れたときは展示室に行って、カフェには寄らなかった。今日は逆だった。展示を楽しむ時間はないから、右側に行った。ドアに「鮨喫茶 すすす」とある。
ふーん、「鮨喫茶」というのも「すすす」というのも面白い。
店内にはお1人様、2人組、4人組の先客がいた。ほとんど女性だった。店で働く人は3名。メニューを見ると、一番上に《岡本かの子の手鞠鮨》とあった。「文学館らしいな」と、それを注文した。
岡本かの子は、画家の岡本太郎の母だ。『食魔』『鮨』などの短篇小説がある。だからこの文学館の「鮨喫茶」でメニューの一つにしたのだろう。
話は、湊という医者が幼いころ、両親が悩むほどに嫌いな食べ物が多かったが、母親が苦慮の末、握り鮨を握ってやったところ、それをおそるおそる食べてみたら普通の食事も少しずつ食べられるようになったと、鮨屋の娘に語るというものだが、小説だからもう少しミステリー気味に書いてある。
今日の手鞠鮨は、名前の通り球状に酢飯が握ってあり、その上に肴の切身が丁寧にのせてある。頂きます。みんな小さいから一口で食べられる。味噌汁も付いていた。そういえば、かの子の鮨には《塩さんまの押鮨》というのが出てくるが、今日の手鞠鮨にはそれはなかった。尋ねてみたら「秋には出したい」という。そうか、ひらがなやカタカナで表記すると意味が消滅するが、漢字で書けば「秋刀魚」、文字通の〝秋〟だなと納得した。
かの子の『鮨』は1941年の作品だ。私が生まれる少し前である。
その中には、こんな箇所があった。
「女学校時代に、鮨屋の娘ということが、いくらか恥じられて、家の出入りの際には、できるだけ友達を近づけないようにしていた」。医師の話を聞いている鮨屋の娘のことである。また娘の親といえば、「自分は職人だったからせめて娘は」教育を受けさせてあげたい、と思っている。
そういえば、親しくしている蕎麦店「小松庵」の社長も同じことをおっしゃっていた。
「お前、蕎麦屋の息子か」と子供のころはいつも言われていた。
それがバネとなって小松社長は〝東京蕎麦〟という概念を考え出された。どういうことかというと、社員が胸を張って「私は蕎麦屋の社員だ」と言われるような素晴らしい会社にしたい、を目指されている。
無理からぬことである。日本の食は、明治の脱亜入欧政策によって「洋食一流、和食二流」となり、江戸四大食の職人たちの技術や誇りは軽視されていった。
その流れを変えたのが、つい10年ほど前の和食のユネスコ無形文化遺産登録であったが、蕎麦界も新世代、私の言う【第四世代】が登場するようになった。
目の前で、手鞠鮨を握っている3名は、若い女性だった。かの子の恥る時代の雰囲気は一片もない。そこもまた面白いと思った。
一息したところで、時間がきた。ごちそうさまと席を立ち、霧笛橋を下りて、「ゆめのたね」のスタジオへ向かった。
〔江戸ソバリエ協会ほし☆ひかる〕