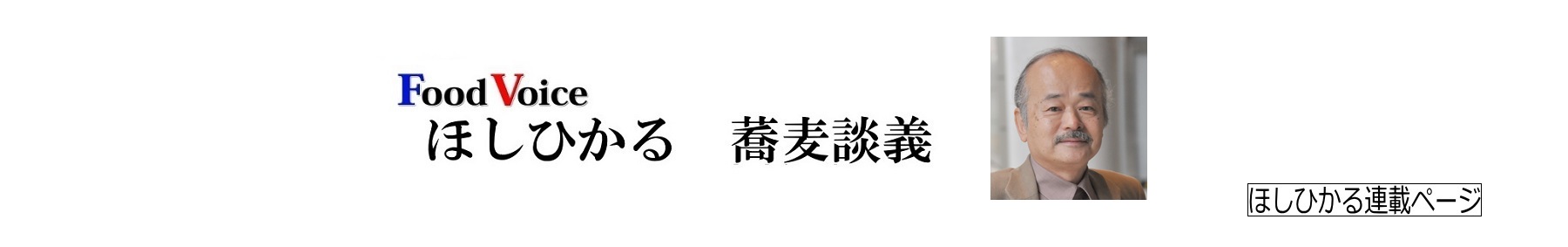第958話 町の蕎麦屋
2025/12/06
☆町の蕎麦屋 江戸料理研究家の福田先生からお電話をいただきました。ごぶさたを詫びながら、話しているなかで「小倉庵」(江戸ソバリエの店)はなかなかいい店だ」という話題になりました。
1)美味しい
2)安い
3)品数が多い。
4)いつ行っても座れる。
5)客の要望を聞いてくれる。
4)と5)はちょっと注釈を入れた方がいいかもしれません。
まず4)は、いつもお客さんが入っているけれど、昼時以外は座れるというわけ。つまり客にとっては安心感があるのです。
5)は、これ抜きにしてとか、個人的わがままを快く聞いてくれる。こちらも安心、信頼感がわくということ。
6)「いらっしゃいませ」と「ありがとうございました」は絶対欠かさない。だけれども、店の人は余計なおしゃべりはしない。それでもお客のことをよく見ているというわけ。
食べる側が「いただきます」「ごちそうさま」なら、店側は「いらっしゃいませ」と「ありがとうございました」は当然です。
1)は腕前、2)は経営、3)4)5)6)が町の蕎麦屋としての役割を果しているということでしょう。だから、安心なお店で、飽きないお蕎麦というわけで、毎日見えるお客さんもいらっしゃるらしいのです。
☆赤茄子
そんなことで、「明日、お昼でも」ということになりました。
その日、頂いたのは《赤茄子切り》と《天麩羅》。
「赤茄子」はトマトのことです。アンデス原産としてヨーロッパへ行き、日本に入ってきたとき、赤い茄子科の野菜というところから、「赤茄子」と名付けられました。
そういえば、前に中国を訪れたときの、《トマト鍋》が美味しかったことを思い出しました。またこの夏モンゴル国を旅したとき、たいていのレストランのテーブルにはケチャプとマヨネーズがありました。この二つはいまや世界的な調味料になっていますが、醤油の道とちょっと違うような気がします。
またトマトがイタリアに入ってきて、イタリア人が《パスタ》と革新的に合うトマトソースを考案したのは《パスタ》にとって、イタリア人にとってラッキーだったと言われています。まさにトマトは世界を席巻していることを実感します。
一言付け加えますが、トマトのことでぱありませんが、醤油+出汁=つゆの開発は《ざる蕎麦》にとって、日本人にとって口福な出来事であったのです。
江戸ソバリエ
ほし☆ひかる