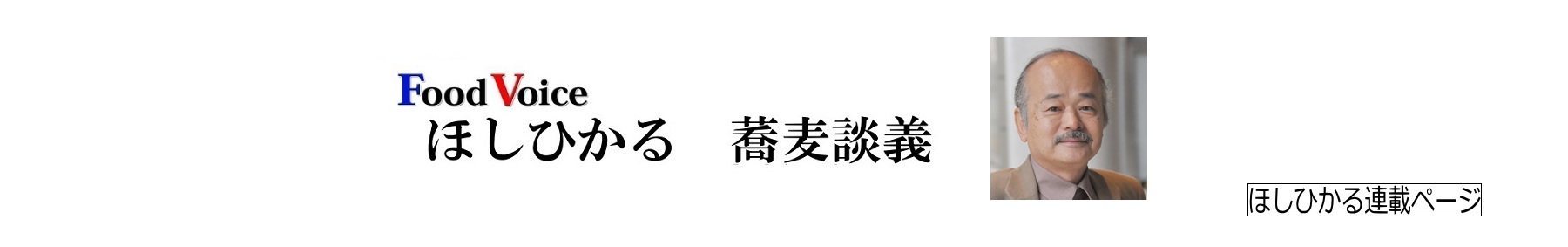第275話 不思議な話:慶喜残月 ― 上の巻
2025/12/06
徳川慶喜公の《しっぽく蕎麦》
徳川慶喜が将軍の地位にいたのはわずか1年である。であるのに、歴史上では「最後の将軍」としてかなり強い印象がある。
歴史をみれば、武家政権になってから、源氏、北條氏、足利氏、織田・豊臣氏の最後は蠟燭の灯が燃え尽きたように消滅していったが、徳川氏の慶喜だけはちがっていた。幕を引くために舞台に登場し、役割が終わるとサッサと下りてしまったのである。
第十五代将軍徳川慶喜は大政奉還後、静岡に約二十九年、豊島区巣鴨に四年、文京区第六天町に十七年住し、生涯を終えた。
この間、勝海舟、渋沢栄一以外はほとんど誰とも会わず、趣味の放鷹、鉄砲猟、大弓、釣、打毱、宝生流謡曲、油絵、写真、刺繍などに没頭していたことは有名な話である。
司馬遼太郎によれば、それは幕府を裏切った薩摩(西郷隆盛・大久保利通)への深い憾みをかかえてのことだったというが、むしろこれが慶喜の本来の性格ではなかったかと思う。
結局、慶喜は古の貴族のように趣味に生きた。それも「凝り性」、「新らしもの好き」との評が目に付く。なかでも飯盒で炊いたご飯を食べていたとか、豚肉が好きだとかの逸話は慶喜らしさの真骨頂というところかもしれない。
私はそんな慶喜公が《しっぽく蕎麦》を食べたという記録が残っているというので、お話をうかがうために慶喜公の侍女アサさんを訪ねた。
第六天町小日向の慶喜邸は左手に新坂、右側を荒木坂に囲まれた丘の崖の上にあった。広さは千八百二十八坪、広大なお屋敷だ。下の方には江戸川が流れていた。
黒塗の御門を入った所に巡査がいた。事情を話すと「玄関の方へ」と指示された。築山の向こうの玄関先には最前からアサさんが立っておられるようだった。私が近づくと丁寧に腰を曲げられ、「お部屋へ」と言われた。でも私は遠慮した。何しろ「最後の将軍」のお屋敷である。中へ入るわけにはいかないだろう。するとアサさんは「それではお庭にでも」とおっしゃって、先に歩かれた。私は砂利の音を分けながら付いて行ったが、不思議なことにアサさんが歩いた跡は砂利の音がしなかった。
辺りは松、樅、木斛、椎、椋、榛などの大樹が亭々と並んでおり、枝葉が風で斜めに揺れていた。
アサさんは板塀の引戸を開けて、私を先に通してくれた。少し行くと、陶製の円い椅子のようなものがあった。「ここでよござんすか。」アサさんが手を差し伸べて言いますから、私はそこに腰を下ろした。
広い庭のずっと奥を見ると、小さなお宮さんが建っている。
アサさんはそちらの方に目をやりながら、「毎朝、食事の前に『お定儀』を行うのが私のお勤めなんですよ」とおっしゃった。
「『お定儀』?」
「はい。ちょっと甘い焼味噌を塗した田楽状のものを、土器の浅いお皿に盛りましてね、神様にお供えするのです。それからお位牌を拝みまして、あそこの隅にお在すお宮さまに、お米とお水とお塩を三宝にのせてお供えするのです。雨の日も雪の日もです。お庭には狐や狸が出ますからね、怖ろしゅうござんすよ。」
これがきっかけで、アサさんも陶製の椅子に坐られました。しかしそれほど強くはなかったのですが、陽を背にされていたため、彼女のお顔が判然としなかった。
「ところで、今日は?」
「はい。慶喜公の曾孫さんにあたられます慶朝さんのご著書『徳川慶喜家の食卓』を拝読いたしますと、小日向邸へ永坂の更科蕎麦の出前を頼んでいたとあります。そこで、もっと詳しいお話をうかがえないものかと思ってまいりました。
「ああ、そのことね。懐かしゅうござんすね。あのころお取り寄せしていたもので特に美味しかったのは、富士見軒の出張西洋料理と永坂の更科のお蕎麦でしたね。もっとも更科の方は出張してくれたわけじゃなくて、御前の十男で、勝海舟伯爵家へご養子に行かれた精さまとご夫人の伊代さまのお土産に頂いたお蕎麦でございましたよ。ですから《ざる》は出来立てでもないし、《しっぽく》もそう温かくもなかったのですけど、それでも美味しくいただきましたよ。御前も満足されておりました。なにしろ、この時の精さまは三人引きの人力の一番最後の一台一杯に汁と実と具の三桶に分けた物をぎっしり乗せて、早駆けで来ましたでしょ。だから美味しく食べられたのでしょう。」
「精さまのお土産だったのですか。」
「そうですよ。」
「更科は『御前蕎麦』と呼ばれていたぐらいですから、精さまは御前のお土産にと思われたのでしょうね。」
「それはそうでしょう。何処のお蕎麦でもいいというなら、ここ小石川にもお蕎麦屋はありますしね。それに精さまがお住まいの赤坂・氷川町四番地から永坂の更科は、そう遠くはありませんしね。」
「西洋料理にしてもね、いいお店に出張してもらっていたのですよ。そう、先ほど申しました富士見軒というのはね、青柳条次郎というお人が明治9年に開かれた店ざんしょ。そのころは、まだ宮内省に洋食部門がございませんから、宮内省御用達の仕出料理店の代表的なお店といえば、富士見軒、それから、岩倉具視さまらのご尽力で明治5年に開業された築地精養軒は、井上浅五郎というお人が明治15年に作った宝亭なんぞが知られておりましたのよ。ところで、貴方はほしさんといいましたか。」
「はい。」
「御前も、私も、もちろん勝精・伊代さまご夫婦も、美味しくいただいたのですけど、そもそもどうして《しっぽく蕎麦》なんていうのかしら?」
「はい。もともとは、《卓袱うどん》というのが関西にありました。椎茸の煮付、湯葉、板麩、蒲鉾、三つ葉などを載せたものだったようです。それを日本橋室町の「近江屋」や人形町「万屋」などという蕎麦屋が、《しっぽく蕎麦》として売り出したといいますね。」
「うどんねえ。蕎麦になったのはいつごろ?」
「江戸中期頃ということになっています。時代によって具は少しずつ異なっているようでして、『そば手引草』(1775年)には松茸・椎茸類、薯蕷あるいは大和薯蕷、烏芋、麩および芹の具を加入すとありますが、幕末頃には、焼鶏卵、蒲鉾、椎茸、クワイなどを加えていたそうです。ところで、アサさんが召し上がられた《しっぽく蕎麦》の具は何でした? 将軍も口にされた高級《しっぽく蕎麦》とはどういうものだろうということで、興味深いところですね。」
「そうねえ。たしか、お蕎麦の上に松茸、椎茸、蒲鉾、半熟卵、野菜などが載っていたと思いますよ。」
「松茸ですか。旬に合わせて、お土産を持参した精さまの粋な計らいが読み取れますね。」
「精さまはお優しい方でしたからね。」
「蒲鉾の色は?」
「白かったわね。」
「野菜というのは。」
「そうね、きれいな緑色をした葉ものだったかしら。」
「小松菜とか。」
「そう。」
「ありがとうございました。お蔭さまで、当事の《しっぽく蕎麦》の様子がわかりましたし、またお蕎麦を通して、慶喜ご一家の一端が見えてまいりました。」
「もういいの。何かあったらまた起こしくださいまし。」
「はい。」
その日はそれで帰らせてもらったが、これがきっかけとなって慶喜公についての資料を漁るのが楽しみのひとつとなり、そうした中から初めて気付いたことも出てきた。
というのも、知られるように、慶喜公のその容貌は凛々しく、いかにも武家の棟梁に相応しい。だが実際の性格は、趣味に対する態度からみても公卿そのものであったと思われる。
この矛盾を抱えたまま、激動の時代は、三○○年続いた徳川政権の、七○○年続いた武家政権の「最後の将軍」として、慶喜を歴史舞台に送り出したといえよう。
とすれば、「最後の将軍」の称号の意味は大きい。なぜなら、戦後、もし誰かが慶喜のように戦争の幕引役を引き受けていたら、今の日本の道はちがっていたのかもしれない、と思ったりするのであった。
〔☆ほしひかる〕