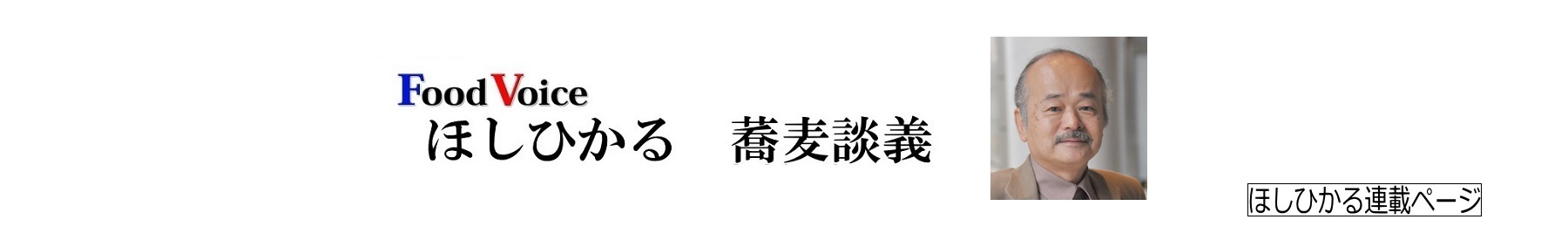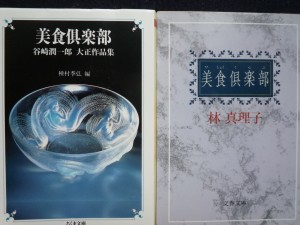第71話 男と女の「美食倶楽部」
2025/12/06
☆二つの「美食倶楽部」
春の皇居を訪れると、桜の花びらが牛が渕の水面を覆い尽くして美しい。こんなときは《桜切り》など食べてみたい。と思って、九段の蕎麦屋さんに立ち寄って、食べ終わってから外に出るともう陽が落ちていた。夜桜は幻想的に咲いている。こんなときは何かミステリアスなことにでも遭遇しないかと期待したくなるが、現実は何事もなく過ぎていく。
しかし、ある美食倶楽部 ― というからには、美食主義者の男たちの会、いいかえれば食べることに関して執拗な、あるいは変わり者の集まり ― のリーダー格であるG伯爵はそうではなかった。名も知らぬ支那人と牛が渕ですれ違ったとき伯爵はその男から〝紹興酒の匂い〟を嗅ぎとった。「自分の知っているかぎり近辺に支那料理屋はなかったはすだが」と興味をもった伯爵は、流れてくる胡弓の音に誘われるまま「浙江会舘」という所を見つけ出す。そこから妖しい世界へとのめり込んでしまい、ついには「高麗女肉」なる料理に行きつく、というのが谷崎潤一郎の描くおどろおどろしい「美食倶楽部」である。
谷崎潤一郎の「美食倶楽部」(大正8年)は、料理小説界のなかでは代表的な作品として知られている。その谷崎に倣ったのが村上龍の料理小説&官能小説であろうが、題名の「美食倶楽部」の方は林真理子が引き継いでいでる。
秋の南麻布だった。日本料理店なのに昼のランチは蕎麦を出すという店があるという話を耳にした。その店は広尾駅から少し離れた所にあった。林真理子の「美食倶楽部」(昭和61年)の主人公の行きつけの店もこんな感じだろうかと思うような小さな店 ― 名前は『もみじ』といった ― の戸を開けると、先客が三人ほどいた。
メニューはというと、《猪つけ蕎麦》《鱈白子つけ蕎麦》《本鮪能天つけ蕎麦》《地鶏つけ蕎麦》といった具合。そして蕎麦を食べ終わったら、「残ったつけ汁に、出汁とご飯を入れて、食べてください」というのである。私は《猪》を頼んだが、すぐに猪と付け汁の匂いとともにそれはやってきた。そして蕎麦の後はご飯である。たちまちお腹いっぱいになったのはいうまでもない。
ところで、林さんの小説の主人公は、変わり者というほどでもない普通の美味しい物好きの女性である。ただ、女性経営者ということから、歳下の若い男と付き合っているという設定である。よく、明治・大正期の小説を読むと、小金を貯めた親父が決まって薄倖の若い女を囲っている。まるで、それに対抗するかのように現代では、経営者的な女性が主役だとすぐ歳下の若い男、とくる。よくある構図ではないかと思わないでもないが、それはさて措き、林さんの「美食倶楽部」でも日本料理屋における〝鮒鮨のにおい〟から、ストーリーは山場へと向かう。といっても、谷崎のように異様な世界ではなく、部下の若い娘と中年男の仲を知って、それまでカッコイイ中年と思っていた男が急に色褪せて見えるという日常ありがちな話だ。
【二冊の『美食倶楽部』】
しかし、この二つの「美食倶楽部」から男と女の美食態度が違うことがうかがえる。男のそれは、奥は深いが、妾を囲うように他人には見せたがらない、病的な世界にちかい。よく聞く「男の隠れ家」という言葉がそれを表している。話は飛び、かつ私見であるが、あの鴨長明が晩年、日野山に方丈(一丈四方)の庵を結んだところから名づけられた随筆『方丈記』も、千利休が創作した僅か二畳の茶室「待庵」も、「男の隠れ家」的発想ではないかと思っている。
ところが、女のそれは、若い男を連れて回るように、オープンといえば聞こえがいいが、見せたがる世界である。だから「女性に人気の有名店」というキャッチコピーがメディアで躍るのではないだろうか。
と、思っていたとき、内田康夫さんの『イタリア幻想曲』の中で、「女は自分の存在をアピールしつづけていないと生きていけないものだが、男は自分の殻に閉じ籠っても、平気で生きていける動物である。」という文を見つけた。
そうそう。男と女の楽しみ方の違いは、私たち蕎麦仲間にも見られる。
女性たちはおしゃべりと様々な料理を楽しむ。
男たちは禅の修行僧のように渋い顔をしながら「まだまだ」などと言いつつ自分で奥を深くしていく・・・・・・。
参考:谷崎潤一郎『美食倶楽部』(ちくま文庫)、林真理子『美食倶楽部』(文春文庫)、内田康夫『イタリア幻想曲』(角川文庫)、
〔蕎麦エッセイスト、江戸ソバリエ認定委員 ☆ ほしひかる〕